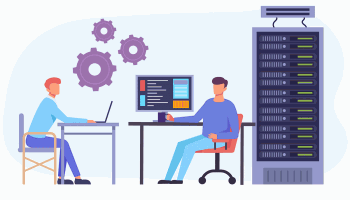【真の残業削減を実現する】「営業職」の労働時間短縮のための業務見直しのポイント
時短コンサルタント・社会保険労務士
山本 昌幸
III. 残業削減&労働時間短縮に取り組むにあたっての心構え
1. 営業職を中心としたホワイトカラーの生産性向上と労働時間短縮のポイント
変形労働時間制の採用やノー残業デーの設置といった小手先の残業削減ではなく、根拠に基づいた真の労働時間削減に取り掛かる前に、非常に重要なことがあります。

このことは、前述した“長時間労働がなくならないのは、そもそも企業が「営業職の長時間労働をなくす気がないから」”に通じるのですが、最初に組織のトップ(通常は社長)が、「何としても残業をなくして適正労働時間を実現する」ことをコミットメントすべきでしょう。残業削減に取り組む強い意欲が芽生えないというトップも多々いらっしゃると思いますが、残業削減に取り組まないことによるリスクを認識しているトップであれば、残業削減と適正労働時間の実現に取り組むことは、必然と言えましょう。
この、トップによる“何としても残業をなくすというコミットメント”なくしてこの取組みは成功しないのです。
2. 社長、管理者の考え方次第で残業は減る
30人までの小規模企業であれば社長、30人超の中堅~大企業であれば部署の管理者の考え方次第で、残業は削減できます。
例えば、企業によっては次のような組織風土を持っていることがありますが、社長や管理者がこのような馬鹿げた組織風土を一蹴することが、残業削減への取組みの第一歩と言えます。
◆残業削減を実現するために改めなければならない社風の例
- 定時に帰り難い
- 部下は上司よりも先に帰り難い(またはその逆)
- 残業しないことは悪
- 営業職は夜討ち朝駆けが当然
- 営業職にプライベートはない
また、“残業時間の発生=問題発生”と説明しましたが、“問題”とは、「不適合」であり、その不適合に対しては、即刻応急処置を施したうえでその原因を突き止め、取り除く是正処置(再発防止処置)を施す必要があります。
小手先の残業代削減対策である変形労働時間制はもちろん、残業の申告制やノー残業デー等は、効果が出る場合もありますが、問題の原因(残業発生の原因)を突き止めて講じる処置ではありませんので、その場しのぎに過ぎず、たまたまうまくいったとしても問題が再発してしまう可能性が高いのです。例えば、一口に頭痛がすると言っても、その原因は脳に血栓ができているのか腫瘍ができているのか、視力の問題なのか、三半規管の問題なのか、風邪なのか、さまざまな原因が考えられますが、それを突き止めなければ処置のしようがありません。残業の発生についても同じです。
要するに、残業を削減するためには、社長、管理者が残業削減についてコミットメントをし、残業の原因を突き止め対策を講じることが必要です。このコミットメントを受けた労働者の活動を、場合によっては「就業規則」に規定する場合もあります。
3. 取組みに抵抗する者への対応
残業削減・生産性向上という極めて真っ当な取組みであっても、抵抗者は必ず存在します。抵抗理由は、次のようなものです。
- 昼間の自由時間を侵害されるのでは?
- 給与が削減されるのでは?
- 自分への管理が厳しくなるのでは?
これらの疑心暗鬼に対しては、組織として毅然とした態度で理解を求めなくてはなりません。この態度が曖昧であると、すぐに足元を見られてしまいます。だからこそ社長のコミットメントが必要なのであり、場合によっては「就業規則」への規定が必要なのです。

筆者はある仕組みの審査員として700回以上、2人~数万人規模の企業に対して審査を実施しましたが、審査を実施するうえで一番厄介な部署が、営業部でした。なぜ厄介なのかと言いますと、「組織立って活動することに抵抗がある方が多い部署」だからです。
組織内で仕組み作りを運用する場合、組織立って活動することが前提ですが、なぜか営業部員は非協力的とはいかないまでも、協力的ではありません。例えば、審査員が「この製品の不良率が問題になっていますが、営業部として不良率低減に寄与できる活動は何かありますか?」と質問しても、「不良率が何ppm単位でどうのこうのなんかより、その分、売ってきますから大丈夫ですよ」という答えが返ってきたりします。
営業担当者は、組織として活動したり仕組みとして活動したりすることには、抵抗があるというよりむしろ苦手のようです。その“苦手意識”を隠すために、あえて非協力的な姿勢を示すこともありますので、少々厄介なのですが、たとえそうであっても、残業削減による適正労働時間の実現は適正な活動ですので、会社は毅然とした態度で臨まなくてはなりません。
4. 労働時間削減に向けた手法はいくつもある
筆者が企業に対して労働時間削減や適正労働時間の実現を指導する場合、業種、職種および企業規模によってアプローチを変えるのですが、今回の残業削減の対象は主に営業職ですので、社内プロジェクトチームを結成してPDCAサイクルを回すことにより残業削減を達成する方法を紹介します。なお、業種、職種によっては残業削減が困難なケースも存在することは否定しませんが、そのようなケースはごく一部であり、また、そのようなケースであっても何らかの削減効果を出すことは可能であることをお伝えしておきます。
この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- その他3
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント