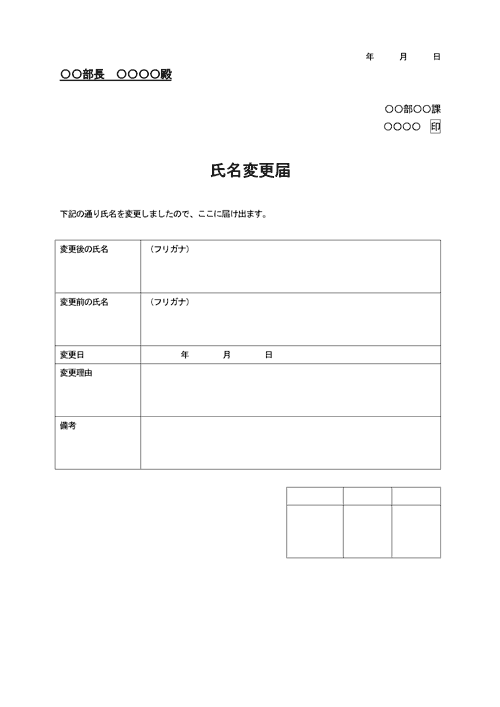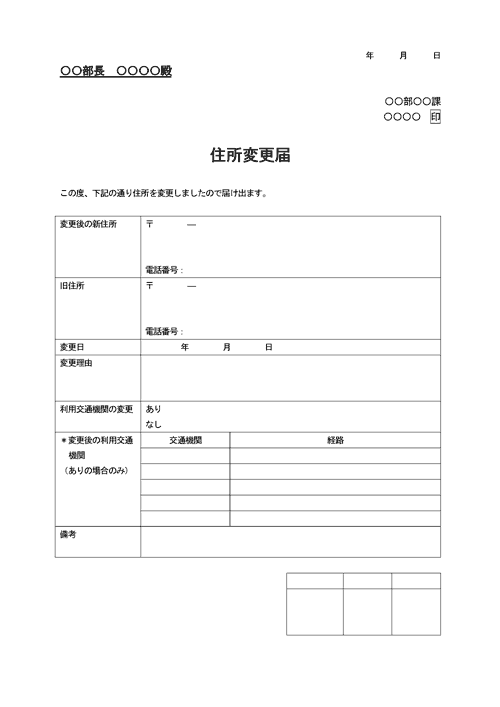定期健康診断結果報告書について
いつも参考にさせていただいています。
定期健康診断結果報告書についてご教示ください。
①在籍労働者数について
弊社では9月~11月に定期健康診断を実施しています。
11月に健康診断予定だった従業員が、9月に退職した場合、在籍労働者数から除いて問題ないでしょうか。
②実施時期について
現在9月~11月に定期健康診断を実施していますが、令和7年から実施期間を4月から3月に変更した場合、報告書の実施年度は令和7年でよろしいでしょうか。
また、実施期間を変更した場合、在籍労働者数はいつ時点の人数を記入すればよろしいでしょうか。
③実施期間変更について
実施期間を変更する際の注意事項はありますか。
質問が多く恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/02/22 22:09 ID:QA-0148836
- オリーブさん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答

- この回答者の情報は非公開になりました
定期健康診断結果報告書について
お問合せ・各問に対し、以下のとおり回答させて頂きます。
(1)在籍労働者数について
弊社では9月~11月に定期健康診断を実施しています。
11月に健康診断予定だった従業員が、9月に退職した場合、在籍労働者数から除いて問題ないでしょうか。
【回答】
定期健康診断結果報告書については、令6・3・18厚生労働省令第45号「じん肺法施行規則等の一部を改正する省令」によって、心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告書、労働者死傷病報告や有機溶剤等健康診断結果報告書など共に、令和7年1月1日以降、電子申請による報告が原則になりました。
原則というのは、従来の紙・様式も当分の間は使用が可能だという経過措置がついているという意味です。
従来の紙・様式(安衛則様式第6号)の裏面には、「在籍労働者数」について、「健診年月日現在の人数を記入すること」「この場合の『在籍労働者数』は、常時使用する労働者数を記入すること」との説明があり、9月~11月が健診実施期間であれば、在籍労働者数は健診の最終実施時期:11月時点の数を記入すれば良いので、お問合せのとおり、9月に退職された方については(11月時点で確定させる)在籍労働者数から除いて差し支えありません。
(2)実施時期について
現在9月~11月に定期健康診断を実施していますが、令和7年から実施期間を4月から3月に変更した場合、報告書の実施年度は令和7年でよろしいでしょうか。
【回答】
健診の「対象年」(お問合せのような「実施期間」を報告する欄はありません)については、年度にすべし、とか、暦年にすべし、とかの定めはありません。従来の1年間の期間:4月~3月を、3月~2月に変更したとしても、実際の実施時期が9月~11月で変わりなければ、報告する関係数値は変わりないので、「対象年」欄の記載を「令和6年(4月~3月分)」から、令和7年実施分について「令和7年(3月~2月分)」と変えるだけでOKです。
(3)実施期間変更について
実施期間を変更する際の注意事項はありますか。
【回答】
「対象年」欄の期間の記載:「〇月~〇月分」が次回・報告分においてきちんと連続していることが必要です。
さらに定期健康診断は1年以内ごとに1回、定期に実施すべきものですから、前回・報告分の「健診年月日」の欄の期日から、次回・報告分の「健診年月日」の欄の期日の間隔が1年を超えていないことが大切なので、御注意ください。
投稿日:2025/03/03 15:21 ID:QA-0149059
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
育児休業中社員の定期健康診断の実施について 今回は、定期健康診断についてご... [2021/07/02]
-
定期健康診断について 現在定期健康診断は1月~2月末ま... [2024/12/11]
-
定期健康診断結果報告書の記載について 雇入時健康診断を行った場合、1年... [2024/03/08]
-
雇用時健康診断と定期健康診断について 弊社では毎年11月に定期健康診断... [2018/08/19]
-
産前・産後休暇の健康診断の受診について 11月頃に会社での定期健康診断が... [2023/07/10]
-
中途入社の定期健康診断 中途入社者の定期健康診断について... [2018/07/06]
-
定期健康診断の実施について 弊社では定期健康診断を年度(4月... [2025/02/05]
-
雇入時健康診断と定期健康診断について 雇入時健康診断と定期健康診断につ... [2022/06/21]
-
雇入れ時健康診断について 派遣社員から直接雇用に変更する社... [2025/12/12]
-
定期健康診断をけがで受けられなかった従業員 弊社では毎年夏に、定期健康診断を... [2020/02/25]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント