質の高い「会議」が従業員のウェルビーイングを向上させる
「ミーティング・サイエンス」に学ぶ、
会議の質を高める技術
桜美林大学 健康福祉学群 教授
松田 チャップマン 与理子さん

多くのビジネスパーソンが、働く時間の多くを会議に費やしています。「なぜこの会議に参加しなければいけないのか」「長時間の会議が何本もある」といった悩みを抱えている人も多いようです。そこで注目されるのが、「ミーティング・サイエンス」。ビジネスパーソンが抱く会議への不満を科学的なアプローチで解決しようとする、新しい研究領域です。日本でこの研究をリードする桜美林大学 教授の松田チャップマン与理子さんは、質の高い会議が、従業員の職場におけるウェルビーイングの向上につながると話します。松田さんに、「効果的な会議」の基準や、非効果的な会議を改善する方法などについてうかがいました。
- 松田 チャップマン 与理子さん
- 桜美林大学 健康福祉学群 教授
同志社女子大学 学芸学部 英文学科卒。国内外の企業に約20年勤務し、その間に英ウエストミンスター・ビジネス・スクールで経営学修士(MBA)、米マサチューセッツ工科大学(MIT)スローン経営大学院でVisiting Fellow Program修了。2007年に桜美林大学大学院 国際学研究科 人間科学専攻 修士課程修了、2010年同国際学研究科 環太平洋地域文化専攻 博士後期課程の単位取得後退学を経て、同年桜美林大学にて博士号取得(学術)。公認心理師、指導健康心理士。主な著書に『従業員-組織の関係性とウェルビーイング(晃洋書房)』『ポジティブ心理学コーチングの実践(共訳:金剛出版)』など。
効果的な会議は、従業員のウェルビーイングを向上させる
松田さんが研究されている「ミーティング・サイエンス」について教えてください。
ミーティング・サイエンスは、会議の設計や進行、参加者の相互作用が意思決定や生産性、ウェルビーイングに与える影響を科学的に研究する新しい学問領域です。会議は文化や組織の規模に関係なく、あらゆる職場で行われる普遍的な現象でありながら、これまで学術的な研究対象としてはあまり注目されてきませんでした。
始まりは1989年頃、ドイツの研究者が職場の会議について論文を発表したことでした。その後、2010年代に米国ユタ大学やノースカロライナ大学の研究者らがミーティング・サイエンスを創始しました。学際的な性格が強い領域であることから、心理学、社会学、政治学、コミュニケーション学などの知見を援用していますが、ミーティング・サイエンスの中核となる理論は今後確立されていく見通しで、さらに 発達していく分野だと思います。
私は会議の時間が長いときや、なぜ自分がその会議に出る必要があるのかが分からないとき、会議後に疲弊してしまうことがありました。その後、研究者になり、ある大手企業のコンサルティングに関った際に「ミーティング・サイエンス」と出会い、「これから必要になる学問だ」と強く感じたのです。私の外資系企業での経験と、研究している心理学の知識の双方を生かせると感じましたね。
多くのビジネスパーソンが、日常の会議に課題を感じています。
コロナ禍によりオンラインによる会議が普及し、世界中で会議の頻度が増加しています。例えば、米国の職場で勤務するリーダーは週に23時間も会議に費やしており、従業員も勤務時間の最大85%を会議に費やしています。
会議は時間や人件費など、組織にとって多大なコストを伴います。また、多くの従業員が会議を時間の無駄で、ストレスの原因だと感じています。私が2023年に行った調査では、「いつも同じメンバーが話し、発言が偏っている」「マンネリ化している」「会議が不必要に長い」といった意見が多く聞かれました。
さらに、多くの研究により、非効果的な会議が従業員の仕事への満足度やモチベーション、職場におけるウェルビーイングを低下させ、離職意図や心身の疲労感を高めることが明らかになっています。
一方、私自身の研究では、効果的な会議が従業員の会議への満足度や心理的安全性を高め、結果としてパフォーマンスやワーク・エンゲイジメント、そして職場におけるウェルビーイングが向上する可能性が示唆されました。会議は、組織の業績はもちろん、従業員のウェルビーイングにおいても非常に重要な要素だといえるでしょう。
「会議の質」は三つの観点から測ることができる
「効果的な会議」は、どのように定義できるのでしょうか。
会議という場が、参加する人やチーム、組織に対して、どれだけ建設的な効果を生み出すのかという観点で質を検証する必要があります。ミーティング・サイエンスでは、大きく三つの観点から会議の質を評価しています。
一つ目は、「目的達成度」。意思決定、情報共有、アイデア創出など、設定された会議の目的をどの程度達成できたかという観点です。達成度が高ければ「会議の質は良好だった」ということになります。
二つ目は、「対人関係の質」。参加者同士の関係性、心理的安全性、信頼、協働意識が会議を通してどのように築かれたか、ということです。会議を通して、一緒に働いていく意識や信頼関係が構築されるかどうかが重要な指標となります。
三つ目は、「参加者の満足度」。参加者それぞれが会議を有意義だと感じたか、自らが会議に貢献でき時間を無駄にしなかったか、といった主観的な満足感です。
| 目的達成度 | 意思決定、情報共有、アイデア創出など、設定された会議の目的をどの程度達成できたか |
|---|---|
| 対人関係の質 | 参加者同士の関係性、心理的安全性、信頼、協働意識が会議を通してどのように築かれたか |
| 参加者の満足度 | 参加者それぞれが会議を有意義だと感じたか、自らが会議に貢献でき、時間を無駄にしなかったか |
三つの観点がすべて高いレベルで達成されて、初めて「質の高い会議」と言えるのです。重要なのは量よりも質です。必要な会議の数は、質が向上すれば自然と適正化されます。
「日本の会議文化」が抱えている課題
日本の会社では日々多くの会議が行われていますが、日本ならではの課題はあるのでしょうか。
大きな問題の一つは、会議の主催者(リーダー、ファシリテーター)が安心感を得たいがために、関係しそうな人を片っ端から招集してしまうことです。特にオンライン会議では、メールのCCで安易に参加者を追加する傾向が見られます。「本当にその会議に参加すべき人は誰なのか」を十分に検討しないまま「後で困るかもしれない」という発想で人を集めてしまう。これは参加者の時間を奪い、集中して取り組むべき仕事を中断させることにもなります。もっとも、この問題は日本に限らず世界共通の課題でもあります。
また、日本は「ハイコンテクスト文化」に属し、沈黙や控えめな態度が「協調」や「慎重さ」と解釈され、言葉に表さなくても相手の意図を“察する”ことが重んじられます。対照的に、ミーティング・サイエンスの研究が進む米国などは「ローコンテクスト文化」であり、自分の考えを言葉で明確に伝えることが非常に重要です。会議で発言しないと「ここにいても意味がない人」「能力が低い人」と見なされがちです。
私も勤務した経験がありますが、欧米企業では言葉にすることを大切にします。「ちゃんと説明する、発言する」ことが参加や貢献の証とされ、発言しないと物事を理解していないと思われがちです。
こうした文化の違いを考慮しつつも、多様性と包摂性が求められる現代、会議ではみんなが発言し、アイデアを出し合い、意思決定に参加することが重要です。日本では根回し後の承認的な会議や、報告中心の会議、沈黙を良しとする文化的背景もあり、活発な議論を促すには工夫が必要です。
心理的安全性と「ボイス」の重要性
発言しやすい環境づくりは、効果的な会議を実現する上で重要な要素ではないでしょうか。
その通りです。ミーティング・サイエンスでは、組織をより良くするために従業員が自発的に行う建設的な発言行動である「ボイス」を活発化させることが鍵となります。そのためには、「心理的安全性」を醸成することが大切です。
ただし、心理的安全性を単なる「仲良しグループ的な雰囲気」と混同してはいけません。周りから変な目で見られたり、上司に忖度(そんたく)して発言を控えたりすることなく、自分の発言に責任を持って率直に声を出せる環境が、真の心理的安全性です。意見の相違を避けずに互いに敬意をもって発言できる環境であり、単に「感じよくするためにいつも同意する」ということではありません。また、自分の発言すべてに無条件の称賛や支持が与えられることを意味するものでもありません。
会議のリーダーやファシリテーターが意識すべきポイントを教えてください。
リーダーには、「この会議にみんなが参加することが大切なんだ」という姿勢を示すことが求められます。
重視すべきは「会話のバランス」です。特定の人だけが発言するのではなく、誰もが意見を言えるような環境をつくる必要があります。順番に意見を求めることを、あらかじめ決めてもいいかもしれません。私自身も少人数の授業では、全員がプレッシャーを感じずに発言できるよう工夫しています。そのためには、発言者が自分の考えを集中して話せるようサポートし、意見に対して批判をせず、ニュートラルな姿勢で傾聴することが大切です。また、参加者に建設的な質問を促すことで、議論をさらに深めることができます。
参加者はどのような心構えで臨むべきでしょうか。
その点については、いま研究を進めている「会議市民行動」(ミーティング・シチズンシップ・ビヘイビア)という概念で説明できると思います。「会議市民行動」は、いわば「組織市民行動」の会議版で、会議がうまくいくために「積極的に貢献する行動」のことです。
具体的には、自分が発言するだけでなく、他の人の発言を奨励したり、他の人の意見をつないだり、全員が役に立つ情報を提供したり。こうした行動を取る人が増えると、リーダーがきちんとファシリテーションできていることと相まって、会議の質は大幅に向上します。
発言することが苦手な人に、発言を促すための具体的な方法はありますか。
人前で発言することが苦手なメンバーが参加する会議では、付箋や紙に意見を書き、それを回覧して重ねていくなど、発言に頼らない方法を取り入れる工夫が必要です。
他にも、大型の会議では、発言しやすいように参加者を3〜4人程度の少人数グループに分けて「小さな声」からアイデアや意見を出し合い、それを全体に集約する、といった方法も有効です。人前で話すことには得手・不得手があり、個人差は避けられません。それを理解しつつ工夫する。地道な努力ですが会議を活性化させるうえで重要なことです。
若手社員には「会議で意見を出しても結局は採用されない、聞いてもらえない」という悩みもあるように思えます。
「上司から『自由な発想で何でも言っていいよ』と言われて意見を出しても、結局採用されない。自分が発表する意義は何なのか」という声を聞くことがあります。人は自分の行動の結果を見て次の行動を決めるので、適切なフィードバックがなければ発言しなくなってしまいます。「今回のアイデアはすごくいいけれど、こういう観点からすると実現するのは難しい」などと、上司は適切にフィードバックするべきです。
発言や貢献を丁寧に認めることで、若手社員は、自尊感情や自己効力感、レジリエンス(回復力)を高めることができます。そうした経験は、ワーク・エンゲイジメントの向上にもつながります。
オンラインでの会議については、どうお考えですか。
オンライン会議は、コスト、時間、参加の柔軟性という点で優れていると言えます。一方、コミュニケーションを取る上では限界があり、会議中に他の作業ができてしまう、いわゆるマルチタスキングや、非言語的な情報が大幅に減ってしまう、という課題があります。
コロナ禍をきっかけにリモートワークを実施している企業は多いでしょう。重要なのは使い分けです。情報共有であれば、短時間のオンライン会議で十分です。一方、深いディスカッションやアイデア創出が必要な場合は、対面の方が効果的でしょう。物理的に同じ空間を共有している環境では、発言だけではなく、いろいろなものを感じ取ることが可能です。対面の会議後は自然な対話も生まれやすく、コミュニケーションが息づくという副産物もあります。

組織として「会議文化を創造する」
「効果的な会議」の実現を、人事部門はどう支援すべきでしょうか。
会議の改善を個人の力量に任せるのではなく、職場全体で変革していく視点が必要です。会議を単なる業務プロセスとしてではなく、戦略的な人材開発の一環として捉える。会議をうまく使ってウェルビーイングを高めたり、人が成長する場にしたりすることを戦略的に考えたいところです。
人事部として、会社の会議を改善するためには、次のことができるでしょう。
一つ目は、会社として「会議とはこういうものだ」という基準を決め、会議文化を創造すること。「声に出すことは自分にとってリスクではなく、むしろ称賛されるべきことだ」という考え方を浸透させると良いでしょう。発言が活発になることで、意思決定が進むことはもちろん、他の人が発言している様子を見て「あの人の発言はうまかったから、次は自分もああしてみよう」と学ぶことができます。そうした代理的体験によって、「自分ならできる」という自己効力感も高まります。
二つ目は、スムーズに会議を行うための制度をつくること。世界的に有名なIT企業では、必ずアジェンダを作成し、参加者に対して「なぜその会議に出る必要があるのか」を明確にして事前に共有することを徹底しています。また、アジェンダ設定や会議の質・内容の評価などは、生成AIを活用することも有効でしょう。良い議題設定や会議の成果を全社で奨励する仕組みを整備することも効果的です。
三つ目は、会議の内容や進め方について、今日の会議はどうだったかを全員で振り返る場を設けるといいでしょう。会議のゴールは、「今日の会議でこういうことが決まり、次はこれをやるべきだ」というところまで合意形成すること。それを達成できたかどうかや、会議の質を測る「目的達成度」「対人関係の質」「参加者の満足度」の観点で会議を振り返ることで、次の会議に生かすことができます。
四つ目は、従業員に対して、効果的な会議を行えるようなトレーニングをすること。「心理的安全性」「明確な目的意識」「質の高い時間の使い方」などの要素を、従業員が意識し、実践できるようなトレーニングを導入すると良いでしょう。
最後に、人事部の方に向けてメッセージをお願いします。
会議は組織文化の縮図です。参加する人の職場に対する態度を変える大きなきっかけになります。質の高い会議を重ねれば、それが職場全体を変える力となります。
重要なのは会議の「量(回数)」ではなく、「質」です。必要な会議の数は、質が向上すれば自然と適正化されます。「とりあえず不安だから開催する会議」「とりあえず関係者を全員集める会議」ではなく、「明確な目的」と「適切な参加者」による質の高い会議を目指すべきです。
従業員が、会議を業務としてとりあえずやらなければならないものではなく、組織にとって重要なものであることを認識し、一人ひとりが「自分がここにいることに意味がある」「自分の貢献が認められている」と感じられる会議にしていく。これが従業員のウェルビーイングの向上や組織全体の活性化につながります。制度的な支援と個々の実践の両輪で、会議を変革していきましょう。
道のりは長いかもしれませんが、まずは身近な会議から一つずつ改善していくことで、必ず変化は生まれます。その小さな変化が積み重なって、やがて大きな組織変革につながっていくでしょう。

(取材:2025年7月28日)
この記事を読んだ人におすすめ
-
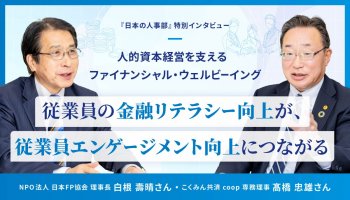
人的資本経営を支えるファイナンシャル・ウェルビーイング 従業員の金融リテラシー向上が、従業員エンゲージメント向上につながる
-

味の素株式会社: 従業員のWell-beingに寄り添い、志の実現へ 味の素が取り組む「人を大切にする」包括的支援
-

株式会社みずほフィナンシャルグループ: 「管理する人事」から「個人に寄り添いサポートする人事」へ みずほフィナンシャルグループが挑戦する、マーケティング視点の人事改革
-

人的資本経営と情報開示を巡る来し方と行く末 ―ウェルビーイング時代の経営の根幹「人」へのまなざし―(パーソル総合研究所)
-

日本における職業生活のWell-beingに関する文化的考察 ―世界116カ国調査を通じて見えてきた日本の特徴―(パーソル総合研究所)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった3
- 共感できる1
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







