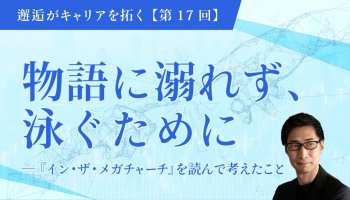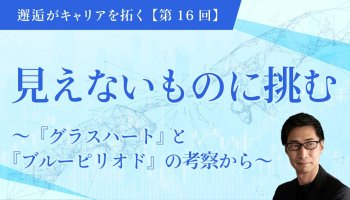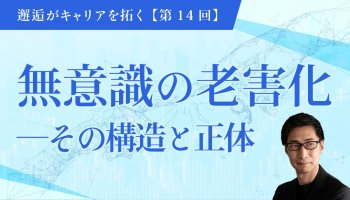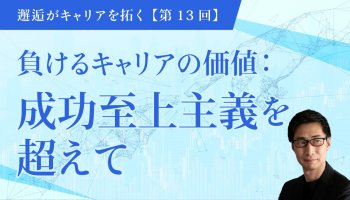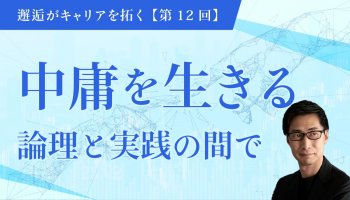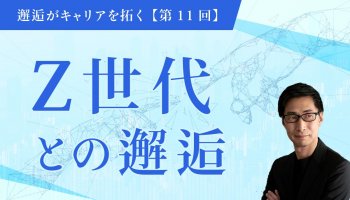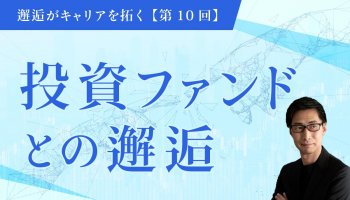邂逅がキャリアを拓く【第15回】
邂逅から始まる「問い」の旅
YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
西田 政之氏
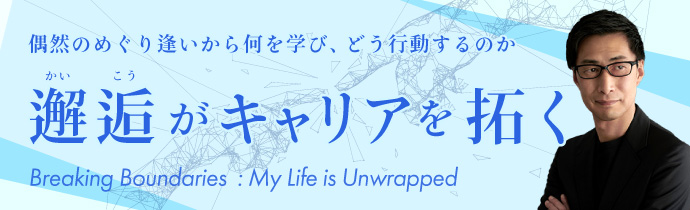
時代の変化とともに人事に関する課題が増えるなか、自身の学びやキャリアについて想いを巡らせる人事パーソンも多いのではないでしょうか。長年にわたり人事の要職を務めてきた西田政之氏は、これまでにさまざまな「邂逅」があり、それらが今の自分をつくってきたと言います。偶然のめぐり逢いや思いがけない出逢いから何を学び、どう行動すべきなのか……。西田氏が人事パーソンに必要な学びについて語ります。
本を読むとは、他者の問いと出会うこと
「人がほんとうに生きるのは、“出会い”のときである」
ユダヤ系ドイツ人の哲学者、マルティン・ブーバーの言葉です。私は、先日終えた「うらほろアカデメイア」の最後に、この言葉を参加者の皆さんへ紹介しました。
北海道・浦幌の大地で、酪農や畑作を体験し、森の中を歩き、地域の方々と語らう三日間。参加者たちは、日常から離れ、土に触れ、牛のまなざしと出会い、森の静けさに耳を澄ませながら、自分の内側にある「問い」と向き合っていました。あの場は、まさに“身体を通じた哲学的対話”の空間だったと、私は感じています。
ある参加者が語った言葉が、今も忘れられません。「最初は“体験型研修”かと思っていました。でも、体を動かすうち、頭より先に、心がざわついてきたんです」。その「ざわつき」こそが、まさに“問い”の芽生えなのだと思います。頭でひねり出すのではなく、体が先に反応する。その瞬間に、人は自分と世界との関係を揺さぶられるのです。
また、夕食後の何気ない会話の中で、印象的な言葉を聞きました。農家の方が「毎年、作物は違う顔を見せる。同じようにやっても、同じようにはいかない。でも、やるしかないんだ」と語ったところ、ある参加者がポツリと「僕たちは“答えの出る仕事”ばかりに慣れてしまっているのかもしれない」とつぶやいたのです。
問いとは、必ずしも答えを得るためにあるのではない。自分の価値観や前提を揺さぶり、世界との関係性を変えていく力。それこそが「問い」の本質であり、その出会いが、人生やキャリアを豊かにし、深めていくのではないか──そう確信した三日間でした。
とはいえ、日常に戻ると、あのような体験の場はそう頻繁には訪れません。では、日常の中で「問い」と出会うにはどうすればいいのか。その一つの手段が、「本を読むこと」だと私は考えています。
本を読むことの矛盾──「抽象」と「具体」のすれ違い
最近、宮森千嘉子さんの新刊『強い組織は違いを楽しむ』を拝読しました。併せて観た楽天大学での対談番組でも語られていたのは、「知ること」と「変えること」の間にある、見えない溝の存在です。
私たち人事パーソンは、多くの場合、本を「組織を変えるヒント」として読みます。事例を学び、理論を知り、「なるほど」と納得する。しかし、いざそれを自社に応用しようとなると、どこかに違和感が生まれる。この違和感の正体は何か──私は、「抽象」と「具体」のすれ違いにあると考えています。
書籍は、多くの個別事象を抽象化し、再構成し、一定の理論や方法論として提示します。一方、私たちの目の前にある現場は、極めて具体的で複雑な文脈を持ち、単純な抽象化にはなかなかなじみません。それでも、私たちは本の知を再び現場へと引き戻そうとします。まるで、乾燥果物から果汁の滴る果実を復元しようとするかのような挑戦をしているのです。
一見すると、それは無謀で、非効率で、意味のない行為のように思えます。しかし私は、そこに「創造的摩擦」があると考えています。抽象と具体の間を往復するプロセスが、新たな意味を生む土壌になるからです。
実際に、宮森さんご本人からも、読後に私が送った感想に対して次のような返信をいただきました。
「本は『問いを深める装置』であり、『知の翻訳者』としての私たちの営みを照らすものだという表現に、深くうなずきながら拝読しました。それぞれの現場に照らして新たな『語り』を紡いでいくこと──それが最終的な実践の在り方だと、あらためて感じさせられました」
この言葉を受け取って、私は勇気づけられました。読書によって立ち上がる「問い」を、現場に合わせて翻訳し、新たな物語として語り直す営み。それは決してムダではなく、むしろ組織の可能性を開く種まきのような行為だと、私は思います。
他者の問いを、自分の問いに翻訳する
哲学者ポール・リクールは、「人間とは、物語を語る存在である」と述べました。私たちは、与えられた知をそのまま受け取るだけでなく、自分自身の文脈に翻訳し、新しい意味を紡ぎ直す存在です。
本の価値は、完成された答えではなく、読者それぞれに異なる問いを芽生えさせる「装置」であること。読書とは、著者の問いを通じて、自らの問いを立ち上げていく営みです。
たとえば、宮森さんの本の中にある「違いを楽しむ組織」という言葉。私はそこから、「違いを翻訳し合える組織とは何か?」という問いを育てました。
「楽しむ」だけでは、違いは消費されて終わってしまいます。しかし、「翻訳する」ことで、違いは意味に変わり、共有知として蓄積されていきます。異なる職種、経験、文化的背景を持つ人々が、それぞれの前提や価値観を自分の言葉に置き換え、相互理解に近づこうとする営みこそが、組織における「違いの力」を発揮させるのだと思います。
ある社員研修で、夜に焚き火を囲んで語り合っていたときのこと。若手社員が「いろんな考え方があるのは分かるけれど、どうしたら本当に理解し合えるのか分からない」と漏らしました。そのとき、別の参加者が静かにこう言いました。「わからないままでも、隣にいることはできると思うよ」
その言葉に、私は“翻訳以前の余白”の価値を見いだしました。理解しきれないことを前提にしながらも、関わり続けようとする意志。そこにこそ、「翻訳し合える組織」の土壌があると感じたのです。
また、以前の職場でも、エンジニアと営業が共同でプロジェクトを進める中、対話が噛み合わずに苦労した経験があります。そんなとき、リーダーがこう呼びかけました。「まずは“翻訳者”になってみよう。自分の言いたいことを、一度相手の言葉で言い直してみよう」と。そのひと言が、プロジェクトの空気を変えました。言葉だけでなく、前提や価値観の翻訳を意識した瞬間、チームの連携が明らかに変わったのです。
邂逅とは、問いとの出会いである
「邂逅(かいこう)」とは、偶然のように見えて実は必然だった出会いを指す言葉です。この言葉は、人と人との出会いにとどまらず、「問い」との出会いにも使えるのではないでしょうか。
本と出会い、問いと出会い、それを仲間との対話で深めていく──うらほろアカデメイアは、まさにそうした「問いとの邂逅の場」だったと感じています。参加者たちは、他者の問いを受け取り、それを自分の文脈に翻訳し、また新たな問いを立てていました。
「50年かかる木を、なぜ今植えるのか」「毎日牛の世話をする意味とは何か」──そうした問いは、単なる知識や業務改善のヒントではなく、私たちの生き方そのものを照らす問いなのです。
終わりに──「問い」を持ち帰るということ
「哲学」とは、ギリシャ語で「philosophia(知を愛すること)」と訳されます。そしてブーバーの言う「生きる」とは、「出会い」のこと。その出会いの核心には、常に「問い」があります。
だからこそ、私は本を「知識の倉庫」としてではなく、「問いの泉」として開いていたいと思います。本で出会った問い、体験で生まれた問いは、キャリアや人生の優先順位を揺さぶるランプのような存在です。
次にあなたが本を手に取るとき、それは何かを得るためではなく、何かと出会うための時間かもしれません。そして、その出会いがあなたの中に新たな問いを芽生えさせ、その問いが未来を切り拓く鍵になると、私は信じています。
強い組織とは、「違いを楽しむ」だけでなく、「違いを翻訳し合える」組織。その第一歩は、本を読むこと。そして読書の先にある「問いとの邂逅」を、どうか大切にしてください。
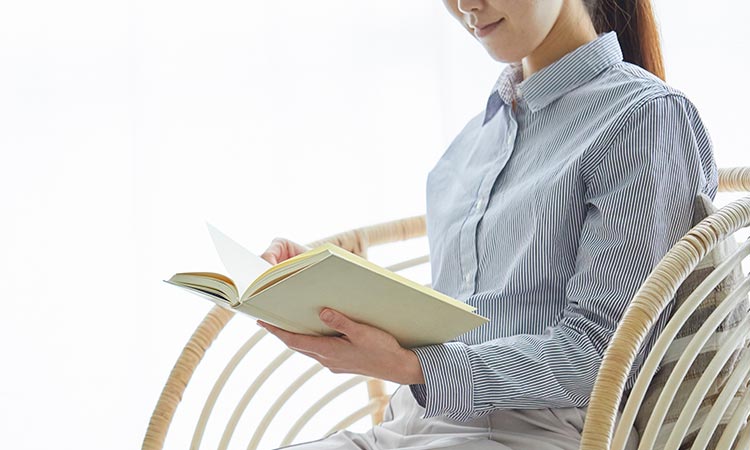

- 西田 政之氏
- YKK AP株式会社 専務執行役員CHRO
にしだ・まさゆき/1987年に金融分野からキャリアをスタート。1993年米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー、金融法人営業、事業開発担当ディレクターなどを経験。2004年に人事コンサルティング会社マーサーへ転じたのを機に、人事・経営分野へキャリアを転換。2006年に同社取締役クライアントサービス代表を経て、2013年同社取締役COOに就任。その後、2015年にライフネット生命保険株式会社へ移籍し、同社取締役副社長兼CHROに就任。2021年6月に株式会社カインズ執行役員CHRO(最高人事責任者)兼 CAINZアカデミア学長に就任。2023年7月に株式会社ブレインパッド 常務執行役員CHROに就任。2025年6月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員、MBTI認定ユーザー、幕別町森林組合員、日本アンガーマネジメント協会 顧問も務める。
- 参考になった0
- 共感できる2
- 実践したい0
- 考えさせられる1
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント