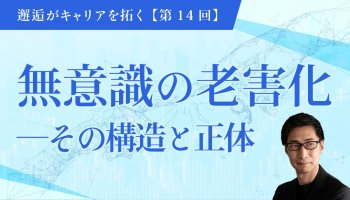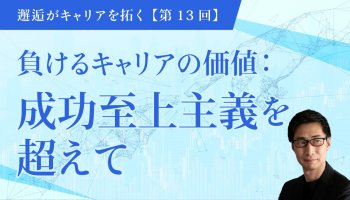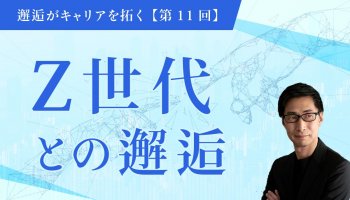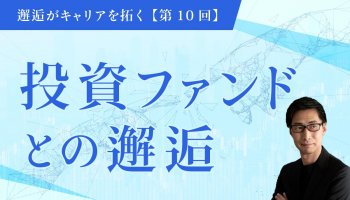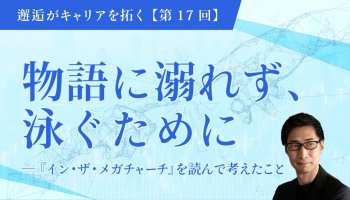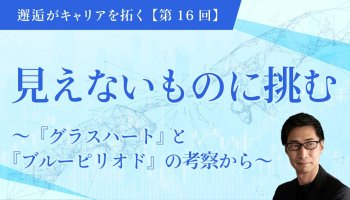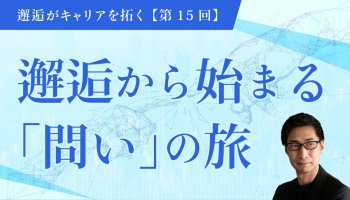邂逅がキャリアを拓く【第12回】
中庸を生きる:論理と実践の間で
ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社
チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー
西田 政之氏
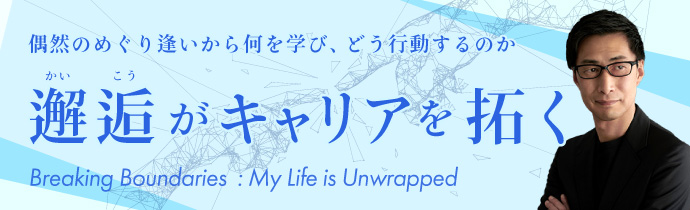
時代の変化とともに人事に関する課題が増えるなか、自身の学びやキャリアについて想いを巡らせる人事パーソンも多いのではないでしょうか。長年にわたり人事の要職を務めてきた西田政之氏は、これまでにさまざまな「邂逅」があり、それらが今の自分をつくってきたと言います。偶然のめぐり逢いや思いがけない出逢いから何を学び、どう行動すべきなのか……。西田氏が人事パーソンに必要な学びについて語ります。
中庸とは、極端を避け、調和を求める生き方です。この概念は古代ギリシャのアリストテレスや中国儒教の『中庸』にそのルーツを持ち、現代社会においても多くの示唆を与えます。しかし、日常生活や仕事で中庸をどう実践するか、その具体的な方法は一様ではありません。今回は、中庸の哲学的背景を振り返りつつ、私自身の経験と最近読んだ本から得た学びを交え、その実践方法を考えてみます。
中庸との邂逅
私が中庸という言葉に出会ったのは30代後半、禅の勉強会に参加したときです。この会で『碧巌録』や『言志四録』を学び、修了時に道名をつけることになりました。そこで名乗ったのが“中道”です。仏教における中道とは、苦行主義と快楽主義という両極端を否定し、その間にある悟りへの道を指します。講師から受けた「ど真ん中を堂々と歩む覚悟が必要だ」という言葉が印象的でした。つまり、中庸とは安易な選択ではなく、自ら問い続けながら進む道なのです。この教えは後に、ヘーゲルの「流動性」の概念とも重なるものだと感じました。
さらに、この経験は私にとって単なる精神的な修練に留まらず、日常生活や仕事にも影響を与えました。特に意思決定の場面で、極端な選択肢に走るのではなく、多角的に物事を捉えた上で最善の道を探る姿勢を意識するようになりました。
アリストテレスは『ニコマコス倫理学』で、中庸(メソテース)を「過剰」と「不足」の間にある徳と定義しています。たとえば、勇気は「蛮勇」と「臆病」の間に位置し、理性によって調整された行動こそが徳となると述べています。一方、中国儒教では『中庸』が孔子の孫・子思によって体系化され、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」という言葉で極端を避ける重要性が説かれています。両者に共通するのは、中庸が単なる妥協ではなく、深い洞察と選択によって成り立つ点です。
現代におけるこの考え方の意義は、私たちが情報過多の時代に生きていることにあります。日々のニュースやSNS上で飛び交う極端な意見に対して、中庸の視点を持つことは冷静な判断を下す助けとなります。これにより、短絡的な結論に流されることなく、より持続可能な選択を可能にするのです。
ヘーゲルの弁証法と中庸
昨年読んだ『ヘーゲル(再)入門』(川瀬和也 著)では、ヘーゲル哲学の核心を「流動性」という言葉で説明しています。この「流動性」の概念は、中庸を考える上で重要な示唆を与えます。
ヘーゲルの弁証法における「アウフヘーベン」は、対立する概念を単に否定するのではなく、より高次の段階で統合する過程を指します。これこそ中庸の本質に通じます。単なる折衷ではなく、動的な変化の中で新たな統合を生み出す創造的なプロセスとしての中庸。これは現代社会の複雑な問題に対する一つの解決策となり得ます。
また、この弁証法的な中庸の捉え方は、個人の成長にも当てはまります。私たちは日々、仕事や人間関係において対立する価値観や状況に直面しますが、それらを単純に受け入れるのではなく、新たな視点を見いだすことで自己を高めていくことができるのではないでしょうか。
中庸とジレンマ:現代社会への適用
現代社会では、『企業変革のジレンマ』(宇田川元一 著)や『イノベーションのジレンマ』(クレイトン クリステンセン 著)で論じられている課題が、中庸の実践の難しさを浮き彫りにしています。宇田川氏は、多くの日本企業が「構造的無能化」に陥り、変革が進まない状況を指摘しています。この状況を打破するには組織内の「対話」が重要であり、対話を通じて保守と革新が交わり、新たな解決策が生まれる可能性があるという方向性が示されています。
サントリーの「オールフリー」事業はその好例でしょう。同社は既存のビール事業を強化しつつ、ノンアルコール市場の成長に対応するため「オールフリー」を開発しました。既存技術を応用しつつ新規市場に進出したこの事例は、単なる折衷ではなく、新たな次元での解決策を見出した成功例と言えます。
このように、対話と創造を通じて新しい価値を生み出すことが、中庸を実践する上での重要なポイントとなります。特に、変化の激しい現代社会においては、極端な変革か現状維持かといった二者択一ではなく、その中間にある柔軟なアプローチが必要です。
中庸へのアプローチ:偶然から学ぶ
私自身も、日常生活や仕事において中庸を探る方法として「偶然」や「兆し」を重視しています。あるとき、今後の挑戦を考えていた時期に、親しいヘッドハンターから「今の西田さんにぴったりの案件がある」と連絡を受けました。その後、会社の特集記事やTVCMを頻繁に目にするなどの偶然が重なる中、何かに背中を押されるようにとんとん拍子で話が進み、転職を決断しました。このような偶然を単なる偶然と捉えるのではなく、選択を考えるヒントとすることで、より良い道を選べることがあります。
さらに、このような偶然は、私たちが見過ごしがちなチャンスを見つける手がかりにもなります。偶然をただの偶然とせず、そこに意味を見出す姿勢は、より充実した人生を築く一助となるかもしれません。
素粒子とゼロポイントフィールドの概念
『量子力学的実践論』(村松大輔 著)では、人間の意識や意志がフォトンとして場に作用し、新たな現象を引き起こす可能性があるとされています。この仮説を理解するには、素粒子とゼロポイントフィールドという概念に触れる必要があります。
素粒子は物質を構成する最小単位であり、電子や光子(フォトン)、クォークなどが含まれます。一方、ゼロポイントフィールドは、真空中にエネルギーが存在するという量子力学上の概念で、すべての物質や現象の基盤となる場です。村松氏の仮説によれば、意志や思考がこの場に影響を与える可能性があるとされ、偶然を捉える新たな視点を提供します。
この仮説を考慮すると、インディケーションも単なる偶然ではなく、自らの意識が場に影響を与え、現象を引き寄せた結果とも考えられます。転職を決断した出来事も、量子力学的視点から見ると、意識と場の相互作用による現象の発現と言えるかもしれません。偶然に見える出来事や兆しを受け止め、それを行動に生かすことが中庸を生きる上で重要ではないでしょうか。
ただし、村松氏の仮説は現時点で科学的に実証されたものではなく、一つの仮説的な視点です。本コラムではこの仮説を、中庸を考える示唆として取り上げており、科学的事実として述べるものではありません。
中庸という知恵
中庸とは極端から離れたバランス感覚であり、理性だけでなく感覚や偶然とも向き合うことで成り立ちます。歴史的にも哲学的にも、この考え方は普遍的な真理として支持されてきました。そして、それは私自身の日々の選択や行動にも深く関わっています。
現代社会ではタイパやコスパが重視され、極端な意見が注目されやすい傾向にあります。だからこそ、中庸の視点から新たな価値を創造することが求められています。私たちは「偶然」や「兆し」に耳を傾け、中庸の視点から物事を見る習慣を大切にすべきです。また、宇田川氏が指摘するように、組織内での「対話」を通じて異なる意見を統合し、新たな解決策を見出すことも重要です。この創造的プロセスこそが持続可能な社会や個人の幸福につながる真の「戦略」ではないでしょうか。
中庸を生きるとは、単に極端を避けることではなく、変化し続ける世界の中で創造的にバランスを取り続けること。現代社会における中庸は単なる理論ではなく、日々の選択と行動によって実践されるべき知恵です。偶然をただの偶然とせず、そこに示唆を見いだし、対話を重ねて新たな解決策を創造する。このプロセスが不確実な時代を生き抜く鍵になると考えます。
一方で、日々の中で偶然に気づき、それを活かすためには感性を磨くことも欠かせません。そのために必要なのは、自分自身に問いかけ続ける姿勢と、対話を重視する柔軟な心、そして、学び続けることです。中庸を生きるためのこの姿勢が、私たちにとって新しい可能性を切り開く鍵となるでしょう。
※本コラムで紹介した書籍の内容や解釈、並びに述べた意見や見解は筆者個人のものであり、必ずしも所属する組織や会社の公式見解を代表するものではありません。

- 西田 政之氏
- ジャパン・アクティベーション・キャピタル株式会社 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー
にしだ・まさゆき/1987年に金融分野からキャリアをスタート。1993年米国社費留学を経て、内外の投資会社でファンドマネージャー、金融法人営業、事業開発担当ディレクターなどを経験。2004年に人事コンサルティング会社マーサーへ転じたのを機に、人事・経営分野へキャリアを転換。2006年に同社取締役クライアントサービス代表を経て、2013年同社取締役COOに就任。その後、2015年にライフネット生命保険株式会社へ移籍し、同社取締役副社長兼CHROに就任。2021年6月に株式会社カインズ執行役員CHRO(最高人事責任者)兼 CAINZアカデミア学長に就任。2023年7月に株式会社ブレインパッド 常務執行役員CHROに就任。2024年7月より現職。日本証券アナリスト協会検定会員、MBTI認定ユーザー、幕別町森林組合員。日本CHRO協会 理事、日本アンガーマネジメント協会 顧問も務める。
この記事を読んだ人におすすめ

HR領域のオピニオンリーダーによる金言・名言。人事部に立ちはだかる悩みや課題を克服し、前進していくためのヒントを投げかけます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント