日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー
スキルと熱意を発掘するHondaの
「Gen-AIエキスパート制度」
わずか3ヵ月の制度設計を実現した原動力とは
安田 啓一さん(本田技研工業株式会社 執行職 コーポレート管理本部 人事統括部長)
佐野 雄樹さん(本田技研工業株式会社 チーフエンジニア デジタル統括部 先進AI戦略企画課長)
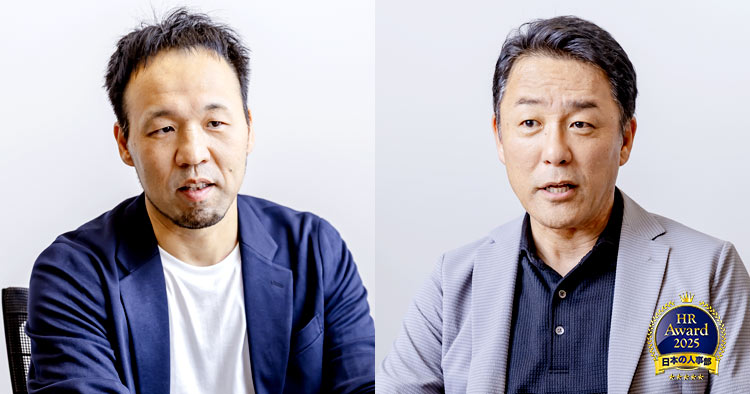
多くの企業が、生成AI(Generative AI)の活用と、それを担う専門人材の獲得・育成・定着に苦心しています。そんな中、本田技研工業株式会社は、3ヵ月という異例のスピードで「Gen-AI エキスパート制度」を構築。ボトムアップの熱意を起点に、個人の成長を組織の力へと転換させるプロセスが評価され、日本の人事部「HRアワード2025」企業人事部門 最優秀賞に輝きました。なぜそれほど迅速に制度を改定できたのか。執行職 コーポレート管理本部 人事統括部長の安田啓一さんと、制度設計のきっかけとなった社内IT技術コミュニティ「Borders」をつくったチーフエンジニアの佐野雄樹さんに聞きました。
「HRアワード」の詳細はこちら

- 安田 啓一さん
- 本田技研工業株式会社 執行職 コーポレート管理本部 人事統括部長
やすだ・けいいち/1990年に本田技研工業株式会社に入社。 日本だけでなく北米、アジアなど海外経験が長い。2015年Asian Honda Motor(タイ)にてアジア・大洋州本部人事責任者、Boon Siew Honda(マレーシア)、Astra Honda Motor(インドネシア)の社長を経て2023年から現職

- 佐野 雄樹さん
- 本田技研工業株式会社 チーフエンジニア デジタル統括部 先進AI戦略企画課長
さの・ゆうき/2008年本田技研工業株式会社に入社。四輪領域でCIVICなどのエンジン開発などを担当。その傍ら、自らのスキルアップのためにプログラミングやAIについて学び始めたことをきっかけに「Borders」を立ち上げ、「Gen-AIエキスパート制度」の企画に携わる。2024年からはデジタル統括部にて同制度をリード。
部門を超えスキルを可視化、現場のニーズとマッチング
「HRアワード2025」企業人事部門 最優秀賞の受賞、おめでとうございます。まずは貴社が推進されている「Gen-AI エキスパート制度」の概要についてお聞かせください。
安田:ありがとうございます。この制度は、生成AIエンジニアの活躍の場を広げるため、2024年6月にスタートしました。エンジニアを3段階で「Gen-AIエキスパート」として認定しています。認定されたエキスパートは個々人の状況に応じて、各部門から寄せられる生成AIを活用したプロジェクトに専任や兼務という形で携わっていきます。現場のニーズと、これまで社内に埋もれていたスキルをマッチングさせ、全社的な生成AI活用の促進につなげることが目的です。
6月、10月、2月と、年に3回、筆記審査や面接を経て、スキルレベルに応じて3段階で認定します。基礎的なレベル1は、生成AIを用いてコーディングができるなど、システム構築を実践的に行えることが求められます。最上位のレベル3は、AIを活用したシステム全体をデザインするだけでなく、事業展開など、戦略まで描ける人材を想定しています。
大きな特徴は、社員が主体的にエントリーする「手挙げ制」にしたことです。一般的な資格制度とは違い、会社や上司から取得を勧められるものではありません。また、プロジェクトに参加するエキスパートに対して、認定レベルと関与度(専任か兼任か)に応じた手当を毎月支給しています。最上位のレベル3エキスパートが専任でプロジェクトに従事する場合、月額15万円。レベル1の兼任でも、月額2万5,000円の手当を設定しています。
認定後はどのように活動するのでしょうか。
安田:認定エキスパートの中からさらに選抜されたメンバーは、デジタル統括部内の「先進AI戦略企画課」に異動し、専任でプロジェクトに従事するケースがあります。また、元の職場に在籍したまま、兼任という形でプロジェクトに参加することも可能です。
佐野:「こんなことに生成AIを活用できないか」という各部署の要望が上がってくると、認定者のリストから最適なスキル、必要な領域の知識を持ったエキスパートを選びます。兼任の場合、所属している部署の上司の承認を得た上で、プロジェクトに参画してもらいます。これまで生成AIに関する知識、スキルを持った人材がどこに、どのくらいいるかがわかりませんでした。エキスパート制度を通して社内の生成AIスキルが可視化できた意義は、非常に大きいと感じています。
佐野:現在、レベル1とレベル2合わせて約170人が認定されています。まだビジネスモデルの構築といったアウトプットが出ていないため、現時点でレベル3の認定者はいませんが、レベル2の人材は外部のコンサルティングファームで十分に通用するほど高いスキルを持っています。レベル2の多くが、さまざまなプロジェクトでリーダーとして活躍中です。

具体的に、どのようなプロジェクトが動いていますか。
佐野:多種多様な、およそ100のプロジェクトが登録されています。すでに発表している事例では、年齢や職位にかかわらず議論するHonda独自の文化「ワイガヤ」に生成AIを活用するものや、株主総会の質疑応答対策を支援するものなどがあります。特に画期的なのは、車両フロントをデザインする際に生成AIを活用する技術です。自然言語によって3Dモデルを生成することができます。
安田:たとえば、デザイナーが「ボンネットをもう少し厚く」「ヘッドライトの位置を少し上げて」といった感覚的な言葉で指示を出すと、生成AIが即座に3Dモデルを再生成します。このシステムの素晴らしい点は、デザイン変更と衝突安全性能の両立を自動で実現する点です。デザインを少しでも変更すれば、安全基準を満たすための再計算が必要になり、数週間から数ヵ月かかることもあります。このプロセスを生成AIが瞬時に行ってくれるのです。
佐野:このプロジェクトにも、エキスパート制度が大きく貢献しています。担当した認定エキスパートは、もともと車体のシミュレーションが専門でした。開発現場の知識を深く理解し、自らAIのスキルを駆使してシステムを構築することで、現場のニーズに即した形で開発を進められたのです。各部門に埋もれていた才能を発掘し、適切なプロジェクトにつなぐという、この制度ならではの成果だと考えています。
10人の自律型コミュニティ。ボトムアップの熱意が原点
すでに数々の成果が出ているエキスパート制度ですが、どのような経緯で誕生したのでしょうか。
佐野:2021年、社内有志のIT技術コミュニティ「Borders」を個人的に立ち上げました。もともと私はエンジン開発の現場にいたのですが、組織の壁によって知見が共有されない状況に問題意識を持っていました。ホンダには優秀な人材がたくさんいるのに、隣の部署が何をしているか分からない。この壁を越えて、誰もが自由に情報交換したり、学び合ったりできる場をつくりたいと考え、仲間を集め始めたのがきっかけです。
新型コロナウイルス感染症が流行していたので、オンラインでの交流が活発で、頻繁に勉強会や情報交換の場を開催しました。最初は10人ほどの小さな集まりで、それぞれ所属部署が異なる、部門の垣根を越えたメンバーでした。
機械学習の基礎を学んだり、株価予測のプログラミングを試したりと、純粋な知的好奇心に基づいたものが中心でしたね。誰かがリーダーシップを取るというよりは、メンバーが自発的に「次はこれをやりましょう」と企画を持ち寄っていました。プライベートで学んだことを会社に持ち帰り、仲間に共有するといった活動も行われていました。
10人で始まったBordersは現在、3000人近くのコミュニティになりました。正社員のみで、モチベーション高く、自律的に学ぶ人が集まっています。月に1、2回勉強会や最新動向の情報共有を行っていますが、今後は領域を増やしたり、開催頻度を上げたりしたいです。生成AIについて体系立てて学べるプログラムの作成も進めるつもりです。
安田:Bordersのメンバーは、生成AIに関する高いスキルと熱意を持ちながら、それを自部門の業務に生かし切れていないという、共通の課題を抱えていました。たとえば、よかれと思って「この業務に生成AIを導入すれば、もっと効率化できます」と提案しても、「自分の仕事に集中しろ」となかなか受け入れてもらえない。せっかく磨いた専門性を発揮できず、もやもやとした気持ちで日々を過ごしているという声を聞きました。
佐野:情報交換をすればするほど、個々の学習スピードは飛躍的に向上します。しかし、その学びを実際の業務に生かす出口がありませんでした。コミュニティは当時、すでに1,000人規模にまで拡大していて、無視できないほどの才能とエネルギーが渦巻いていました。埋もれた才能を、会社として正式に認め、活躍の場を提供する必要がある。その思いが、制度化に向けた大きな原動力となりました。
人事部門の危機感が処遇制度を3ヵ月で整備した
ボトムアップの熱意が大きな原動力となった一方で、会社として制度化に踏み切った背景には、どのような課題があったのでしょうか。
安田:私が現職に就いた2023年4月当時は、優秀な生成AIエンジニアのリテンションが大きな課題でした。IT業界全体で人材獲得競争が激化しており、特に若いエンジニアにとっては、転職した方が大幅な給与アップを見込めるケースもありました。
実際に、社内で優秀なAIエンジニアが転職するという事態が発生し、人事部門も強い危機感を抱いていました。破格の条件を提示して個別に慰留するといった、いわば「一本釣り」のような対応では根本的な解決にはなりません。専門性の高い人材に報いる仕組みを早急に構築する必要に迫られていました。
佐野:2023年10月、生成AI活用に向けたタスクフォースが社内に発足したことが大きな転機でした。Bordersでの課題意識を役員に直接伝えると、前向きな反応が返ってきたのです。手当のことは頭になく、「社内に埋もれている生成AIエンジニアを認めてほしい」「スキルを生かす場がほしい」という思いで提案したのですが、むしろ役員の方が「市場価値の高い人材にしっかり評価と対価を与えるべき」と後押ししてくれました。
正直なところ、人事制度にまで踏み込むとは想像していなかったので、この展開には驚きました。制度運用後は、インセンティブはモチベーションにつながり、会社への貢献意欲をさらに高める大きな力になるのだと実感しました。
安田:人事部門が抱えていた危機感と、現場から上がってきた課題感が、経営層の強いリーダーシップによって一気に結びついたのです。経営会議でトップから「このままでは駄目だ」というメッセージが繰り返し発信され、変革への機運は高まっていました。
役員の承認を受けてからわずか3ヵ月で制度を設計したのは、人事部門としてかなり思い切った改革です。手当を支給するため、処遇に関わる人事制度を変更する必要がありました。労働組合との交渉も含め、年単位の時間がかかってもおかしくありません。それを3ヵ月で実現したスピード感こそ、今回の取り組みで最も特筆すべき点だと考えています。

急ピッチの中でも信頼性と公平性を丁寧に議論
3ヵ月という短期間での制度化にあたって、特に工夫された点や、注力した点をお聞かせください。
安田:最も注力したのは、制度としての「信頼性」を担保することです。手当という直接的なインセンティブを設ける以上、認定プロセスが曖昧では、社員から共感と信頼を得られません。「あの人がなぜエキスパートなのだ」という不満が出てしまえば、制度そのものの価値が毀損されてしまいます。
そのため、評価基準の策定には細心の注意を払いました。筆記審査だけで認定するのか、面接が必要か。面接を行うとすれば、どのレベルから対象とするのか。先進AI戦略企画課と人事部門が何度も協議を重ね、具体的な審査プロセスを作り上げました。
佐野:制度設計の際、人事部門がとても丁寧に検討していたのが印象的です。生成AIをどのように定義するのか、エキスパート認定後の働き方はどうするか。細かいところまで、一つひとつ議論を重ねていました。
エントリーに上司の承認を不要とした点も、画期的だと思います。初めは上司の承認を必要として進めていたのですが、生成AIに理解のない上司だった場合、エントリーしづらくなるという懸念が浮上しました。そこで、「部下が応募していることを把握してもらう」という目的の「確認」にとどめたのです。心理的なハードルを感じることなく、誰もが自身のスキルを試せるようになりました。

現場の視点を取り入れた制度設計が、信頼性につながっているのですね。
安田:一方で、人事部門としては「公平性」に関する議論もしなくてはなりませんでした。「なぜ生成AI領域だけが特別扱いされるのか」「他の専門領域はどうなるのだ」という声が上がることが予想されたからです。自動車開発には、自動運転技術やバッテリー開発など、他にも重要な専門領域は数多く存在します。
最終的には、生成AIの重要性と変化のスピードは異質だという社会的な共通認識に後押しされた面もあります。しかし、私たちはこの制度をAI限定の特別立法にするつもりはありません。今後、会社が必要だと判断すれば仕組みを応用していくという方針で、まずはやるべきところから迅速に始める決断に至りました。
処遇に関わる制度を導入するにあたり、苦労された点はありましたか。
安田:資格制度であり、同時に処遇制度でもあるこの仕組みは、人事制度の根幹に関わるものです。通常の手続きを踏めば、これほどの短期間での導入は不可能でした。
今回はアドオン(追加)の仕組みであること、そして何よりも「この変革を今、成し遂げなければならない」という全社的な熱量が、あらゆる障壁を乗り越える力になりました。経営層、現場、そして私たち人事部門が、それぞれの立場で「これはやるべきだ」という強い意志を共有できたこと。それが、常識を覆すスピードを実現した最大の要因だと思います。
Hondaはもともと「スピード感」を重視する会社ですが、組織が大きいこともあり、人事制度の変革などは、時間をかけて慎重に検討してきました。全社の制度を抜本的に変えるものではありませんが、現場からの声を出発点に、埋もれている才能、熱意に光を当てる今回のプロセスは、Hondaが大きく変わる原点になり得ます。長年人事部門に携わっているので、このスピード感は画期的だと感じています。
個人の熱意を企業の競争力へ。柔軟かつ大胆な人事施策を
制度が導入され、多くのエキスパートが活躍されています。あらためて、この一連の取り組みが会社や社員にどのような変化をもたらしたと感じていますか。
佐野:最も大きな変化は、同じ志を持つ「仲間」が可視化され、部門を越えた情報交換が活発になったことです。エキスパート同士がつながり、互いの知見を共有することで、学習スピードがさらに加速しています。
また、会社から公式に「エキスパート」として認定されたことで、自部門での発言力が増し、「自分の業務を認めてもらえるようになり、やりがいが向上した」という声も多く聞かれます。個人の活動が、会社の正式な業務として認められ、組織に貢献できるようになった。この意識の変化は、極めて大きいと感じます。
安田:これまで個人のコミュニティの中で完結していたエネルギーが、会社のプラットフォームに乗ることで、明確なアウトプットに結びつくようになりました。これは、まさに人的資本経営の考え方を具現化したものだと言えます。
今回の取り組みを通じてあらためて認識したのは、事業戦略や経営戦略と連動した、スピーディーな人的資本施策の重要性です。変化の激しい時代に、時間をかけて制度を検討していては、ビジネスチャンスを逃してしまいます。その時々で必要な人材要件を定義し、いかに迅速に人材を確保・育成・リテンションしていくかが問われているのです。そのために、私たちは常に現場にアンテナを張り、社員一人ひとりの熱意や才能を察知しなくてはなりません。
個人の「こうありたい」というエネルギーと、会社の「こうなってほしい」という方向性を、スピーディーに結びつけていく。その結節点としての役割を担うことこそが、これからの人事部門に求められる使命だと考えています。
さらなるAI活用に向けた展望を教えてください。
佐野:自動車のデザインで使用するCADのデータは、世の中にそれほど多く出回っていないため、生成AIの学習があまり進んでいない領域です。こういったHondaならではの領域、得意領域を強化したいですね。部門の壁を超えたAI活用をさらに進め、人とAIが共存し、わくわくするような、HondaのAI活用を突き詰めていきます。
安田:生成AIの進化は止まりませんが、それを本当に生かし切れているのか、という議論が出ています。処遇、教育、そして採用。活用を加速させるための人事施策に取り組まなくてはならないと考えています。
私たち人事部門のメンバー自身が生成AIへのアンテナを高くしなくてはと考え、人事統括部内で、生成AIを活用した事業変革施策を募集する「AIデアコンテスト」を開催しました。全メンバー700人を対象に勉強会も開いています。引き続き、人事部門内のAIスキルを高めていきます。
最後に、読者である人事パーソンにメッセージをお願いします。
佐野:今回の取り組みは、決して特別なものではないかもしれません。しかし、この小さな仕組みで社員の表情が変わり、組織の風土に「もっと挑戦しよう」という新たな芽が生まれました。大きな企業でも変わることができる。仕組みが変われば、人は変わります。HRの重要性をあらためて実感しました。
安田:人事部門の仕事は、ルールを作ることや、制度を運用することだけではありません。現場で燃え上がろうとしている「火」を見つけ出して燃料を注ぎ、さらに大きな「炎」へと育てていく。その炎を、事業や経営が乗り越えるべき課題、現場のニーズを照らす光へとつないでいく。このプロセスを、スピード感を持って進めることが重要です。
規則や法律など、人事部門の業務には守らなくてはならないことがたくさんありますが、過去の慣習やルールに縛られていてはいけません。未来に向けて会社はどうあるべきか、社員一人ひとりは何を望んでいるかを起点に、柔軟かつ大胆に施策を打っていくべきです。その積み重ねこそが、競争力の源泉となる「人」を輝かせ、ひいては日本全体の活力を高めることにつながると信じています。
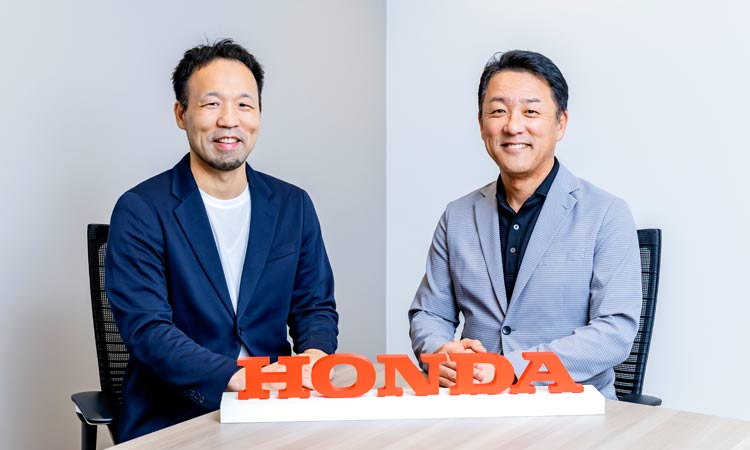
(取材:2025年10月6日)
この記事を読んだ人におすすめ

人事・人材開発において、先進的な取り組みを行っている企業にインタビュー。さまざまな事例を通じて、これからの人事について考えます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる1
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント












