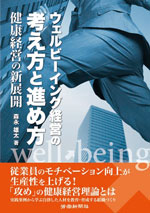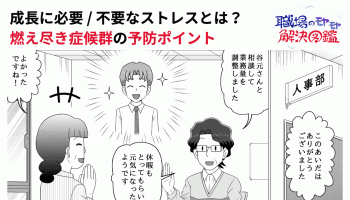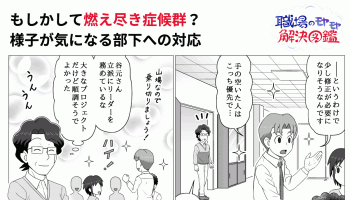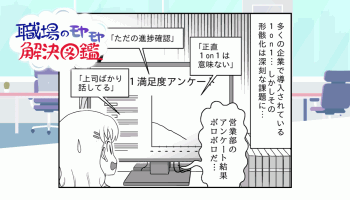職場のモヤモヤ解決図鑑
【第24回】健康経営は何から始める?
導入ステップと支援ツール、成功事例を紹介
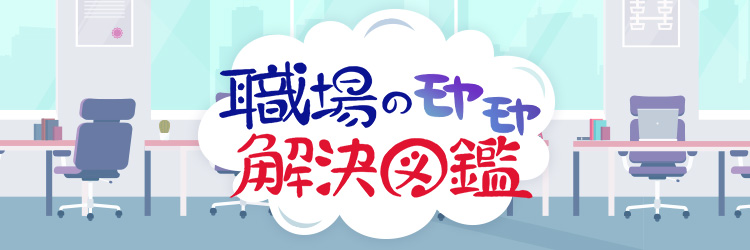
自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。昔思い描いていた理想の社会人像より、ずいぶんあくせくしてない? 働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!


-
吉田 りな(よしだ りな)
食品系の会社に勤める人事2年目の24才。主に経理・労務を担当。最近は担当を越えて人事の色々な仕事に興味が出てきた。仲間思いでたまに熱血!
禁煙支援や運動習慣支援、メンタルサポートに働き方改革……健康経営の取り組み範囲は多岐にわたります。何から始めたらいいのか、人事部長も吉田さんも悩んでいる様子。健康経営をはじめるにあたり、何から手をつければいいのか、基本ステップとポイントを解説します。
健康経営をはじめるための五つの基本ステップ
健康経営の導入ステップは、「健康経営を明文化する」ところから始まります。四つの基本ステップを見ていきましょう。
ステップ1:健康経営を明文化する
明文化とは、経営トップが健康経営を経営課題の一つに位置付けるとメッセージを発することです。企業のコーポレートサイトや全社会、株主総会資料など、社外・社内の両方で発信します。これにより、健康経営が全社的な取り組みであることを印象付けられます。
ステップ2:健康経営の運用体制を整える
次に必要なのが、健康運営の施策を展開する部署や担当者を決めることです。新たに健康づくり担当者を任命するほかに、既存の安全衛生委員会の組織が役割を担うこともあります。
社長直轄のプロジェクトとして専任チームを立てれば、社内横断的な動きが期待できるでしょう。
ステップ3:従業員の健康意識や、自社課題の把握
健康経営の具体的な取り組みは、「現状把握」「目標設定」「対策実行」が基本セットです。自社の課題に沿った対策を進めるために、まずは健康診断の受診率や受診データ、ストレスチェックの結果など、自社のデータに立ち返り、手を付けるべきポイントを見極めます。また、アンケートなどを使い、従業員が健康に対してどのような意識を持っているのかを認識することも大切です。
ステップ4:具体的な施策に取り組む
課題が明らかになったら、解決のための具体的制度や施策を検討し、目標を設定して取り組んでいきます。
具体的な取り組みや目標を設定するうえでは、協会けんぽの各事業所の事例(健康づくり宣言や健康づくりチャレンジ宣言)も参考になります。
健康経営の先進企業の事例を紹介します。企業ごとにさまざまな課題があり、社員の特性によって取り組みも異なります。

常識にとらわれず、PDCAを回し続ける
生産性向上に直結したフジクラ流・健康経営とは

最先端のIoT導入と健康経営を生かした
WILLER EXPRESSの行動変革施策

DeNAが取り組んだ健康経営
“プレゼンティーイズム”の解消とは
ステップ5:取り組みを評価する
健康経営の最終目標は、企業の業績向上です。しかしながら、具体的施策の効果を経営面で実感するには長い時間がかかります。定期的に取り組みを評価する機会をもうけ、PDCAを回しながら改善していくことが重要です。
おすすめは、取り組み開始から最終目標までを3段階に分け、それぞれに指標を設けて評価することです。はじめは「施策の取り組み状況」として、健康教育等のプログラムへの参加率や満足度を指標とします。その次の段階では「従業員の意識・行動変容」を見ます。その際は、実際に禁煙できた人の継続率など、変化の数値が成果をはかるポイントです。そして最後に、従業員の健康状態・精神状態・就業環境などの「最終的な目標数値」を達成できたかを測ります。
人への作用を重視する 健康投資効果の可視化と検証ポイント
健康経営の成果を見える化するポイントは森 晃爾先生のインタビューをチェック。

人への作用を重視する
健康投資効果の可視化と検証ポイント
健康経営を進めるために知っておくべきポイント
健康経営を実施するために、知っておくべきポイントについてみてみましょう。
健康経営に対する二つのアプローチ方法
人々の健康を促進する方法には「ハイリスクアプローチ」と「ポピュレーションアプローチ」の2種類があります。
ハイリスクアプローチ
健康リスクを抱えた人を主な対象とした取り組みです。重症化させないために、保健指導などを行います。健康リスクが顕在化しているため、取り組みの費用対効果は高いものの、1回の指導では成果が表れにくいという側面があります。
ポピュレーションアプローチ
集団の大部分の人の健康リスクを軽減する取り組みで、予防的な意味を持ちます。健康教育、運動推奨、メンタルヘルス対策が一例です。コストがかかりますが、方法次第では従業員の活性化や組織の一体感の醸成につながります。
自社の従業員の健康状態を把握し、二つのアプローチを並行して取り入れることが重要です。
「ゼロからプラスへ」という健康経営の取り組み
健康経営で目指すのは、従業員が活力ある状態でいきいきと働けることです。それには、喫煙率の低下や生活習慣病のリスク改善など「マイナスをゼロにする」施策のほか、「プラスを生み出す」発想から生まれる施策がポイントとなります。
「病気でない状態であれば健康だ」と位置付けていると、健康経営の取り組みが個人の問題として考えられがちです。丸井グループでは、健康経営に取り組むにあたって、「輝くようにいきいきしている状態」である「ウェルネス」という言葉を使うようにし、病気や不調がない状態の従業員も巻き込んでいきました。また、ヤフーは社員の「コンディション」を良くし、パフォーマンスを上げるという観点で健康経営を進めています。
「ゼロからプラスへ」の発想があれば、ワークライフバランスの推進やチーム内のコミュニケーション活性化、病気の治療と仕事の両立支援など、就業環境を整えていくことも健康経営に必要な取り組みとして受け入れられるでしょう。
「ゼロからプラスへ」の発想で健康経営に取り組む企業のインタビュー

「手挙げ式」のグループ横断プロジェクトで、
社員が自ら活力向上に取り組む社会とつながるウェルネス経営

従業員は事業を動かすプロフェッショナル
ヤフーが進めるコンディショニング発想の健康経営
中小企業での健康経営の推進に役立つ事例集やガイドライン
健康経営の取り組みを考える際は、他社の事例集やガイドラインも役立ちます。
| 健康宣言リーフレット|協会けんぽ |
|---|
| 取り組むべき項目を必須項目と選択項目に分かれています。健康経営にはじめて取り組む中小企業でもわかりやすく参考になります。 |
| 健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)認定法人 取り組み事例集 |
|---|
| 健康経営優良法人に認定された企業の、具体的な取り組みのほか、きっかけや効果などがまとまっています。 |
| 健康投資管理会計ガイドライン |
|---|
| すでに健康経営の取り組みを始めている企業向けです。経営課題解決のための健康経営の実現という視点から作成されています。 |
| 健康投資管理会計作成準備作業用フォーマット |
|---|
| すでに健康経営の取り組みを始めている企業向けです。より投資効果の高い健康経営の取り組みに向けた実務用のフォーマットです。 |
健康を経営理念とリンクさせ、できるところからはじめよう
健康経営の取り組みの延長線には、「社会に求められる企業とは?」という問いがあります。あるべき組織の姿になるために、従業員一人ひとりがどのような状態で働けるのが理想なのかを念頭に置くことで、「健康への取り組み」と「経営課題の改善」が結びつきます。
大きな変更を行ったり、予算をかけたりしなくても、日常的で小さな取り組みから健康経営を始めることができます。定期健診の周知の徹底や休憩時間でできるストレッチの紹介など、できるところから取り組んでいきましょう。
【まとめ】
- 健康経営の明文化、実施のための組織づくりが第一歩
- 定期健診やストレスチェックなどを通じて健康課題を把握する
- 従業員が活力ある状態で働けるよう「プラスを生み出す」施策が健康経営のポイント
- 既存のガイドラインや他社事例を活用しよう
オススメ書籍
ウェルビーイング経営の考え方と進め方 健康経営の新展開
改訂版 企業・健保担当者必携!!成果の上がる健康経営の進め方
この記事を読んだ人におすすめ
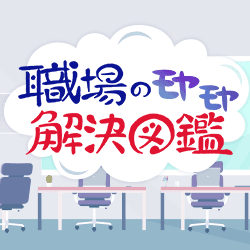
自分のことだけ集中したくても、そうはいかないのが社会人。働き方や人間関係に悩む皆さまに、問題解決のヒントをお送りします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント