日本の人事部「HRアワード2025」受賞者インタビュー
変革とは「自分たちであり続ける」こと
――父への思いを越えて、「構造的無能化」を
論じることが必要だった
埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 教授
宇田川 元一さん

多くの企業が「変革」の必要性を叫びながら、なぜ進展しないのでしょうか。『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』で、日本の人事部「HRアワード 2025」書籍部門優秀賞を受賞した埼玉大学大学院の宇田川元一さんは、根幹に「構造的無能化」という病巣があると言います。緻密な論考の裏には、「父への思いから自由になるためだった」という、著者自身の強烈な原体験と個人的な戦いがありました。「人生の賭けだった」と語る執筆過程でつかんだ変革の真義と、人事パーソンに「同志」として伝えたいメッセージとは――。
「HRアワード」の詳細はこちら
- 宇田川 元一さん
- 埼玉大学大学院 人文社会科学研究科 教授
うだがわ・もとかず/専門は経営戦略論、組織論。ナラティヴ・アプローチに基づいた企業変革やイノベーション推進の研究を行っている。また、さまざまな企業のアドバイザーとしてその実践を支援。近著『企業変革のジレンマ 「構造的無能化」はなぜ起きるのか』(日本経済新聞出版(日経BP))は「HRアワード2025」書籍部門優秀賞を受賞。他に『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング、「HRアワード2020」書籍部門最優秀賞)、『組織が変わる――行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法2 on 2』(ダイヤモンド社)の著書がある。
「変革」のためには、「面倒くさい」ことに向き合う
ご著書『企業変革のジレンマ』が「HRアワード2025」書籍部門 優秀賞を受賞されました。感想をお聞かせください。
本書は、主に経営者の方々に向けて執筆しました。そのため、人事パーソンの方々が中心の「HRアワード」での受賞は、正直なところ難しいと思っていました。受賞の知らせには少し驚きました。
本書で論じている、変革プロセスを組織内部から支える「変革支援機能」は、まさに人事部門や経営企画部門の方々が担うべき役割と言えるでしょう。旧来の人事という枠組みから、「経営から人事を見る」という視点、つまり経営から自分たちを見るという視点の動きを感じ取ってくれた方が、少なからずいらっしゃったのかもしれません。
コロナ禍を経て、世界が大きく変わったにもかかわらず、自社の変革が進まないことに焦りを感じている企業は多いのではないでしょうか。コーポレートガバナンス改革、GX(グリーントランスフォーメーション)、人的資本経営の開示、アクティビストの台頭など、企業は本質から変わらなければならない状況に直面しています。
そのような中で、私は変革に関する本を書かなければならないと考えました。ただ、無駄に焦りを生み出しても良いことはありません。大切なのは、地に足のついた変革をどう進めるかです。
多くの企業から「成功事例を教えてください」「エンゲージメントの数字を上げる方法を教えてください」といった、解決策の模索に偏った相談を受けます。しかし、「HRアワード」の表彰式のスピーチでも申し上げましたが、そもそも「なぜ問題が起きているのか」「どのような構造で生まれているのか」という、問題の捉え方自体を考えるプロセスが抜け落ちていることが多いのです。
そのようなアプローチは「面倒くさい」ものです。今回の受賞は、その「面倒くさいこと」の重要性に気づき、向き合おうとされている方々が増えてきた証左かもしれません。その点でも評価していただけたのであれば、うれしく思います。

「HRアワード2025」表彰式での宇田川さん
本書の執筆の原点には何があったのでしょうか。
2021年の4月に前著『組織が変わる』を出版した直後くらいから考え始めていたのですが、原点には「『一人のカリスマ経営者が会社を変えた』という変革に広く普及している物語は、本当に妥当か」という問いがありました。
多くの場合、財務的に回復することを「会社が変わった」と考えます。もちろん、瀕死の状態を立て直すことは重要でしょう。リストラをしなければならないこともあります。しかし、その成果をカリスマ経営者に帰してしまうと、多くの人がその人に「依存」するようになってしまいます。それは、会社が変わったと言えるのでしょうか。むしろ、長い目で見て、変革とは反対の方向に行っていないか。
一人の強いリーダーに面倒くさい問題の解決を頼るようになり、自らが思考することを放棄するようになる。それが依存の構造を生む。組織としての力が落ちていく。誰か特定の「変革する人」が変革を行う構図は、サステナブルではありません。
宇田川さんが考える「サステナブルな変革」とは、どのようなものでしょうか。
組織としての能力を高めていくことです。「組織の能力が高まる」とは、さまざまな変化の兆しを捉え、新しいことに取り組みながら、自分たちらしさ、つまり自社の伝統の上に次の伝統を築いていくことです。
そのような変革を実現するにはどうしたらよいのかを議論している本は、世の中にない。『V字回復の経営』といった、劇的な変革を論じた本はあっても、緩やかに衰退していく「慢性疾患」に対する地道な変革を論じた本は、一般向けにはほとんど見当たりませんでした。理論研究者として、この問題は論じなければならないと強く思いました。
「構造的無能化」という病巣
その核心にあるのが「構造的無能化」という概念だと思いますが、どのようにしてこの言葉が生まれたのでしょうか。
2022年の9月頃でした。ある方とのディスカッションの中で、組織が陥っている状況を「これは構造的に無能化されてしまう感じですね」という言葉が自分からふと出てきて、「これだ」と直感しました。
もともと組織論の研究には、カール・E・ワイクという研究者が提唱した「適応が適応可能性を排除する」という重要な命題があります。ある事業環境にうまく適応したことによって、かえって違う環境認識を持つことが難しくなる。「強みが弱みになる」というパラドックスです。当初は、このワイクの理論を丁寧に説明しようと試みたのですが、哲学的で難解なため、読者に伝わらないと感じました。
そんな中、私自身が多くの企業に関わる中で、何度も奇妙な現象に直面していました。経営課題として取り組むべきテーマ、例えば新規事業や人事施策について、その意義が変革の推進側と受け手で全く違う解釈になっている。受け手の側は、「言われたから処理する」という、既存の業務の延長線上で解釈してしまうのです。
受け手も決して愚かな人たちではなく、むしろ優秀な方々です。しかし、変革の命題を、既存事業を回す枠組みの中で解釈する。だから「わからない」。あるいは、直感的にわかると面倒だからシャットアウトする。それは既存事業や業務の短期の成果からは合理的な判断です。でも、推進側はわかっていないのではないかと、わからせようとする。そして行き詰まる。そうしたことが、一社だけではなく、多くの企業で繰り返し起きていました。まさに「適応が適応可能性を排除」している状態です。事業の最適化が進むことで組織が断片化し、必要な変化が滞る。このメカニズムを、私なりにひも解かなければならないと強く感じました。

「父への思いから自由になる」ための戦い
その「構造」への強い問題意識は、もともとはどこから来ているのでしょうか。
私の原体験は、経営者だった父がバブル期に銀行の話にのせられて多額の借金を背負い、貧しい思春期を過ごしたことです。父は私が大学院生の頃にがんで亡くなり、私自身がその「敗戦処理」を経験したことは深い心の傷となっています。
父と同様に、人生を狂わされた経営者を多く見てきましたが、当時、中小企業にお金を貸していた銀行員も個々は悪人ではなかったはずです。そこで、「なぜ一人ひとりは悪人ではないのに、結果として多くの悲劇が起きてしまうのか」という問いが生まれました。この問いこそが私の経営学者としての探求テーマであり、今回の「構造的無能化」という問題意識の根幹につながっています。
1冊目の『他者と働く』、2冊目の『組織が変わる』は、父との経験から来る、世の中に対する怒りや悔しさが執筆の直接的な燃料になっていたように思います。しかし、負の感情は瞬発的なエネルギーにはなっても、持続しません。3冊目となる本書では、個人的な怒りや悔しさを燃料にすることから自由になりたかった。父の経験をきっかけに生まれた「構造の罪」という経営学的な探求テーマを25年間研究してきた私が本当に論じるべきことを書くんだ、という強い思いがありました。
これまでの著作によって、私がコミュニケーションや狭義の「対話」の人だと思われてしまったことへの悔しさもありました。上司と部下とのコミュニケーション研修を依頼されることもありましたが、私の本意はそこではありません。もっと経営や変革そのものを論じたかったのです。個人的な過去の体験や思いから脱却し、研究してきた「経営」や「変革」そのものを論じる本書を書き終えられるかどうかは、私にとって人生の大きな賭けでした。
書き終えたときに鳴り響いた「ゴルトベルク変奏曲」
執筆はどのように進みましたか。
2021年から 2023年にかけての執筆期間中、コロナ禍で一人の時間が多く、自分自身の内面と向き合わざるを得ませんでした。
構成は、初めに決めた企画書通りには全く進みませんでした。アジャイル開発のように、書きながら考え、考えながら書き直す。順番通りに書いたわけではなく、4章、5章、6章あたりを書きながら2章や3章に戻ったり、途中で重要なことが抜け落ちていると気づいて、また最初から書き直したりしました。
■『企業変革のジレンマ』の目次
- 序章│企業変革のジレンマにどう挑むか
- 第1章│あなたの会社で今、起きていること
- 第2章│ 企業変革に必要な4つのプロセス
- 第3章│ 構造的無能化はなぜ起きるのか──組織の機能不全のメカニズムを読み解く
- 第4章│ 企業変革に必要な3つの論点
- 第5章│ 「わからない」壁を乗り越える──組織の「多義性」を理解する
- 第6章│ 「進まない」壁を乗り越える──組織の「複雑性」に挑む
- 第7章│ 「変わらない」壁を乗り越える──組織の「自発性」を育む
- 第8章│ 企業変革を推進し、支援する
- おわりに
特に6章の、変革が進まない理由として「トップが戦略を考えていないからだ」と論じる部分で、「なぜ、戦略を考えられないのだろうか」と考えこんでしまい、長い間、筆が止まりました。そして、多くの企業の「戦略」という言葉の使われ方や、実際に策定が進むプロセスを見ると、あることに気がつきました。多くの企業で、戦略は数字を達成するためのロジックとして語られており、「計画策定」とセットで考えられていました。経営企画部門が取りまとめて数字を作り、それが経営陣に承認され、事業部に降りてくる。事業部側は、降ってきた数字のロジックを後から考える。具体的な事業や顧客の課題よりも先に数字が出てくるのです。
経営学者のリチャード・P・ルメルトが著書『戦略の要諦』で述べているように、戦略構想と計画策定は全く別物です。多くの中期経営計画や統合報告書に、目標や数字は書いてあっても、本来の意味での戦略が書かれていないのは、このためです。構造的に、戦略を「考える機会」がそもそもない。だから「考えられるようになっていない」のだとわかり、執筆が再び進み始めました。
さまざまな試行錯誤と苦闘を経て、完成した本なのですね。
執筆過程は本当に地獄でした。もう寝ても覚めても執筆のことを考えていて、夢にも出てくる。1ヵ月ぐらい、ずっとゾンビと戦う夢ばかり見ていました(笑)。執筆期間中、私と連絡を取っていた幼馴染みは「あのとき、宇田川は異常にピリピリしていた」と言っていました。自分では気づきませんでしたが、それほど追い詰められていたのでしょう。
2023年8月末には、コロナに感染して倒れました。強制的に休まざるを得なくなったことで、頭の中でデフラグ(バラバラになったデータが整理されること)が起きたような感覚がありました。余計なものがそぎ落とされたのかもしれません。そのとき、「問題の二重性」という言葉が浮かびました。一気に視界が開け、12月の初めに最初の草稿を書き上げました。
書き終えた直後のことは、今でも鮮明に覚えています。書き終えて、メールの送信ボタンを押した後、頭の中で、バッハの「ゴルトベルク変奏曲」の第30番変奏曲が鳴り止まなかったのです。「ゴルトベルク変奏曲」はピアニストのグレン・グールドが、若き日に鮮烈なデビューを飾った曲であり、彼のキャリアの最晩年に、この変奏曲集を新しい解釈で再録音しました。そして、その最後の第30番変奏曲は、彼の音楽人生にとって結論のような曲です。
後から調べたら、「クオドリベット」と呼ばれ、当時の二つのドイツ民謡を組み合わせた曲なのだそうです。一つは「長い間ごぶさただったね(久しぶり)」、もう一つは「せっかく来たのにキャベツとカブしか食べられなかった。肉でもあったらもっと長くいられたのに」という内容の歌詞だとか。
これは私の解釈ですが、「やっと帰ってきた」という感覚と、「これで終わってしまうのは寂しい」という感覚。書き終えたときの私の心境そのものでした。自分でも、なぜ書き終えられたのかがわからない感覚があります。今でも、書き終えられない世界線を生きている違う自分がいるような気さえします。
変革とは「自分たちであり続ける」こと
執筆の末にたどり着いた、「変革」の真義とは何だったのでしょうか。
書き終えて気づいたのは、「慢性疾患」的な問題としての変革を論じることは、結局「経営」そのものを論じることだった、ということです。
急性の疾患ではなく、慢性疾患と共に生きることが「生きる」ことそのものであるように、組織の慢性的な問題に向き合い続けることが「経営する」ことなのだと。だからこそ、次は「経営するとはどういうことか」をテーマに書かなければならないと感じています。
本書で印象的だったのは「時間軸で考える」「過去の成功体験をひも解く」という記述でした。一般的に、「過去の成功体験」は「変革」の障害になる、と認識されていることが多いと思うのですが、いかがでしょうか。
過去の成功体験が変革の障害になるのは、体験の「中身」が忘れ去られ、制度やプロセスの「側(がわ)」だけが残骸のように残っているからです。なぜその制度ができたのか、なぜ当時はそれが機能したのか、という経緯が忘れられています。
ナラティヴ・セラピーの世界では、「出来事を経験にするのは物語である」と言われます。過去に起きたさまざまな「出来事」も、結び直し方を変えれば、違う「経験」を生み出すことができます。過去の成功体験も、丹念に掘り起こし、その経緯を「結び直す」ことで、「自分たちはこういう基盤を持っていたのだ」という、うそではない組織のアイデンティティーを再構築できるはずです。
変革とは、過去を捨てることではないのですね。
そこが重要な点で、私には変革という言葉の意味を変えたいという思いがありました。ハーバード・ケネディ・スクールのロナルド・ハイフェッツも述べていますが、変革とは、適応(アダプテーション)です。「自分たちが自分たちであり続けるために、変えるべきものを変える」のです。自分たちであり続ける必要がないのなら、変革などせず、会社をたためばよいのです。
宇田川さんは、「本書は解決策を書いたものではない」とおっしゃっていますが、本の後半部分は、解決策とは異なっても、「次への道筋」や「方向性」を示しているように感じました。
そういう思いはありますね。いろいろと考えた結果、「変革のためには、こちらに向かったほうがいいと思うけれど、皆さんはどう思いますか」という感覚です。人事の方々が次に向かっていけるような道筋、例えば「変革支援機能」や「経営のファシリテート」といった方向性を、後半で見いだしてくださったのであれば、非常にうれしいことです。
もちろん、そう主張するために、論拠を積み重ねた上で「こうではないか」と提示しているつもりです。これが単なる抽象論ではないことは、きっと伝わると思っています。
最後に、読者である人事パーソンの方々へ、メッセージをお願いします。
変革に取り組むとき、少なからず会社への違和感や不満が原動力としてあるかもしれません。しかし、一番大事なのは、関わる仲間、あるいは顧客といった「人」です。その人たちに、どうなってほしいのか。変革や会社を動かすための「道具」として人を見るのではなく、哲学者のマルティン・ブーバーが言う「我と汝」の関係、つまり、一人の人間として相手に向き合い、「こうなってほしい」と願う、愛や愛着のようなものが必要です。
テクニックで「うまくやろう」としても、必ずバレます。皆、そういうところを一番よく見ていますから。むしろ、「ちゃんと失敗する」ことが大切です。「ああ、自分は今、うまくやろうとしていたな」と気づくこと。それ自体が、変革の大きな一歩です。そうした失敗や気づきを積み重ねた結果、5年後に「少し会社が変わったかな、自分も変わったかな」と感じられる。それが変革の本当の姿ではないでしょうか。
大事なのはスキルや優秀さよりも、「なんだかんだ言っても、この会社が好きだ」という会社への愛着です。その思いを忘れずに、人間を相手にしているという原点に立ち返って、取り組んでほしいと思います。
私にとって本を書くことがそうであるように、皆さんも変革に取り組む「同志」です。本書が、変革に取り組むきっかけになれば、著者としてこれほどうれしいことはありません。一緒に頑張っていきましょう。

(取材:2025年10月20日)
この記事を読んだ人におすすめ
-
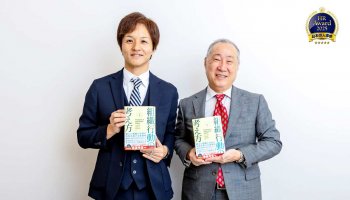
高橋潔さん・服部泰宏さん: 「組織行動の考え方」が届ける“元気” HRの未来は「心理と感情を束ねる場づくり」にある
-

名古屋鉄道株式会社: 名古屋鉄道の「介護離職ゼロ」に向けた挑戦 「まずは気軽に相談してほしい」という、人事部からのメッセージ
-

中外製薬株式会社: キャリアは会社が与えるものではなく、社員が自ら創るもの 「個」の主体性を覚醒させる、中外製薬の人事制度改革
-

西田政之さん: CHROに求められるのは制度の設計ではなく「関係性の土壌」を育むこと YKK AP 西田氏が語る“組織の気象予報士”としての人事哲学
-

木下達夫さん: 世界中の現場で学んだ「人事は運用が8割」 一人ひとりのポテンシャルをアンロックして、パナソニックから日本の人事を変える

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる1
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







