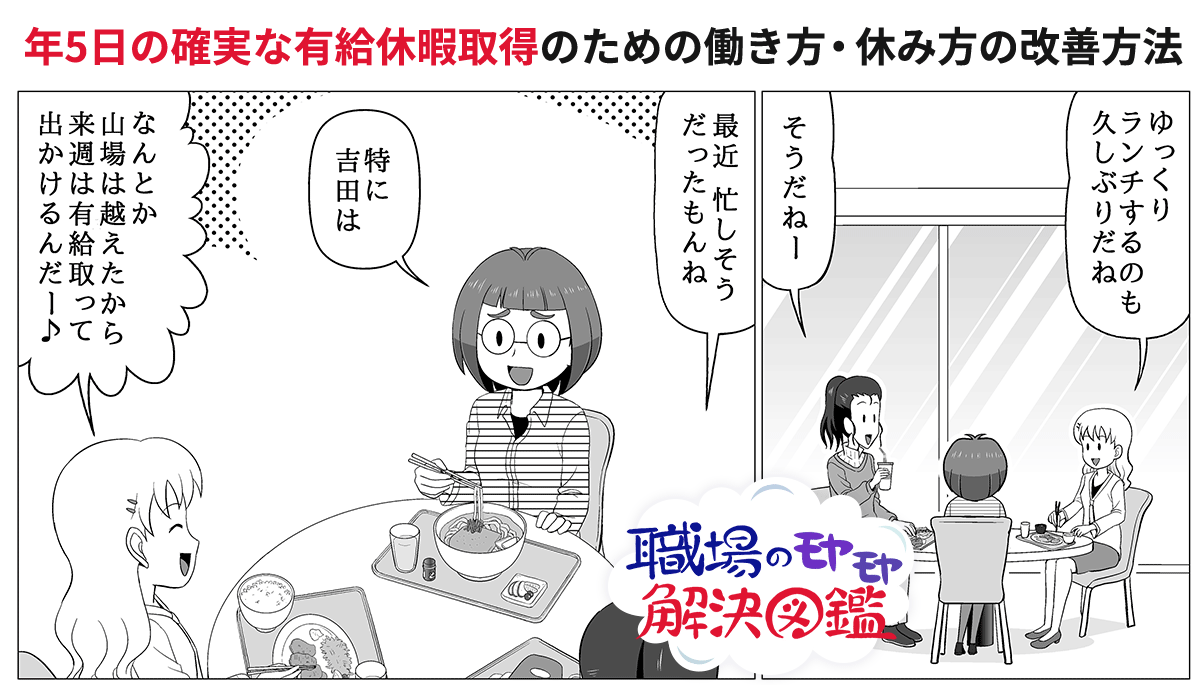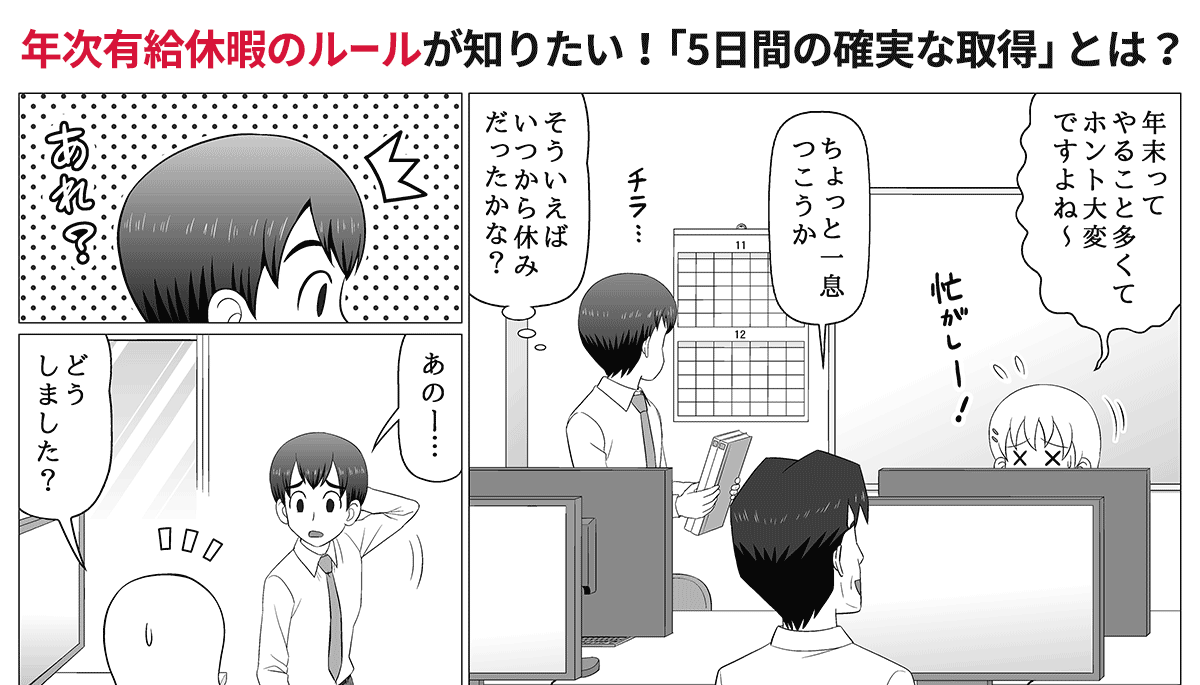有給休暇の付与基準日の変更について
いつも参考にさせていただいています。
有給休暇付与基準日の変更についてお伺いします。
現在、当法人の有休休暇の付与基準日は8月6日としていますが、近々これを従業員の入社日の6か月後に変更する予定(全従業員)です。
10年以上前の4月1日(基準日10月1日)に入社した従業員(従前であれば8月6日に20日付与される従業員)を例にすると
①
R6.8.06 付与日数20日
R7.8.06 付与日数03日(基準日までの案分)
R7.10.1 付与日数20日
R8.10.1 付与日数20日
と考えていたのですが、これまでは本来の基準日(10.1)より前倒し(8.6)で付与されていたとして、監督署より
②
R6.8.06 付与日数20日
R7.8.06 付与日数03日(基準日までの案分)
R7.10.1 付与日数17日
R8.10.1 付与日数20日
となる、という回答がありました。
監督署からは「R7.8.6~R8.10.1までに計20日の付与、その後は1年後の10.1に20日付与で問題ない。」とのことです。
②の場合、R7.8.6~R8.10.1(約1年2カ月)で20日付与となります。3日+17日の分割付与という考えであればR8.8.6に20日付与されるべきと考えますがいかがなものでしょうか。
こちらとしては①の考え方の方が妥当だと考えています。
説明が難しいのですが、ご教授いただければ幸いです。
投稿日:2025/06/17 16:53 ID:QA-0154060
- なべやんさん
- 宮崎県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
有給休暇の基準日の繰り下げについて 有給休暇の基準日の繰り下げについて質問させて下さい。当社では、9/16と3/16に基準日を設け、有給休暇の斉一的付与を行っています。今回給与の締日の変更に... [2021/10/22]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺いします。入社日に10日を付与し4月1日を基準日とした場合、3月に入社した人は入社日に10日付与され4月1日にまた11日付... [2008/04/11]
-
年休計算基準日の変更について 当社の年休付与制度は、入社半年後に出勤率が8割以上の場合に10日付与し、以後毎年3月11日を基準日として一斉付与をしております。今回、基準日を変更するとい... [2010/03/01]
-
アルバイトの有給休暇の一斉付与について アルバイトの方に有給休暇を付与する場合、1年間の所定労働日数によって付与日数が変わりますが、一斉付与する場合の基準日はいつからになるのでしょうか。例えば、... [2025/02/20]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
基準日変更は、前倒しは可能ですが、
後ろへの変更はできません。
いったん8月6日に付与したのであれば、
少なくとも1年後の8月6日あるいはそれ以前に20日付与する必要があります。
1年後の8月6日に3日だけ付与ということはできません。
投稿日:2025/06/17 18:26 ID:QA-0154071
相談者より
ご回答ありがとうございます。
至急人事内にて再考いたします。
投稿日:2025/06/18 11:20 ID:QA-0154096大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。
結論、ご質問者様のご見解通り、「1」の考え方が適切です。
理由もご質問者様のご見解通りで、「2」の場合は、
R7.8.6~R8.10.1(約1年2カ月)で20日付与となり、
明らかに労働者が不利な取扱いとなります。
今一度、労基署の方へ、回答の取扱いに対する理由(根拠)を加えて、
お尋ねいただくことをお勧めいたします。
投稿日:2025/06/17 18:33 ID:QA-0154073
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従業員に不利にならないよう、至急人事にて再考いたします。
投稿日:2025/06/18 11:21 ID:QA-0154097大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
労基署の言う「R7.10.1に17日付与(2案)」という処理は、過剰付与を防ぐための合理的処理であり、法的には認められるものです。
一方、御法人の(1)のように「03日(案分)+20日(新基準日)」とすることも、過少付与でなければ問題なく、従業員に不利益がなければ許容される方針です。
つまり、
労基署案(2)は「これまで前倒しで与えていた分を調整して付与日数を平準化」
法人案(1)は「従来よりも長い付与期間を設定することになり、従業員に有利」
なので、(1)案を採用することに問題はなく、むしろ安全側の措置といえます。
2.両案の比較と法的解釈
(1)御法人の案(前倒し+案分+新基準日で20日)
日付→内容→付与日数
R6.8.6→旧基準日に通常どおり付与→20日
R7.8.6→新基準日までの案分付与→3日(例)
R7.10.1→新基準日として再設定し、20日付与→20日
メリット:
従業員にとって不利益なし(むしろ少し多め)
新旧の基準日が明確に区切られ、社内での混乱も最小限
実務上、誠実な措置と評価されやすい
留意点:
R7.8.6~R8.10.1の間に計23日与えられることになるため、結果として年20日を超える(やや多い)。
ただし法的には「過少付与でなければ問題ない」ので、違法ではなく、問題視されにくい。
(2)労基署の案(前倒しを調整、1年2カ月で合計20日)
日付→内容→付与日数
R6.8.6→旧基準日に通常どおり付与→20日
R7.8.6→新基準日までの案分付与→3日(例)
R7.10.1→調整して17日付与(合計で20日に)→17日
メリット
1年2か月の期間で「ちょうど20日」付与であり、従来の付与総量をキープ
長期的にみて毎年10月1日で均等な管理が可能になる
留意点
「R7.10.1に20日でよいのでは?」という受け止め方も多く、従業員側が「減った」と感じる可能性あり
人事労務上の説明に慎重さが求められる(「損をしていない」旨の理解が必要)
3.労基署の意図と企業の選択肢
(1)労基署の考え方(2案)の根拠
実質的に1年2か月で20日与えているので、適正な付与である
有休付与は「最低限」であり、企業がそれ以上与える義務はない
(2)御法人が(1)案を採る場合の対応:
「R7.10.1に再度20日付与」としても問題なし(過少付与にならない限り)
就業規則の変更や説明資料には、
「制度変更に伴い、R7年は特例として案分付与+通常付与の2段階とします」
といった明示が望ましい
4.実務的なおすすめ対応
項目→対応
就業規則の変更→「有休は入社から6か月経過時に付与」と記載し、必要に応じて経過措置も明記
社内説明資料→「2025年(R7年)は特例措置として、旧基準日8月に案分付与を行い、10月に通常通り付与します」と明記
対象従業員への個別通知→必要に応じて「新旧で合計何日になるのか」を明示した個別通知が安心です
5.まとめ
法的には(2)案も(1)案も認められます。
(1)案の方が従業員に有利であるため、過少付与にさえならなければ妥当です。
従業員に「不利益ではない」ことを丁寧に説明すれば、(1)の対応でも労基署に問題とされる可能性は低いです。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/17 18:43 ID:QA-0154074
相談者より
ご回答ありがとうございます。
メリットデメリット合わせて、従業員の不利にならないことを第一に、また理解してもらえるよう人事にて再考いたします。
投稿日:2025/06/18 11:23 ID:QA-0154098大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
お考えのとおり、①が妥当です。
監督署の回答は、あくまで②で問題はないですよといっているだけで、必ず②にするようにとはいっていないはずです。
ですから、御社が①で運用するのであればそれで問題はありません。
投稿日:2025/06/18 08:34 ID:QA-0154080
相談者より
ご回答ありがとうございます。
おっしゃる通り、労基は最低限の保証内容を提示していると感じています。
至急、人事にて再考します。
投稿日:2025/06/18 11:26 ID:QA-0154099大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
有給休暇の基準日の繰り下げについて 有給休暇の基準日の繰り下げについて質問させて下さい。当社では、9/16と3/16に基準日を設け、有給休暇の斉一的付与を行っています。今回給与の締日の変更に... [2021/10/22]
-
年次有休休暇斉一付与 年次有休休暇斉一付与についてお伺いします。入社日に10日を付与し4月1日を基準日とした場合、3月に入社した人は入社日に10日付与され4月1日にまた11日付... [2008/04/11]
-
年休計算基準日の変更について 当社の年休付与制度は、入社半年後に出勤率が8割以上の場合に10日付与し、以後毎年3月11日を基準日として一斉付与をしております。今回、基準日を変更するとい... [2010/03/01]
-
アルバイトの有給休暇の一斉付与について アルバイトの方に有給休暇を付与する場合、1年間の所定労働日数によって付与日数が変わりますが、一斉付与する場合の基準日はいつからになるのでしょうか。例えば、... [2025/02/20]
-
有給休暇付与日数 非常勤職員で、1日8時間週3~4日の不定期勤務の場合の有給休暇付与日数は何日になりますか [2025/12/21]
-
年休付与基準日を設ける場合 年休付与基準日を(例えば4/1)設けた場合、入社後6ヶ月の付与日数10日を、日割りして付与ができますか。例)5月21日入社→6ヶ月後(12/21)本来10... [2019/03/13]
-
有給休暇の一斉付与 有給休暇の一斉付与について教えていただきたいです。うちの会社では4月1日を基準日としています。9/21に新入社員が入社しました。 その人に半年後、有給休暇... [2024/09/24]
-
有給休暇の前倒し付与 有給休暇の付与基準日よりも前に、「前倒しでの付与」のような特例措置を行うことは、法律上問題ありますでしょうか。例)来年4月1日(基準日)に12日付与予定の... [2009/06/01]
-
有給休暇 基準日統一について 弊社は、パートアルバイトを含め1,000名ほどの企業です。この度、年次有給休暇の基準日を統一したいと考えております。「4月1日を基準日とする」とした場合、... [2019/06/03]
-
有給休暇の基準日と入社日について 有給休暇の基準日と入社日の関係について、ご教示頂けますと幸いです。弊社では就業規則の見直し(作り直しが近いです)に伴い、有給休暇付与について基準日を明確に... [2022/08/19]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント