「人件費の変動費化」で、グローバル競争時代を乗り切る
解説:福田敦之(HRMプランナー/株式会社アール・ティー・エフ代表取締役)
グローバル競争が激しさを増す昨今、景気には減速感が見られ、企業の売上高は頭打ち状態が続いている。一方で、少子化による人材難の影響もあり、「採用」や「育成」などの人材に関するコストの増大が問題となっている。そのような背景を受け、「人件費」の問題が再び大きくクローズアップされ始めた。ここで必要になるのは、従業員にかかる費用のトータル(=総額人件費)という概念である。売上げが不透明な中にあって、この先の総額人件費をどうコントロール(変動費化)していくのかは、経営者や人事責任者にとっての緊急課題。今回は、人件費の変動費化をどう進めていけばいいのかについて、解説していきたい。
なぜ、人件費の「変動費化」なのか
「変動」に耐え得る筋肉質な経営体質への転換
景気拡大の局面にかげりが見え、売り上げが伸びない、あるいは伸びても利益が思うように出ないという声が大きくなっている。事実、日銀が7月1日に発表した6月の企業短期経済観測調査(短観)を見ると、企業の景況感を示す景況判断指数(DI)は大企業製造業でプラス5と、3月の前回調査から6ポイント低下した。原油などエネルギー・原材料の価格の高騰が響いた格好で、3四半期連続の悪化となっている。景気への影響が大きい大企業製造業のDIは2003年調査以来、実に4年9カ月ぶりの低水準となった。今後についても改善に繋がる材料は乏しく、今年度の経常利益については7年ぶりの減益になると見込んでいるという。さらに、設備投資計画も低水準のままで続いており、景気の足取りはいっそう弱まっていると判断するエコノミストが多い。
一方で、経済のグローバル化現象は否応なく日本経済を直撃する。近隣アジア諸国を見ると、政治や経済の情勢の変化が激しく先行きの読めない状況が続いており、アメリカのみならず世界各国からの影響を受けるスピードが一段と早く、かつ影響を受ける領域も増えている。いずれにしても、これまでのような経済成長に疑問符が付き始めた現在、厳しいグローバル競争時代を乗り切っていくために、売上げの変動に耐え得る筋肉質な経営体質を作り上げることが欠かせない条件となってきた。特に、費用のうちの固定費で最も大きな部分を占める「人件費」をどうするか、すなわちどう「変動費化」していくかが、極めて大きなテーマとなってきたのである。
「固定費」を抱えるリスクを避ける
このことは、少し前の出来事を思い出してみるとよく理解できる。バブル崩壊後の「失われた10年」と言われた時期、それこそ血を流すようなリストラ策で低迷期を何とか乗り切っていったのを覚えている方も多いことだろう。その際、当然のことながら「人件費」にも大きなメスが入れられた。
人件費には、「固定費」的な側面と「変動費」的な側面がある。給与のうち、基本給部分は固定費であり、残業代やボーナスは売上高や利益の増減に伴って伸縮するので変動費ということになる。「失われた10年」と言われていた頃、企業の多くは景気の変動に柔軟に対応するため、人件費をできるだけ変動費化しようと考えた。売上げが期待できない状況下にあって、固定費を抱えるリスクを努めて回避したというわけである。
バブル崩壊後、多くの企業は業績を回復したにもかかわらず、基本給のベースアップはできるだけ抑え、ボーナスを増加することで対応していった。というのも、ベアを引き上げると基本給が増加することになるからだ。いったん基本給を上げてしまうと、売上げが落ちた場合に賃金カットが難しくなる。ボーナスで対応するのも、人件費の固定費化を抑制し、不況期での抵抗力を高めるようにするために他ならない。
固定費の削減策は、これだけにはとどまらなかった。正社員の雇用を減らし、パートタイム労働者や派遣スタッフで代替する企業が増えた。さらには、外部労働力としてアウトソーシングの活用を積極的に進めていくケースも見られた。雇用形態の多様化、人材の流動化というトレンドに乗り、「必要な時に、必要な人材を、必要なだけ」という人材活用の考え方の下、人件費全体をできるだけ変動費化していき、不況に強い企業体質を作っていったのだ。
同時に、賃金制度の見直しも進んだ。従来の賃金体系の基幹となっていた年功給的な制度の見直しを行い、能力や業績をベースとした賃金体系が広がっていった。いわゆる「成果主義」の導入である。コストの割高な中高年を中心に苦渋のリストラ策を進めていたこの時期、「固定費」を下げて人件費を「変動費」化する動きが一気に加速していったのだ。これらの努力が、後々の景気回復への大きな原動力となったのは言うまでもない。
人材難による「人コスト」の増大
それが一転、ここ3~4年はバブル期並みの人材不足であり、それまでの状況が大きく変わってしまった。予想を超えた少子化のスピードと人材難に対処するために、企業はさまざまな手を打つ必要があった。何より、優秀な新卒を採用するためには初任給を引き上げなくてはならず、給与水準のベースが上がっていった。一方で、採用が難しいとなると従業員の定着を考えて、成果主義を見直す企業も出てきた。そして、手厚い福利厚生の充実。実際、福利厚生に関する費用について見ると、ここ数年過去最高を更新し続けている。
加えて、これらの動きと歩調を合わせるかのように、変動費化の有効な手段だったパートタイム労働者や派遣スタッフに関して、正社員との「格差」を是正するために法律改正が進んでいった。働く人の3分の1を占めるようになった非正社員というワークスタイルが、格差を生む“温床”であるとの世論の後押しもあり、非正社員の正社員化という動きが加速していったのである。その結果、「人」に関わるコストが再び増大してきたというのが昨今の状況である。
「人コスト」を構成する要素
そもそも、「人件費」とは何か?
このように、人件費の変動費化を考える上で、以前とは前提となる条件が幾つか変わってきた。そこで、「人」に関わるコストについて、今一度整理してみたいと思う。
実は、よく使われる「人件費」という費目だが、いわゆる「決算書」の用語ではない。そのため、人に関わるコストについては、別途まとめて集計しなければならないのである。その「人コスト」を構成する要素を整理したのが、図1および図2である。
図1に示したように、「月例給与」は「所定内賃金」と「所定外賃金」を合わせたもの。「現金給与」はそれに「賞与・一時金」が加わったのもの。そして、「人件費」はさらに「退職金・年金費用」「法定福利費」「法定外福利費」が加算されたもの、という図式になる。
ただし、企業経営にとって重要なのは、従業員を雇用するためにかかる全てのコストである。このような広い意味から「人コスト」を見るとすれば、「教育訓練費」や「採用・募集費」なども含まれると考えるのが妥当であろう。これらをすべて合わせたものが「労働費用」と呼ばれ、「総額人件費」としてとらえるべきなのである。
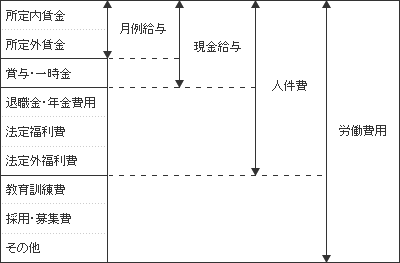
「総額人件費」は「所定内賃金」の1.72倍に
次に、図2を見てほしい。いろいろある人件費の中でも、一般的には「所定内賃金」が60%前後となっており、最も大きなウエートを占めている。そこで問題となるのは、「所定内賃金」が上がると、それに伴って「時間外手当」や「賞与・一時金」「退職金・年金」などの費用も大きく影響を受けるということ。つまるところ、「総額人件費」は「所定内賃金」の上昇分以上に上がる、ということを忘れてはならないのだ。ここが大きなポイントである。
こうした“懸念”を具体的に示すのがいわゆる「はねかえり率」である。少し古いデータで恐縮だが、所定内賃金を1とした場合の総額人件費は、実に1.72となる。つまり、従業員にかかるトータルの人件費は、所定内給与の1.72倍に相当するのである。ちなみに、大企業で2.0前後、中小企業では1.5前後と言われている。これらをどう判断するかは各社の置かれた状況で違ってくるが、人事担当者にとって1つの目安となるだろう。
| 所定内賃金 | 60%前後 | 所定労働時間に対応した賃金 |
|---|---|---|
| 所定外賃金 | 5%前後 | 残業代など |
| 賞与・一時金 | 20%前後 | 毎月の給与とは別に支給されるもの |
| 退職金・年金費用 | 4%前後 | 退職金、年金積み立て等に関わる費用 |
| 法定福利費 | 8%前後 | 健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労災保険料、児童手当拠出金、労働基準法上の休業補償のうち、企業が負担する分(従業員負担分は除く) |
| 法定外福利費 | 2%前後 | 上記以外で企業が任意に行うもの |
| 教育訓練費 | - | 教育訓練に関わる費用 |
| 採用・募集費 | - | 採用・募集に関わる費用 |
| その他 | - | 転勤に要する費用、作業服、社内報費用など |
*内訳の構成割合は、一般的なケースを想定したもの
「総額人件費管理」への考え方
前述したようにバブル崩壊後、多くの企業で「総額人件費管理」を実施していた。そこで、幾つかの企業をヒアリングしてみたところ、以下のようなことが分かった。
まず、総額人件費の管理基準においては、「積み上げ方式で設定する」が最も多かった。その他では、「売上高に対する一定比率で枠を設定する」「労働分配率で枠を設定する」といった方法を採用する企業が見られた。ちなみに、「業界他社の動向を見て決める(特に総額設定はしない)」とする企業があったことも付け加えておく。
これらの中で、最も戦略的な基準と言われているのが付加価値ベースで行う「労働分配率で枠を設定する」方法である。しかし、先々の業績が読みにくい現状にあって、労働分配率で枠を決めるというやり方では、年度による変動がどうしても大きくなってしまう。現実的な状況を考えると、当面は「積み上げ方式」や「売上高一定割合」といった基準が主流となると考えられる。
次に、人件費の項目の中で抑制したいと考えられるのは、「残業手当」や「諸手当」「法定外福利費」などであった。特に「残業手当」については、成果主義への移行がその背景にあるわけだが、その実効力が極めて大きいと考えたのだろう。ただ、福利厚生関係の項目に関しては、削減を行うとしても既得権の問題もあって、「諸手当」のように簡単には削減できない部分もある。
反対に「教育訓練費」などについては、増やしたいと考える企業が多かった。全体的に抑制方向にある中で、企業間の競争がより一層激しさを増していく今後、社内の人材のスキルや専門性を高めるには、ぜひとも必要だということか。こうした人材育成に力を入れるのも、この十数年間で業態や仕事の内容が大きく変化したことで、人材による格差が企業格差を生んでいくと考える企業が増えていったからであろう。
また、総額人件費管理にはこの他にも、「ホワイトカラーの生産性向上」「パート・アルバイトなどの非正社員の活用」「業務の外注化・アウトソーシングの推進」「退職金制度の見直し」「派遣労働者の受け入れ」など、さまざまな方法や考え方がある。いずれにしても、今後の方向性としては、「外部労働力」の活用を考える企業が多くなることは間違いない。内部的な各種施策で対応するより、外部労働力をダイレクトに活用したほうが、人件費の管理においてはより有効だと考えているからである。
人件費を変動費化する「方法」
変動費化実現への3つの「アプローチ」
ここまで見てきたことを踏まえて、次に人件費を変動費化する方法について、具体的に考えていくとしよう。人件費の変動費化への方法としては、短期的な取り組み、中長期的な取り組み、そして賃金以外の取り組みの3方向のアプローチが考えられる。以下、順に見てみる。
(1)短期的な取り組み
●業績賞与
賞与は、個人の年収総額の3割前後を占めると言われている。とはいえ、これは諸外国ではあまり例のない、日本独特の仕組みなのだ。その是非はさておき、問題は「基本給の何カ月分」といった安定的な支給額が確保されていることが前提となっている点である。賞与とは本来、企業業績に連動して支払われるべきものであるということを忘れてはならない。
ただし、賞与については既得権の問題もあるので、そう簡単にいかない。そこで、業績に連動する部分と固定的に支払われる部分とをまずは明確に区分し、業績的賞与は完全に業績に連動される仕組みとすることである。さらに、職位や職責によって、業績連動比率を上げていくといった方法を採用することで、賞与のうちの一部を変動費化していくことができる。
また、業績と連動する部分については、組織目標と個人目標を明確に定め、達成イメージがわくようなものとしていく。そうすることで、業績賞与の増額が実感でき、従業員の労働意欲、動機付けを鼓舞することができる。全体としても、企業業績に対する意識高揚も図ることができる。何より、一定のルールの下で各人の評価に基づいて業績賞与が支給されるので、納得性が高まっていく。このような運用を行っていけば、既得権に対する意識も徐々に薄らいでいくと思われる。
●成果配分制度
月例給与や賞与とは別に、一定期間の生産性向上や目標達成による「成果」を、変動的な金銭給付として配分する方法である。売上げが厳しく賃金水準が下がってしまっている状況でも、このような仕組みを意識的に設けることで、努力と結果が直接的に賃金に結び付くことを示し、従業員のモラールや部門の団結力の向上を誘発することができる。
●年俸制
そもそも年俸制は成果や業績主義に基づいた方法なので、人件費という固定費を業績に応じて変動させる場合、非常に適した制度である。ただ、日本企業で導入されている年俸制は欧米のものとは異なり、「固定的年俸」と「変動的年俸」の2つの要素から構成されている。前者は会社が支給を保証した安定的な年俸であるのに対し、後者は業績への貢献度により変動する年俸である。考え方としては、業績賞与と同じである。
ポイントは、評価基準をはっきりとさせ、納得性を持たせた状態で厳格な運用を行うことである。その結果、格差にメリハリが付いていく。
●個人の賃金の変動費化
年齢給や勤続給などの年功給を廃止し、個人の業績や能力を反映させた実力・実績重視の賃金制度を導入していくこと。具体的には、定期昇給制度やベースアップを廃止し、個人の賃金も個人業績や会社業績に応じて上がったり、下がったりする仕組みを作っていくことである。
●資格等級の「ブロードバンド化(広い括り)」
現在8~10等級もあるような資格等級を、シンプルに3~4等級に半減する、あるいは廃止する方向に持っていく。実際問題として、複雑な等級は昇格査定があいまいになる一方で、降格査定はできないというのが実情である。その結果、下方硬直性を招くことになっている。それよりも、等級が上がることで賃金が上がるというシンプルなシステムのほうが合理的であり、何より変動費化が可能だろう。これまでモチベーション管理のため等級を増やしてきたという経緯はあるものの、今やブロードバンド化は世界のトレンドでもあることを知ってほしい。
(2)長期的な取り組み
●ポイント制退職金
ポイント制退職金を導入することで、人件費の変動費化に貢献していく。具体的には、全体に占める勤続ポイントの割合を少なくし、職能ポイントを多くするという方法が一般的である。
その際、資格等級ごとの点数を上位等級ほど多くし、一般社員と管理職とで格差を設けることにより、能力主義人事を反映していく。また、役職の在任期間に応じて役職ポイントを別途設けるなどの方法により、会社への貢献度をより反映させる形とする。このようなメリハリのある退職金制度とすることで、長期的な人件費の変動費化の実現に結び付いていく。
●ストックオプション
ストックオプションもまた、長期的な取り組みの1つである。何より、長期業績に連動する報酬として、長期の業績向上に取り組むインセンティブを高める効果が期待できる。
(3)賃金以外の取り組み
●人材ミックス
さまざまな就業形態の人材を組み合わせ、固定費化しやすい正社員の比率を下げていく。アルバイトやパートタイム労働者、派遣スタッフなどのフロー人材を活用することにより、労働力を「必要な時に、必要な人材を、必要なだけ」調達する仕組みを作っていくのである。
このような方法によって人件費の変動費化を図る場合には、前提として2つの社内整備が必要となる。1つは、人材ミックスを行うために、誰に何をやってもらうのかを明確にすること。もう1つは、評価制度の確立。個人の業績を正確に測定し、それを処遇に結び付ける仕組みがなければ、従業員の納得を得ることは難しいだろう。その結果、逆にモラールダウンを招く危険性がある点に注意したい。
●業務のアウトソーシング
バブル崩壊後、大手企業の8割以上が何らかのアウトソーシングを導入したと言われている。導入した分野も、経理、総務、人事、企画などの管理部門から、研究開発、営業部門など、あらゆる業務に対象領域が広がっていった。
実際、自社で業務を遂行するよりも専門的なアウトソーサーに任せたほうが、コストは安くなる。何よりも業務のスピードが速く、納期も計画通り。外部に任せることで自社のコア業務へ戦力を集中できるなど、さまざまなメリットがある。まさに変動費化の申し子のような存在である。
変動費化施策を行う際の「留意点」
以上のような変動費化施策を行う場合、留意してほしい点がある。いかにその施策が必要不可欠であり、実施する際に趣旨を丁寧に説明したとしても、従業員はどうしてもマイナスの施策としてとらえてしまうということである。これは、組織における立場の違い上、仕方のない点である。その結果、従業員のモチベーションが下がり、組織・チーム力が低下していった例を数多く見てきた。
しかし、それでも経営者や人事責任者の立場にある人は、これらの施策に対してチャレンジしていかなければならない。避けてはならない、ミッションだからだ。
そのためには、とにかく一人ひとりに対して誠意を持って説明していくことが最も大切だと思う。なぜなら、現在はかつてのように容易に人材を採用したり、入れ替えたりすることができない時代だからである。
また、諸々の施策を導入した後は、各人の生産性を向上させていくことに注力してほしい。そのためのサポートは惜しんではならない。人件費を変動費化すると同時に、やればやっただけ報われるというメリハリを従業員が感じられるようにし、会社から期待の表明として能力開発にも力を入れていくことである。そして、長い目で見ていくこと。こうした心遣いとアプローチが、変動費化の施策を実のあるものとするためには欠かせない条件である。
ただ、それでも駄目ならば、変動費化ということから外れて、「給与外給与」へと訴えることも1つの方法だと思う。結局のところ、賃金は「衛生要因」であり、際限がない。手法として限界があるのだ。だから、それを補うためには「動機付け要因」へと働きかけていくことも考えていくべきである。
そう、モチベーション向上への施策だ。例えば、「理解する」「共感する」「褒める」「承認する」「チャンスを与える」といったお金のかからない方法がたくさんある。これらについては、また別の機会で改めて解説していくことにする。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント











