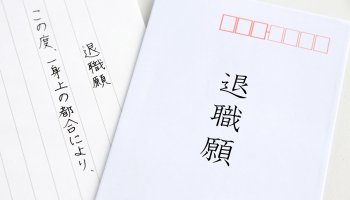改正育児・介護休業法への対応アンケート
育児期の柔軟な働き方を実現するための措置として
「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」の⼆つを選択するパターンが4割
労務行政研究所

⺠間調査機関の⼀般財団法⼈ 労務⾏政研究所(理事⻑:猪股 宏)では、2025年4⽉および10⽉に段階的に施⾏されている改正育児・介護休業法(以下、改正法)への企業の対応状況について、2025年4⽉7〜18⽇にアンケートを実施しました。このほど、回答のあった344社の集計結果がまとまりましたので、⼀部抜粋して紹介します。
-
【2025年4⽉1⽇施⾏分】
- テレワークの実施・導⼊状況: 3歳未満の⼦を養育する従業員については、「既存のテレワーク制度で対応」が57.3%で半数超。⼀⽅、34.0%の企業は「対応する予定はない」[図表 1]。要介護状態の対象家族を介護する従業員についても同様の傾向。
- 介護両⽴⽀援制度等を取得しやすい雇⽤環境整備のための措置の実施状況: 法改正前後における実施状況を⾜し合わせると、「相談体制の整備・相談窓⼝の設置」が89.1%と9割近くに上る[図表 2]。
- 介護に直⾯する前の早い段階(40歳等)での情報提供: 情報提供のタイミングは「該当者を対象に、年に1回まとめて実施」が55.0%と過半数を占める[図表3]。 【2025年10⽉1⽇施⾏分】
- 「育児期の柔軟な働き⽅を実現するための措置」の実施状況: 実施する措置の組み合わせでは、「始業時刻等の変更」と「短時間勤務制度」の⼆つを選択するパターンが全体の約4割を占める。措置に関する個別周知・意向確認の⽅法は、「対⾯での⾯談」が65.8%で最多[図表4〜5]。
1.テレワークの実施・導入状況
改正法では、3歳未満の⼦を養育する従業員および要介護状態の対象家族を介護する従業員がテレワークを選択できるように措置を講ずることが努⼒義務化された(2025年4⽉1⽇施⾏)。
3歳未満の⼦を養育する従業員については、「既存のテレワーク制度で対応」が57.3%で半数を超える⼀⽅で、「対応する予定はない」と回答した企業は34.0%と約3社に1社の割合であった。産業別に⾒ると、製造業は「対応する予定はない」が40.4%と、⾮製造業(29.3%)よりも11.1ポイント⾼い[図表1]。
要介護状態の対象家族を介護する従業員についても同様の傾向で、「既存のテレワーク制度で対応」が58.4%と6割近くを占める⼀⽅、「対応する予定はない」は33.1%である([図表]なし)。
![[図表1]3歳未満の⼦を養育する従業員に対するテレワークの実施・導⼊状況](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-0730-01-01.png)
2.介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備のための措置の実施状況
改正法では、介護休業や介護両⽴⽀援制度等の申し出が円滑に⾏われるようにするため、①研修の実施、②相談窓⼝の設置、③事例の収集・提供、④取得・利⽤促進に関する⽅針の周知のいずれかの措置を講ずることが義務化された(2025年4⽉1⽇施⾏)。
[図表2]では、法改正前後における雇⽤環境整備の実施状況をまとめている(複数回答)。法改正前から実施していた取り組みでは、「相談体制の整備・相談窓⼝の設置」が 56.2%で最も⾼い。法改正後に新しく実施した取り組みも、「相談体制の整備・相談窓⼝の設置」が最多の32.9%だが、「従業員への利⽤促進に関する⽅針の周知」(32.3%)と拮抗する。
法改正前後における実施状況を⾜し合わせると、「相談体制の整備・相談窓⼝の設置」が89.1%と9割近くに上る。
![[図表2]介護両⽴⽀援制度等を取得しやすい雇⽤環境整備のための措置の実施状況(複数回答)](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-0730-01-02.png)
[注]「法改正前から実施」と「法改正を受けて実施」の両方に回答いただいた企業を集計した。
3.介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
今回の法改正では、従業員が介護に直⾯する前の早い段階(40歳等)で、介護休業や介護両⽴⽀援制度等の理解と関⼼を深めるための情報提供を⾏うことが義務づけられた(2025年4⽉1⽇施⾏)。
そこで、該当社員に対する情報提供を⾏うタイミングを尋ねたところ、「該当者を対象に、年に1回まとめて実施」が55.0%と過半数を占め、次いで「該当者に対して個別に実施」が33.3%と約3割であった[図表3]。
![[図表3]介護に直⾯する前の早い段階(40歳等)での情報提供を⾏うタイミング](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-0730-01-03.png)
[注]「その他」は、 "全従業員に向けて年に1回実施" など。
4.「柔軟な働き方を実現するための措置」の実施内容
改正法では、3歳から⼩学校就学前の⼦を養育する従業員に対して、次の五つの中から⼆つ以上の措置を選択して講じることが義務化される(2025年10⽉1⽇に施⾏予定)。
- 始業時刻等の変更
- テレワーク等
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ⼦を養育することを容易にするための休暇(以下、養育両⽴⽀援休暇)の付与
- 短時間勤務制度
調査時点(25年4⽉)での対応状況を尋ねたところ、「既に実施している」が55.2%、「実施する措置が決定しており、今後実施予定」が16.6%と、約7割の企業は調査時点で措置を決定していた([図表]なし)。
これらの企業に対し、五つの措置のうち、どの措置を選択しているかを尋ねた(複数回答)。実施する措置の組み合わせについて、上位5パターンを⽰したものが[図表4]である。「①始業時刻等の変更」と「⑤短時間勤務制度」の⼆つを選択するパターンが43.4%と約4割を占め、これら⼆つの措置に「②テレワーク等」を加えた三つの措置を選択するパターンが24.7%で続く。上位2パターンで全体の7割弱を占める結果となった。
(上位5パターン)
![[図表4]「柔軟な働き⽅を実現するための措置」で実施している/実施予定の措置の組み合わせ(上位5パターン)](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-0730-01-04.png)
[注]法定では⼆つ以上の措置を実施することが求められるため、選択した措置が⼀つのみの企業は集計から除外した。
また、「柔軟な働き⽅を実現するための措置」は、従業員の⼦が1歳11カ⽉に達する⽇の翌々⽇から2歳11カ⽉に達する⽇の翌⽇までの1年間に、当該従業員に個別に周知し、意向確認を⾏う必要がある。この⽅法・⼿段として、既に実施している、もしくは予定している内容を尋ねたところ(複数回答)、「対⾯での⾯談」が65.8%で最多となった[図表5]。
(複数回答)
![[図表5]「柔軟な働き⽅を実現するための措置」の個別周知・意向確認の⽅法・⼿段(複数回答)](https://img.jinjibu.jp/updir/kiji/SUV25-0730-01-05.png)
[注]個別周知・意向確認の⽅法・⼿段について、「検討中・未定」の企業は除いて集計した。
- 調査名: 改正育児・介護休業法への対応アンケート
- 調査対象: 『労政時報』定期購読者向けサイト「WEB 労政時報」の登録者から抽出した⼈事労務担当者2万5816⼈
- 調査期間: 2025年4⽉7〜18⽇
- 調査⽅法: WEBによるアンケート
- 集計対象: 調査対象のうち、回答のあった344社(1社1⼈)
労政時報は、WEBや定期刊行誌を通して、人事部門の実務対応や課題解決をサポートする会員制のデータベースサービスです。1930年に定期刊行誌を創刊して以来、常に時代の変化に合わせて、人事・労務の最新情報を提供し続けています。忙しい人事パーソンの実務をWEB労政時報がサポートします。
(運営・発行:株式会社労務行政、編集:一般財団法人労務行政研究所)
http://www.rosei.jp/

この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント