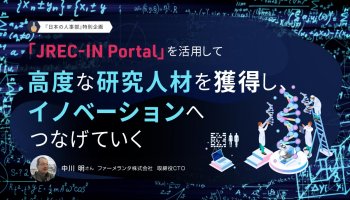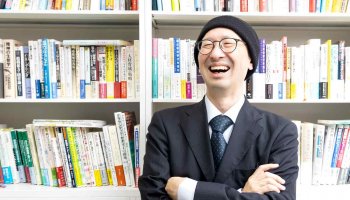新規事業を生み出す人と組織の育て方
人事に求められるイノベーティブな挑戦とは
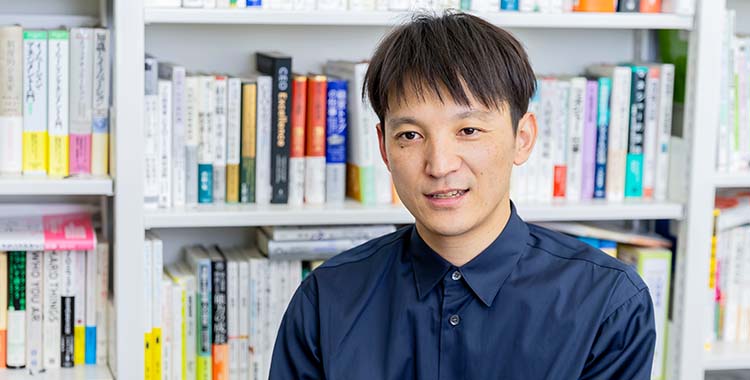
外部環境の急激な変化を受けて、企業には果断なイノベーションが求められています。一方で、新規事業の創出やイノベーティブな組織づくりに苦戦し、頭を悩ませている担当者も多いでしょう。立教大学の田中聡准教授は、「事業を創るには『創る人』『支える人』『育てる組織』の三位一体改革が必要」とし、経営者と人事にこそイノベーティブな挑戦が求められると言います。経営者や人事リーダーに求められる、エンパワーメントの取り組みについて聞きました。
※「日本の人事部 LEADERS(リーダーズ)2025 Vol.13」巻頭インタビューを加筆・修正したものです。

- 田中 聡さん
- 立教大学 経営学部 准教授
たなか・さとし/1983年山口県生まれ。東京大学大学院学際情報学府博士課程修了。博士(学際情報学)。2018年より現職。専門は人的資源管理論・組織行動論・チームワーク論。主に経営人材の育成、新規事業部門の人材開発・組織開発などを研究している。著書に『経営人材育成論』(単著:東京大学出版会)『チームワーキング』(共著:日本能率
協会マネジメントセンター)『シン・人事の大研究』(共著:ダイヤモンド社)など。
新規事業に本気になれない状態
多くの日本企業が新規事業創出に悩みを抱えています。
新規事業にまつわる日本企業の課題は決して今に始まった話ではありませんが、ここ5年ほどで課題の「質」が大きく変わってきたと感じています。
これまで新規事業といえば、戦略立案や財務計画が主なテーマとして語られてきました。しかし、最近では「人と組織」に関する課題が表面化し、ますます重要になってきています。新規事業の推進においては、戦略や資金を整えるだけでは十分ではなく、それを実行し、推進する「人」をどう見出し、育てるのか。そして、その「人」が力を発揮できるような「組織」のあり方、たとえば人事制度や組織構造、さらには組織風土をどうデザインするかが問われています。
私が2018年に出版した『事業を創る人の大研究』では、「事業開発」と「人材開発・組織開発」を一体として考える重要性を指摘しました。当時、事業開発は経営企画部の役割、人材開発・組織開発は人事部の役割といった管掌範囲の違いから、両者がセットで議論されることはほとんどありませんでした。しかし、最近では多くの企業から「新規事業を創る人材をどのように発掘し育成すればよいのか」「新規事業を促進するための組織や風土をどう整備すればよいのか」といったテーマで相談を受けるようになっています。
このような流れの変化は、日本企業が新規事業創出において、単に「0から1のアイデアを生み出す」ことだけでなく、それを実現可能な形で推進する力が求められていることを示しています。新規事業は企業の未来を担うものです。既存事業のアセットを活用しながらも、革新を生み出し、それを実行するための「人と組織」にあらためて注目が集まっているのです。
具体的に「人と組織」からみた新規事業についてどのような課題があるのでしょうか。
経営層、ミドル層、若手層それぞれに課題が存在し、それらが複雑に絡み合っています。
まずは経営層の課題です。大企業のトップの多くは任期制であり、長期的な視点で新規事業に取り組むインセンティブが働きにくい仕組みになっています。実際、10年以上の長期政権となるケースは珍しい。新規事業は短期的な利益を追求するだけでは成功しません。それにもかかわらず、株主や機関投資家からの圧力もあり、在任期間中に成果を出す必要性に駆られ、経営層が新規事業に対して本気でコミットできない状況が生じやすいのです。また、経営層のリーダーシップが新規事業開発を推進する風土の醸成に不可欠であるにもかかわらず、それが欠けている場合も多いと感じます。
次に、ミドル層の課題。現在、管理職は「罰ゲーム」や「無理ゲー」とも形容されるように、膨大なタスクと重い責任を一手に引き受けています。部門の業績管理や多様化するチームのマネジメント、一人ひとりのメンバー育成や働き方改革への対応など、さまざまな課題に向き合っていて、ただでさえ忙しい。このような状況では、管理職が新しい挑戦に前向きになることは難しく、結果的に新規事業へのエネルギーやリソースが割かれにくい構造が生まれています。加えて、管理職には既存事業で成果を上げた人が就いていることが一般的ですが、新規事業開発の経験が乏しく、それが新規事業特有の不確実性への対応力を妨げているケースもあります。
最後に若手層の課題です。若手社員の多くは「新しいことに挑戦したい」という意欲を持っていますが、そのエネルギーが自社の新規事業に向きにくい現状があります。これは、若手が会社に対する帰属意識や貢献意欲を持ちにくい企業文化が影響しています。さらに、人材の流動化が進む中、個人のキャリア自律を優先する傾向が強まり、自社での長期的な挑戦よりも短期的な成果を求めがちです。
新規事業をうまく育てている組織には、どのような共通点が見られますか。

新規事業を成功させている企業にはいくつかの共通点が見られます。その中でも特に顕著なのは、経営トップ自らが新規事業に積極的に関与し、意思決定と推進の中心的役割を果たしていることです。
たとえばサイバーエージェントでは、成熟した既存事業を持ちながら、インターネットTVの「ABEMA」など、社会的に大きな存在感を放つ新規事業を生み出し続けてきました。同社は若手を積極的に経営幹部に抜てきすることで有名ですが、社運を賭けた新規事業とも言われるABEMAについては、経営トップである藤田晋氏自らが陣頭指揮を執り、事業の立ち上げを行なっています。経営トップが事業の成否を自らの責任として引き受ける姿勢は組織全体に挑戦への意識を根付かせるドライバーとなります。
スタートアップの例では、SmartHRが特筆すべき例だと言えるでしょう。創業者の宮田昇始氏はクラウド人事労務ソフトの既存事業を成長させた上で代表取締役の座を譲り、自らは新規事業領域に集中できる体制としました。
これらの事例に共通するのは、「会社の将来を担う新規事業を安易に担当者任せにしない」という点です。経営トップ自らが意思を持ち、リーダーシップを発揮していることが新規事業の成功の鍵となっています。実際、私たちが行った調査でも、「役職上位層が管掌している新規事業ほど事業の成果が高い」ということがわかっています。
一方、海外企業では、CEOが新規事業担当役員を兼務しているケースが多く見られます。たとえば、Amazonの創業者ジェフ・ベゾス氏は、同社の新規事業であるAWS(Amazon Web Services)の初期構想段階から深く関与し、その成長をけん引しました。こうした事例は、大企業の経営トップが新規事業にリーダーシップを発揮することがどれほど重要かを物語っています。
今後は日本企業でも、経営トップが率先して新規事業に向き合い、リーダーシップを発揮してその推進を主導することが求められるでしょう。それは単なる権限や責任の問題ではなく、企業全体に挑戦の風土を根付かせることにつながります。
創る人に求められる「学習目標志向性」
「創る人」を育成するために経営者や人事リーダーに何が求められるのでしょうか。
繰り返しになりますが、大前提として、経営トップ自らが「創る人」であるという自覚を持ち、行動することが大切です。とはいっても、実際にはさまざまな制約がある中で、誰かにその役割を託さざるを得ない場合もあるでしょう。その際に大切なのは、「誰に託すのか」をしっかりと見極めることです。
事業を創る人に求められるのは、いわゆる戦略家としてきれいな事業計画や財務計画を描くことではありません。まず動き出し、試行錯誤を重ねながら前進していける行動力です。
新規事業には多くの不確実性が伴いますから、すべてを予測できません。重要なのは、実際に走りながら学び、柔軟に変化に対応していくマインドです。また、新規事業には一人では成し遂げられず、組織の力学を理解し、多様なステイクホルダーを巻き込んでチームを作る力が必要です。社内外の人々と協力関係を築くためには、単に自分のビジョンを語るだけでなく、相手の期待や利益を理解した上で、共通の目標を設定できる能力が求められます。特に社内では、既存事業部門や経営層との信頼関係を構築しながら進めることが求められます。
さらに、想定外のトラブルや失敗に直面しても落胆せず、むしろそれを学びの機会として捉え、軌道修正しながら進めるタフさも欠かせません。失敗を前提として行動し、そこから得た学びを事業の進化につなげられる人が、新規事業を成功に導けるのです。
そのような人材を、どのようにして見極めればいいのでしょうか。
新規事業に適した人材を見極める際は、「業績目標志向性」と「学習目標志向性」という二つの志向性に注目することが有効です。
業績目標志向性の高い人材は、業績目標の達成を重視し、過去に誰かがやっていて「勝ち筋」が見える仕事や、自分が経験したことがある仕事を積極的に好む傾向があります。既存事業で成果を出せる人だと言えるでしょう。
一方、学習目標志向性の高い人材は、自分の能力は環境や機会次第で成長し続けると考え、能力を伸ばすことそのものに強い関心を持っています。このような人材は、新規事業のように成功の保証がなく、不確実性が高い状況でも適応力を発揮できます。未知の課題に挑戦し、それを学びの機会として捉えることができるため、大きな成果を期待できるのです。
二つの志向性が決定的に分かれるのは、壁にぶつかったときの反応です。業績目標志向性の人は失敗の原因を自身の能力に見いだしがちで、「自分はこの仕事に向いていない」と考えますが、学習目標志向性の人は、失敗を新たな学びとして活用し、「この方法でうまくいかないなら、次は別のやり方を試してみよう」と柔軟に考え方や仕事の仕方を切り替えることができます。
新規事業は、オペレーションが確立している既存事業とは違い、うまくいかないことの連続と言っても過言ではありません。そんな状況では、経験やスキル以上に、仕事の仕方や考え方を柔軟に変えながら「アンラーニング」するマインドが不可欠です。そのため学習目標志向性を持つ人を見極め、新規事業を任せるべきです。
創る人の「越境」を支える
創る人に対して、経営者や人事リーダーが「支える人」となるために必要なことを教えてください。
事業を前に進めるための事業開発の支援だけでなく、人材開発の支援にも注力すべきです。特に大企業の新規事業を担う人材には、周囲の協力を引き出し、組織全体を巻き込む力が求められます。
新規事業の初期段階では、社内ネットワークの構築が極めて大きな意味を持ちます。たとえば、既存事業部門に頭を下げてリソースを確保したり、必要な技術を持つ人を探し出したりと、幅広く社内関係者と連携します。ただし、こうした動きには多大なエネルギーを要します。担当者が孤軍奮闘するのではなく、経営者や周囲が支える仕組みを整えなければなりません。
さらに、私たちの研究で明らかになったのは、新規事業の成果を高める上で効果的な支援が二つあるということです。一つ目は「経営者からの内省支援」で、経営トップがメンターとして新規事業担当者に寄り添い、内省を促す役割を果たすこと。たとえば、担当者が事業の推進を通じて「経営人材としての視座」を養えるようサポートし、自らの挑戦を深く振り返る機会を提供することが求められます。こうした内省支援によって、担当者は単なる事業推進者ではなく、次世代の経営リーダーとして成長することが期待できます。
二つ目は「社外新規事業担当者からの業務支援」です。新規事業立ち上げの経験を持つ外部の専門家から、業務的なアドバイスや知見を得ることは、担当者にとって大きな力になります。外部とのネットワークを広げることで、社内にはない知識や視点を取り入れられるため、新規事業の成功確率が高まります。そのため、越境学習の機会を積極的に提供することも有効です。
ネットワーク作りを支える動きは、社内だけでなく社外に向けても求められるのでしょうか。
その通りです。新規事業を立ち上げる人には、社内外の知識やリソースを柔軟に引き出す力、特に、社外のネットワークを活用する力が求められます。
たとえば、社内では得られないアイデアや視点を外部から取り込むことで、事業の新たな方向性を模索することができます。社外とのネットワークづくりは、一部の経営者や上司からすると、「数字を上げないのに社外をふらふらしている」という逸脱行動に映るかもしれません。しかし、そうした外部との関わりが、長期的には事業の推進に不可欠です。むしろ、「専業禁止」の感覚で越境行動を奨励し、社外の知を持ち込めるようにすべきです。
大切なのは、創る人の越境学習を妨げる評価やルールで縛らないこと。新規事業は既存事業とは異なり、明確な成功パターンや勝ち筋がないため、KPIマネジメントのような評価手法は適用しにくいケースが多く見られます。評価を保留しつつ、担当者が目の前の事業に集中できる環境を整えることが求められるのです。
ある企業の新規事業責任者は、「ずっと同じ主張を繰り返している人は、社外の人と関わりがない人だ」と語っていました。多様な情報源を持つ人は、外部の環境変化に触れることで、自身の考えや行動を柔軟に変えられます。こうした外部とのつながりを通じて、創る人がより大きな可能性を引き出せるよう、組織としてサポートしていくべきです。

「エース級人材の処遇」は強力なメッセージ
「育てる組織」の風土を延ばすために、経営者や人事リーダーにはどのような取り組みが求められますか。
風土というものは、何らかの種をまけば勝手に育つものではありません。経営者や人事リーダーの一貫性のある行動が積み重なって形づくられるものです。たとえば、「当社は新規事業に注力する」と経営者がいくら言葉で訴えても、それだけで風土は醸成されません。本当に重要なのは、実際に何件の新規事業に投資したか、エース級人材を新規事業担当にアサインしているかといった、具体的で目に見えるアクションです。これらの行動こそが、組織全体に「新規事業を重視している」というメッセージを強く伝えます。
また、日常の会議で新規事業が必ずアジェンダに上がるような状態を作りだすことも必要です。これが、組織として「事業を育てる組織」の象徴といえます。そのためには、まずは経営層全員が新規事業の重要性を理解し、経営課題の最優先項目という認識を持たなければなりません。
新規事業担当役員のポストを新設し、外部から鳴り物入りで経験豊富な人材を迎えても、周囲は冷淡に「お手並み拝見」という態度を取ってしまう。そうならないように、既存事業の役員も新規事業の重要性を認識するべきなのです。既存事業の成果を守ることが優先されがちな中で、新規事業が軽視されることがあれば、その時点で風土づくりは失敗します。
エース級人材を新規事業に配置することには、どのような効果がありますか。
社内の人事異動情報は、社員たちが最も注目する話題の一つです。エース級の人材がどの部門に配置されているかは、組織として何を最も重視しているのかを如実に表します。たとえば、社内で一目置かれる人材が新規事業にアサインされた場合、その配置自体が強力なメッセージとなり、「新規事業が本当に会社の未来を担う重要なテーマなのだ」と周囲に認識されやすくなるでしょう。
さらに、配置された人の処遇も大切です。エース級の人材をアサインして新規事業を立ち上げても、すぐにうまくいくとは限りません。結果的にうまくいかなかった場合、その人材がどのようなポジションに戻るかは、組織全体に強い影響を与えます。
残念ながら失敗してしまった人材が以前よりも高いポジションに就くことで、「新規事業への挑戦はキャリアのリスクではなく、むしろ成長のチャンスである」というメッセージが浸透します。これにより、多くの社員が新規事業に手を挙げる文化が育ちます。
私はよく、新規事業を跳び箱にたとえて話します。どんな企業でも、新規事業コンテストを行ったり、専門部署を設けたりといった「精度の高い踏み台」を作ることには投資しますが、その後に跳び箱を飛び越えた社員を受け止める「マット」が狭すぎることが多い。運良くマットに着地できればいいのですが、外れてしまうと戻る場所がなくなり、他の人も挑戦をためらってしまいます。このような状況を変えるために、新規事業に挑んだ人材が安心して次のステップを踏める仕組みが必要です。
新規事業に挑んだ人の評価では、何を重視すべきでしょうか。
新規事業の成果を評価する際、業績だけにとらわれるべきではありません。成果は担当者だけでなく、組織全体の支援や環境の影響を受けます。それよりも、経験を通じて何を学び、どのように次へ生かせるのかという学習成果を重視するべきです。
失敗には「避けられた失敗」と「知的な失敗」があります。前者は、十分な支援体制や事前のリスク評価で防ぐべきです。もう一つの「知的な失敗」は、新しいアイデアや方法を試す過程で起こるものであり、会社全体の学習資産となり得ます。このような失敗を積極的に奨励することが、新規事業を育てる上でのポイントです。
また、挑戦者が得た学びは、知識やスキルだけでなく、視座の広がりといった成長も含まれます。経営視点を持つようになったり、組織全体の力学を理解したりすることは、次世代のリーダーを育成する上で重要です。担当者が失敗から何を学び、次にどう生かせるのかを深く評価し、それに応じたポジションを与えることで、再挑戦の意欲を引き出せる環境を整えるべきです。
最終的には、新規事業に挑戦すること自体がキャリアのリスクではなく、むしろ成長と評価を得るチャンスであるという認識を社内に浸透させることが、「挑戦を歓迎し、失敗を学びに変える組織風土」を築く鍵となります。
人事はイノベーション職。黒子でいる必要はない
新規事業を通じてイノベーティブな組織を実現したいと考えている経営者や人事リーダーへ、メッセージをお願いします。
既存事業と新規事業の対立は、多くの企業に共通する根深い課題です。ただ、その捉え方を変えることで新たな風土を生み出すことができます。
「既存」と「新規」という分断を生む言葉を使わず、新規事業を「育成事業」、既存事業を「基盤事業」と位置付けてみてはいかがでしょうか。基盤事業があるからこそ育成事業が生まれ、育成事業が成功すれば基盤事業もさらに強化される。このように、両者が相互に支え合う関係性を共有することが、イノベーティブな組織風土を育む第一歩です。
新規事業に光が当たるとき、社内で最大の抵抗勢力になるものは、「何かよく分からない」という漠然とした不快感です。この不明瞭さが、既存事業側に無意識の反発を生み出します。だからこそ、新規事業に関する情報をオープンにし、広く共有しなければなりません。育成事業と基盤事業、それぞれがどのような課題と目的を持ち、どう連携できるのかを一つの物語として共有することで、両者の溝を埋めることができます。これを理想論と考えるのではなく、経営層を中心に、ワンチームでストーリーを語れるようにすべきだと考えます。
こうした取り組みを実現するために、人事が果たす役割は非常に大きいと考えます。その一つが、人材開発という手段を通じて、誰もが「新規事業にトライしたい」と思える風土を育てることです。多くの企業では、事業開発は経営企画、人材開発は人事と役割が分断されているのが現状です。しかし、よい事業開発は人材開発に支えられ、よい人材開発には事業開発が伴うものです。両者は一体不可分だと理解し、経営企画と人事が連携を深めることで、より強い組織を作ることができるでしょう。
私は、人事は空前のイノベーション職だと思っています。外部環境が急激に変化し、人的資本経営が求められる中で、人事は今、最も先進的な課題を抱えている立場だと言えます。だからこそ、これからの人事は黒子にとどまる必要はありません。むしろ、人事こそが率先して挑戦し、イノベーティブな行動を起こすべきです。人事がその姿勢を示すことで、組織全体が新規事業を育て、挑戦を重ねる文化が生まれます。
新規事業を成功させる組織への成長は、人事から始まるのです。人事が前に出て、変革の旗手として行動することで、経営層や社員が共鳴し、組織全体が一丸となる風土を育てられるでしょう。


人・組織に関する課題や施策についての調査レポートを公開。貴社の課題解決にご活用ください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント