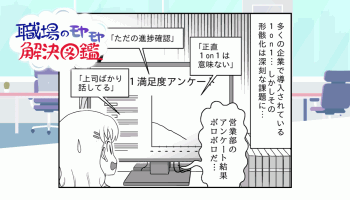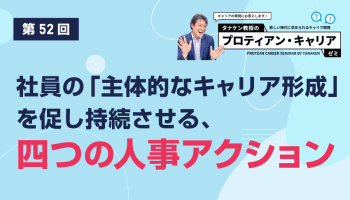自身のマネジメントの失敗を経て起業
個人の能力に左右されないマネジメントの実現により
すべての人の可能性が毀損されない世界を目指す
株式会社KAKEAI 代表取締役社長 兼 CEO
本田 英貴さん

社会環境の変化に伴い、日本企業のマネジメントスタイルは「管理型」から、従業員一人ひとりの状況に応じた「支援型」へと転換が求められています。しかし、「支援型」の成功はマネジャー個人の能力に左右されやすく、企業はその難しさに直面しています。そこで注目されているのが、上司と部下のコミュニケーションをサポートする1on1プラットフォーム「Kakeai(カケアイ)」です。同サービスを運営する株式会社KAKEAIの代表・本田英貴さんに、起業の経緯やKakeaiの強み、マネジメントや1on1の現状・課題をうかがいました。
- 本田 英貴さん
- 株式会社KAKEAI 代表取締役社長 兼 CEO
ほんだ・ひでたか/筑波大学卒業後、2002年に株式会社リクルート入社。商品企画、グループ全体の新規事業開発部門の戦略スタッフなどを経て、(株)電通とのJVにおける経営企画室長。その後、(株)リクルートホールディングス人事部マネジャー。人事では「ミドルマネジメント層のメンバーマネジメント改善施策」や「Will,Can,Must・人材開発委員会・考課・配置等のデジタル化」を担当。2015年リクルート退職後、スタートアップ数社での役員を経て2018年4月に株式会社KAKEAIを創業。
「人の生き方に関わり、支援したい」という思いでリクルートに入社
本田さんはどのような学生生活を送っていましたか。
部活と学業一色の学生生活を送っていました。筑波大学の体育専門学群に所属し、体育科の教員を目指していたのですが、周りが就職活動をし始める時期になったときに、ふと立ち止まって考える機会があったのです。漠然と教員になりたいと思ってきたけれど、それは一体なぜだったのか、と。そこで思い至ったのは、自分自身が幼少期からさまざまな先生に出会い、苦しいときや道を踏み外しそうになったときに支えてもらったことが原体験となっていた、ということです。教員を志望した理由の根底にあったのは、人の生き方に関わり、支援していく仕事がしたいという思いでした。
そう考えると、教員ではなく一般企業でもできることがあるかもしれないと思い、就職活動を始めることにしました。
新卒でリクルートに入社されますが、その背景や思いについてお聞かせください。
商社やメーカーなどさまざまな業界を見てみましたが、当時の自分には「人の生き方に関わる」こととは距離が遠いように感じ、しっくりこなかったのです。そんなときにリクルートに出合いました。就職や転職などの人生の転機において、情報を提示することで考える機会を提供し、行動を促すという事業内容を知り、人の生き方に関わっていける仕事だと感じて、入社を決めました。
その後のキャリアの変遷についてお聞かせください。
リクルートではさまざまな職種を経験しました。入社後は求人メディアの営業職に就き、企業の採用を支援。その後自ら手を挙げて商品企画に移り、アルバイト求人メディアの商品企画を担当しました。さらに、社内の新規事業を支援する部門に異動し、事業計画の作成支援や人事面でのサポートなどを担当。その後、リクルートホールディングスの人事部へ異動することになりました。
人事部では、具体的にどんな仕事をされていたのですか。
現場のマネジャーがメンバーの力を引き出すための仕組みづくりを行いました。リクルートには「Will/Can/Must」や「人材開発委員会」といった人事制度や取り組みがありますが、それらをブラッシュアップしつつ、より効率的かつ効果的に運用できるようデジタルツールを用いて仕組み化する仕事です。
当時はそれらの仕組みやデータを統合的に運用できるツールがなかったので、Salesforceをカスタマイズしてシステムを作りました。今考えるとかなり使いにくいものだったと思いますが、テクノロジーを使って人の力を補い、ある一定の水準に整えることができる可能性を感じました。
一方で、いかにテクノロジーが進化しても、人にしかできない部分は必ず残ることも強く感じました。現場のマネジャー個人の姿勢やコミュニケーションが、メンバーの成長とその先にある組織の成果に対してとても大きな影響を与えることを実感したのです。この気づきは、その後のKAKEAIの事業にもつながっていますね。

「あなたには誰もついて行きたくないって知っています?」――360度評価で突きつけられた現実
その後、どのような経緯で起業に至ったのでしょうか。
実は、リクルートでの人事時代に大きな転機となる出来事があったのです。今振り返ると、当時の私はとても調子に乗っていました。リクルートで新規事業や人事の仕事を任され、どこかで自分は仕事ができる人間だと勘違いしていた。また、当時はチームのメンバーをマネジメントする立場にあったのですが、最適なマネジメントができていると思い込んでいました。
そんなとき、人事になって初めての360度評価が実施されました。メンバーからは高い点数やポジティブなコメントがもらえるだろうと、ワクワクしながら結果を見ました。
すると、そこに書かれていたのは「あなたには誰もついていきたくないって知っています?」という無記名のコメント。さらに、さまざまな観点の点数のどれもが自己評価とはかけ離れたとても低いものでした。最初は、私宛ではないものが紛れ込んだのだと思いました。でも、間違いなく私宛のものでした。今まで思ってきたことややってきたことは何だったのだろうと、大きなショックを受けました。
今で言う「1on1」のような時間を頻繁に設け、メンバーと丁寧にコミュニケーションをとっていたつもりでした。しかし今振り返ると、それがメンバーのための時間ではなく、上司である私が自分自身の満足のための時間になっていたのだと感じます。
人の生き方に関わっていきたいと思って社会人になった私が、すぐそばにいる人たちに対してネガティブな影響を与えてしまっていた。情けなく、恥ずかしい思いでいっぱいでした。そこから、メンバーとの関わり方がわからなくなりました。仕事を任せることもできなくなり、一人で仕事を背負い込むように。次第に夜も眠れなくなり、心身に不調をきたして休職することになりました。
つらい経験をされたのですね。
自業自得です。休職したまま退職することも考えました。しかし、メンバーにきちんと償いたいという気持ちと、ここで向き合わなければ一生心に引っかかったまま生きていくことになるという思いから、しばらく休んだ後に全く同じ仕事で復職しました。
すると、休職前とは全く違った景色が見えるようになったのです。以前は現場のマネジャーを、自分自身の競争相手のような見方をしていました。しかし、休職を経てフラットな目線で見られるようになると、私のように苦しんでいるマネジャーがいることが見えてきました。また、メンバーのエンゲージメントが高く業績も出ている組織のマネジャーの存在を、素直に受け入れられるようになりました。
上司は選べないにもかかわらず、上司個人の力量によって部下の成長やモチベーションが左右されてしまうことがある。これは従業員個人の人生にとっても、組織にとっても、良いことではありません。この頃から、こうした状況をなくしたいと考えるようになりました。
そうした経験や思いが、KAKEAIの創業につながっていくのですね。
属人的なマネジメントをなくすには、研修やマニュアルのようなものではなく、日常のコミュニケーションそのものを支えていく必要があると考えていました。人事として組織の中で取り組むことも不可能ではありませんが、人事が介入する状況では、現場の皆さんは本音のコミュニケーションがしにくくなると思ったのです。外側からいろいろな会社を支えていくほうが役に立てるのではと考えるようになり、復職から1年ほどでリクルートを退職しました。
その後、転職されていますが、すぐに起業しなかったのにはどんな理由があったのでしょうか。
現場のすべてのコミュニケーションに直接関与してサポートすることは物理的に不可能なので、何らかの仕組みが必要だと考え、ソフトウエアという形でサービス提供することをイメージしました。
そのためにはエンジニアの力が必要です。しかし、当時の私の周りにはスキルを持つ仲間がいませんでした。起業には資金も必要ですが、資金調達の方法もわかりませんでした。そこで、まずはスタートアップに飛び込んで事業を成長させる経験を積もうと考え、SaaSの開発・販売を行う会社に転職したのです。
この会社では多くの仲間との出会いに恵まれ、そのうちの一人がKAKEAI創業時に一人目のエンジニアとして加わってくれました。彼自身もマネジメントに苦労した経験があり、「自分のようにマネジメントが苦手な人を助けるプロダクトを作りたい」と賛同してくれたのです。他にも当時の仲間が何人か、転職などを経て今のKAKEAIで働いてくれています。
資金調達については、その仕組みを学ぶだけでなく、ベンチャーキャピタルとのご縁にも恵まれました。当時所属していた会社に出資されていたベンチャーキャピタルがKAKEAI創業時に支援してくださり、現在も継続して応援してくださっています。
2018年の4月に、KAKEAIを創業されますが、どのような経緯だったのでしょうか。
2017年の後半ごろから、のちのKAKEAIの共同創業者である皆川に、私が考えている事業アイデアに対して意見をもらっていました。皆川はリクルートでの私の同期で、当時は個人で人事系のコンサルティングや研修などの仕事をしていました。その頃の私はまだ、会社を起こす決心ができていなかったのですが、皆川が「私も覚悟を決めて一緒にやるから、きちんと会社としてやろう」と言ってくれて。ようやく覚悟が決まりました。スタートアップでの仕事が一区切りしたタイミングで、KAKEAIを創業しました。
ユーザーの視点に立ったプロダクト開発で、1on1の負担軽減と質向上を実現
「あなたがどこで誰と共に生きようとも、あなたの持つ人生の可能性を絶対に毀損させない。」という貴社のパーパスに込めた思いについてお聞かせください。
原点にあるのは、私自身の経験から感じた「属人的な人への関わり方によって、共に生きる人の可能性を毀損させるようなことをなくしたい」という強い思いです。
どんなに世の中が変わっても、人が人と関わらずに生きていくことはできません。そして誰もが、関わる人やその人との関係性から影響を受けながら生きています。問題にぶつかったとき、人と人とのコミュニケーションが助けになることがあります。そこはAIには完全に置き換えられない、人だからこそできる領域だと思っています。一方で、人間である以上間違えることもあり、それが難しさや苦しさにつながることもあります。
Kakeaiというプロダクトや、KAKEAIという会社、そこに関わる人の力を通じて、「人だからこそ発揮される力」を高め、足りない部分は補う。それが私たちの目指していることです。
Kakeaiの特長について教えてください。
KakeaiはAIとデータを活用し、上司と部下のコミュニケーションを支えるツールです。主な目的は、1on1を現場に定着させ、コミュニケーションの質を高める、そして成果と成長を生みだすことにあります。具体的には、事前に部下が話したいテーマや上司への期待を設定し、それをもとに、上司にはAIによるサジェストや類似事例に基づいた対話設計のアドバイスが提供されます。1on1の状態についても測定され、そのデータをもとにした、マネジャー個人への前向きなフィードバックはもちろん、上司間での気づきの共有や、人事との連携による組織的なマネジメント改善にも活用されます。

他社のプロダクトと比較した際の強みとは何でしょうか。
現場での使いやすさを最優先している点です。管理や可視化の要望が企業から寄せられることもありますが、むしろ現場の本音のコミュニケーションを妨げる可能性があります。Kakeaiではあえてそうした機能を避け、現場のユーザーの皆さまの視点を重視した開発を続けているところが、大きな特長だと考えています。
今後貴社が新たに手掛けようと考えていらっしゃることはありますか。
当社のパーパスで示されている「あなた」とは、世界中のすべての人を指します。「どこで」に関しては、国や地域を問わないことはもちろん、職場だけでなく家庭や学校、さまざまなコミュニティーなど、どんな場もありえると考えています。
つまり、Kakeaiが支援できる可能性があるのは従業員に対する1on1に限らない、ということです。実際に、教員と生徒、教員と保護者、企業の営業担当と顧客などの間での活用事例もあります。現在は人生の中で占める割合が大きい「働く」という領域をメインに展開していますが、それ以外の領域にも広げていきたいですね。
また、「働く」という領域でも進化の可能性がまだ多くあります。例えば、社外の方とのコミュニケーション支援です。社内では相談しにくい話題や、経験者が身近にいないケースでは特に効果的だと思います。さらに、退職後の従業員(アルムナイ)との関係構築でも、私たちが貢献できる領域があると考えています。人がどこで誰と生きるとしても、「関係」は常にその人の今と未来に影響を与える。だからこそ、Kakeaiは“働く”に限らず、すべての関係のなかで必要とされる存在でありたいと考えます。
過去の経験すべてが今につながっている。何ごともまずはやってみることが大切
現在の日本企業の「マネジメント」「上司と部下のコミュニケーション」「1on1」に関して、現状と課題をどのように捉えていらっしゃいますか。
事業や雇用を取り巻く環境が大きく変化する中で、これまでのように従業員を一律に管理し指示命令で動かすスタイルから、個別の状態に合わせた支援で動かすマネジメントのスタイルへと転換せざるを得ない時代になっています。
1on1は、まさに個別支援の象徴的な場で、企業と従業員の接点そのものです。しかし、「1on1に取り組んでさえいれば転換に乗れる」というように、方法論が先行している風潮も少なからずあると思います。ただ1on1を実施するだけでは劇的な変化は起こりません。だからこそ、環境変化を見据えたうえで、何のために1on1を実施するのかという目的意識を持って取り組むことが重要です。
貴社を含む、HRテクノロジー関連の業界の現状や課題をどのように捉えていらっしゃいますか。また今後、この業界はどのようになっていくとお考えですか。
マネジメントのスタイルが「管理」から「個別支援」へと移行することで、マネジメントの主体は人事から現場へとシフトしていきます。そのため、HRテクノロジーのサービスでは、いかに現場のマネジャーやメンバーに寄り添えるかが重要です。
大切なのは「なんとなく良さそう」という総論ではなく、具体的な効果です。そのサービスを導入し施策を実施することが、事業の成長につながらなければ意味がありません。また世の中にさまざまなサービスがあふれているなかで、多機能で網羅的なサービスを目指すのか、特定の領域に特化して圧倒的な強みを持つサービスを目指すのか、どちらかかに舵を切る必要があると考えています。中途半端では生き残れないのが現状です。
さらに、今後はツールの提供だけでなく、それを活用するための支援も重要になるでしょう。導入によってある程度の変化は得られるかもしれませんが、人の意識や行動が一気に変わるわけではありません。私たちもカスタマーサクセスの活動により支援していますが、より一層、企業ごとの事情に合わせたサポートを強化していく必要があると感じています。
本田さんが仕事をする上で、大事にしていることを教えてください。
20代の頃から意識しているのは、「解こうとすること」、そして「決して、解けないと思わないこと」です。自分で「できない」「難しそう」と思い込んでしまうと、簡単なことでもハードルが高くなってしまうので、その考えを一旦頭から取り払い、まずはやってみることを大切にしてきました。
私はこれまでさまざまな職種を経験してきましたが、すべての経験が掛け算となり、現在に生きていると感じています。私の仕事に向き合う姿勢やスキルは、ほとんど20代の頃の経験によって培われたものです。
例えば営業時代には、お客さまごとの個別のリアルな状況、営業活動の難しさややりがいを強く体験しました。商品企画では、事業全体の視点に立った、プロダクト・価格・営業戦略を通じて、インパクトやダイナミクスの本質を学びました。新規事業支援の仕事では、電通とのジョイントベンチャーを立ち上げ、経営企画室長としてその会社に出向したこともありました。私のようにリクルートから来ている人だけでなく、電通からの出向者やプロパーの社員もいる環境で、多様性のある組織運営の難しさも経験しました。これらすべての経験が、今につながっています。
最後に、人材サービス・HRソリューションなどの業界で働いている皆さまにメッセージをお願いします。
業界内での連携が大切だと思っています。サービス提供者同士で競争することでサービスが磨かれる側面はありますが、競争が本当に世の中に役立つ状況につながるかというと、必ずしもそうではありません。見るべきは社会やお客さまの課題です。横ばかりを見ることで、本質的な目的達成が阻害されてしまうなら、協力したほうがいい。そのことが、世の中を前に進めることにつながっていくと信じています。ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

(取材:2025年3月11日)
| 社名 | 株式会社KAKEAI |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区北青山2-13-5 青山サンクレストビル8F |
| 事業内容 | 1on1・面談支援プラットフォーム「Kakeai」の開発・運営 |
| 設立 | 2018年4月12日 |
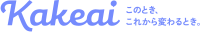
この記事を読んだ人におすすめ

日本を代表するHRソリューション業界の経営者に、これまでのキャリア、現在の取り組みや業界で働く後輩へのメッセージについてインタビューしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント