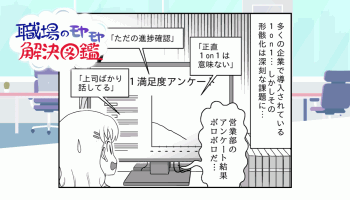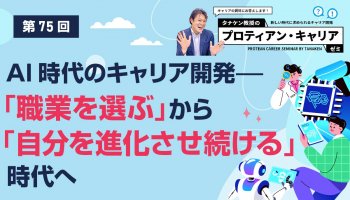タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第64回】
「キャリア対話」を組織文化に
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
田中 研之輔さん
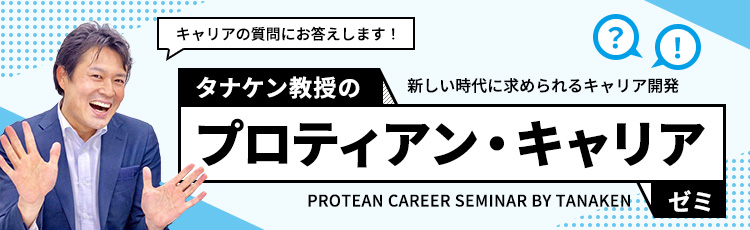
令和という新時代。かつてないほどに変化が求められる時代に、私たちはどこに向かって、いかに歩んでいけばいいのでしょうか。これからの<私>のキャリア形成と、人事という仕事で関わる<同僚たち>へのキャリア開発支援。このゼミでは、プロティアン・キャリア論をベースに、人生100年時代の「生き方と働き方」をインタラクティブなダイアローグを通じて、戦略的にデザインしていきます。
1on1、キャリア相談、キャリア面談など、企業現場では今、「キャリア対話」に注目が寄せられています。そこで今回のプロティアン・ゼミでは、キャリア対話の理論的背景や企業現場における価値を確認しながら、実際にキャリア対話の問いかけリストを見ていくことにします。
自らのキャリアを築いていく上で「キャリア対話」は不可欠
前提として、キャリア対話の魅力は、社員一人ひとりのキャリアコンディションに寄り添い、これまでとこれからのキャリア形成にじっくりと向き合うことができる、という点にあります。キャリア形成が多様化する中で、個人が自らの価値観や目標、能力を深く理解し、環境の変化に柔軟に対応しながらキャリアを築くための手段として、キャリア対話が重要な役割を担っているのです。
キャリア対話とは、自分のこれまでとこれからのキャリアについて職場の上長・同僚・後輩・家族・友人などと会話を重ね、考えを深めていくプロセスです。より専門的なキャリア対話は、キャリアアドバイザーやキャリアコンサルタントが伴走役をつとめます。
キャリア対話を通じて、自分の価値観やスキル、目指す方向性が明確化され、意思決定の質が向上します。また、自分では気づかない新たな視点や選択肢に気づけることも大きな利点です。
キャリア対話は、キャリア理論の中でも注視されています。たとえば、マーク・サビカス(Mark Savickas)教授のキャリア構築理論では、キャリアを「自己概念を具現化するプロセス」と定義し、対話がその核心を成す要素とされています。
人は自らのキャリアを物語として語り直すことで、自分が本当に大切にしているテーマや価値観に気づくことができます。対話はその物語を形作るための重要な場を提供します。
さらに、クランボルツ(John Krumboltz)の計画的偶発性理論は、キャリアにおける偶然の重要性を強調しています。この理論は、計画だけでキャリアを築くのではなく、偶然を柔軟に活用することの価値を説いています。キャリア対話は、偶然の機会を見逃さないための「アンテナ」を高める役割を果たします。他者との対話によって新しい視点やネットワークが得られることで、予期しなかったチャンスが広がるのです。
また、キャリア適応力という概念も、キャリア対話の重要性を裏付けています。キャリア適応力とは、環境の変化に対して柔軟に適応し、キャリアを能動的に形成していく能力のことです。これには好奇心や忍耐力、自己効力感などが含まれます。対話を通じてこれらの適応力を高めることは、変化の激しい現代において特に重要です。自己理解を深め、未来の可能性を模索するプロセスとしてのキャリア対話は、単なる「話し合い」を超えた戦略的な意味を持つのです。
キャリア対話は実際に、さまざまな場面で活用されています。たとえば、企業における上司と部下のキャリア面談では、従業員が自身の目標を明確にし、それに対して会社がどのような支援を提供できるかを話し合う機会が設けられています。こうした対話は、社員のモチベーションを高め、会社全体の生産性向上にもつながります。個人がキャリアコンサルタントとの一対一の対話を通じて具体的なキャリア戦略を立てることも浸透しつつあります。
キャリア対話を効果的に行うためには、いくつかのポイントがあります。まず、相手の話を丁寧に傾聴することが大切です。一方的に自分の意見を押し付けるのではなく、共感的に耳を傾けることで、対話の質が向上します。また、オープンクエスチョンを活用することも重要です。「今後どのようなことに挑戦したいですか?」「その選択にどのような意味を感じていますか?」といった質問を通じて、対話者が深く考えるきっかけを提供することができます。さらに、建設的なフィードバックを通じて、対話者が自信を持って次のステップに進めるようにサポートすることも忘れてはなりません。
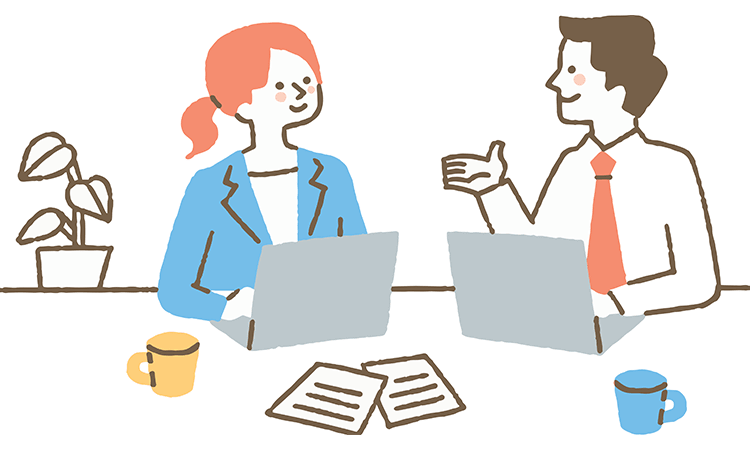
このようにキャリア対話は、人的資本経営の促進やキャリアオーナーシップの実現において非常に重要な役割を果たします。単なる自己分析や相談の場にとどまらず、自らのキャリアを主体的に形成する力を育むプロセスです。キャリアに迷いや不安を抱える人々にとって、対話は希望や解決策を見出すための鍵となります。そして、対話を通じて得られる自己理解や他者からの新たな視点は、これからのキャリアを切り開くための大きな力となるでしょう。
自らのキャリアを築くことは、容易ではないからこそ、キャリア対話が不可欠なのです。キャリア対話というプロセスを活用することで、どのような変化や課題にも柔軟に対応できる力を身につけることができます。このような対話を積極的に取り入れることこそが、豊かなキャリアを実現する第一歩だと言えるでしょう。
キャリア対話の際に鍵となる20の質問
それでは、キャリア対話の際に鍵となる20の質問を皆さんに共有しておきます。これらの質問は、自己理解を深め、具体的なキャリアゴールを見出すために役立ちます。
- これまでのキャリアで最も誇りに思う成果は何ですか?
- 現在の仕事で特に満足している点と、不満に感じている点は何ですか?
- 今後のキャリアで大切にしたい価値観や信念は何ですか?
- 新しいスキルや知識を身につけることに対して、どのような意欲や関心を持っていますか?
- キャリアを通してどのような影響や貢献をしたいと考えていますか?
- 今後のキャリアで挑戦したいと思う分野や職種はありますか?
- 現在の仕事やライフスタイルにおいて、何か変えたいと思っていることはありますか?
- 定年後も仕事を続ける意欲がありますか? 続ける場合、どのような形が理想ですか?
- これまでに獲得したスキルや経験は、他のどのような分野で活かせると考えていますか?
- キャリアの新しい方向性を探るために、何を犠牲にしてもいいと思っていますか?
- 仕事と生活のバランスについてどのように考えていますか?
- キャリアの変化に対してどれくらいのリスクを取る意欲がありますか?
- 今後のキャリアで何を達成したいと考えていますか? そのために必要なステップは何ですか?
- 自分の強みや得意分野について、どのように活かすことができると考えていますか?
- 経験や知識を次世代にどう伝えていきたいと考えていますか?
- 新しい人脈やネットワークをどのように築いていきたいですか?
- 退職後の生活やキャリアに対して、どのようなイメージを持っていますか?
- 現在の職場での役割や仕事の内容をどのように変えたいと思っていますか?
- 人生の目的やミッションと、仕事の関係性についてどのように感じていますか?
- キャリアの開拓を進めるために、最初に取り組むべきことは何だと思いますか?
20の質問を全て、1回のキャリア対話で投げかけるのではありません。この中からいくつかを選び、問いかけるようにするのです。対話者とスケジュールがあわない場合は、自分自身に問いかけるセルフキャリア対話も効果を発揮します。
これらの質問を通して、自分の価値観や目標、スキルの棚卸しを行い、これからのキャリア開拓に対する明確なビジョンを描くサポートができるでしょう。
まず、過去を振り返ることから始めましょう。これまでのキャリアの中で最も誇りに思う成果や、現在の仕事に対して満足している点、逆に不満に感じている点を明確にすることは、現状を見つめ直す第一歩です。自分がどのような状況で成功を収め、何がモチベーションとなったのかを知ることで、自分の強みや価値観が見えてきます。また、仕事に対する満足や不満を分析することで、現状のキャリアをどのように調整していくべきか、その方向性を見定めることができます。
次に、自分が大切にしている価値観や信念について深く考えることが重要です。キャリアの選択は、その人が何を大切にし、何に意味を見いだすかに深く関係しています。社会に貢献したいのか、個人としての成長を重視するのか、あるいは家族との時間を大切にしたいのか。こうした価値観を明確にすることで、キャリアを進める際に迷うことが少なくなり、判断がしやすくなるでしょう。
さらに、新しいスキルや知識を身につける意欲があるかどうかを考えることも重要です。私たちの働く環境は常に変化しています。そのため、学び続ける姿勢を持つことが、キャリアの選択肢を広げる鍵となります。同時に、自分のスキルや経験が他の分野でどのように活かせるのかを探ることで、新たな方向性を見出すことができます。挑戦したい分野や職種が明確になれば、それに向けたステップも具体化しやすくなるでしょう。
キャリアを考える際は、仕事と生活のバランスも無視できません。現在のライフスタイルで変えたいことや、理想の働き方について考えることは、長期的な満足感に直結します。退職後の生活やキャリアについてイメージを描くことも、未来を見据えた計画を立てる助けとなります。定年後も仕事を続ける意欲がある場合、その働き方や内容が自分にとってどのような形であれば理想的かを具体的に思い描くことが必要です。
また、自己の強みや得意分野を活かす方法を考えることも大切です。自分の能力や経験をどのように活用できるか、そしてそれを次世代にどのように伝えるかを検討することで、キャリアの意義や価値がさらに深まります。これにより、単に自分のためだけでなく、周囲や次世代に対しても貢献できるキャリアを築くことが可能になります。
キャリアの変化には、ある程度のリスクが伴うことを理解する必要もあります。変化を受け入れる意欲があるか、どの程度のリスクを許容できるかを自問することは、キャリア選択の自由度を広げるうえで重要です。さらに、新しい人脈やネットワークをどのように構築していくかも、キャリアの方向性を大きく左右します。人とのつながりは、思わぬチャンスや新しい視点をもたらしてくれることが多いため、積極的に築いていくことが求められます。
最後に、人生の目的やミッションと仕事の関係性について深く考えることが、これからのキャリア形成の重要な要素となります。キャリアが単なる生計の手段ではなく、自分の人生の目標と一致しているとき、仕事への情熱や満足感は格段に高まります。これを実現するためには、自分の人生の目的を見極め、それがキャリアとどのように結びついているかを明確にすることが不可欠です。
これらの問いをベースにキャリア対話を重ね、現時点での暫定的な答えを丁寧に整理することが、キャリア開拓の第一歩となります。具体的な目標や価値観を見定めることで、行動に移す際の迷いが少なくなり、自信を持って新たな挑戦を始めることができるでしょう。
キャリアは人生の一部であり、同時にそれ以上の意味を持つものです。これらの質問を活用しながら、自分らしい道を見つけるためのプロセスを進めていきましょう。キャリア対話がさまざまな部署で日頃から積み重ねられるようになると、組織は生まれ変わっていきます。キャリア対話の積み重ねが社員一人ひとりの可能性に寄り添う組織文化を構築していくのです。
それでは、キャリア対話を始めてみてください!

- 田中 研之輔氏
- 法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事/明光キャリアアカデミー学長
たなか・けんのすけ/博士:社会学。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学。社外取締役・社外顧問を31社歴任。個人投資家。著書27冊。『辞める研修辞めない研修–新人育成の組織エスノグラフィー』『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ&ソウル』『ストリートのコード』など。ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』、『ビジトレ−今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』、『プロティアン教育』『新しいキャリアの見つけ方』、最新刊『今すぐ転職を考えてない人のためのキャリア戦略』など。日経ビジネス、日経STYLEほかメディア多数連載。プログラム開発・新規事業開発を得意とする。
この記事を読んだ人におすすめ

HR領域のオピニオンリーダーによる金言・名言。人事部に立ちはだかる悩みや課題を克服し、前進していくためのヒントを投げかけます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント