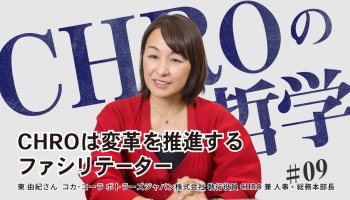ドライバーズシートに座る
――豊田通商CHRO濱瀬牧子さんが語る、キャリアの原点と人事パーソンへのエール
豊田通商株式会社 CHRO
濱瀬 牧子さん

「人事は、事業をリードする『ドライバーズシート』に座るべきだ」。そう語るのは、グローバル企業の第一線で人事改革を率いてきた、豊田通商CHROの濱瀬牧子さんです。なぜ、人事は守りの姿勢から、攻めの役割へと転換する必要があるのか。その答えは、ソニー時代に「自分のキャリアは自分で作る」という文化の中で育まれた、個人の自律性を信じる強い思いにありました。「強い個」が「強い組織」を作るという信念は、いかにして7万人のグローバル企業を動かす力となったのか。濱瀬さんの経験から、変化の時代に求められる人事の役割と、本質的な組織変革を成し遂げるための哲学をひもときます。

- 濱瀬 牧子さん
- 豊田通商株式会社 CHRO
はませ・まきこ/MBA取得後ソニー株式会社にて、国際人事、Sony Universityの設立、タレントマネジメント構築から労務・制度まで、ニューヨーク勤務も含めて人事全般を幅広く担当。2013年より株式会社LIXILに執行役員として入社。上席執行役員、グローバルカンパニーCHRO、グローバル人事本部長などを歴任。2019年6月、豊田通商株式会社に入社、経営幹部、CHROを務める。その他各省庁委員や大学評議委員、講演等。
人事は人の心に火をつける仕事。「強い個人」が「強い組織」を作る原体験
濱瀬さんは長年、人事のプロフェッショナルとしてキャリアを歩んでこられました。人事という仕事のどのような点に魅力を感じていらっしゃるのでしょうか。
人事の仕事は、実に多岐にわたります。私はこれまで、グローバル企業の本社人事と、各国や各事業の特性や事業戦略に基づいた海外・事業部人事の双方の立場を経験しました。実務に関しても、制度や労務管理などの仕組み作りの領域、人材ポートフォリオや採用・育成といった戦略的な領域と、幅広く担当してきました。さまざまな経験を通じて、人事は私の天職だと思っています。
経営資源は「ヒト・モノ・カネ・情報」と言われますが、最初に「ヒト」が来るにもかかわらず、その議論は後回しにされがちでした。しかし、モノもカネも情報も、それを動かすのは全て「人」。人の心に火をつけ、一人ひとりの能力を最大限に引き出し、活躍してもらう。ここに、人事という仕事の最大のダイナミズムがあると考えています。
キャリアのスタートは国際事業部でマーケティングの仕事を担当され、その後人事の道に進まれています。どのようなお考えがあって、事業サイドから人事へと領域を変えたのでしょうか。
大学院に進む前は、マーケティングと人事の両方に強い関心がありました。自身がマネジメントの立場になるにつれて、ビジネスの課題は究極的には「人」に行き着く、という思いが強くなっていったのです。
人事の仕事はマーケティングと非常に似ており、A&R(Attraction&Retention)、すなわち人を惹きつけ最大限持てる力を発揮し共に成長するために何をするか、これは人的資本経営そのものです。事業戦略と人事戦略が表裏一体だとすると、人事にとっての顧客である従業員や組織、そしてそのコインの表裏であるビジネスについてもよりよく理解することが重要です。ゆえにこの仕事は広く深い。その中で、人が最も輝くのは、自らの強みを生かし、貴重な人生の時間の大半を費やして没頭しながら活躍しているとき。その究極のライフストーリーに伴走できる人事の仕事は非常にやりがいがあり、面白いと感じています。
私が社会に出たのは、バブル経済が頂点を迎え、はじけていった激動の時代でした。日本のプレゼンスが最高潮に達した時期と、その後の停滞期を両方経験し、この状況を立て直せるのは「人」しかないと痛感しました。この原体験も、人事への興味を深めたきっかけです。
キャリアオーナーシップや、自律的な人材の重要性について発信されていますが、考え方の根幹には、どのような経験があるのでしょうか。
私のキャリア観は、ソニーでの経験に大きく影響されています。ソニーには、創業当初から「自分のキャリアは自分で作る」という根強い文化がありました。創業者の一人である盛田昭夫さんが、入社式で「ソニーが合わないと思ったら、今日辞めていい」と語った逸話は象徴的です。個人と会社が最高の関係を育む上で、個人にも対等に自律的な考えをもって仕事をしてもらいたいという非常に意義の深い考え方だと思います。
もう一人の創業者である井深大さんが提唱した「人材石垣論」も、私の思想の根幹をなしています。企業はお城と同じ。その城壁は、同じ形のブロックでできていては脆いけれど、さまざまな形をした石ががっちりと組み合わさっていれば決して崩れない。さまざまな人材が力を発揮することが、強い組織の構築につながります。井深さんは外形的属性からのダイバーシティでなく、個人ひとりひとりの力を活かすという本質的な多様性の力を、1960年代に認識されていたのです。

多様性の本質を、半世紀以上も前に見抜いていたのですね。
その通りです。DE&Iで重要なのは、単に多様であることではありません。ミュージックのバンドやオーケストラと同じで、異なる個性を持つ人々が、一つの目的に向かって組み合わさることで生まれる強さこそが本質です。実現するためには、一人ひとりが自身の強みとは何なのか、仕事を通じてどのような人生を送りたいのかを考える必要があります。
会社が一方的にキャリアパスを示すことは、本人の成長を願ってのことで、価値のあることです。それと同時に個人は、自らのキャリアや人生について主体的に考え、それら両者が高いレベルでかみ合ったとき、「強い個人」が「強い組織」を作るという、理想的な関係が生まれるのではないでしょうか。
「Why」から始める。人事改革を形骸化させないために
ソニー、LIXIL、そして現在の豊田通商と、異なる文化を持つ企業で改革を推進されてきました。豊田通商では、54あった評価指標を抜本的に見直し、5項目のグローバル共通指標に刷新されたそうですね。
改革を行う際に最も重要なのは、まず「なぜ、これまでの仕組みがあったのか」をしっかりと理解し、リスペクトすることです。過去の仕組みを設計した当時の意図や、それが果たしてきた役割を分析した上で、現在の事業戦略や経営が目指す方向に合わせて、何を変えるべきかを考えます。
かつて54項目あったコンピテンシー評価は、その時代では有効でした。しかし、当社はこの20年で社員数が7倍、企業価値は35倍と、組織の規模が劇的に変化しています。1万人規模の組織で有効だった仕組みが、世界7万人のグローバル組織でそのまま機能するとは限りません。54項目は多すぎて、会社の求心力として何が大事な評価指標なのかがあいまいという現実的な問題もありました。
組織の成長に合わせて、仕組みも進化させる必要があったのですね。
はい。評価指標を刷新した目的は二つあります。一つ目は、グローバルでの「共通言語」を作ることです。世界中の誰もが理解できるシンプルな指標があれば、国や組織を超えた人材の異動や人の可視化が容易になります。
二つ目は、求心力と遠心力のバランスを取ることです。組織が大きくなると、経営の目が隅々まで届きづらくなります。その中でグループとしての一体感を保つには、「豊田通商グループが大事にしている価値観とは何か」をあわせること、つまり個人に対する求心力が必要です。刷新した五つの項目は、その求心力の核となるものです。
こうしたミニマムな共通言語は、グループ社員全員に求められる成長ドライバーとして作用し、各事業や各拠点が独自の権限で遠心力を効かせて自律的に活動することにつながります。
重要なのは、評価指標は社員に「マルバツ」をつけるためのものではない、ということです。むしろ、グループの一員として皆が伸ばし続けてほしい資質を示すものであり、だからこそ、シンプルなものにしました。これは、評価制度を「管理のためのツール」から「成長のためのツール」へと転換する試みでもあります。
大きな改革には現場からの反発も想定されますが、どのように乗り越えてこられたのでしょうか。
改革を成功させるために、意識していることが三つあります。
一つ目は、先ほど申し上げた「過去を否定しない」ことです。これまでの歴史や背景に敬意を払い、なぜ今、改革が必要なのか意識を合わせていくことが重要です。
二つ目は、「徹底的に現場に行く」ことです。机上の空論ではなく、現場の声を聞き、肌感覚をつかむ。毎年、年間の3分の1以上は国内・海外に出張し、現場の社員と対話を重ねました。
そして三つ目が、それらを通じて「信頼関係を構築する」ことです。「この人が言うことなら、一度やってみようか」と思ってもらえる関係性がなければ、何も始まりません。
過去へのリスペクトを示しながら、対話を通じて信頼を得て、一緒に目指す未来を語る。この三つが相互に作用することが、改革には不可欠だと考えています。
改革の成果として、どのような変化が表れていますか。
最も確実な変化は、海外のローカルメンバーの活躍です。日本に本社があるため、これまではどうしても日本人中心の組織運営になりがちでした。しかし、サクセッションプランをポスト(役割)ベースで検討する仕組みを導入したところ、ダイバーシティが一気に進みました。
役割を果たす上で、国籍は本質的な問題ではありません。客観的な視点を持ち込んだことで、現在の事業フェーズを考えればローカル人材がポストを担う方が合理的である、という判断が可能になりました。
これは、人事を「科学する」アプローチとも言えるかもしれません。もちろん、人の持つ経験値や肌感覚も重要です。その良さを生かしながらも、客観的な仕組みやデータを掛け合わせることで、バイアスを排し、より最適な人材配置が実現できると考えています。時間はかかりますが、会社が着実に変わりつつあるという手応えを、多くの社員が感じていると思います。
「日本 対 グローバル」ではない。7万人組織の求心力を生む「共通言語」とは
濱瀬さんにとって、「グローバル」はキャリアを通じたキーワードだと感じます。多くの日本企業が「グローバル化」を課題としていますが、どのように捉えるべきでしょうか。
私のキャリアは常に「グローバル」の軸と共にありました。しかし、私が考えるグローバルとは、単に国境を越えることではありません。そもそも「グローバル化を進めましょう」と声高に言っているのは、日本企業くらいではないでしょうか。無意識のうちに「日本 対 グローバル」という二項対立の構造で物事を捉えているからです。
本来、グローバルは一つです。目指すべきは、会社そのものが「グローバル・ワン」な組織になることであり、それがグローバル化の大前提です。その上で、中央集権的に進めるのか、各地域に遠心力を効かせるのかは、事業戦略によって異なります。豊田通商に入社した際も、まず経営陣と「われわれが目指すグローバル化とは何か」という定義そのものを議論することから始めました。

豊田通商という舞台を選ばれた理由にも、濱瀬さんのグローバル観が関わっているのでしょうか。
はい、私が豊田通商を選んだ理由は三つあります。
一つ目は、経営陣が本気でグローバル展開を考えていたことです。商社というとトレーディング主体のイメージが強いかもしれませんが、当社は事業利益が8割を占めます。商社パーソンとして入社した社員が、自動車部品工場を運営したり、風力発電の現場でヘルメットや作業着を着て実務に携わったりするなど、自ら現場に入り込んで事業を推進しています。現場でお客様に寄り添い、共に悩みながら成果に至るというスタンスは、AIにはできないヒトの価値貢献であり、私の育ったメーカーの感覚にも近いと思いました。
二つ目は、アフリカというラストフロンティアで事業を展開していることです。当社はM&Aを通じて、アフリカ大陸54ヵ国全てをカバーするネットワークを持っています。私はこれまで、中国やインドで人事戦略を先行して手掛けてきましたが、ゼロから未来を作り上げることができるアフリカに計り知れない可能性を感じ、非常に心が躍りました。
そして三つ目は、良い意味での「マイノリティ」性です。当社はBtoB主体ということもあり、さほどコーポレートブランディングに力を割いてこなかったように思います。しかし、とてつもないポテンシャルを秘めており、社内外のEmployer Brandingにも力を入れ始めています。自分たちが価値を信じる事業にいち早く取り組める強さがあり、そのポテンシャルを解放することに、大きな魅力を感じています。
ご自身の経験が、新しい挑戦の場で生きると確信されたのですね。
おっしゃるような立派なものではありません(笑)。しかし、常に○○初というチャレンジを通して、大変さはあってもそれ以上の面白さと、仲間で乗り越える楽しさを感じて仕事をしてきました。それらの経験の一つ一つが、今につながっています。人事だからといって守りだけではなく、常に新しいことに挑戦させてもらえました。
2000年代初頭、インド工科大学(IIT)からの新卒採用とインターンを始めた時は、日本企業はまだどこも取り組んでいませんでした。ソニーがハードからソフトに事業戦略をシフトしていく中で、今後はソフトウエア人財が不可欠という方向性が出ていた頃です。たまたまNHKでインドのIT企業の採用を見て「これだ」とひらめき、徹夜で企画書を書いて、翌朝には「インドに行かせてください」と提案しました。
会社がさまざまな挑戦を許してくれたからこそ、今の私があります。「人事だから」という枠にとらわれず、会社や世界の未来のために良いと思うことを仕掛けていく。仕事のダイナミズムは、そうした主体的な行動から生まれるのだと信じています。
人事がドライバーズシートに座る。事業をリードするために心がけるべきこと
人事パーソンに向けて、これからの時代に大切にしてほしい姿勢など、メッセージをお願いします。
一言で申し上げるなら、「ドライバーズシートに座る」ことをぜひ意識してください。人事の役割には、車の座席で例えると三つのポジションがあります。
一つ目は「バックシート」です。これは人事の仕事の一丁目一番地。労務問題への対応や制度の安定運用など、いわゆる守りの人事により、社員の健康と安全、人権確保といった土台を盤石にします。これがゆらぐと、元も子もありません。会社の根幹を支える上で不可欠な素晴らしい仕事です。
二つ目は「助手席」。HRビジネスパートナー(HRBP)として事業に寄り添い、課題解決を目指し、組織力を最大化する役割です。
そして三つ目が、「ドライバーズシート」です。ときには人事が事業をリードしたっていいではないか、ということです。5年先、10年先を見据えて、「この事業には、こういう人材戦略が必要」と、こちらから仕掛けていくことが今の人事には求められています。
日経新聞の一面に載るような取り組みを人事が主導し、会社の成長をドライブしてほしい。黒子に徹するだけでなく、自らがドライバーズシートに座り、会社を前に進めていく役割を担ってください。
トヨタグループである豊田通商ならではの、示唆に富む比喩だと感じました。
共に人に携わる仕事をしている皆さんへのエールです。これまでの人事は、管理屋・制度屋としてバックシートや助手席の役割を求められることが多かったかもしれません。しかし、これからはもっと多くの人事パーソンにドライバーズシートへ座ってほしい。そうした気概を持つ人々が増えることが、企業そして社会全体の活力を生み出すと信じています。
最後に、目指す未来の組織像をお聞かせいただけますでしょうか。
「自分達は最高最強のチームだ」「いい仕事したな。」と矜持を持てる組織がいいですね。年齢や国籍、役職に関係なく、誰もが「自分はこう思う」と堂々と発言できる組織です。会社の中で一番偉いのは、役職者ではなく、良いことを言う人や、良いことをしている人。仲間と仕事を通じて学びあい、高めあい、成長し、共に次元上昇していく楽しさを経験する、そんな文化を醸成していきたいですね。
そして、7万人の社員一人ひとりが、豊田通商グループという広大なフィールドの中で多様な経験を積み、自らのキャリアを主体的に築いていく。個人のステージが上がることで、会社のステージも上がっていく。そんな未来の姿を想像すると、楽しみでなりません。強い個人の集合体としての「最高最強のチーム」作りが、私の最大のモチベーションです。

(取材:2025年7月18日)
この記事を読んだ人におすすめ

各企業の人事リーダーが自身のキャリアを振り返り、人事の仕事への向き合い方や大切にしている姿勢・価値観を語るインタビュー記事です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる2
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント