「納得感」とは「目標の明確さ」「目標達成の意欲」そのもの
――上司と部下と組織をつなぐリモート時代の人事評価
神戸大学経済経営研究所 准教授
江夏 幾多郎さん
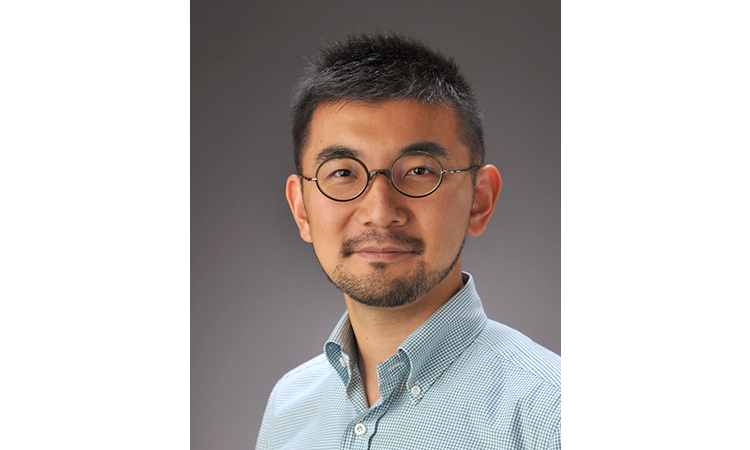
組織を機能させるうえで、避けては通れない人事評価。しかし、人事評価と聞くだけで、憂鬱な気分になる人は少なくありません。その要因のひとつに、評価の納得感を得られにくい点が挙げられます。加えて昨年からリモートワークが一気に普及し、評価の不透明性が懸念されています。オフィスワークに比べて部下の様子を捉えにくい状況の中、上司はどのように人事評価に臨むとよいのでしょうか。またどうすれば、評価の納得感を高められるのでしょうか。人事評価についての従業員の認識メカニズムを研究する神戸大学経済経営研究所・江夏幾多郎さんに、リモート時代ならではの人事評価の課題と改善の糸口を聞きました。
- 江夏 幾多郎さん
- 神戸大学経済経営研究所 准教授
えなつ・いくたろう/1979年生まれ。一橋大学商学部卒業。同大学にて博士(商学)取得。名古屋大学大学院経済学研究科を経て2019年より現職。専門は人的資源管理論、雇用システム論。主著に『人事評価における「曖昧」と「納得」』(NHK出版)など。
リモートワークにより人事評価の課題が露見した
この1年、ホワイトカラーを中心に、多くの企業で働き方が大きく変化しましたが、人事評価にどのような課題をもたらしたのでしょうか。
オフィスワークからリモートワークに移り変わったことで、よく聞かれるようになったのは「相手の雰囲気がつかみづらくなった」という声です。画面越しのやり取りでは、十分にわかり合えたという感覚が得られにくい。オフィスワークで一緒に働いていた頃なら、自然と入ってくる情報やその場の空気も含めて相手のことが理解できていたけれど、それがなくなってしまった、というのです。人事評価についていえば、部下を見ている、上司に見てもらっているという感覚が失われ、それが不安として表れているのだと思います。
裏を返せば、これまでは雰囲気で人を評価していた側面があった、ということでしょう。社員の目標も、達成に向けたプロセスも、評価指標として客観化をしつつも、実際はさまざまな要素が絡んでいて単純に測定できないものばかりです。また、上司は一緒に働いているからといって、部下を四六時中見ているわけではありません。上司も人間ですから、認知能力には個人差があり、限界もあります。そうした曖昧な要素をはらむのが、人事評価なのです。
だから今回のケースも、離れ離れになったから評価できなくなった、という話ではないと思います。もともと人事評価が抱えていた課題が顕在化したのです。純粋にリモートワークが問題となっているケースもあるのかもしれませんが、従来の感覚的な評価では新しい状況に適応しきれず、モヤモヤ感が増していると考えるのが適切でしょう。何もかもリモートワークのせいにするのは危険です。

働き方が変わって上司が部下の状況がつかみづらくなったことから、成果主義やジョブ型雇用の導入についての議論が活発化しています。
仕事に対するモチベーションや向き合い方は、成果が評価される場合とプロセスが評価される場合とでは、表れ方や性質が異なります。人事評価の方針は、会社の理念や価値観、事業戦略、あるいはもっと具体的にいうと職務特性や社員同士の連携のあり方によって決められるべきものです。例えば業績を重視するほうが職場内での連携がうまく回り、事業目標の達成が見込めるのであれば、成果主義を適用するのが望ましいといえます。しかし、それらの要因はリモートワークに移行したからすぐに変わるというものではないし、職場や社員にはリモートワークへの適応力があるはずです。
これを踏まえると、リモートワークになったから成果主義にしよう、という考えは、やや短絡的ではないでしょうか。確かに個人的成果による評価はプロセス評価よりも明快ですから、導入して数年はうまく回るかもしれません。しかし、集団戦で力を発揮してきたような会社だと、長期的に見ると意図しない方向へ組織が動き、事業戦略と合わなくなることも起こりうるでしょう。リモートワークによる不透明性を改善するなら、振り返りの回数を増やしたり、行動規範に合った業務プロセスを設定したりするなど、別の方法があるはずです。「リモートワークの環境下では成果評価が合っていて、プロセス評価は向いていない」という考え方に、私は疑問を感じています。
ジョブ型雇用についても、同じことがいえます。成果主義もジョブ型雇用も本来の意味とは違って、「今までとは違う新しい評価や雇用の総称」として用いられている言葉のように感じます。
おそらく背景には年功主義的な人事慣行があるのでしょう。人事「制度」とはあえて言いません。経験年数は成長の代理指標ではない、年齢は会社への貢献の代理指標ではない、ということは半世紀以上常に言われてきたし、その流れの中で職能資格制度、職能給、目標管理、業績給、と言った人事制度が登場してきました。
しかし実際に運用してみると、従業員の能力や業績の評価が難しい。結局は年齢や経験年数が高い人に高い評価がついてしまい、年功序列がなかなか是正されない。こうした、少なくとも一部の人にとってストレスフルな状況の中、リモートワークが広まり、あらためて成果主義やジョブ型雇用が脚光を浴びているだけなのだと思います。年齢に頼ってしまう運用慣行の是正が求められるわけですが、制度を変えるだけで慣行の是正に至ると考えるのはあまりに楽観的です。
正確に測る努力のプロセスに評価の納得感は生まれる
評価手法をどうするかといった部分ばかりに終始しても、小手先の議論になってしまう、ということでしょうか。
評価項目には、会社から社員に向けての期待が現れます。こういう貢献をしてほしい、こういうプロセスでやってほしいという期待は、会社の事業が変わらない限り変わらないはずです。「これまでの伝え方が悪かったので改める」というのならわかりますが。そして人事評価で大事なのは、貢献の定義が社員の行動基準に沿っていること、また、「望ましい貢献や行動」が社員に腹落ちした状態にすることです。少し評価項目や制度を変えたくらいでは、“腹落ち”には至りません。
なぜなら、言葉の受け取り方は人によって違っており、それをある程度すり合わせる必要があるからです。例えば、成果や業績を”Performance”と表現することがあります。しかし、この言葉に含まれる意味は結構広いですよね。音楽やダンスでも同じ言葉を使うし、行動そのものを指すこともあります。すなわち「パフォーマンスを見る」とはわが社にとってどういうことなのか、どうあるべきなのか、それを定めることがまず大事になってくるのです。
さらに、従業員一人ひとりに期待するパフォーマンスを、上司と部下の間で握り合う必要があります。会社が定める評価項目について、「あなたにとっては具体的にはこういうことですね」などと、きちんと個別に定義する。評価項目は全社や事業部、階層で共通のものを使うので、抽象的な表現にとどまりがちです。しかし、担う仕事や役割がそれぞれ違うので、それぞれの立場で落とし込むことで自分ごとにする、合意形成のプロセスが必須なのです。この過程が抜け落ちると、会社としての評価基準はきちんと示されていても、日々の業務の指針にはなりえません。
それが評価の納得感の欠如や不満感につながってしまうのですね。
計測できる評価要素なら、可能なものはできる限り客観的な形にしたほうが望ましいのは確かです。仕事や活動を要素分解し、今年はこれを何回やろうとか、今月は先月比で105%をめざそうとか、測る努力は必要だと思います。ただ、仕事が複雑であればあるほど、ホワイトカラーを中心に、あらかじめ成果を数字では定義できない要素が出てくるでしょう。それにイノベーションや新しい価値は、数字で測りきれないところを攻めることで見出せるものです。
そうした予め定められない部分について日々の仕事の中で徐々に可視化したり、優先度の低い目標を落としたりするといったことを、上司と部下が時折合意形成をしなおすことが大事なのだと思います。特に複雑なパフォーマンスを追求するときは、何をどうすべきかについて、議論し合うことが欠かせません。上司だけでなく部下自身が当事者となって。複雑だから測れない、などといって、上司が部下の預かり知らぬところで“鉛筆なめなめ”で評価し、後から部下が文句を言うのではなく、評価に先んじて上司と部下が協力して正確に測ろうとするプロセスの中に、評価の納得感が生まれるはずです。
定義づけの部分で人事や評価者、さらには被評価者自身がどれだけ手をかけているかによって、働く人たちの評価に対する捉え方も変わってくるはずです。結局のところ、合意形成のプロセスについてこれまでさぼりがちだったことが、リモートワークになったことで露呈したに過ぎないのだといえます。
一方で、個別に評価項目を再定義するのは、とても手がかかることです。
たしかに、それ単体では、決して楽なことではありません。しかし、そもそも従業員が評価項目を理解していない、評価結果に納得していないと、どうなるのでしょうか。評価項目が示すのは会社が社員に期待することなので、社員がそれに納得できていない場合は「どう貢献すればいいのか、わからない」あるいは「どう貢献すればいいのかはわかるが、貢献する気にはならない」という状態だといえます。両者とも、評価項目に対する腹落ちができていないことから生じるものです。どちらか一方だけでなく、両方の問題を抱えている場合もあります。
納得感のない状態で働き続けても、いいことは何ひとつありません。職場を漂流し、目の前のことに打ち込めないような状態では、生産性にも影響するはずです。また、何が評価されているのかよくわからない中で評価結果を言い渡されたところで、受け取りようがないでしょう。
逆に今述べた二つの問題を克服できたら、評価の項目にも結果にも納得しやすくなるはずです。「納得感は目標の明確さや目標達成意欲そのものだ」と捉えるといいと思います。評価項目と日々の業務上の目標は明確に結びついているので、納得感を日々の業務上のやり取りの中で培っていこうと考えれば、負担感も軽減されるのではないでしょうか。
目標設定時の合意形成と中長期的視点を持たせることの重要性
人事評価は評価する時点ではなく、目標を決める最初の段階がとても大切だといえそうです。
そうだと思います。最初の段階で合意形成ができていると、後で楽になる。評価項目をそれぞれの社員のサイズに落とし込んでおけば、互いの共通言語ができるので、1年を通じて意思疎通がスムーズになるでしょう。
たとえ状況が変わっても、「じゃあ、こうしましょう」といった話し合いを行いやすくなります。もし期待するパフォーマンスを具体化しないまま1年過ごしたら、上司も評価の段階でとても苦労するでしょう。何となく正しい、間違っている、という判断になってしまいますから。フィードバックするにも、「どうせ彼/彼女は納得しないだろうな」と思うとストレスになるし、評価される側も「自分のどこを見て、この評価になったのだろう」と感じるでしょう。
そもそも組織において、一人で完結する仕事はありません。社員自身が組織という全体のシステムの中で何を担っていて、その遂行には誰とどのような関係を築き、どう調整するのかを理解していなければ、チームで成果を上げることはできないはずです。活躍のフィールドを日常的に自覚できていれば、日々のコミュニケーションも具体的なものになるでしょう。人事評価には個々の位置づけを定義し、組織化を促す役割もあるはずです。単に「A,B,C,D」と、ランク付けするツールではないのです。
評価される側は、ランクに気を取られがちです。
それは仕方がないし、会社にも原資の制約がある以上、評価の不満をゼロにすることが難しいでしょう。だからこそ人事や上司は、社員の短期的な不満を長期的に解消するための別の視点を与えることが大事なんです。社員自身も積極的に関与して年初に目標を設定し、定期的に自身の成長を振り返ることで、彼らの次の仕事や目標に結びつけていく。そのサイクルを数年かけて回すことでパフォーマンスを伸ばし報酬につなげていく、あるいは「今の私はチームや組織の中で、こういう役割を担っているのだな」という意識の動機づけを促して仕事に打ち込みやすくする。
キャリアには、波があります。自分の力だけではどうにもできず、不本意な評価に終わることもあって当然です。経営状況が悪かった、異動したばかりで周りとの関係がまだ構築しきれていない、上司との巡り合わせが悪かった、といったことはあり得ます。単年での評価にこだわり過ぎると、評価が今ひとつだったときに自分の中で折り合いをつけられず、後々まで引きずってしまいがちです。むしろ経験を客観的に捉え、「昨年はこうだったから、今年はこうしよう」などと、長い時間軸の中で自分が達成すべきことを意識できるほうが、本人にとってもいいはずです。そのうえで、何年も続けて納得できる評価を得られないのなら、異動や転職を希望するのも選択肢のひとつだと思います。そうした人にきちんと報いるように人事や上司が汗をかくことが、より良い組織づくりにつながります。
会社は、社員の無関心や善意に甘えるべきではありません。人事評価制度の改善に努めると同時に、上司と部下の間で評価項目と具体的行動について合意すべきです。それでもなお、社員の中に「正しく評価してもらえなかった」という感覚が生じることもあるでしょう。そのときに「上司は日ごろから、丁寧に目標をすり合わせてくれた」「会社が事業方針に合わせてこういう項目を立ててくれた」などと、制度や運用の素地に誠実さを感じられると、「今年の評価は今ひとつだったけど、そういうことも当然ありうる」と、結果の受け止め方も変わってくるはずです。
人事評価には主観的観点が入り込む以上、信頼関係の構築が欠かせません。
私はこのごろ、定量評価と定性評価、あるいは客観的評価と主観的評価は、別の次元で語るものではないと考えています。なるべく数値的に測定する努力を重ね、最後の詰めにあたる、見切れない部分に感覚が入り込んでくるのではないでしょうか。
上司と部下で評価項目の定義づけをするのは、評価用のものさしをつくるプロセスだといえます。実際の評価では、ものさしの目盛りが0から10だとしたら、ある部下が6か7のどちらかの評価か、くらいまでは割と客観的に行えます。そのうえで「6なのか7なのか」という、“ラストワンマイル”のところで主観が含まれるようになる。それは上司か部下どちらかの思い込みではなく、互いに議論を尽くす中で見えてくる、「共同的主観」であるべきです。
共同的主観は最終的にどっちに転ぶかが予見できない、いわば“落としどころ”ですが、そこに真実性を宿らせるためにも、上司と部下の1年間の共同作業が必要になります。年度末の面談だけで落としどころが見つかるなら、誰も苦労はしません。評価項目は、日々の仕事に関することを取り上げているはずです。本来は1年中向き合うべきものであり、日々の行動のチェックシートとして使い続けてこそ、評価結果に確からしさが備わるでしょう。もちろん、すでに述べたように、部下にとって不満がゼロになるわけではないでしょうが、そこには許容の余地も備わるはずです。
1年かけて落としどころを調整していくとなると、リモートワーク下でも上司、部下間のコミュニケーション頻度を保つことがポイントとなるのでしょうか。
一緒に働いている、共にいる、という実感を得られる場を築くことが重要です。それには相手への関心や相手を知るためのアクション、あるいは相手に自分を知ってもらうためのアクションが今まで以上に必要となるでしょう。そうしたコミュニケーションを上司と部下の双方が意識しなければ、共に働く場にはならないのでしょうね。
場をつくる意味では、この1年は大きなチャンスでした。急にリモートワークの必要に迫られて、上司も部下も関係なく、一緒にあたふたできたわけですから。上司から部下に「困っていることやノウハウを共有しよう」「おすすめの仕事術があれば教えてほしい」などとお願いをし、ゼロベースでコミュニケーションのあり方を対等な立場で構築するいい機会だったと思うんです。チームで仕事をする、目標を達成する、という意識の醸成にもつなげることができたでしょう。

評価制度改革の前にチームのあり方を振り返る余裕を設ける
個々のコミュニケーション能力も問われますね。
リモートワークによって、それが明らかになりました。働き方の変化にうまく適応できた職場は、意味のある声かけや相談が、日常的に行えていたようです。「最近どう?」ではなくて「○○の××の件は、今どういう段階ですか」と尋ね、答えるほうも「大丈夫です」ではなく「◇◇な状態で、△△を待っているところです」と解像度の高いコミュニケーションが習慣化すれば、リモートワークでも意外に一体感を持てるものです。
人事評価を上手に活用すれば、ある程度具体的なやり取りが可能です。また、マイクロマネジメントの回避にも役立ちます。部下の仕事の押さえておくべきツボがわからないから、連絡の頻度を増やしたり、詳細な日報を要求したり、常時カメラをオンにすることを求めたりするなど、包括的な監視・管理を行ってしまう。「ここさえ握っておけば大丈夫」というポイントがわかっているなら、「上司はずっと監視しているけれど、自分のことを全然見ていない、わかっていない」ということにはならないはずです。
おそらく今は、管理職を中心に部下との関わり方をやり直したり、適切なマネジメントをあらためてトレーニングしたりするタイミングなのでしょう。「何となく」では組織を回せなくなっているため、管理職にも「変わらなければまずい」という動機が生まれていますし、絶好の機会ですよね。コロナショックが一段落したときに、組織も人もアップデートできていなかった、というのではもったいなさ過ぎます。コロナショックを機に顕在化した課題を克服しておくことが、それぞれの職場にとって大事なのだと思います。
現場での人事評価の運用やコミュニケーション活性化に向けて、人事は何ができるのでしょうか。
人事評価の「課題」に見えるものは、実は「課題」でもないのかもしれません。組織の共通目標の実現に向けて、上司と部下がそれぞれすべきことを果たすために、情報交換や意思疎通を図るというのがベースにあって、人事評価は機能します。評価結果への納得感、目標達成、成長、の全ての面において。そのため、会社や職場としては、人々がチームとして連携する際のボトルネックがどこにあって、それをどのように克服していくかを考えて実践し、改善していく余裕が必要だと思います。
ただし実際の現場は、「この人数でどうやってこの業務量をこなせばいいのだろう」と焦っていて、チームのあり方をじっくりと振り返っている余裕などない、というのが本音でしょう。だからこそ人事は、経営に対して、現場に余裕を与えるように働きかける必要があります。人員確保のための予算を獲得する、個人や集団の能力開発のための時間的余裕を設ける、職場が前向きにかつ程よい負担の中で活動できるような事業上の領域や目標を定める、などです。
そして現場に対しては、チームにもっと目を向けてほしいと訴えていく。もしかすると、お願いに近いのかもしれません。そのうえでチームビルディングのノウハウ共有や情報提供、あるいは表彰制度やワークショップを開催するなど、組織への関心を醸成する風土づくりを、経営や人事が主体となって推進していくべきだと考えます。
最後に、人事はどのように人事評価と向き合うべきか、お聞かせください。
人事評価は単に社員を査定したり、報酬を割り振ったりするだけのものではありません。経営や事業の方向性や価値創造の基準を示し、社員たちがチームとして仕事を遂行する道しるべとしての役割も果たします。また、評価項目は万能ではありません。評価制度の段階で示せるのは大まかな指針であって、社員一人ひとりへの腹落ちは実際の運用に任せないといけません。だからこそ、人事評価が仕事に生かせる可能性、生かす意義を現場に伝え、実践を支援しなければなりません。
しかし、現状としては、人事評価について当事者意識や役立ち感を持てている人はほとんどいないでしょう。人事は現場で起きていることを観察し、彼らの関心に寄せる形で評価制度を設計して、浸透を図っていくべきです。決して独り相撲になってはいけません。
人事評価の積極的な理解や活用が組織力の向上につながり、ひいては部門の業績や自分の待遇につながるんだと、経営と現場でWin-Winを感じられるような巻き込みを図ることが大切です。人事評価への現場のニーズを作り出し、それにきちんと答えるというマーケティングが必要になるわけですが、人事自身が自信を持って現場に示せる人事評価の理念と制度を持ってほしいと思います。
(取材:2021年3月25日)
この記事を読んだ人におすすめ

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる1
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント












