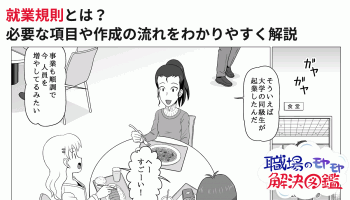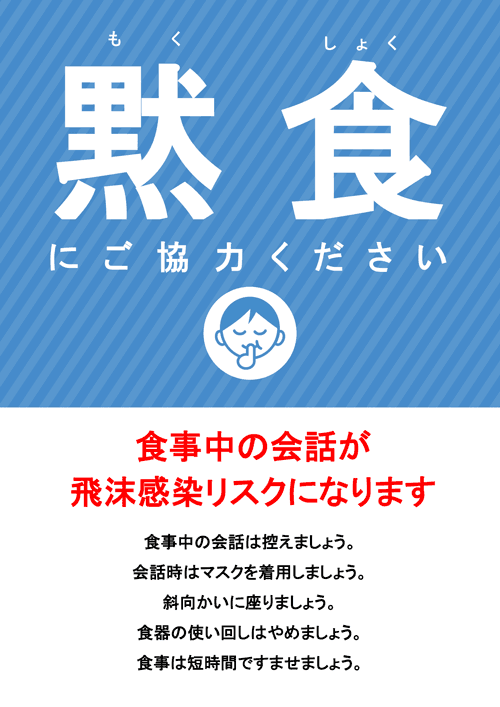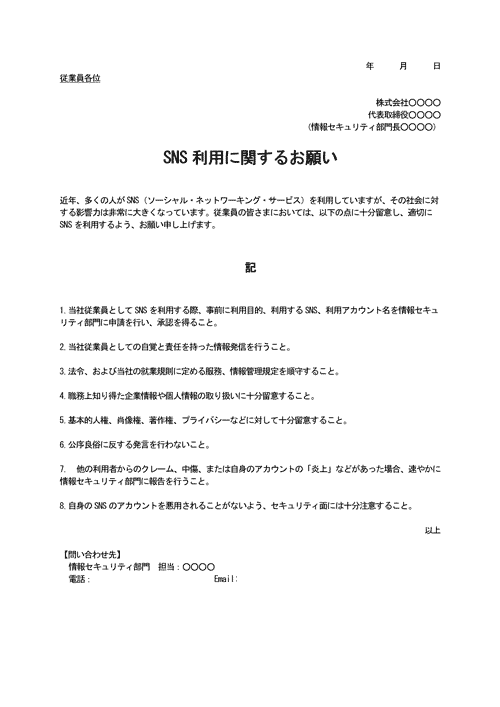コンプライアンス、リスクマネジメント
近年、企業経営におけるコンプライアンス(法令遵守)、リスクマネジメントへの対応が重要視されています。適正な対応を怠ると、社会的な信用を無くすばかりか、社内における人と組織に対しても大きなダメージを被ることになるからです。ここではコンプライアンス、リスクマネジメントをどのように進めていけばいいのか、そのポイントを解説します。
1.コンプライアンス、リスクマネジメントとは
コンプライアンス、リスクマネジメントが求められる背景(目的)
「コンプライアンス」は「法令遵守」と訳されますが、遵守するのは法令だけに限りません。「企業倫理」などの企業が求められるさまざまな規範や、社会的な約束事・常識など、広範囲に及びます。事業活動を進めていく中で、それらを適正かつ健全に行うための仕組みや仕掛け作りが、「リスクマネジメント」です。
現在、従業員規模や業種にかかわらず、多くの企業でコンプライアンスやリスクマネジメントに対する取り組みが積極的に行われており、その内容も非常に高度なレベルとなっています。また、関連子会社やグループ企業における行動規範や社内規程を整備して社員に対する研修や勉強会を行い、内部通報窓口を構築することは、当然の対応として認識されています。
ビジネスがグローバル化、複雑化している昨今内外に潜んでいるさまざまなリスクに対して、企業は敏感でいなければなりません。コンプライアンス違反による不祥事は、瞬く間に訴訟問題へとつながり、深刻なダメージとなるからです。コンプライアンス・プログラムをいかに効果的に機能させるかは、企業にとって重要な課題といえます。

コンプライアンス、リスクマネジメントを無視することで被るダメージとは
では、コンプライアンス、リスクマネジメント上の問題が発生したとき、企業は具体的にどのようなダメージを被るのでしょうか。まずは、行政からの罰則・処分があります。近年、法令違反に対する行政の対応は、より一段と厳しくなっています。以前は是正勧告を出し、それに従わなかった場合に罰則を科すというスタンスでしたが、コンプライアンスが重視されるようになった2000年以降は、違法行為が確認された段階で、摘発や処分が可能になる「直罰規定」を盛り込むケースが増えています。
また、訴訟手続きが簡素化されたことにより、株主代表訴訟を起こしやすくなったことも、影響を及ぼしています。例えば、コンプライアンス違反で企業がダメージを受けて株価が下がった場合、株主は経営層に対して必要なコンプライアンス体制の構築を怠った責任を強く問い正し、損害賠償を求める訴えを起こすことが現実的になっています。裁判所がその責任を認めれば、社会的信用やイメージが大きく損なわれるのは間違いありません。
違法行為を当然とするような事業運営を行っていると、従業員も不正が行われるのを当たり前と感じ、コンプライアンスに対して“鈍感”になります。その結果、消費者や取引先への不当な営業、自社の物品や資金の横領、不良品の見逃しなど、問題を起こしやすい職場環境となってしまいます。このような状態では従業員のモラルや忠誠心が低下し、一方で、離職者も増えていくでしょう。
その結果、「内部統制の効いていない企業」「リスクマネジメントができていない企業」というイメージが世の中に広がり、長年かけて築き上げてきた信用は一気に失われてしまいます。消費者・取引先からは不買や取引自粛などの動きが出て、売上・収益が大きく低下。すると株価も下がり、安定株主からも見放されてしまいます。仮に事業を継続でても、企業イメージ、ブランドが失墜したことにより、採用競争力は著しく低下するでしょう。良い人材が採用できない状態が続くと、長期的に企業力が低下することになります。
近年の動向
2000年以降、バブル崩壊後の日本経済の立て直しを目指して、規制緩和が進められました。規制を撤廃し、民間企業の参入を促すことによって、市場を活性化させ、経済成長を実現する政策が取られたのです。ただ、企業の自由な活動に委ねると、社会の安全・公正が保てないおそれがあります。企業に対しても、自己責任体制の確立や情報公開を求める動きが強まった結果、規制改革とセットで企業の責任ある行動を求めることが盛り込まれたさまざまな法制度が、一気に導入されることになりました。例えば、「公益通報者保護法」「改正独占禁止法」「会社法」などは代表的なものです。
このような規制緩和によるさまざまな変化によって、企業は適正なコンプライアンス対応とリスクマネジメントを強く要請されることになりました。企業はそれまでの社内体制を評価し直し、改めてコンプライアンス&リスクマネジメント経営へと、改革を進めていく必要に迫られているのです。さらに近年では、事業の適正な運営、労働者保護の観点から、労働関連の法改正が盛んに行われており、こうした動きをより加速させています。
特に、リスクマネジメントの観点からすると、「現在のコンプライアンス体制の評価」→「コンプライアンス経営の改革方針の策定」→「コンプライアンス経営の方針の採用・決定」→「コンプライアンス改革の実施」→「監査・チェック・問題処理」→「継続的な改善」といった一連のプロセス管理が、一段と求められるようになっています。
2.コンプライアンス、リスクマネジメントの対象
人事労務管理の観点から、企業が留意しなくてはならない代表的なコンプライアンス、リスクマネジメントの対象と、そのポイントを解説します。
採用・雇用管理
【募集・採用】
人事労務管理の最初のプロセスが採用、それに続く雇用管理です。まず「募集」に当たって留意しなければならないのは、年齢や性別に関する規制が設けられていることです。そして、募集する段階では、「従事すべき業務の内容」「労働契約の期間」「賃金の額」など、労働基準法で決められた事項を明示しなくてはなりません。
「採用」の際は、「採用面接」において、募集業務に関係のない質問は差し控えなくてはなりません。特に、基本的人権に関わる身上、経歴、思想、信条などに関する情報収集は禁止されています。また、「内定」に関しては、法令ではその定義や効力に関する事項について、特に規定されていません。そのため、採用することが決定した者に対しては、「通知書」を交付するなどして、内定に関する諸条件について書面で交わしておくことが重要です。
【雇用契約】
「雇用契約」は、期間の定めのない者を除き、原則として3年(一定の者との契約については5年)を超える期間について、締結してはなりません。2013年には労働契約法が改正され、有期労働の契約が通算5年を超えた場合、労働者から会社に対して、無期労働契約の申し込みができるようになりました(無期転換ルール)。そして5年後、「2018年問題」として、この点での適切な対応が強く求められています。
【試用期間】
「試用期間」の有無や期間、延長などに関する内容は、原則として会社が自由に決めることができます。ただ、実際には試用期間について定めた「就業規則」に基づいて運用されるので、事前にそのルールを明確に規定しておく必要があります。
【人事異動】
「人事異動」は、社内の異動である「配置転換」、社外への異動となる「出向」「転籍」に大きく区分されます。人事異動を就業規則に規定しておくことによって「包括的合意」がなされ、会社は従業員に対する命令権を有することになります。しかし、その命令が不当な動機や目的をもって行われている場合や、従業員に明らかな不利益をもたらすと社会通念上認められる場合は、その命令は権利の濫用になると見なされ、無効とされる判例が出されています。人事異動は合理的な理由に基づき、その必要性に応じて実施されることが求められます。
【休職】
「休職」は、特に法令で定められた事項ではありません。対象事由や取り扱いについて、会社が任意に定めることができます。しかし、働く人にとっては重要な事項のため、就業規則でルールや基準を規定しておくことが大切です。
【表彰・制裁】
「表彰・制裁」は、労働基準法において「表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を就業規則に記載しなければならない」と規定しています。無用なトラブルを避けるためにも、就業規則には具体的な内容・要件などを記載し、適切に運用することが重要です。
【定年制】
「定年制」とは、あらかじめ一定の年齢を定め、その年齢に達したら自動的に労働契約が終了する制度です。近年、高年齢者の活用が求められる中、「高年齢者雇用安定法」によって高年齢者雇用確保措置が設けられました。現在、65歳未満の定めをしている会社では、「定年の引き上げ」「継続雇用制度の導入」「定年の定めの廃止」のうち、いずれかの措置を講じなくてはなりません。
【解雇】
「解雇」は、従業員にとって非常に重いものです。そのため、従業員を「解雇」する場合、30日前に「解雇予告」をしなくてはなりません。予告できない場合は、その日数分の「解雇予告手当」を支払う必要があります。ただし、「懲戒解雇」(本人の責による解雇)では、労働基準監督署に「解雇予告除外認定」の申請を行い、承認されれば、解雇の予告や解雇予告手当を支払うことなく、即時に解雇することができます。
服務規律
【服務規律】
「服務規律」は、必ず定めなければならないものではありませんが、職場の秩序を維持するために必要です。服務規律違反があった場合に処分を行う際の「根拠」とするためにも、「入退場の制限」や「競業避止の取り扱い」「損害賠償」などの服務規律に関して、就業規則で明確に規定しておくことが求められます。
【兼業・副業】
近年、働き方改革が進められる中、「兼業・副業」を認める動きが活発化しています。そもそも憲法で、人には「職業選択の自由」が補償されていますので、全てを禁止することには問題があります。そのため、就業規則において兼業・副業を行う場合の規定を定めておく必要があります。
【セクシャルハラスメント・パワーハラスメント】
近年、社会的にも大きな問題となっているのが「セクシャルハラスメント」(セクハラ)です。セクハラを防止するために、会社は「事業主の方針の明確化、周知徹底、啓発活動」「行為者に対する対処方針の明確化」「相談窓口の設置」「セクシャルハラスメントに関する事後の適切な対応」といった措置を講じる必要があります。また、「パワーハラスメント」(パワハラ)についても、セクシャルハラスメントと同様に、方針の明確化、啓発活動、対処方針の明確化、相談窓口の設置などの対応が求められます。
賃金管理
【賃金の支払い】
「賃金」は、従業員の生活に大きな影響を及ぼすため、労働法を正しく理解し、適切に運用しなくてはなりません。賃金の支払いに関して注意すべきこととして、遅刻・早退時に不就労時間の賃金控除の取り扱いがあります。賃金の不就労時間を控除することは問題ありませんが、給与計算の手続きが煩雑となることから、30分単位に切り上げて控除しているケースがあります。実際の不就労時間以上に控除すると「全額払い」の原則に違反することになるので、注意が必要です。
【差別的取リ扱いの禁止】
「賃金」について、性差による「差別的取り扱い」を行ってはいけません。例えば、家族手当の支給基準を「扶養している妻がある」としているケースがありますが、この場合、妻を配偶者に改めなくてはなりません。同様に、従業員の国籍、信条、社会的身分などを理由として、差別的な取り扱いをすることは禁止されています。
【出来高給の最低保証】
業績によって支給額を決定する「出来高給」を導入しているケースがありますが、この場合も、労働時間に応じて一定額の保障が必要となります。保障する賃金額は、法令で「常に通常の実収賃金とあまり隔たらない程度の収入が保障されるように保障額を定めるべき」と規定されています。この場合、「休業手当
を参考に考えると、少なくとも平均賃金の100分の60程度の保障が妥当だと考えられます。
【賞与】
「賞与」の支給や有無については、法令で特に定められておらず、企業が自由に決定できます。ただし、賞与も賃金に該当します。そのため、「賃金規程」などで明確にしている賞与支給に関するルールを、企業側の一方的な都合で変更することはできません。賞与は社員の働く意欲に大きな影響を与えるので、その設計や基準には十分な配慮が必要です。
【退職金】
「退職金」をどう設計するかは、企業の自由です。しかし、退職金も労働基準法の賃金に該当するため、支給する場合には、その支給方法などのルールを明確にし、「退職金規程」に記載する必要があります。近年の傾向として、これまでの退職時の基本給に連動する方法から、在職時の貢献度が反映される「ポイント方式」へと見直す企業が増えています。
労働時間・休日、法定休業・休暇
【フレックスタイム制】
「フレックスタイム制」において、「フレキシブルタイム」(選択により労働する時間帯)、「コアタイム」(労働義務のある時間帯)を設定する場合、フレキシブルタイムが極端に短い場合や、コアタイムと標準となる1日の労働時間がほぼ一致している場合など、労働基準法で定めた趣旨と合致しないケースについては、否認されることがあるので注意が必要です。
【36協定の限度時間の遵守】
「36協定」における法定労働時間を超える時間外労働の「限度時間」(上限)は、労働基準法によって定められています。この限度時間を遵守することはコンプライアンス上、非常に重要なことです。労働基準監督署による調査で限度時間を超えている事実が判明した場合、36協定違反として「是正勧告」を受けやすくなるので注意が必要です。
【労働時間の把握】
「労働時間の把握」について、労働基準法では直接定められてはいません。現実的には、「タイムカード」や上司が部下の出社・退社の時刻を目で見て確認する「現認」、「自己申告」などに任せる方法が行われています。これらの方法の中で、問題となるのが自己申告です。実態との乖離(かいり)が発生しやすいため、定期的な調査が求められます。さらに、調査で明らかとなった私的な理由による乖離時間については、「労働時間に当てはまらない」という根拠を残していける仕組みや、具体的な事例を考える必要があります。
【持ち帰り残業】
「持ち帰り残業」は、会社の指揮命令が及ばないため、時間外手当の支給対象となるかどうか判断が難しい事項です。しかし、実際には会社からの“黙示の指示”で行うことが想定されます。そのためにも、持ち帰り残業が必要なときは、予定作業時間を事前に上司に申告し、承認を得た上で行うなどのルールを作成し、社内で周知徹底させることが必要です。そして後日、実作業時間について申告させ、上司が実態を正しく把握できるようにすることが重要です。
【休日】
「休日」とは、働く義務のない日のこと。そして、労働基準法では休日について、「毎週、少なくとも1回の休日を与えなくてはならない」と定めています。ただ例外として、4週間を通じて4回の休日を与える方法も認められています。こうした休日を「法定休日」と呼び、それ以外の休日は「法定外休日」といいます。休日に関してはこのような意味合いがあるため、後々のリスクとならないよう、就業規則にその趣旨と運用のルールを明確に記載しておく必要があります。
【休憩】
労働基準法では、長時間の継続した労働が心身に与える影響から従業員を守るため、「休憩」についての定めを設けています。休憩時間に関しては、「6時間の労働を超える場合は、少なくとも45分の途中休憩を与える」「8時間を超える労働の場合は、少なくとも1時間の途中休憩を与える」ことが求められます。休憩は「労働からの開放」を意味し、前後に労働時間があることが前提となるため、仕事の始めや終わりにまとめて与えたとしても、休憩には当たりません。
【休暇・年次有給休暇】
「休暇」とは、本来働かなくてはならない日に労働を免除すること。そして、「年次有給休暇」(年休)とは、会社が従業員の疲労回復、健康の保持・増進を目的とし、所定の休日以外に休暇取得を認め、働かなくても一定の賃金を支払う休暇のことをいいます。年次有給休暇は、従業員が入社して6ヵ月継続して勤務し、所定労働日の8割以上出勤した場合に付与されます。また、正社員だけでなくパートタイム労働者やアルバイト、嘱託社員にも権利が発生する点に、注意する必要があります。
【法定休業】
「法定休業」とは、労働基準法で定められた「産前産後休業」、育児・介護休業法で定められた「育児休業」「介護休業」など、本来は仕事をしなければならない日に労働者側の事情に配慮して、会社が労働義務を免除する日のことです。例えば、育児については、出産後の産後休業が過ぎ、育児のために休業することが必要な労働者は、子が1歳になるまでの期間、育児休業を取得ことができます。また、子が1歳を過ぎても保育園が定員で入れないなどの理由がある場合は、子が1歳6ヵ月になるまでの間、さらに2017年の法改正により同様の理由で会社に申請すれば、最長2年間まで延長されることになりました。
- 【参考】
- 「ノー残業デー」とは
- 「固定残業代」とは
就業規則・労使協定・法定帳簿
【就業規則】
常時10人以上の労働者を使用している事業所は、「就業規則」を作成しなくてはなりません。この場合、労働者は必ずしも正社員だけに限りません。パートタイム労働者、契約社員なども含まれ、事業所に労働者が10人以上いれば、作成する義務があります。なお、就業規則の記載事項は、「始業・終業の時刻」「休憩時間」「休日」「休暇」「賃金」など、必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と、「退職手当」「賞与」など、定めがあれば必ず記載しなければならない「相対的必要記載事項」とに分かれます。
【就業規則の効力】
「就業規則」と、「法令」(法律・命令)、「労働協約」(会社と労働組合の取り決め)、「雇用契約」(民法による労務と報酬の定め)の効力がよく混同されますが、その効力の関係は、次のようになります。
法令>労働協約>就業規則>雇用契約
労働協約は、会社と労働組合との合意により成立するもの。それに対して、就業規則は会社が一方的に作成できるものであり、労働協約の方が効力として高い位置づけとなります。コンプライアンス上での対応を考えると、労働協約がある場合には、就業規則より労働協約の内容をしっかりと確認することが大切です。
【労使協定】
「労使協定」とは、企業内の事業所単位で、使用者と労働者(労働者の過半数を組織する労働組合がある場合はその労働組合、ない場合は労働者の過半数を代表する者)との間に結ばれる書面による協定です。労使協定を締結することによって、就業規則や労働基準法で禁止されていることもできるようになり、その際のルールも同時に定めることになります。例えば、36協定によって可能となる残業代・労働時間のルールなどが、その典型です。なお、会社が指名した従業員を過半数代表とするなど、過半数代表の選出基準を満たさずに代表者が選任されている場合、労使協定は法的効力を持たなくなる可能性があるので、注意が必要です。
【労働者名簿】
労働基準法第107条で、会社は事業所ごとに各労働者の「労働者名簿」を法定帳簿として作成し、労働者の氏名、生年月日、履歴、雇入れの年月日など一定事項を記入しなければなりません。また、記入事項に変更があった場合は、遅滞なく訂正する必要があります。なお、労働者名簿を賃金台帳と合わせて作成することも認められています。保存期間は、労働者の退職、死亡、または解雇の日から3年間となっているため、しっかりとした保管体制を整備する必要があります。
【賃金台帳】
労働基準法第108条で、会社は事業所ごとに「賃金台帳」を法定帳簿として作成し、賃金の基礎となる事項・賃金の額など、一定事項を記入しなければなりません。労働者名簿は、日々雇入れられる労働者については作成する必要がありませんが、賃金台帳は日々雇入れられる労働者についても作成する必要があります。賃金台帳の保管期間は、最後に記入した日から3年間。「是正勧告」を受けやすい帳簿なので、正しく整備されているか、日ごろからの確認が大切です。
特定層(障がい者、外国人労働者、パートタイム労働者、派遣労働者、請負)
【障がい者】
障がい者雇用促進法の改正により、民間企業では、常用雇用労働者の2.0%(法定障がい者雇用率)に相当する障がい者を雇用することが義務付けられました。具体的には、常用労働者が50人以上いる会社では、少なくとも1人以上の障がい者を雇用しなければなりません。法定障がい者雇用率を下回っている会社は、「障がい者雇用給付金」を納付する必要があり、一方、超えている会社は「障がい者雇用調整金」を受給することができます。なお、未達成企業には「障がい者の雇入れに関する計画」の作成を命じられることがあります。その際、計画の内容や実施が不適切な会社には、指導・勧告が行われます。正当な理由がなく勧告に従わない場合は、企業名が公表されることになります。
【外国人労働者】
「外国人労働者」を採用する場合は、就労させる業務の内容が「在留資格」の範囲内にあるか、「在留期間」を過ぎていないかをしっかりと確認する必要があります。正規の在留資格がなく就労させたり、在留資格以外の職業に就かせたりすると、不法就労と判断されます。また、就労が認められている在留資格かどうかを確認せずに、不法就労外国人を雇用した場合は、「不法就労助長罪」に該当することになり、罰金が適用されます。そのため、在留資格などの確認を適正に行える社内体制を構築することが重要です。なお、外国人であっても日本国内で就労する限り、国籍を問わず労働関連法令が適用されます。
【パートタイム労働者】
「パートタイム労働者」(短時間労働者)とは、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べ短い労働者」のことをいいます。ただし、通常の労働者と就業の実態が同一であるような場合には、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇について、パートタイム労働者であることを理由にした差別的取り扱いは禁止されています。パートタイム労働者を雇入れる際、労働基準法第15条に規定された一定事項を正社員と同様、文書の交付などにより明示しなくてはなりません。また、パートタイム労働法では、特にトラブルとなりやすい「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」について、文書の交付などによって明示することになっています。
【派遣労働者】
労働者派遣法は、2012年、2015年に改正が行われました。2012年は日雇い派遣の原則禁止、派遣先企業の社員との均衡(賃金など)の配慮など。2015年は専門26業務の廃止、最長3年の派遣期間、そして雇用安定やキャリアアップを目的とした措置などが義務化されました。これらの改正により、派遣先企業では派遣労働者に対して、待遇や賃金の保護、キャリアアップ支援を以前より意欲的に行うことが求められるようになりました。また、派遣期間が最大3年に延長され、さらに雇用継続などの措置を行う必要性もあるため、雇用を開始した起算日をきちんと管理することも実務上、重要となっています。今後は派遣労働者に対して、雇用の安定、キャリアアップにつながる支援がより求められるようになるでしょう。
【請負】
「請負」とは、民法第632条で「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。このような請負と労働者派遣の大きな違いは、請負では注文主と労働者の間に、「指揮命令関係」が生じないという点です。しかし、請負契約によって行われる業務でも、注文主と労働者の間に直接的に指揮命令関係が生じている場合があります。こうしたケースでは、実態として労働者派遣に該当すると判断され、「偽装請負」となるおそれがあります。偽装請負の状態で労災事故などが発生した場合、大きな社会問題となるため、コンプライアンス上、偽装請負の解消は必要不可欠と言えます。
- 【参考】
- 「外国人採用」とは
健康管理・安全衛生
【健康管理】
労働安全衛生法では、会社に「雇入れ時の健康診断」をはじめ、「定期健康診断」「特定業務従事者の健康診断」「海外派遣労働者の健康診断」などの「健康診断」を義務付けています。また、これら健康診断の受診要件に該当する従業員に対しては、健康診断を受診させるだけでなく、受診結果を記録することや、診断結果によっては医師の意見を聴取することまで求めています。さらに会社には「安全配慮義務」があり、健康診断の受診や受診後の措置も、安全配慮義務の一部と考えられます。労務リスクを軽減し、会社を健全に運営するためにも、健康診断の受診要件や医療・看護など、その後必要となる措置・対応をよく理解し、従業員の健康管理をサポートする体制の整備が求められます。
【安全衛生】
労働安全衛生法では、会社が自主的に安全衛生活動に取り組むよう、管理体制を具体的に定めています。例えば、常時50人以上の労働者を雇用する事業所は、職場の衛生に関する事項を管理するための「衛生管理者」が、一定の危険な作業を行う事業所では、安全に関する技術的な管理を行うための「安全管理者」の選任が義務付けられています。さらに、従業員規模が100人を超えると、業種により「統括安全衛生管理者」の選任が必要となります。統括安全衛生管理者は、安全管理者や衛生管理者を指揮し、職場の安全と衛生についての管理を行います。なお、業種・従業員数により、整備される安全衛生管理体制は異なります。
その他にも、「安全委員会」「衛生委員会」の設置など、会社だけではなく従業員も安全衛生に関与させ、全社的な取り組みを促してます。労働災害や健康障害を防止するためには、安全衛生管理体制を整備することが重要です。管理者の選任、委員会の設置の要件や運営方法について、正しく理解することが求められます。
労働保険・社会保険
企業は労働者を一人以上雇用する事業場ごとに、「労働保険 健康関係成立届」を、また雇用保険の被保険者となる労働者を一人以上雇用する事業場ごとに、「雇用保険 適用事業所設置届」を提出しなければなりません。また、加入条件を満たす労働者を「雇用保険」、または「社会保険」(健康保険・厚生年金保険)に加入させなければなりません。パートタイム労働者など短時間就労者の場合、「1週間の所定労働時間が20時間以上であること」「31日以上の雇用見込みがあること」に該当する者は、雇用保険に加入する必要があります。社会保険についても、「1日または1週間の労働時間が、正社員の4分の3以上であること」「1ヵ月の労働日数が、正社員の4分の3以上であること」に該当する場合、加入することになります。雇用保険、社会保険については、加入手続き漏れがあると大きな労務リスクとなるので、厳密にチェックすることが重要です。

3.コンプライアンス、リスクマネジメントの進め方
「PDCA」サイクルに基づいて行う
社内組織において、コンプライアンスの管理体制を整え、リスクマネジメントを全社的に推進していくには、「PDCA」(PLAN→DO→CHECK→ACTION)サイクルに基づいて行うことが効果的です。
【PLAN:基本方針・基本計画の策定】
まず、企業としてどのようにコンプライアンス、リスクマネジメントに対して対応していくのかという「基本方針」を、トップメッセージとして発信していくことがスタートとなります。基本方針を明確に打ち出していくことは、社内外のステークホルダーに対して大きな意味を持つからです。その上で、行動に移すための「基本計画」を策定します。直面しているさまざまな課題に対して、どこからどのように対応していくか「対策」を決めるのです。優先順位の高い課題に対しては、目標と期限を設けて、速やかに進めていくことが重要です。
【DO:対策の実施】
具体的な対策を進めていくに際して、現場で具体的な行動を起こせるような「アクションプラン」(手法)を作成する必要があります。ただ、コンプライアンスやリスクマネジメントに関しては、対象となる事項が多岐にわたり、求められる専門性も高くなります。そのため、現場に全て任せ切るのは現実的でありません。各分野の専門家などを交えた専門のスタッフ部門や事業部門がイニシアティブを取り、実施していくのが効果的です。
【CHECK:対策の検証】
実際の活動が実効性を伴っているか、あるいは形骸化していないか、対策の「検証」(モニタリング)を行います。検証には、「自己評価」と「第三者評価」がありますが、自己評価は客観性の点で問題が生じる場合があります。そこで、中立な立場にある第三者が、基本方針・基本計画に沿った活動が行われているかどうかを確認・検証し、その結果を経営者に報告します。
【ACTION:是正・改善】
検証された「結果」(問題点・課題)を、是正・改善していきます。取り組みが期待した通りに行われているかどうか、その実効性を担保するには、しっかりとレビューすることが不可欠です。特に法改正が頻繁に行われている現在では、コンプライアンス・リスクマネジメントに対する取り組みも、常に見直しが必要となっています。
社内体制の構築・維持
全社的にコンプライアンス、リスクマネジメントへの対応を進めていくには、社内体制の構築と維持が不可欠です。経営トップの下、担当責任者(役員)、専門委員会、専門管理部署などを置いた全社を統括する体制と、現場である各部門・部署の管理体制の二階層に分けて対応していくことが求められます。
【全社の統括体制】
経営トップは、コンプライアンス、リスクマネジメントに対する「基本方針」を決定し、社内外にそのメッセージを強く宣言して、最終責任を負う役割を担います。その下で、専任の役員(オフィサー)がこの問題に関わる業務を統括する役割を担います。基本計画や実行に関する指示・承認を行う一方、トップが経営判断を下すための報告や提案なども行います。
近年は、コンプライアンスやりクスマネジメントへの取り組みの一環として、専門の委員会を設置するケースが増えています。専門の委員会があれば、問題に特化した議論が詳細に行われ、タイムリーな標語を作成するなど、スピーディーで的確な意思決定ができるからです。人事や総務、法務などの下部組織が現場で行われている活動の取りまとめを行いますが、近年は事務局機能を持った専門の管理部署を設置するケースも見られます。
【現場の管理体制】
事業活動を担う現場では、各部門・部署の責任者が常に全社の統括体制からブレイクダウンしてくる課題、求められる対応を十分に理解し、各メンバーに対して周知徹底していくことが求められます。ただ、テーマやリスクの性質・内容に応じて、実効性を高めるために「管理単位」を変えていくケースもあります。そういう場合には既存部門の枠組みを越え、テーマ・リスクごとに管理単位プロジェクトチームにすることも、考えておくべきでしょう。

4.コンプライアンス、リスクマネジメントに関する法律
コンプライアンス、リスクマネジメント関連法律(目的・内容・ポイント)
コンプライアンス、リスクマネジメントに関連する法律・法令は、非常に多岐に及びます。ここでは、主要なもののポイントを解説します。
【労働基準法】
「労働基準法」は、賃金や労働時間など労働条件の最低基準を定める法律です。「最低賃金法」「労働安全衛生法」などの関連する法律も含めて、条件を満たしているかどうか(違法性)の確認が、コンプライアンス、リスクマネジメント上、大変重要です。
【男女雇用機会均等法】
「男女雇用機会均等法」は、男女均等となるルールの徹底を求めています。例えば同法第5条では、労働者の募集・採用に関して、性別を理由とする差別を禁止し、男女均等な取り扱いを求めています。また、同法第7条では、業務上の必要性など合理的理由がない場合に、募集・採用において労働者の身長・体重、体力を要件とすること、そして労働者の募集・採用、昇進、職種の変更をする際に転居を伴う転勤に応じることを要件とするのは、間接差別として禁止しているので、注意が必要です。
【公益通報者保護法】
「公益通報者保護法」は、不正を発見して通報した従業員を保護する法律。外部通報も認めているため、コンプライアンス体制を適正に構築・運用していなければ、不正な外部通報が行われかねません。コンプライアンスを重視した経営を行う“きっかけ”となったといわれる法律です。
【改正独占禁止法】
「独占禁止法」は、市場経済において健全で公正な競争状態を維持するために設けられた法律です。「改正独占禁止法」では、課徴金の算定率が大幅に引き上げられたため、不正を行った企業の受けるダメージが非常に大きくなりました。一方、違反行為を自ら申告した企業には「課徴金減免制度」が設けられました。これにより社内のコンプライアンス体制を有効に機能させ、不正行為を早期に把握・申告すれば、行政処分によって受けるダメージを少なくすることができます。
【会社法】
「会社法」は、会社の設立、組織、運営、管理一般について定めたもので、会社経営の基本となる法律です。会社法では、資本金5億円以上、または負債200億円以上の大企業に対して、内部統制システム(コンプライアンス体制を含む)の構築を義務付けています。必要な役割を果たせなかった場合は、内部統制システムの構築を怠ったとして、損害賠償を請求されます。
【金融商品取引法】
「金融商品取引法」は、投資しやすい市場機能の確保と金融・資本市場の国際化への対応を目指して、整備されたもの。上場企業にとっては、会社法と並んで重要な法律です。金融商品取引法は、株式・社債などの取り引きやコーポレートガバナンスなどに大きな影響を及ぼします。また、その中でも不公正取り引きの典型である「インサイダー取引」の規制に関しては、特に注意する必要があります。重要事実の入手と利益の間に因果関係があったかどうかは関係がない、と判断されるからです。そのため、問題となりそうな取り引きを行う場合は、インサイダー取引違反にならないかの判断基準、どこの誰に相談するのかなど相談者に関して、事前に会社として詳細を決めておくことが必要です。
【ISO2600】
「ISO2600」は、企業の社会的責任(CSR)に関する国際規約。人権、労働慣行など、七つのテーマごとに対応すべき課題をまとめたものです。2010年に策定されて以降、ISO2600を採用する国が増えており、同規格が定める人権、労働慣行などの基準をクリアにすることが、企業のグローバル化展開を進める上で、不可欠となっています。
【外国法】
「外国法」を違反した場合、日本企業に適用されるリスクには、「業務停止など、市場から追放される」「法外なリーガルコストが生じる」「外国で訴訟が起こされる」「外国法を適用される」などがあります。グローバル展開が進んでいる昨今では、外国法違反を犯すと日本では考えられないほどの大きなダメージを被ります。海外と取引関係を持つ企業は国内法令だけではなく、海外の法令にも十分に注意を払う必要があります。
【環境規制】
環境問題が深刻化している中、「環境規制」への対応は必要不可欠であり、企業イメージを高めるためにも大変重要です。法令などの改正が頻繁に行われており、また、法規制の内容もかなり複雑になっているので、きめ細かな対応が求められます。担当責任者を定めて、環境規制に的確に対応できる体制を構築することが重要です。
【人権問題】
「人権問題」に関しては、直接的に法律の記載がなくても、十分に注意して当たらなければ大きな問題に発展する危険性があります。例えば、厚生労働省(公正な採用選考の基本)では、採用選考時において人権問題に抵触し、就職差別につながるリスクがある事項を、以下のとおり挙げています。
- 本人に責任のない事項の把握:本籍・出生地、家族、住宅状況、生活環境・家庭環境などに関すること
- 本来自由であるべき事項(思想信条に関わること)の把握:宗教、支持政党、人生観・生活信条、尊敬する人物、思想、労働組合に関する情報、購読新聞・雑誌・愛読書などに関すること
- 採用選考の方法:身元調査などの実施、合理的・客観的に必要性が認められない採用選考時の健康診断の実施
- 【参考】
- 「人権リスク」とは
5.コンプライアンス、リスクマネジメントの見通し・課題
トップのメッセージ
企業が健在なコンプライアンス体制、リスクマネジメントの仕組みを構築できるかどうかは、経営トップが問題の本質を十分に理解し、何をやるべきかを把握し、それを徹底的に実践できるかどうかにかかっています。また、どのような企業風土、組織体質になるのかも、経営トップの姿勢に大きく左右されます。
法令違反は、最低レベルのモラル違反といえます。社内に将来問題となりそうな“芽”があれば、決して軽視することなく、早めに摘んでおく必要があります。「黙認した方が会社のためだから」などと、見て見ぬふりをしている役員や管理職、従業員の姿勢を、仕方のないものとして諦めてはいけません。経営トップには、強いリーダーシップを発揮して「あるべき姿」を社内に対してイメージさせ、長期的展望の下、改革を進めていくことが求められます。
それと同時に、経営トップは必要に応じてシステムの見直しを行い、不祥事を防止できる体制が整っているかどうかをチェックしなければなりません。徹底的に問題を分析して解決し、感覚的処理を避けるようにすることは、まさに経営トップにしかできない決断です。
ステークホルダーへの対応
社会的存在である企業は、その活動が社会に与える影響に対して常に責任を持ち、あらゆる「ステークホルダー(利害関係者)」からの要求にも、適切に対応しなくてなりません。企業のステークホルダーは消費者をはじめ、顧客、従業員、取引先、地域社会、その他の幅広い関係者へと及びますが、特に問題が起きたときのステークホルダーに対する対応は、非常に重要です。
不祥事が起きた際に、「法令違反はしていない」「ルール通りに行っている」といくら弁解しても、ステークホルダーからの理解が得られなければ、説明責任として不十分です。実際、法令やルールは必ずしも万全なものではなく、解釈によって“グレーゾーン”が存在します。判断を誤ると、倫理に反する行為が大きな法律問題へと発展するリスクが高くなります。
このようなときに求められるのは、企業社会における「倫理」です。「法例に定めがない」などといった理由による、企業倫理にもとる行動や誠意のない対応は、法律の不備を突く脱法行為といえます。「訴えられなければ構わない」などといった姿勢では、ステークホルダーからの信用を失い、市場から排除されることになります。企業社会の倫理を正しく理解すると同時に、問題が起きた際の対応が社会的な要請に合致したものであるかどうかを、常にさまざまな観点から意識し、実践していくことが大切です。
リスク回避、ダメージ低減をいかに進めていくか
コンプライアンス、リスクマネジメント上の問題が起きたときに、リスクを回避し、ダメージを低減していくには、どのように対応すればいいのでしょうか。危機管理の面で重要なのは、日ごろから被害を最小限にとどめるための対策を事前に講じておくことです。
【問題発生時の対応】
まず、問題が起きたときに心がけるのは、現場で問題の中身を分析・検討することよりも、大至急、担当する専門の管理部署・部門に情報を的確に伝えることです。その際、伝達ミスが起こさないことが重要です。そのため、マニュアルなどを整備し、伝達書式や緊急時用語を社内で統一しておくこと、起こり得る問題に対して共通認識を持たせて誤解のないようにしておくことが重要です。
【緊急対策本部の設置】
問題が発生したときは、緊急対策本部を設置する必要があります。構成メンバーは、経営者、担当役員、広報、人事・総務、法務、各事業部の責任者、そして弁護士などです。ここで緊急情報を集中管理し、発信情報を一本化させます。社内に対しては、決して個別の対応をしない旨を、周知徹底します。
【社外への対応】
社外への対応の基本は、都合の悪いことを隠ぺいすることなく、正しい事実を誠意を持って公表することです。その際に心がけなければならないのは、自社の信用の維持と向上です。特に緊急時は、謝罪と原因究明、再発防止を速やかに伝えていくことが求められます。そのためにも、弁護士などの専門家を交えて、事前に「適切なシナリオ」を入念に考え、用意しておくことが重要です。
【人事としての対応】
このような事態に直面したとき、事前の対応策として、人事が果たす役割も大きいと思われます。例えば問題が発生する前に、従業員に何かしらの“兆候”が認められることがあります。そのため、日ごろから従業員の勤務状況や生活態度などに変化がないかどうか、現場の管理職などの協力を得て、よく観察しておくといいでしょう。また、「社内相談室」を設けて、気軽に相談を受け付けられるような仕組み、雰囲気を作っておくことも必要です。また、コンプライアンス、リスクマネジメントに関する啓発を、階層別教育の中のプログラムに盛り込むなどして指導していくこと、「就業規則」や「服務規程」などの中に、コンプライアンスやリスクマネジメントの項目を設けて周知徹底させることなども重要です。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント