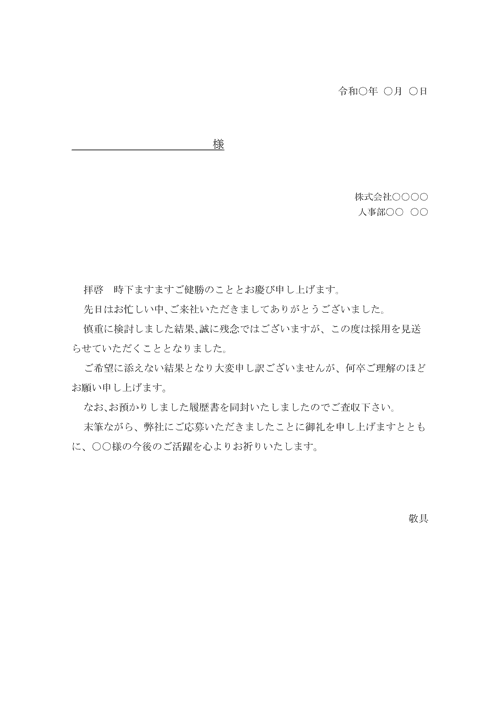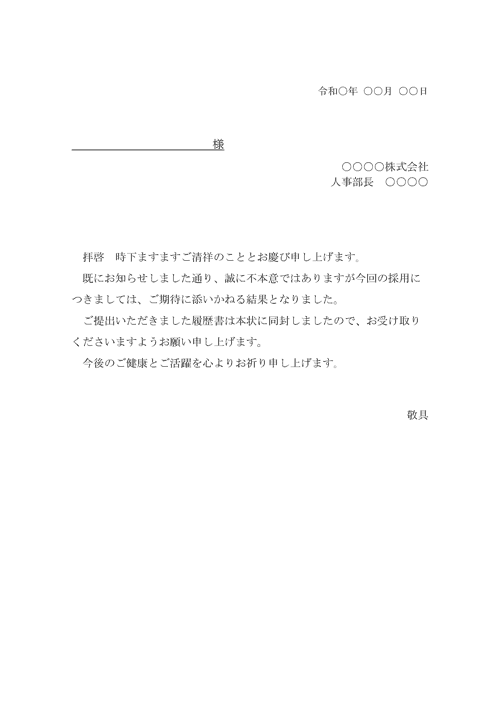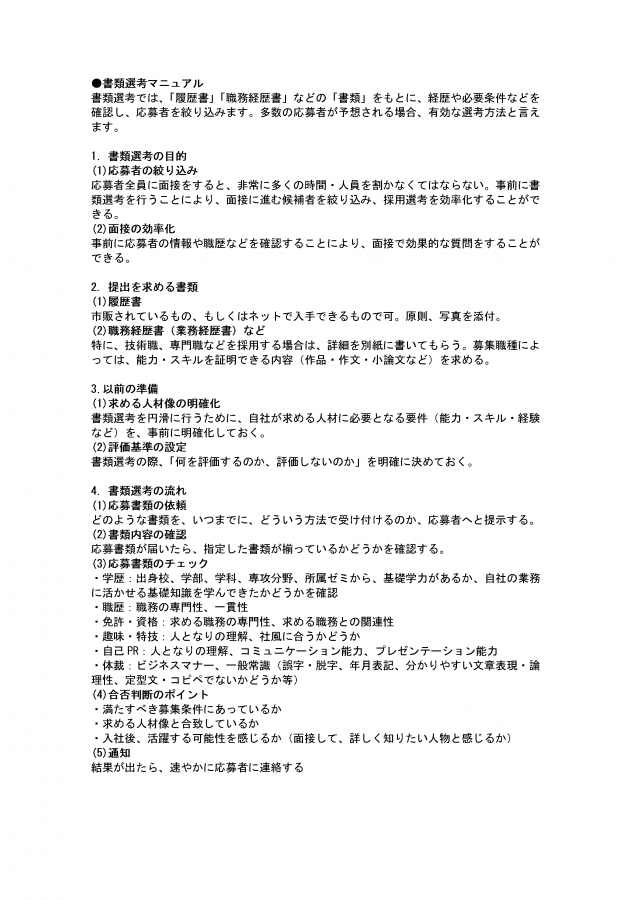歩留まり
歩留まりとは?
「歩留まり」とは、投入した資源(原材料、時間、人員など)に対して、最終的に得られた製品や成果の割合を示す言葉です。もともとは製造業で用いられる品質管理の指標でしたが、現在ではビジネスのさまざまな分野で活用されています。採用活動にける「歩留まり」とは、選考プロセスにおいて「次のフェーズに進んだ候補者の割合」を指します。また、この割合をパーセンテージで示した数値を「歩留まり率」と言います。歩留まり率を計算することで、採用プロセスのどこに課題があるのかを定量的に把握し、効果的な改善策を立案できます。
採用活動における歩留まり率の計算方法と改善策
「歩留まり率」は、【そのフェーズを通過した人数÷選考を受けた人数×100】で算出されます。例えば、書類選考に100人応募し、30人が通過した場合、歩留まり率は30%となります。
書類選考の歩留まり率が低い場合、応募資格や募集要項が不明確である可能性が考えられます。改善のためには、応募資格を明確にすること、また、ターゲット人材に響く魅力的な求人票への見直しや、採用広報の強化が必要でしょう。
一次面接や二次面接の歩留まり率が低い場合は、面接官のスキル不足や評価基準の曖昧さが原因と考えられます。面接官トレーニングの実施や、候補者全員に同じ質問をして明確な基準に沿って評価する構造化面接の導入により、評価の客観性と公平性を高める必要があります。
内定承諾の歩留まり率が低い場合は、内定者フォローが不足している、競合他社に比べて魅力が感じられない、提示条件がニーズと異なる、といった原因が考えられます。内定者に対して、定期的な面談や社員交流の機会を設けることで、入社への意欲を高めることが重要です。また、自社の魅力や強みを再確認し、競合他社と比較した際の優位性を明確に伝える努力も必要です。市場の給与水準や福利厚生を調査し、条件を見直すことも検討すべきでしょう。
このように、歩留まりは単なる数値だけでなく、採用プロセスの課題を浮き彫りにし、人事戦略の改善につながる重要な指標となります。各フェーズの歩留まりを継続的に分析し、PDCAサイクルを回すことで、より効率的で効果的な採用活動を実現できるでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント