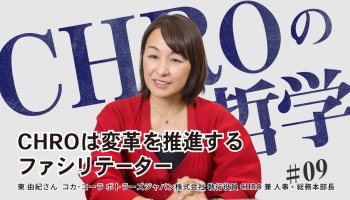「修羅場」を乗り越え、CHROに就任
人事パーソンに不可欠な「責任感」と「やり抜く信念」
三菱電機株式会社 常務執行役 CHRO、広報担当
阿部 恵成さん

事業の構造改革、子会社の経営統合、全社を揺るがす品質不正問題。数々の「修羅場」ともいえる経験を乗り越え、現在三菱電機のCHROを務めるのが、阿部恵成さんです。キャリアを歩み始めた当初から、人事業務の最前線に身を置き、経営と向き合い続けてきました。困難な局面において、人事パーソンは、何を考え、どう行動すべきなのでしょうか。事業変革をリードするために不可欠な視点、それを支える「責任感」と「やり抜く信念」の源泉に迫ります。

- 阿部 恵成さん
- 三菱電機株式会社 常務執行役 CHRO、広報担当
あべ・やすなり/1989年、三菱電機株式会社に入社。神戸製作所にて人事としてのキャリアをスタート。本社のほか、事業の構造改革を経験した製作所や、分社化した関係会社への出向も経験し、人事制度の統合などに尽力する。本社人事部で人事企画グループマネージャー、人事部次長を歴任後、2020年に広報部長に就任。困難な時期のコーポレートコミュニケーションをリードした。2022年より人事部門のトップを務め、2023年4月より現職。現場と経営、双方の視点から人財戦略を推進している。
リクルーターの人柄にひかれ入社、人事の道へ
1989年に三菱電機へ入社されています。まずは、入社の経緯や当時の就職活動についてお聞かせください。
きっかけは、大学の先輩だったリクルーターとの出会いです。当時はバブル景気の初期で、売り手市場でした。私は業界を絞らずに、さまざまな企業に資料を請求していました。その中の一社が三菱電機で、大学に来ていたリクルーターと会うことになったのです。
多くの企業のリクルーターとお会いしましたが、選考が進むにつれて、その企業の雰囲気が徐々に見えてくるようになりました。特に三菱電機の人たちは、こちらの話を非常に真摯(しんし)に、また親身になって聞いてくれたのが印象的でした。内定をもらった後も、どの会社に進もうかと悩んでいる私に対して、ただ自社に誘うのではなく、一個人として向き合い、最後は自分で決めることの重要性を説いてくれました。こうした姿勢に強くひかれ、入社を決意。会社の風土や人の「フィーリング」で選んだというのが正直なところです。
入社後は、神戸製作所の人事からキャリアをスタートされています。当初から人事を希望されていたのでしょうか。
いえ、特定の職種を希望していたわけではありません。当時は今と違い、勤務地や職種の希望を強く出す学生は少なく、会社から配属先を伝えられるのが一般的。「どこに配属されても頑張ります」というスタンスだったので、特に驚きはありませんでした。ただ、生まれも育ちも東北でしたから、東京を飛び越えて神戸に行くことになったことには、少し驚きました。
配属先は総務部門の人事課。最初に担当したのは給与計算の業務です。後から聞いた話ですが、神戸製作所には「将来人事を担う人材は、まず給与業務から始める」という伝統があったようです。
なぜ、給与業務からなのでしょうか。
「給与」には、会社の制度やルール、社員一人ひとりの情報がすべて詰まっているからです。各種手当や評価、個人の勤怠状況など、あらゆる情報が給与に反映されます。給与業務を担うことは、会社の就業規則や賃金規則といったルール、各種制度を深く理解することにつながります。
また、給与計算のプロセスでは、各部署の課長や勤怠を管理する担当者など、工場内のさまざまな立場の人と関わることになります。期日までに正確なデータを集めなければ給与支払いが滞ってしまうので、密なコミュニケーションを取り、信頼関係を築いていく。こうした経験を通じて、工場全体のネットワークを自然と形成することができました。人事としてキャリアを歩む上での、いわば「土台作り」を、給与業務を通して徹底的にたたき込まれたのです。
神戸製作所では、その後どのような業務を経験されたのですか。
給与業務を2年弱経験した後は、労務の世界に移りました。傷病で休職している方への対応や、懲戒案件の処理、工場の現場で働く従業員の処遇制度や評価制度の運用などを担当しました。技能系のいわゆる現業系の人事を3年ほど経験し、次に技術者や事務職という非現業系の人事を担当し始めたところで、本社の人事部へ異動することになりました。入社6年目のことです。

子会社出向で直面した「一国二制度」
本社へ異動された後は、どのようなミッションを担われたのでしょうか。
本社の人事部では、主に本社に勤務する従業員の人事を担当するグループに所属しました。同時に、課長級以下の社員に関する全拠点の人事処遇制度の設計や運営も担当していました。つまり、本社という一つの拠点の「拠点人事」と、会社全体のルールを作る「全社機能」、その両方を担うことがミッションでした。特定の事業本部を担当しながら、現行制度の運用と、その制度の改定や改善の両方に関わることで、幅広く、また複合的な視点を得られた期間でした。
本社で4年ほど勤務した後、鎌倉にあった情報システムの工場へ異動しました。当時、その工場が手掛けていたコンピューター事業は、技術的には優れた製品を生み出していましたが、莫大(ばくだい)な投資がかさみ、常に赤字が続いている状況でした。私に与えられたミッションは、その事業の構造改革、つまり事業再編に人事として対応することでした。
異動して間もなく、モバイルPCの製造現場を閉鎖することが決まり、事業の縮小と、それに伴う従業員の再配置や雇用の確保が主な業務になりました。社内の別部署への異動はもちろん、他工場や関係会社への異動など、社員一人ひとりのキャリアと生活に向き合う日々でした。2001年には、この事業は分社化されることになります。
ご自身も、その新会社へ出向されたのですね。
はい。分社化された新会社に、人事課長として出向しました。もともと三菱電機の子会社だった企業に、本体から移ってきた事業・人材が統合されてできた会社です。旧子会社のプロパー社員と、三菱電機本体からの出向者という、異なる文化を持つ人々が混在していました。人事制度や労働条件も異なっていたため、「一国二制度」の状態でスタートしたのです。
私の最大のミッションは、二つの制度や文化を一つに統合し、新しい会社としての骨格を作り上げること。就業規則の統一や人事制度の刷新、退職金制度の構築など、課題は山積していました。また、私の部下のほとんどは、旧子会社のプロパー社員。いかに信頼関係を築き、一つのチームとして難題に取り組んでいくかが問われました。労働組合とのコンフリクトもありました。
私のキャリアの中で、最もタフな経験だったかもしれません。胃に穴が開くような日々でしたが、それでもやり切ろうと考えました。「お前、もう本社に戻ってこい」と言われたこともありましたが、「退職金制度の構築まではやらせてください」と主張し続けました。
その原動力は何だったのでしょうか。
「やりきらないと気持ちが悪い」という、責任感に尽きます。自分が始めたからには、最後までやり遂げたい。中途半端な状態で後任に引き継ぐことはできない、という思いが強かったですね。次から次へと課題が現れ、当初の想定よりはるかに長い時間が必要となりましたが、一つひとつ解決していきました。
結局、8年間その会社に在籍しました。最後は「この会社を見届けたい。転籍させてほしい」とまで申し出たほどです。それだけ愛着が湧いていましたし、この会社をもっと良くしたいという思いが強くなっていました。
仕事が面白くなっていた、という側面もあります。2005年に総務部次長に就任し、実質的には部長のような仕事をしていました。総務の仕事では、人事のときには関わらなかった人とも関わるようになり、そこに面白さを感じていたのです。たとえば、経営者と近い距離で仕事をしていました。特にIT企業は「人が資本」であり、経営戦略と人事戦略が直結しています。プロジェクトごとにいかに効果的に人を配置するか、事業環境の変化にどう対応してリソースを最適化するか。常に経営者と膝詰めで議論し、意思決定を行いました。
この経験を通じて、単なる人事担当者ではなく、経営の一員として事業を動かしていくという当事者意識が強く芽生えました。経営者が何を考え、何を課題としているのかを肌で感じながら仕事ができたことは、その後のキャリアにおいて大きな財産となっています。
「戦う広報部長」――CHROへの道筋
子会社への出向後、中津川製作所での勤務を経て、2014年に再び本社の人事部に戻られています。
本社では、幹部社員の処遇制度や報酬決定、ローテーションなどを担当する人事企画グループのマネージャーを務めました。役員人事に関わる指名委員会や報酬委員会の事務局機能を担っていて、会社法や株主総会に関する知見も求められる、極めて専門性の高いセクションです。会社の経営の中枢に関わる仕事であり、緊張感のある毎日でした。その後、人事部次長として、部長の補佐をしながら人事部門全体の司令塔のような役割を担うことになりました。
人事のキャリアを順調に歩まれていた中で、2020年には広報部長に就任されています。大きなキャリアチェンジだったのではないでしょうか。
私は、このまま人事部長になるというキャリアパスは描いていませんでした。むしろ、自分のような人事一筋の人間がこのままトップになるのは、会社にとって良くないと考えていたのです。これからの時代の人事部長は、海外の事業所や経理、事業企画といった他部門での経験を持つ、より幅広い視野を持った人物が担うべきだ、と。広報部への異動を告げられたとき、驚きはありましたが、ある意味で納得感もありました。
広報部長時代は、品質不正問題への対応という、非常に困難な時期と重なりました。
就任してすぐに、当社製品の品質不正に関する問題が明らかになり、広報部は「守りの広報」に徹せざるを得ない状況に陥りました。有事の際、組織はどうしても内向きになります。社会からの批判を恐れ、不祥事を包み隠さず説明することを避けようとする、根深い組織風土の問題がありました。ステークホルダーに対する説明責任をいかに果たすかが最大の課題でした。
私の役割は、議論が内向きに流れそうになったときに、それを断固として引き戻すことでした。たとえ相手が役員でも、「今、議論すべきはそこではありません」「それでは社会の信頼は得られません」と、厳しく指摘し続けました。「戦う広報部長」と呼ばれたほどです。
その覚悟が実を結んだと感じる出来事があります。当時その場にいた役員が後日、「あのとき、阿部さんが引き戻してくれなかったら今の私たちはない」「あの発言で、我に返った」と話してくれたのです。自分の役割は間違っていなかったのだと、確信した瞬間でした。
その行動を支えた信念は何だったのでしょうか。
広報部は、常に体の半分、あるいは6割、7割を会社の外に出しておかなければならない部署だという覚悟です。社会から自分たちの会社がどう見られているのか、何を期待され、何を問われているのか。そのような外の視点を、社内にいる経営層や従業員に伝え、同じ方向を向かせる。たとえば記者会見では、「語りたくない事実も、社会のために語らなければならない」という強い意志が不可欠です。
広報部での2年間の経験は、精神的には非常に厳しいものでしたが、CHROとなった今、会社を客観的に、そして複眼的に見る上で、かけがえのない経験だったと感じています。

困難を乗り越える原動力は、「責任感」と「やり抜く信念」
これまでのお話をうかがい、困難な状況でも最後までやり抜く姿勢や、強い正義感といった阿部さんの人柄が、キャリアを形作ってきたように感じました。
「責任感」が原動力なのかもしれません。子どもの頃から頑固で、一度決めたことは曲げない、そして何より負けず嫌いな性格でした。そうした部分は今も変わっていなくて、周囲からは「精神力が強い」と言われることもあります。「なぜそこまでやり遂げようとするのか」と問われると、最後は「気合です」としか答えようがないときもあります。
広報部長時代に、たとえ役員が相手であっても断固として引き戻す役割を担われたという話にも、その人柄が表れているように思います。
相手が誰であろうと気にしません。言うべきことを言わなければ、本質を見失い、筋が通らないからです。特に経営に近い立場にありながら、忖度(そんたく)をしているようでは、存在する意味がないと考えています。
ただし、何でもかんでも真正面からぶつかるわけではありません。相手の立場や抱えている悩み、あるいは心の揺れといったものをきちんと理解した上で、どのように伝えれば本質が伝わるのかを常に考えています。時には直接的な言葉ではなく、自ら軌道修正してもらえるような働きかけも必要です。
さまざまなご経験を経て、CHROに就任されました。ご自身のキャリアを振り返り、これからのCHROや人事パーソンには何が求められるとお考えでしょうか。
三菱電機のような会社でCHROを担う人間は、人に対してしっかりとした思いがあり、人で苦労し、人事や人というものを決してひとごとにしない。そういう人物であるべきだと、私は考えています。
その上で、どれだけ多様な経験を積み、視野を広げられるかが重要になります。幸いにも私は、子会社への出向で経営と一体となって事業を動かす経験や、広報部長として会社を外から見る視点を養う機会に恵まれました。工場、関係会社、本社。それぞれの場所で、異なる事業環境、異なる文化を持つ人々と交わりながら鍛えられた経験が、今の私の土台となっています。
最後に、次代を担う人事パーソンの皆さんへメッセージをお願いします。
AIやロボティクスの進化により、仕事のあり方そのものが大きく変わろうとしています。変化の激しい時代に、私たち人事パーソンが変化を後から追いかけるような姿勢でいれば、求められている役割を果たすことはできません。常にアンテナを高く張って、世の中で何が起きているのかを学び、自社に足りないものは何か、次に何をすべきかを考え続ける必要があります。
そのためには、内向きだけになってはいけません。会社の外に目を向けること。そして、自社の中で起きていることを、現場の隅々まで見聞きすること。両方が不可欠です。情報を吸い上げ、コミュニケーションを密にし、現状を正しく把握する。そうして初めて、私たちは自らがよって立つ「殻」を認識し、それを破っていけるのです。
過去の成功体験や既存の制度に安住していると、あっという間に時代に取り残されてしまう。危機感を常に持ち、信念を持って変革をやり通す。人事パーソン一人ひとりがそう覚悟することが、今まさに求められていると思います。
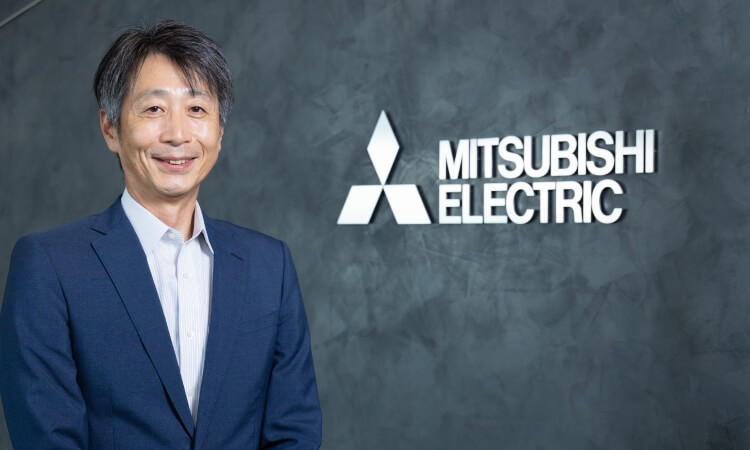
(取材:2025年9月11日)
この記事を読んだ人におすすめ

各企業の人事リーダーが自身のキャリアを振り返り、人事の仕事への向き合い方や大切にしている姿勢・価値観を語るインタビュー記事です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント