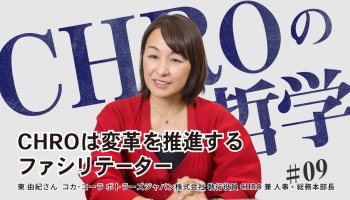「人事は主役ではなくプロデューサー」
希望しない異動で始まった、リコーCHRO長久良子さんの原点とは
株式会社リコー コーポレート執行役員 CHRO 人事総務部 部長
長久 良子さん

企業の競争力の源泉として「人的資本」への注目がかつてないほど高まっています。その担い手である人事部門は、日々変化する事業環境と、多様化する従業員の価値観の間で、自らの役割を問い直しているのではないでしょうか。株式会社リコーでコーポレート執行役員 CHROを務める長久良子さんは、人事の役割を「プロデューサー」と定義します。希望したわけではない異動から始まった人事キャリアを歩む中、多くの壁を乗り越えてきた長久さんの言葉から、人事パーソンに求められる「常識」や「視座」を探ります。

- 長久 良子さん
- 株式会社リコー コーポレート執行役員 CHRO 人事総務部 部長
1993年3月慶應義塾大学法学部政治学科卒業。同年4月日産自動車株式会社 部品事業部海外部品部入社、2001年4月より人事部門に異動、2018年4月ボルボ・カー・ジャパン株式会社入社 人事総務部ディレクター、2021年4月株式会社リコー入社 人事部HRBP室室長、人事部タレントアクイジション室室長、2022年4月人事部人事室室長・人事部タレントアクイジション室室長、2023年2月人事部人事室長、人事部タレントアクイジション室室長、プロフェッショナルサービス部人事総務センター所長、同センターHRIS室室長、同センター人事サポート室室長を経て、2024年4月より現職。
マイナスからのスタート。逆境を乗り越えた原動力
長久さんの社会人としてのキャリアは、自動車メーカーで海外向けの部品営業からスタートし、2001年に人事部門に異動しました。
新卒で入社した日産自動車では、まず部品事業部で海外向けの営業を担当しました。そこで7年を過ごして業務にも慣れた頃、事業を巡る環境が変化する中、突然、人事部に異動となりました。
仕事の楽しさを感じていましたし、決して異動を希望したわけではなかったこともあり、人事としてのキャリアは、マイナスの感情を抱いてのスタートでした。
人事部に異動してからご苦労はありましたか。
配属された海外人事部では、直属の上司やチームメンバーがとても良い方で、仕事も丁寧に教えてくださいました。しかし、配属後1年半から2年ほどは、なかなか人事部門になじめませんでした。
当時は他部門からの異動や中途入社者が少なく、人事一筋のキャリアを歩んできた方々からは、事業部から来た私が異物に映ったと思います。今振り返ると、周囲の気持ちが分からなくはありません。希望したわけではない部署でそのカルチャーになじめず、会社を辞めたい気持ちが強まっていきましたが、当時の経験があったからこそ、今の自分があるのもまた事実です。
孤立した状況を、どのように乗り越えたのでしょうか。
とにかく負けず嫌いな性格が幸いしたのだと思います。このまま辞めてしまっては、自分は仕事ができない人間だと認めることになる。いつか辞めるにしても、同僚から「長久さん、教えてください」と言ってもらえるようになるまで頑張ろう。そう心に決めていました。
実際に周囲から頼ってもらえる日が来るのですが、それよりも先に仕事が楽しくなってきました。社内の環境も少しずつ変わってきて、中途採用を強化し、人事部門にも中途入社者が増加。その頃には「ここで頑張ろう」という気持ちが芽生えていました。

「1000人に会えば分かる」。“怖さ”が“面白さ”に変わった
「仕事が楽しくなった」とのことですが、具体的にどのようなきっかけがあったのでしょうか。
人事部に配属されてからしばらくは、「人のことが分からない」と悩んでいました。部品事業部時代に扱っていた部品には部品番号があり、価格があり、ロジックは明快。ところが、人事の対象は感情を持つ「人」です。社員番号はありますが、部品の値付けと同じ感覚で人の給与を決めるわけにはいきません。また、採用は人が人を選ぶ行為ですが、それを怖いと感じていました。
あるとき、フランス人上司に「どうすれば人のことが分かるようになるのか」を尋ねました。すると「1000人に会ったら分かるようになるから、実践してみなさい」という言葉が返ってきました。
それから、従業員との面談や会議など、1対1で話す機会を数え始めました。すぐに400人くらいに達し、数えることはやめましたが、多くの人と対話するうちに、だんだん人の特性や考え方のパターンが見えるようになってきたのです。もともと人間観察は好きでしたが、上司からの一言がきっかけで、人の内面を見ることの面白さに気づきました。気難しい人、価値観が合わない人……さまざまな人と向き合う中で、多くの発見がありました。これほど多様な人に出会える仕事は他にはない、と思えるようになったのです。
もう一つ、別の上司から掛けられた「自分の色を出すように」という言葉も忘れられません。“自分の色”が何なのかを模索する中で、「きちんと仕事をする。特に必ず締め切りを守る」ことを意識し始めました。基本的なことですが、日々の積み重ねによって、徐々に人事部の同僚から認められていくのを感じました。その上司からは「間違ったら自分が謝るから、思ったようにやってこい」とも。これらの言葉は、今の私を支える考え方につながっています。
責任を持てる範囲では、自分の裁量で動くべき
その後、ボルボ・カー・ジャパンを経て、2021年にリコー入社後はHRBPもご経験されています。HRBPと本社の人事部門ではどのような点が違うとお考えですか。
日産では事業部から人事部に異動しましたが、海外リージョンを担当することがほとんどで、いわゆる本社人事の業務は経験しませんでした。一方で、事業部にいたおかげで、人事部が外からどのように見られているのか、また人事が何を求められているのかを肌感覚で知っていました。その経験がHRBPの仕事に生きたと感じています。
HRBPの仕事は、事業計画や目標を達成するために、人員の手配など、人事として何をすべきかを考えることであって、単に現場に寄り添うことではありません。立ち位置としては、常に現場と本社の「間」にあるべきです。時には本社の方針を現場に浸透させ、時には現場の代弁者となり本社を動かすこともあります。
私はその時々の状況に応じて、自分の裁量でどちらに軸足を置くかを決めていました。HRBPに限った話ではなく、私は基本的に「責任が持てる範囲では自分の裁量で動くべき」と考えています。
例えば、本社人事部から「これをやりなさい」と指示が来たとします。もちろん実行すべきことは実行しますが、現場の実情を知っているのはHRBPです。本社が言っているからといって、実情に合わないことを進めるわけにはいきません。海外の拠点を担当していたときは特に、自身の責任で「この国では、このように解釈するのが妥当だ」と判断したこともあります。
現在は会社全体の人事をまとめるCHROという立場ですが、HRBPに対してはどのように接していますか。
当時の私がそうしていたように、「HRBPが現場の実情に合わせて裁量を持って動く」ことを推奨しています。もちろん、その人の成長度合いや専門性、判断能力を見極めた上での話です。リコーという会社の文化や守るべきラインは崩せませんから、どこが落としどころになるのか、ギリギリのラインはどこかという対話は欠かせません。その範囲内であれば、HRBPの判断を最大限尊重したいと思っています。
CHROとしてHRBPに接する際は、「自分がHRBPの立場だったらどう考えるか」と、「本社人事として会社全体を見なければならない」という二つの視点を常に意識するようにしています。この両方の視点を持つ人材を育成するために、リコーでは今、若手人事のローテーションを推進しています。本社人事を経験したら事業部人事へ、事業部を経験したらまた本社人事へ、というサイクルです。
たとえば、新卒から事業部人事に就いていたある若手社員が自ら、「現場が最も関心を持つのは給与と評価なので、本社で処遇の業務を勉強したい」と希望してきました。まさに、私たちが目指している姿です。現場の視点を持った人材が本社で制度を設計し、本社の意図を理解した人材が現場をサポートする。この循環が組織を強くすると信じています。
先日その社員に会った際、「仕事がすごく楽しい」と話してくれました。いきいきと仕事をしている姿を見て、こちらもうれしくなりましたし、心強く感じましたね。きっとリコー人事部の良いロールモデルになってくれると思います。
「常識」を持ってグレーゾーンの濃淡を決める

リコーは8万人のグローバル組織ですが、人種や文化的背景が異なる従業員をまとめる上でご苦労はありませんでしたか。
日産時代に海外人事部、その後リージョン人事でアジアやインド、アフリカなどを担当し、「横に外国籍の従業員がいる」環境が当たり前でした。また、前職のボルボはスウェーデンに本社があるので、北欧諸国と日本との考え方、価値観の違いを実感する日々でした。こういった経験を通じて、文化的・宗教的背景の違いに慣れていきましたね。
価値観や文化的・宗教的背景が異なる人と一緒に働くために必要なのは、「おかしい」「自分とは違う」と思っても、まずは受け入れてみることだと思います。相手もきっと、私のことを「自分とは違う」と感じているので、お互い様です。相手を受け入れ、自分を開示し理解を深めていけば、ビジネス上で良好な関係を築けると思います。
8万人をまとめるCHROとして、どのような姿勢を大切にしていますか。
「常識を持つこと」です。「1000人に会うように」と言ってくれた上司から、人事になりたての頃にアドバイスされました。
私たちが人事・総務として行う仕事の多くは、法令や社内規定などのルールに基づいています。しかし、現実に起こる事象や人が関わる問題は、ルールだけでは「白黒をつけられない」ことばかり。白と黒の間の「グレーゾーン」に対して、白寄りなのか、黒寄りなのか、その濃淡を判断し行動することが、私たち人事パーソンが存在する意義だと考えています。
全てのことがルール通りに白・黒をはっきりさせられるなら、私たちの仕事はAIに代替されるかもしれません。しかし、グレーゾーンがある限り、人間が介在する必要があります。そして、その判断のよりどころの1つであり、非常に重要なのが、自身の「常識」なのです。
注意すべきは、その常識は一つではなく変化する、ということ。人によって判断基準は異なるし、今日の常識は明日の非常識かもしれません。ですから、常に自分の常識を疑い、「本当にこれで良かったか」を振り返ることが大切です。
私がリコーに来てから、何かを判断する際に「リコーでは、これまでどう判断してきたのか」を必ず聞くようにしています。それぞれの会社には、その成り立ちや文化の中で培われてきた独自の判断基準、つまり「常識」があります。自分の常識とリコーの常識をすり合わせ、時にはリコーの常識を尊重し、時には世の中の変化に合わせて変えていくべきだと働きかける。その対話と実践の繰り返しが、人事の仕事の核心です。
そういった考え方は、リコーの人事制度にも反映されているのでしょうか。
当社は2022年に「リコー式ジョブ型人事制度」を導入し、年功序列からの脱却を進めてきました。その結果、30代の管理職比率が導入前の2.5%から11.4%(2025年4月1日時点)まで向上しました。
若い世代がミドルマネジメント層に加わることで、組織に健全な変化が生まれています。彼らは良い意味で遠慮しません。臆せずに「なぜですか」「これではダメなのですか」と問いかけてくれたり、我々が固定観念にとらわれていることを指摘してくれたりします。
これこそ、リコー式ジョブ型人事制度を導入した最大の成果だと感じています。もちろん、年功序列を崩すことで、これまで通りのキャリアを描けなくなる人も出てきます。しかし、会社は利益を出さなければならない組織です。優秀な人材が、年齢に関係なく活躍できる機会を提供することが、企業の持続的な成長につながると確信しています。
私は、サクセッション・プランも「後継者」個人ではなく、チームとして考えるべきだと思っています。例えば、私のようにリコー生え抜きではない場合、周囲にはリコーの歴史や文化、価値観に詳しい方がいた方が望ましいし、逆にリコー在籍歴が長い人には、“外からの視点”が必要でしょう。一つの考え方にとらわれないチームづくりが重要です。
会社を動きやすくすることで存在価値の発揮を
最後に、これから人事のキャリアを歩む若い方々へ、メッセージをお願いします。
大前提として、仕事は楽しまなければなりません。人生の中で仕事が占める時間は非常に長い。その時間がつらいものであれば、人生そのものがつらくなってしまいます。私には若いころから、「仕事を楽しむ」という考えが根底にあります。特に人事は、自分たちが楽しんでいなければ、従業員に対して「エンゲージメントを高めよう」などと言っても説得力がありません。「人事は“他人事”」と言われないように、人事も従業員の一人であることを忘れてはならないと思います。
ウェルビーイングが注目されている通り、心身ともに健康で働くことがすべての根底にあります。リコーにとっては、「人を愛し 国を愛し 勤めを愛す」という創業の精神「三愛精神」がウェルビーイングそのもので、全社に浸透しています。従業員が心身ともに働ける環境のために人事制度を整え、時代に遅れないようにマイナーチェンジを続けることが必要です。
その上でお伝えしたいのは、「人事は主役ではない」ということ。人事部門が会社を動かしていると言う人がいますが、私の考えは違います。会社は人事部門ではなく、従業員一人ひとりが動かしているのです。では、人事には何が求められているのか。それは、会社を動きやすくする「プロデューサー」としての役割です。
「人事は人事。事業は事業」と分けて考える人もいます。しかし、会社は人事と事業ががっちりとかみ合ってこそ、前に進むのです。会社の事業計画を達成するため、従業員が能力を最大限に発揮できる組織という舞台を整え、時には潤滑油として「油を差す」。適所適材を実現し、人の成長を促すことで、会社をより円滑に運営できるようサポートする。それが人事の役割であり、存在価値を発揮する道です。
そして、そのプロデューサーの仕事を支えるのが、先ほどお話しした「常識」です。もう一つ付け加えるなら、「常に考える」こと。組織はどうあるべきか、どうありたいのか。分からないことがあれば、聞きに行けばいい。その際には必ず「自分はこう思う」という仮説を持っている必要があります。それなくして成長はありません。
今は、「人的資本経営」という言葉が追い風となり、人事の重要性が広く認識されるようになってきました。これは大きなチャンスです。ぜひ、自身の存在価値を会社への貢献という形で示し、人事という仕事を通じて、楽しく、充実した日々を送ってほしいと思います。私のように、人事一筋でなくてもCHROになる道はあります。多様な経験こそが、これからの人事に求められる強みになるはずです。

(取材:2025年7月25日)
この記事を読んだ人におすすめ

各企業の人事リーダーが自身のキャリアを振り返り、人事の仕事への向き合い方や大切にしている姿勢・価値観を語るインタビュー記事です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント