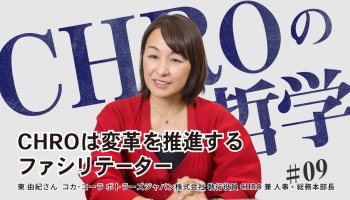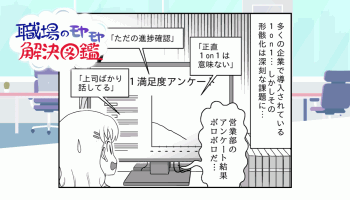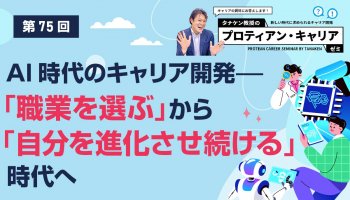タナケン教授の「プロティアン・キャリア」ゼミ【第66回】
「対話的自己理論」で深化させるこれからの1on1
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
田中 研之輔さん
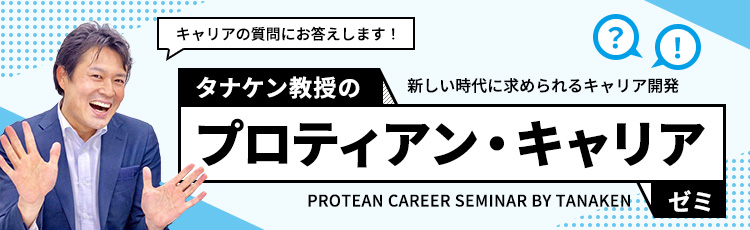
令和という新時代。かつてないほどに変化が求められる時代に、私たちはどこに向かって、いかに歩んでいけばいいのでしょうか。これからの<私>のキャリア形成と、人事という仕事で関わる<同僚たち>へのキャリア開発支援。このゼミでは、プロティアン・キャリア論をベースに、人生100年時代の「生き方と働き方」をインタラクティブなダイアローグを通じて、戦略的にデザインしていきます。
前回の「キャリア対話」に続いて、今回も「対話」を取り上げます。その理由は明確で、人的資本経営と社員の主体的なキャリア形成を同時に実現していく「ラストワンマイル」が、組織内の「対話」だからです。
人的資本経営を推進する企業現場では、1on1がマネジャーとメンバーとの相互コミュニケーションの貴重な場となっています。社員一人ひとりの成長を促し、組織の生産性を向上させる重要な機会として認識されています。
しかし、その効果が十分に発揮されているかというと、必ずしもそうではありません。多くの企業が1on1を導入していますが、単なる業務報告や指示伝達の場になってしまい、深い自己理解や内省を促す場になっていないケースが多いのが現状です。社員管理として運用され、一人ひとりの成長につながっていないのです。
特に昨今の1on1の課題として、「対話の形式化」と「上司の一方的な指導」が挙げられます。本来、1on1は部下が自身のキャリアや働き方を見つめ直し、より良い選択をするための場であるべきですが、実際には、評価面談の延長のようになっているケースが少なくありません。また、部下自身が自らの考えを深める機会を持つことができず、受動的な姿勢のまま対話が進んでいることも大きな問題です。
こうした状況の中で、対話的自己理論(Dialogical Self Theory)の可能性を今改めて深掘りする必要があると考えています。対話的自己理論とは、一人の内面に多声的な存在が共存し、それらが対話する声を聞いて自己を捉える、という考え方です。
この理論を提唱したオランダの心理学者、ヒューベルト・ハーマンス博士は、実際に一人の中に多様な声があり、それらは国際的、文化的、コミュニティ的な要因と関わりながら変化し続けるとしています。
ハーマンス博士は、心理学の分野で広く知られた研究者であり、特に自己理論や動機づけに関する研究に数多く貢献してきました。彼の研究は、従来の自己概念に対する新しい視点を提供し、自己を静的で固定されたものではなく、社会的・文化的な文脈の中で絶えず変化し続ける動的な存在として捉える考え方を発展させました。
ハーマンス博士は、対話的自己理論の構築にあたり、ミハイ・バフチン(Mikhail Bakhtin)の対話理論や、ウィリアム・ジェームズ(William James)の自己理論などを基盤にしながら、自己の多声性や対話性を強調しました。また多数の学術論文を発表し、特に「Dialogical Self Theory and Positioning Theory」において、自己が異なる文脈に応じて変化する様子を詳細に説明しました。
対話的自己理論は、一人の中に多声的な自己が共存し、それらが内的対話を通じて統合されていくプロセスを重視します。単なる意見交換ではなく、個人が自らの中にある異なる価値観や視点を理解し、それを整理することによって、より納得感のある意思決定ができるようになります。1on1に対話的自己理論アプローチを取り入れることで、マネジャーとメンバーの関係性がより双方向的なものとなり、メンバーが主体的にキャリアを考える機会を増やすことができるでしょう。
また、ハーマンス博士の研究はキャリアカウンセリングや教育心理学の分野でも応用されています。自己対話を促進することで、個人の成長や意思決定を支援する手法の開発に貢献しました。ハーマンス博士の研究は、現代のグローバル社会における多文化共生やアイデンティティの問題にも適用され、移民や異文化環境での自己形成に関する研究にも影響を与えています。
1on1における具体的な実践方法
1on1において、対話的自己理論を活用するためには、上司が以下のようなプロセスを意識することが重要です。
1.メンバーの多声性を引き出す質問をする
「今の仕事を通じて、どんなことを感じていますか?」
「別の立場や役割の自分がいたら、今の仕事ぶりについて何と声をかけますか?」
「過去の自分なら、この状況をどのように捉えていると思いますか?」
2.異なるアイポジションを可視化するセルフワーク
自身の役割それぞれにおける声を複数書き出してもらう。たとえば、「マネジャーとしての自分」「プレイヤーとしての自分」「父親・母親としての自分」「息子・娘としての自分」「趣味に没頭する自分」など、それぞれの思いを書き出す。
3.異なる自己の声を対話させる
記載した思いを見ながら、上司が対話を深めていく。仕事の業務を現在という「点」で捉えるのではなく、複数の自己を生きる「面」として捉えるよう、声をかける。必要に応じて、「どの自己の声が今一番強くなっているか?」といった問いかけを行う。
4.自己ナラティブの作成を促す
メンバーに自身のキャリアや意思決定について物語を作ってもらうことで、自己の声を整理させる。その上で、「未来の自分はどう語るだろうか?」と問いかける。
5.アクションプランを立てる
1on1の中で見えてきた自己の対話を踏まえ、メンバーに次の行動を決めさせる。「どの自己の声を尊重しながら、どんな一歩を踏み出せそうですか?」「仕事を通じて、何を得たいのですか?」「人生を通じて、何を成したいのですか?」と問いかける。
このように、対話的自己理論を活用することで、1on1が単なるフィードバックの場ではなく、自己探求と自己統合の創造的なコミュニケーションプロセスとなるのです。

プロティアン・キャリア理論などとの接続
対話的自己理論は、プロティアン・キャリア理論とも深く接続します。プロティアン・キャリア理論は、個人が自らの価値観や目的に応じて柔軟にキャリアを形成しながら、個人と組織の持続的成長をプロデュースしていく考え方です。対話的自己理論の多声的な自己概念を活用することで、キャリア選択においても、異なる「自己の声」を対話させながら最適な選択を行うことが可能になります。
たとえば、プロティアン・キャリアを実践する人が「安定した職に就きたい自己」と「新たな挑戦を求める自己」の間で葛藤している場合、対話的自己理論のアプローチを使えば、それぞれの声を可視化し、自己対話を通じて最も納得のいく意志決定につなげていくことが可能になります。これは、キャリアの方向性を柔軟に変化させながらも、自身の内面的な統合を保つために極めて有効な手法といえます。
また、対話的自己理論は、サビカスの社会構成主義的キャリア理論(Career Construction Theory)とも深く関係しています。サビカスは、キャリアを単なる職務の積み重ねではなく、個人が自身の物語を構築しながら成長していくプロセスとして捉えました。この視点は、自己の多声的な側面を重視する対話的自己理論と共通しています。
このように、対話的自己理論と社会構成主義的キャリア理論の統合は、キャリアの自己構築プロセスをより深く理解し、実践するための強力なフレームワークを提供します。現代のキャリア環境において、個人が自己の多様な側面を受け入れながら柔軟に成長していくためには、これらの理論の接続が非常に有効であると言えるでしょう。
今後の理論的・実践的可能性
対話的自己理論は、実践的なニーズが高まっているともいえます。個人の自己理解を深化させるだけでなく、AI技術や組織開発、教育、メンタルヘルスといったさまざまな分野にも応用できるからです。
まず、AI技術との融合は、対話的自己理論の発展にとって非常に興味深いテーマです。近年、対話型AIが進化し、個人の内面との対話をサポートする技術が発展しています。たとえば、個人の多声的な自己を可視化し、それぞれの声を整理するAIシステムが登場すれば、自己対話のプロセスをより構造化し、効果的に進めることができるでしょう。AIによるフィードバックやパーソナライズされた質問を通じて、個人の意思決定を支援する仕組みも構築可能です。私も、キャリアAIコーチングの開発に携わっています。
次に、組織開発の分野においても、対話的自己理論は大きな役割を担います。企業では、従業員一人ひとりが複数の役割を持ち、それに伴う多様な声を内包しています。リーダーシップ開発において、対話的自己理論を活用すれば、自分自身の異なる側面を認識し、それぞれの声を適切に統合するスキルを磨くことができるでしょう。また、1on1ミーティングの場では、社員が自身の多声性を整理し、より納得感のある意思決定を行えるようになるはずです。
教育の分野でも、対話的自己理論の可能性は広がっています。現代の学生は、自分の将来やキャリアについて多くの選択肢に直面します。対話的自己理論を基にした「自己対話ワークショップ」を導入すれば、学生が自らの内面と対話しながら、納得のいく進路を選択できる環境を整えることができます。また、教師やカウンセラーがこの理論を活用し、生徒一人ひとりの多様な声に耳を傾けることで、より個別化されたサポートが可能になるでしょう。
メンタルヘルスの分野では、対話的自己理論が自己受容やセルフ・コンパッション(自己への思いやり)を促す強力な手法となりえます。たとえば、PTSD(心的外傷後ストレス障害)や不安障害を持つ人々が、自己の中の異なる声を認識し、それらの声を統合することで、心理的な回復を促進できるのです。自己の声を可視化し、それぞれの声の意義を理解するプロセスは、カウンセリングや心理療法においても有益でしょう。
このように、対話的自己理論は、テクノロジーの進化とともに新たな領域へと広がり続けています。個人の自己理解を深め、より納得感のある意思決定をサポートするこの理論は、これからの時代においてますます重要性を増していくでしょう。
理論の受容と実践の需要は、ときにタイムラグがあるものです。2006年に邦訳版『対話的自己』が出版されてから約20年。サビカスのナラティブアプローチへの発展的深化の土台をつくったと言っても過言ではないヒューベルト・ハーマンス博士の対話的自己理論を今改めて企業現場で受容し、人的資本経営と主体的なキャリア形成の実現のための有効的なアプローチとして展開していくことが求められています。
それでは、また次回に!

- 田中 研之輔氏
- 法政大学キャリアデザイン学部教授/一般社団法人プロティアン・キャリア協会 代表理事/明光キャリアアカデミー学長
たなか・けんのすけ/博士:社会学。一橋大学大学院社会学研究科博士課程修了。専門はキャリア論、組織論。UC. Berkeley元客員研究員、University of Melbourne元客員研究員、日本学術振興会特別研究員SPD 東京大学。社外取締役・社外顧問を31社歴任。個人投資家。著書27冊。『辞める研修辞めない研修–新人育成の組織エスノグラフィー』『先生は教えてくれない就活のトリセツ』『ルポ不法移民』『丼家の経営』『都市に刻む軌跡』『走らないトヨタ』、訳書に『ボディ&ソウル』『ストリートのコード』など。ソフトバンクアカデミア外部一期生。専門社会調査士。『プロティアン―70歳まで第一線で働き続ける最強のキャリア資本論』、『ビジトレ−今日から始めるミドルシニアのキャリア開発』、『プロティアン教育』『新しいキャリアの見つけ方』、最新刊『今すぐ転職を考えてない人のためのキャリア戦略』など。日経ビジネス、日経STYLEほかメディア多数連載。プログラム開発・新規事業開発を得意とする。
この記事を読んだ人におすすめ

HR領域のオピニオンリーダーによる金言・名言。人事部に立ちはだかる悩みや課題を克服し、前進していくためのヒントを投げかけます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント