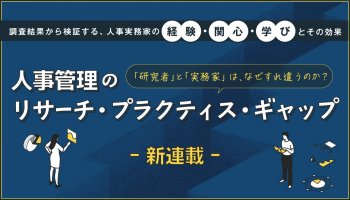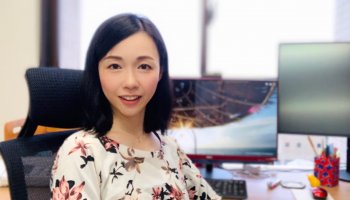「研究者」と「実務家」はなぜすれ違うのか?
人事管理に関する研究と実務のギャップを調査し、人事パーソンに役立つ研究を実現
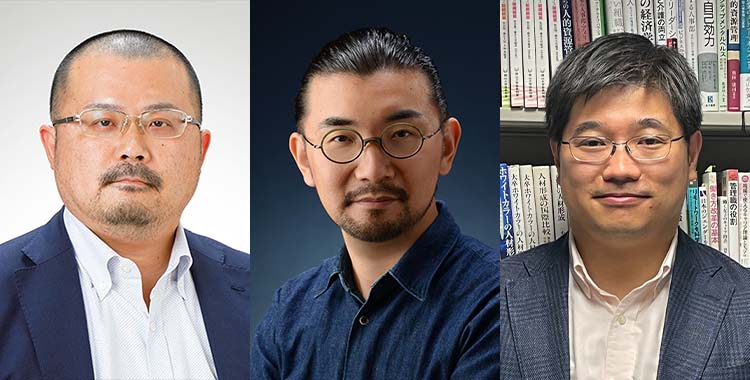
同じ人事管理という領域に対峙しているにもかかわらず、研究者と実務家の関心になぜギャップが生じるのか――。そのような問題意識から、神戸大学 江夏幾多郎氏、同志社大学 田中秀樹氏、南山大学 余合淳氏は、過去50年にわたる資料を分析。『人事管理のリサーチ・プラクティス・ギャップ』という書籍で、研究者と実務家の関心のズレが埋められてこなかったことを明らかにしました。さらに現状に迫るべく、『日本の人事部』と共同で、人事パーソンへの調査を行うことが決定。その現状を明らかにすることで、研究者と実務家がどのように接すれば双方にとってプラスになるのかを見いだし、イノベーションやクリエーションへとつなげていくことを目指しています。江夏氏と余合氏に、今回の研究の目的、今後の展開について伺いました。

- 江夏 幾多郎氏
- 神戸大学 経済経営研究所 准教授
えなつ・いくたろう/一橋大学大学院商学研究科博士後期課程、名古屋大学大学院経済学研究科講師などを経て、現職。企業における人事管理に関して、さまざまな角度からの研究・調査を行っている。主な著書として『人事評価の「曖昧」と「納得」』(NHK出版)、『コロナショックと就労』(ミネルヴァ書房・共著)、『日本の人事労務研究』。『やさしい経済学』(日本経済新聞)、『学者が斬る・視点争点』(週刊エコノミスト)などのコラム、講演、日本労務学会会長など、幅広く活動。

- 田中 秀樹氏
- 同志社大学 政策学部 総合政策科学研究科 教授
たなか・ひでき/同志社大学⼤学院総合政策科学研究科博⼠後期課程、⻘森公⽴⼤学経営経済学部講師、京都先端科学⼤学経済経営学部准教授などを経て、現職。日本企業におけるタレントマネジメント、人事部の役割を中心に、海外も含めて様々なフィールドで調査・研究を行っている。主な論文に"Effects of talent status and leader-member exchange on innovative work behaviour in talent management in Japan”(Asia Pacific Business Review・共著)、“Protection for the self-employed in Japan: Needs and measures” (International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations・共著)。

- 余合 淳氏
- 南山大学 経営学部 准教授
よごう・あつし/神戸大学大学院経営学研究科博士後期課程、岡山大学大学院社会文化科学研究科准教授、名古屋市立大学大学院経済学研究科准教授を経て、現職。現在の研究関心は、働き方の人事施策の効果と従業員知覚への影響、専門職女性のキャリアと就業継続など。主な論文に「歯科衛生士の就業継続」(『キャリアデザイン研究』・共著)、「働き方の人事管理と従業員の受け止め方」(安藤史江編著『変わろうとする組織 変わりゆく働く女性たち』晃洋書房)。
※今回のインタビューでは、江夏氏、余合氏にお話をうかがいました。
普遍性を追及する研究者、目前の事象に対処する実務家
人事管理に関して、「研究者」の関心と「実務家」との関心のギャップを調査するとのことですが、どのような問題意識があったのでしょうか。
江夏:2024年に、人事管理の研究者と実務家の関心の推移、研究と実務のギャップについてまとめた書籍『人事管理のリサーチ・プラクティス・ギャップ』を刊行しました。研究者を対象に刊行される「日本労務学会」の文献と、実務家を対象とする「労政時報」の主要記事、それぞれ過去50年分の頻出用語について計量テキスト分析を行い、両者の関心の推移、一致点と相違点を探ったものです。
背景には、これまであまり交流のなかった研究者と実務家の関係性をアップデートしたい、という問題意識がありました。研究者と実務家は人事管理という同じ領域に携わっていますが、それぞれ別のフィールドで活動しています。両者が協働すれば、人事管理がより進歩するのではないかと考えたのです。
こうした問題意識は海外の研究者のほうが強く持っているのですが、その主張の多くが「我々のエビデンスや理論を受け入れたら、実務がうまくいく」となりがちで、あまり共感できるものではありませんでした。実社会でも活用できる理論を生み出すためには、研究者の独善的な考えではなく、現場の意見も踏まえた内容でなければいけません。そこでまず、日本の実態について独自調査してはどうかと考え、余合さん、田中さんと共に調査することになりました。
余合:研究者が接する実務家は、大学院に学びに来る社会人など、そもそも「研究に関心がある人」がほとんどです。実際に企業で働く実務家の大多数は、研究にそこまでの関心はないと思います。よく経営学は実学と言われますが、実務家の方々に研究の価値はあまり理解されていないのが現状ではないでしょうか。私たちの研究の存在意義を確かめる意味でも、今回の調査は大変重要だと考えています。
研究者と実務家の関心には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
江夏:これまでの調査からは、大きく分けると「同じ用語を違う意味で捉えること」と「違うものに関心があること」の二点で、違いが見られることが分かっています。
一つ目の「同じ用語を違う意味で捉えること」については、具体例を挙げると、例えば人事管理について、研究者は「最適な施策は戦略や組織の目標や特徴しだい」という側面を相対的に重視します。一方、実務家は「現場での利害調整や合意形成を経て、少しずつ施策を形にする」という側面を研究者以上に重視します。また、望ましい人事管理にしても、研究者は個別事例を超えた一般的傾向に関心を持ち、実務家は具体的でさまざまな個別事例に注目する傾向が見られます。結果として研究者は,理論やデータによる裏付けを、実務家は目新しさを是とする傾向があります。
従業員については、研究者は組織を構成する一部と捉えますが、実務家は会社の代理人として従業員に向き合うことが多いため、組織とは別物の組織と取引する存在として捉えています。報酬やインセンティブの考え方も、研究者は業績や年齢といった報酬の設定基準や、報酬やインセンティブが従業員のモチベーションにどう影響するかといったことに関心を持ちますが、実務家は賃金水準、支払われるお金が手当と給与のどちらに該当するのかといった形式に関心を持ちます。どちらが正しいということではなく、同じ用語を用いていても、両者の考え方に隔たりがあることが分かっています。
二つ目の「違うものに関心があること」については、研究者はデータから一般的な傾向を導き出そうとしますが、実務家は最新事例を好む傾向があります。研究者は、従業員のやる気や能力を高める業務の特性、従業員の能力やキャリア開発、非正規社員や外国籍社員などのマイノリティとの関わり方について、実務家以上にウエイトを置きがちです。一方で実務家は、従業員の安全衛生や不利益変更、最新の法改正に自社ではどう対処するかなど、可及的速やかな対応を要する事柄についての情報を求める傾向にあります。
| 同じ用語を違う意味を捉える |
|---|
|
| 研究者が関心を寄せがち |
|
職場の業務プロセス、従業員の能力やキャリアの開発、非典型雇用のあり方、日系多国籍企業や海外企業の人事管理 |
| 実務家が関心を寄せがち |
|
従業員の安全衛生、従業員への不利益提示、法律の制定や改正への反応 |
余合:研究者は、今起きている事象をどう論理的に説明するかについて関心があります。過去に行われた研究・理論を基に、現状をどう分かりやすく説明できるかについて考えているといえます。しかし実務家は、江夏さんが指摘した通り、過去よりも現在に強い関心があります。近々に起きている人手不足をどうするか、ライバル企業の人事制度に対して自社はどうするかなど、目の前で起きている事象についてすぐに対応しなければならないため、最新の事例を基に自社でどう使えるかに関心があります。言い換えれば、膨大な研究の中から最適な理論を見つけ出し、違いを検証するだけの余裕も実用性もないのです。
それぞれの仕事の性質もあって、同じ人事領域でもお互いの関心にギャップが生まれているのですね。
江夏:研究者は今起きている事象について説明しますが、内容が俯瞰的すぎて、実務家が現場でどう使えばいいのかまでは落とし込めていない現状があります。一方で少なくない実務家が「最新事例だからすぐに使えそう」「この人が推薦しているから良いものだろう」など、情報の内容よりも鮮度や発信者を結果として重視している可能性があります。こうした背景から、両者の関心にギャップが生じるのです。
とは言え、これは私たちが集めた過去の文献情報の分析に基づくもので、当事者に直接聞いたわけではありません。実務に従事している人たちの声を直接聞き、「この知的資本や社会関係資本からこういう関心が生まれる」など、今回の調査を基に因果関係が見出せればと考えています。将来的には研究者にも同じような調査を行い、比較を目指しています。
ハイパフォーマンスの背景は? 実務家の「生の声」に迫る
今回の調査概要と、具体的な調査内容について教えてください。
江夏:『日本の人事部』を通じて人事パーソンの皆さんにアンケートを取ることで、実務家の現状を知りたいと考えています。これまでの研究で研究者と実務家の関心にギャップが生じることが分かってきましたが、一方でまだ調べきれていない部分があることも分かりました。
例えば現在、研究者や実務家が自分だけでなく相手の領域についてどこまで知っているか、どれだけ大事だと思っているか、なぜそうした知り方や思い方になるのかについては明らかになっていません。実務家が最新の事例を追い求めたり、特定の人事領域にとりわけ関心を寄せがちだったりするのは理由があるはずなので、現在の考えに至るまでの背景や接してきた媒体について調査したいと考えています。
また、企業で立派な実績を残し、人事という仕事に強い想いを持っている実務家がそこに至るまでにどういった領域に関心を持ち、どのような情報に触れてきたかについても調査し、実務家のパフォーマンス向上と研究との関わり方についても示唆できればと考えています。
調査によって、どんなことを明らかにしていきたいとお考えですか。
江夏:研究者と実務家のギャップを解明するためには、過去の文献という間接的情報ではなく、直接当人に聞くことが大切です。これまで人事の実務家は、人事管理の課題が企業や各種制度によって異なることから、個人プレーで仕事に取り組んできました。実際の調査結果を見ないと何も言えませんが、「異分野の人とのコラボもいいな」と実務家が気付きを得て、研究が日々の実務を少しでも後押しできたらいいと考えています。
実務家の多くは「研究は実務では使えないもの」と感じていますし、研究者側にも実務家とはほとんどつながりがないという人がたくさんいます。人事業界に携わる研究者と研究者の双方の能力やエンゲージメントの背景、両者の良い関わり方について指針が示せたらいいですね。
余合:書籍の中で取り扱ったのは二次情報なので、そこから言えることはあくまでもデータ分析の結果導き出された推論に過ぎません。今回の調査では、これまでの研究で捉え切れていない、人事管理に携わる実務家の生の声に迫りたいと考えています。また、実務の現場で知っておくと役立つ研究領域もあるので、「ここまでは知っておくといいよね」という線引きを明確にしたいですね。

研究者や海外に向けて日本の人事の立ち位置を発信する
調査結果の発表方法や、今後の展開についてお聞かせください。
江夏:調査の集計・分析結果は、『日本の人事部』主催の「HRカンファレンス」などのイベントやセミナー、WEBの連載記事などで発表します。日本の人事パーソンは今どんな状況にあるのかといった結果だけでなく、結果から考える私たちの解釈や私たちの見解、研究者と実務家の理想的なあり方も発表する予定です。アンケートにご協力いただいた方や実務家からのフィードバックも受けて、将来に向けた指針の精度を高めていきたいと考えています。
また、研究者にも今回と同じ内容の調査を行う予定です。両者を調査することで、研究者と実務家がお互いに関心があるのかどうか、お互いの存在をどう捉えているのかが明確になります。
研究者と実務家のギャップについて調査した論文は、海外でもほとんど見られません。海外ジャーナル誌でも発表することで、世界の多くの人に日本の人事管理の現状について知ってもらい、議論が生まれることで、日本の人事領域の底上げを図っていきたいと考えています。
今回の調査によって、研究者と実務家のそれぞれにどんな変化や動きがあることを期待されますか。
江夏:昨今の変化の激しい状況下では同じ理論や手法を使い続けられず、その都度答えをアップデートすることが求められます。しかし、研究者も実務家も個別に答えをアップデートし続けるのは大変です。複雑な人事領域では、個人戦よりも違う領域の考え方や経験を取り入れて協力し合った方が良い結果が出やすいでしょう。
私たちも、研究者と実務家の適切な関係が見えているわけではなく、日々手探りです。ただ、少なくとも両者にほとんど交流がない状態のままでは、前進できません。調査を進めていく中で研究者と実務家の「程良い付き合い方」を見出し、イノベーションやクリエーションにつなげていければと考えています。
余合:これまでは研究者から注目の(流行の)理論・専門用語が出ると、それに実務家が興味を持つというような、研究が一過性のブームとして捉えられてきた側面があるように思います。ただ研究には、人事の現場で役立つ普遍的な内容も決して少なくないので、一時的な流行ではなく、中長期的な視点で緩やかな関係性を築ける方が、お互いにとって良い関わり方だと考えています。
最後に、現在人事に携わられる皆さまへ、メッセージと調査協力の呼びかけをお願いします。
江夏:日々の活動や関わり合いがどのように人事の実務家の知見を育て、実際の仕事に影響するのかといった因果関係の調査は海外でも類を見ないので、ぜひ私たちと一緒に人事管理のフロンティアに挑戦してください。研究者も実務家も忙しいので、交流している暇なんてないと考えるかも知れませんが、違う立場にいるからこそ見えてくるものもあります。日本の人事パーソンが現在どういう場所に立っているのかが判明すれば、効率の良い仕事の進め方も見えてくるでしょう。今回の調査が、研究や実務を前進させるきっかけとなることを願っています。
余合:研究者と実務家のギャップというと堅苦しい表現ですが、研究者と実務家の仕事の棚卸しをしましょう、というのが今回の調査の趣旨です。普段研究に触れる機会がない実務家の皆さんにも、今回の調査を通じて新しい用語や考え方に触れるなど、協働、コミュニケーションの場として活用していただければと思います。「研究者の世界をのぞいてみよう」くらいの軽い気持ちで、多くの方にご協力いただけるとうれしいです。
「人事実務家の経験・関心・学びとその効果」調査にご協力ください!
企業の人事パーソンを対象としたWEBアンケートを実施します。
ぜひ、アンケートにご回答ください!
人事パーソン個人に焦点をあてるので、同じ会社の人事の方が大勢で回答されても問題ございません。本研究について、広く社内にシェアしていただけると幸いです。ご協力のほど、よろしくお願いいたします!
回答締切:3月3日(月)予定
研究結果は人事の一大イベント「HRカンファレンス」や、WEBサイト『日本の人事部』などで発表する予定です。皆さまの回答をお待ちしております!
この記事を読んだ人におすすめ

人・組織に関する課題や施策についての調査レポートを公開。貴社の課題解決にご活用ください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント