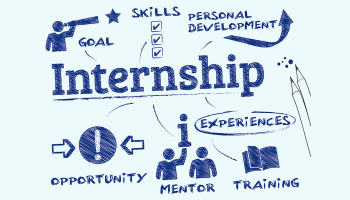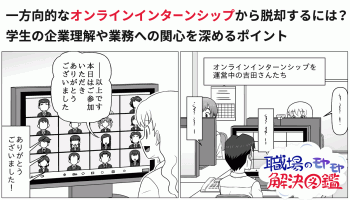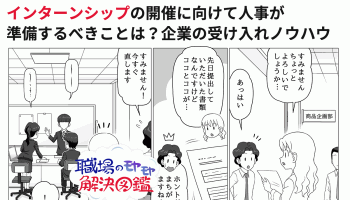インターンシップで優秀な学生に出会ったら、多くの企業が「個人的な関係を維持し、継続的にアプローチする」と回答 ~「2016年卒採用」を見据えた、インターンシップの取り組み状況を調査~
『日本の人事部』では、全国のビジネスパーソン(経営者、管理職、人事担当者など)に対して「インターンシップ」に関するWEBアンケートを実施し、その結果をまとめました。(調査期間:2014年8月4日~8月17日、回答社数:230社)
2016年卒の新卒採用から、日本経済団体連合会(経団連)の「採用選考の指針」に基づき、「広報開始」が2015年の3月以降、「選考開始」が8月以降に後ろ倒しになります。従来より3ヵ月後ろ倒しされることで、企業の採用活動にも大きな影響が及ぶことが予想されますが、企業は「インターンシップ」の実施についてどのように考えているのでしょうか。「今年、大学3年生(大学院1年生)を対象としたインターンシップを行うかどうか」のほか、「今年のインターンシップの目的」「インターンシップで会った学生の中に優秀な方がいた場合のフォロー」「インターンシップ後の学生へのアプローチ方法」について、『日本の人事部』読者にうかがいました。
今年、大学3年生(大学院1年生)を対象にインターンシップを行う企業は54.8%
「今年大学3年生(大学院1年生)を対象としたインターンシップを行うかどうか」という質問に対する回答は、「行う」(54.3%)が最も多く、次いで「行わない」(22.3%)、「未定」(23.4%)という結果になりました(図表1)。行わない理由として多かったのは「マンパワーが不足しているため、学生をケアする余裕がない」や、「プログラムを考えるための時間がない」など。インターンシップの有効性は認識しながらも、そのために時間を割くことが難しい企業の実情が明らかになりました。
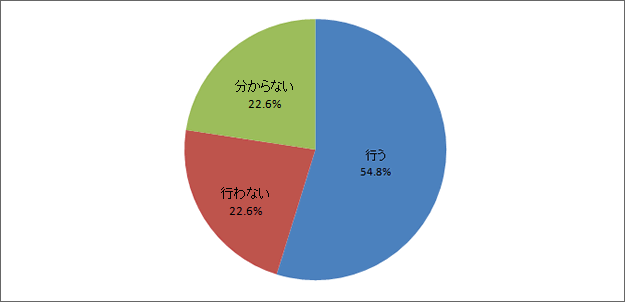
多くの企業がインターンシップを重要な“選考プロセス”として認識
「今年インターンシップを行う目的」について聞いたたところ、「会社の認知度を上げるため」(40.5%)との回答が最も多く、以下、「自分が求めるタイプの学生を見つけるため」(21.4%)、「大学との連携を強化するため」(19.0%)と続きます(図表2)。インターンシップを、重要な「選考プロセス」の一つとして考えている企業が多いことがわかります。
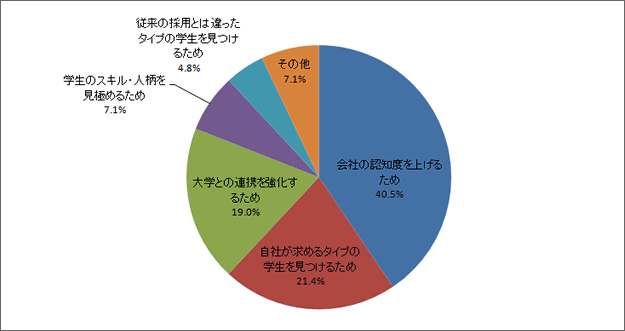
インターンシップの選考では、スペックや属性よりも「やる気」「意欲」を重視
「インターンシップの選考で最も重視するもの」という質問に対しては、「本人のやる気、意欲」(31.7%)、「特に重視するものはない」(19.5%)という回答が上位になりました(図表3)。細かいスペックや属性を重視するのではなく、実際に会って本人のやる気や意欲を確認した上で、結論を出す企業が多いことが分かります。実際、ご回答いただいた方からは「多くの学生と出会いたいので、あまりフィルターはかけたくない」「弊社との相性を見極めた上で判断したい」などの声が多く聞かれました。
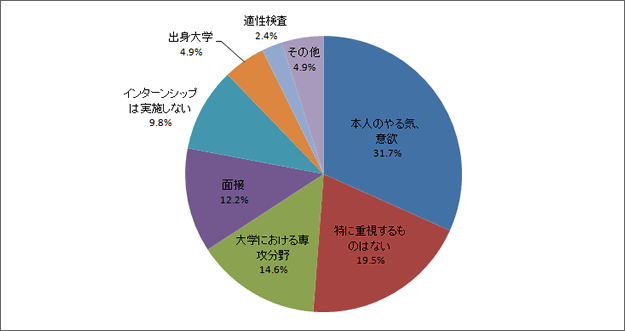
「個人的な関係」を維持することで、優秀な人材に継続してアプローチ
「インターンシップで会った学生の中に優秀な人材がいた場合、フォロー(働きかけ)で最も重要なもの」という問いに対しては、「個別面談(接触)の機会を設ける」(23.8%)、「受け入れ部門の担当者が個人的に関係を維持する」(21.4%)、「インターンシップの内容(結果)をフィードバックする」(21.4%)、「交流会を実施する」(19.0%)、「人事担当者が個人的に関係を維持する」(7.1%)などが上位を占めました(図表4)。インターンシップを通じて出会った優秀な学生に対しては、「個人的な関係の維持」を中心に、戦略的にアプローチしていることがわかります。
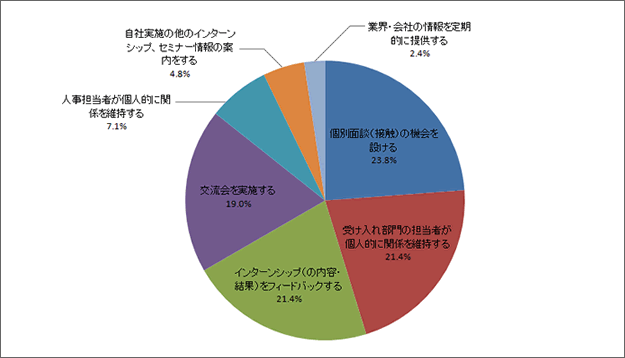
【調査概要】
調査対象 :全国のビジネスパーソン(経営者、管理職、人事担当者 など)
調査期間 :2014年8月4日~8月17日
調査方法 :WEBアンケートによる回収
有効回答社数:230社
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント