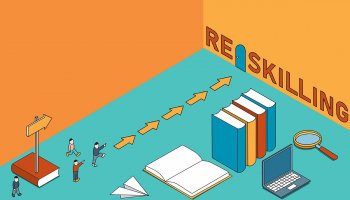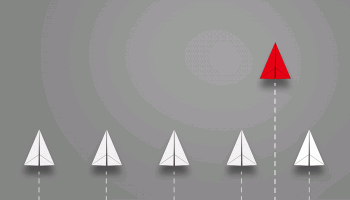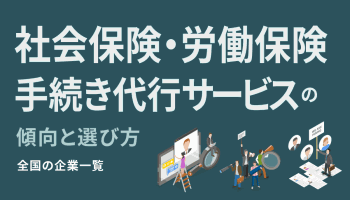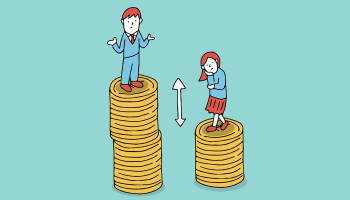106万円の壁~社会保険料の負担OK企業が増加~
古橋 孝美(ふるはし たかみ)
パートタイマー白書や学生を対象にした就職活動に関する意識調査など、当研究所が独自で行っている調査から見えてくることを考察します。
2016年10月、社会保険の適用範囲が拡大されました。今まで、社会保険の加入が必要となる短時間労働者の要件は、「概ね正社員の4分の3以上の労働日数・時間で働いていること」でしたが、新しい適用基準は以下のようになっています。
- 月額8.8万円以上(年収106万円以上)
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 1年以上の雇用見込みがある
10月時点では、社会保険の被保険者が501名以上いる企業が対象となりますが、今後は対象となる企業も段階的に広がっていくと思われます。

社会保険料は、企業側と労働者側が折半して納めています。ただ、企業側にとっては、対象となる労働者が増えれば、その分社会保険料の負担も増えます。そのため、新たな適用基準に該当する労働者、もしくは旧基準と新基準の狭間の労働者がいる企業では、「“週20時間未満/月8.8万円未満”になるよう、パート・アルバイトの労働時間を調整するのか」、それとも「社会保険に加入させるのか」対応を決めかねている企業もあるのではないでしょうか。
弊社が発行している『パートタイマー白書』では、数年来、企業に対して「社会保険の適用基準が拡大されたら、どのような対応を取るのか」を聞いています。直近の平成27年版では、「保険料負担が増えても、特に非正規雇用従業員の労働時間の調整は行わない」が43.8%で最多となりました。4割以上の企業が、法改正でのしかかる社会保険料の負担よりも、パート・アルバイトの戦力を“取る”意向のようです。
今でこそ、パート・アルバイトの社会保険料の負担を厭わない企業が増えてきましたが、以前はそうではなかったようです。過去の『パートタイマー白書』を追っていくと、企業の意識が変化してきたことがうかがえます。調査年によって、調査対象企業の抽出方法や一部の選択肢が異なっているので、単純に比較はできないものの、ここでは一定の傾向が見られました。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント