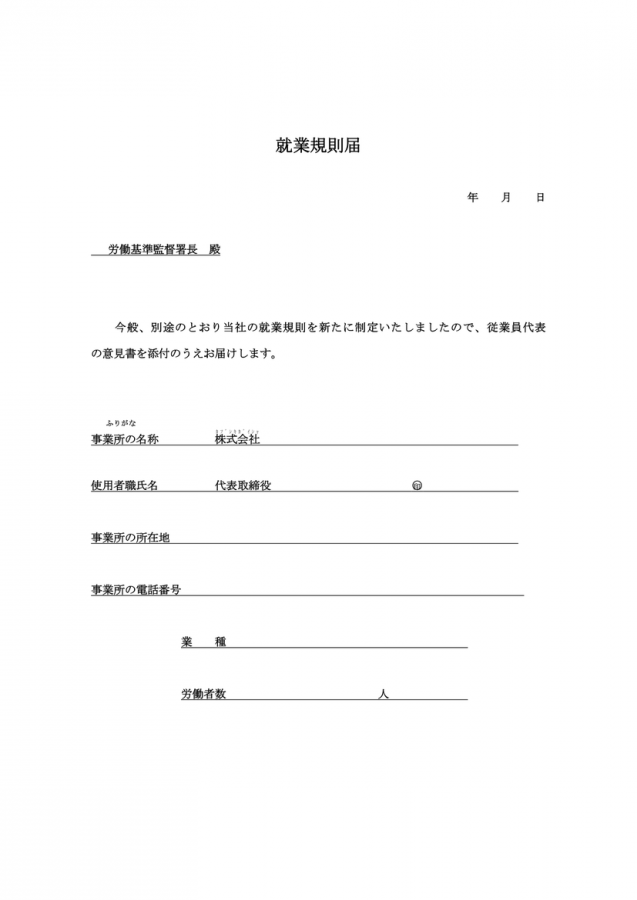退職者に競合への転職を禁じることはできるか
自社の重要ポストを担っていた社員から、同業・競合他社への転職を告げられた――。「企業の機密情報やノウハウが流出してしまうのでは」と、人事担当者として頭を抱える場面は少なくありません。退職者に競合への転職を禁じる「競業避止義務」は、企業の正当な利益を守るための手段ですが、その運用は一筋縄ではいきません。「職業選択の自由」との調和をいかに図るかが、裁判実務上も常に問われています。本記事では、競業避止義務契約の有効性を判断する法的基準を解説するとともに、トラブルを未然に防ぐための具体的な予防策から、実際に問題が発生した際の対応フローまで、人事担当者が現場で役立つ実務知識を提供します。
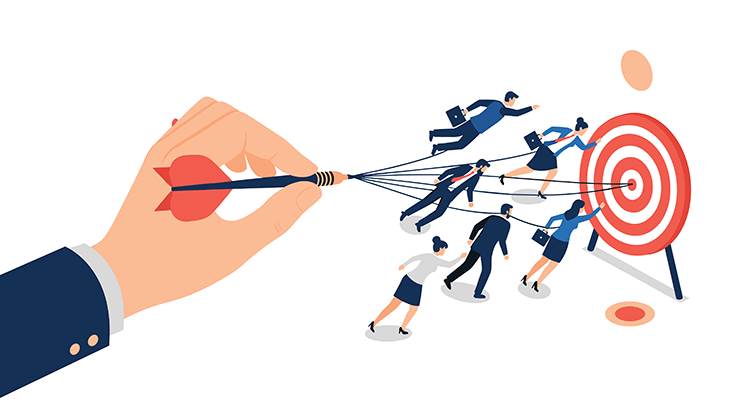
競業避止義務の有効性と判断基準
企業の成長を支える技術、顧客情報、独自のノウハウは、企業にとって競争力の源泉であり、守るべき重要な資産です。社員の退職に伴い、これらの情報が競合他社に流出することは、企業にとって大きな脅威となり得ます。そこで活用されるのが「競業避止義務」ですが、その効力は無制限に認められるわけではありません。
競業避止義務は、在職中と退職後で性質が異なります。在職中の競業行為は禁止が当然に認められる一方(労働契約上の誠実義務による)、退職後の競業避止義務は、労働契約終了後の行動を制限するものであり、特に慎重な検討が求められます。
「職業選択の自由」と「企業の正当な利益」
大前提として、日本国憲法第22条では「職業選択の自由」が保障されています。労働者が退職後にどのような職業に就き、どの企業で働くかは、原則として個人の自由です。そのため、企業が退職後の転職先を不当に制限することはできません。
一方で、企業側にも、不正な競争から自社の営業秘密や顧客との関係性といった「守るべき正当な利益」があります。両者のバランスをどう取るかが、競業避止義務の有効性を考える上での核心となります。
競業避止義務が「有効」と判断されうるポイント
過去の判例を分析すると、競業避止義務契約の有効性は、主に以下の六つの要素を総合的に考慮して判断される傾向にあります。人事担当者は、自社のルールがこれらの要素を満たしているかを、常に点検しておく必要があります。
- 守るべき企業の利益は何か:保護に値する具体的な企業秘密やノウハウが明確に存在するか。単なる業務上の知識や経験など、労働者個人のスキルに属するものは対象外とされやすい傾向にあります。
- 従業員の地位:対象となる従業員が、企業の秘密情報にアクセスできるような限定された地位にあったか。役員や管理職、研究開発職など、地位が高く、機密情報を取り扱う立場であるほど、義務の必要性は高く評価されます。全従業員に一律で課すことは、合理性を欠くと判断されるリスクが高まります。
- 地域的な限定:競業が禁止される地理的範囲が、企業の営業エリアなど、事業実態に即して限定されているか。例えば、国内でしか事業展開していないにもかかわらず、全世界での競業を禁じるような規定は、無効と判断される可能性が高いでしょう。
- 期間の限定:禁止期間は、企業の利益保護に必要かつ合理的な長さに設定されているか。判例上は1~2年程度が有効とされる傾向にありますが、技術の陳腐化スピードや代償措置の有無によっては、もう少し長期でも有効とされた例もあります。
- 禁止される行為の範囲:禁止される競業行為の内容が、具体的に特定されているか。「同業他社への一切の就職を禁じる」といった包括的なものではなく、「自社と直接競合する〇〇事業部門への就職」など、範囲が明確であるほど有効性が認められやすくなります。
- 代償措置の有無:競業避止義務という制約を課す見返りとして、従業員に十分な代償(在職中の手当支給、退職金の上乗せなど)が支払われているか。代償措置がなければ無効と判断される可能性が高まります。
人事担当者が講じるべき「事前対策」
競業避止義務に関するトラブルは、発生してから対応していると手遅れになるケースが少なくありません。重要なのは、いかに「予防」するかです。人事担当者が主導して、実効性のある仕組みを構築しておく必要があります。
就業規則と誓約書、いつ・誰と・どのように結ぶべきか
まず、競業避止義務を課すための根拠規定を就業規則に設けることが第一歩です。「業務上知り得た会社の機密情報を利用して、在職中および退職後一定期間、会社の不利益となる競業行為を行ってはならない。詳細は個別の合意による」といった定めを置くことで、個別合意の正当性を補強します。
ただし、就業規則だけでは退職後の義務付けとして十分ではなく、個別の誓約書(合意書)が必要とされます。締結のタイミングは「入社時」が最も望ましく、採用条件の一部として提示し、本人の自由意思に基づいて署名を得ることが重要です。退職時に初めて提示すると、強要と見なされるおそれがあるため避けるべきです。
実効性を高める誓約書の作り方
誓約書を作成する際は、前述した「有効と判断される六つのポイント」を強く意識する必要があります。あいまいな表現を避け、具体的かつ合理的な内容にすることが肝要です。
- 目的の明記:なぜ競業避止義務が必要なのか(例:「当社独自の〇〇技術および顧客情報を保護するため」)を具体的に記載します。
- 義務の具体化:禁止する行為(例:「〇〇製品と直接競合する製品を取り扱う企業への転職」「在職中に担当した顧客への営業活動」)、期間(例:「退職後1年間」)、地域(例:「日本国内」)を合理的な範囲で明確に定めます。
- 対象者の限定:役員、特定の技術者、部長職以上の管理職など、対象者を限定する理由も付記するとより丁寧です。
- 代償措置の明記:競業避止義務の対価として、在職中に「競業避止手当」を支給する、あるいは退職金に一定額を上乗せするなど、具体的な代償措置を記載します。金額の妥当性も重要です。
- 違反時の措置:違反した場合のペナルティー(例:「退職金の減額・不支給」「損害賠償請求」)を、根拠規定と合わせて記載します。過度に高額だと公序良俗違反で無効となる可能性もあります。
退職希望者から「競合へ転職します」と告げられたらどうするか
どれだけ事前に対策を講じていても、退職希望者から競合他社への転職を告げられる場面が訪れる可能性があります。その際の初動と冷静な判断が、事態の悪化を防ぐ鍵となります。
退職面談でのヒアリングと注意点
まずは感情的にならず、冷静に事実関係を確認することが重要です。「裏切りだ」といった言葉は禁物です。退職面談では、以下の点を丁寧にヒアリングします。
- 転職先の企業名と事業内容:自社とどの程度競合するのかを客観的に把握します。ただし、無理に聞き出そうとしてはいけません。
- 転職先での職務内容:自社で担当していた業務や取り扱っていた機密情報と、直接的な関連性があるかを確認します。こちらも、無理に聞き出そうとしてはいけません。
- 本人の認識の確認:入社時等に締結した競業避止義務に関する誓約書の存在を本人に再認識させ、「誓約内容をご理解いただいていますね?」と穏やかに確認します。この際、高圧的な態度で義務の履行を迫るのではなく、あくまで「確認」にとどめることが重要です。
ヒアリングした内容は、後の交渉や法的手続きの際に重要な証拠となるため、日時や同席者を含めて正確に記録しておきます。
法的措置は最後の手段。現実的な選択肢とリスクを考える
誓約書違反の可能性があるからといって、直ちに差止請求や損害賠償請求といった法的措置に踏み切るのは得策ではありません。訴訟には多大な時間とコストがかかる上、企業の評判に傷がつくリスクもあります。また、企業側は「どのような機密情報が、どのように不正に利用され、どれだけの損害が発生したか」を立証する責任を負いますが、そのハードルは高いのが実情です。
まずは、本人との対話を通じて、現実的な落としどころを探るべきです。例えば、「特定の顧客リストは持ち出さない、接触しない」「開発中の〇〇に関する情報については一切口外しない」といった具体的な約束事を再度取り付け、念書を交わすといった対応が考えられます。それでも懸念が払拭できない重大なケースに限り、弁護士と相談の上で、内容証明郵便による警告書の送付や、仮処分の申し立てといった次のステップを検討することになります。
この記事の監修

井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表
井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
井上 久 昭和30年11月25日の69歳です。2021年4月1日に開業しました。得意な業務は、交通事故相談とクレーマ一・ヘビークレーマ一対応です。「本気・本音・本物」のアドバイスをさせていただきます。お気軽にご相談ください。
人事のQ&Aの関連相談
競業他社への転職について
いつも拝見させて頂いております。
弊社、就業規則に
(退職後の競業避止)の条項があり、
退職後2年間は、会社と競業する業務を行ってはならない。
在職中に知り得た顧客と、離職後2年間は取引をしてはな...
- 名ばかり役員さん
- 愛知県 / 鉄鋼・金属製品・非鉄金属(従業員数 31~50人)
元役員の競合企業への転職
元役員が退職することになりましたが、競合企業への転職の噂があります。
当社では、社員が退職するときに、秘密保持と退職後2年間は競合へ就職しない旨の誓約書をかわすことになっています。
この場合、役員で...
- k2takenさん
- 東京都 / 機械(従業員数 51~100人)
就業規則の変更
就業規則の変更について質問いたします。
現在、就業規則の変更を検討しておりますが、その中で、いわゆるライバル会社への転職を防止する条項が設けられないか検討しております。そこで質問なのですが、次のような...
- *****さん
- 東京都 / その他メーカー(従業員数 1001~3000人)
退職後の競業企業への就業規制について
いつも大変参考にさせていただいています。
退職後に競業企業へ転職をし、顧客をそちらに誘導していると思われる事例が今までにありました。
そこで、その対策として、退職にあたっての規則をつけることは可能で...
- *****さん
- 東京都 / 美容・理容(従業員数 301~500人)
退職後、次の就職先に現職の競合他社の選択禁止
退職者が、次の就職先の選択に競合他社に入社するのを禁止することを集合規則で明文化したいのですが、可能ですか。
また明文化したとしても効力はあるのでしょうか。
- *****さん
- 静岡県 / 商社(専門)(従業員数 51~100人)
退職予定者による部下の引き抜きについて
いつも参考にさせていただいております。
さて、相談内容は退職予定者による社員の引き抜きについてです。
ある営業幹部が部下を引き連れて同業他社へ転職する動きがあります。そのなかの何名かは公休や有給を使用...
- *****さん
- 東京都 / 美容・理容(従業員数 301~500人)
退職金規程について
いつもお世話になります。
現在、退職金規程の見直しを検討しております。知人から聞いたことがあるのですが、役職や担当業務を考慮して、会社が必要と認める者に限り、退職後の競業行為の禁止と秘密保持についての...
- *****さん
- 兵庫県 / その他業種(従業員数 11~30人)
同業他社への転職・起業禁止
過去に退職した社員に、同業へ転職・起業されたことがあります。(今ではエリア内の競争相手となっています)
あまり法的拘束力がないとは聞き及んでいるのですが…何もせず、今後の退職者にも同様に許容するよりは...
- *****さん
- 長崎県 / その他業種(従業員数 11~30人)
退職者の競合会社への就職
営業管理職が退職後、当社と完全に競合する会社へ就職しました。入社時に退職後3年間は競合会社へは就職しない旨の誓約書は取っておりますが、会社として本人もしくは本人が就職した会社へ何らかの賠償を請求するこ...
- ヴァンブーさん
- 東京都 / その他業種(従業員数 1~5人)
退職時の競合避止契約
退職者に対し競合避止の誓約書を取りたいのですが、制約期間や就業場所などを内容に盛り込む必要性があると聞きました。具体的に妥当な年数が地域(日本国内?)を教えて下さい。また、そもそもこのような契約は労働...
- *****さん
- 東京都 / 証券(従業員数 101~300人)
退職時の競業禁止について
社員が退職する際に、秘密保持誓約書を交わし、2年間の競業禁止をうたっています。この『競業禁止』とは、どの程度の制約ができるものでしょうか。たとえば、類似業務として業種を括られるような会社であれば、この...
- *****さん
- 東京都 / その他業種(従業員数 101~300人)
- 1


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント