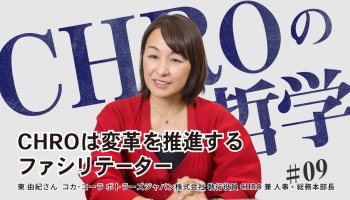CEOと二人三脚で成し遂げる「企業文化」の変革
レゾナックCHRO今井のりさんが体現する「戦略人事」
株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高人事責任者(CHRO)
今井 のりさん

企業の持続的成長の鍵として、事業戦略と連動した戦略人事の必要性が叫ばれてきましたが、その実践に悩む経営者や人事パーソンは少なくありません。昭和電工と旧日立化成の統合により誕生した株式会社レゾナック・ホールディングスは、この難題に正面から向き合い、大きな変革を遂げつつあります。その中心にいるのが、CHROの今井のりさんです。CEOとの強固な二人三脚を基盤に、トップのビジョンと人事の緻密な戦略をいかに連動させてきたのか。その軌跡から、次世代の人事パーソンが明日から生かせる変革のヒントを探ります。

- 今井 のりさん
- 株式会社レゾナック・ホールディングス 取締役 常務執行役員 最高人事責任者(CHRO)
いまい・のり/慶応義塾大学理工学部卒業後、旧日立化成株式会社に入社。経営企画、オープンイノベーション、米国駐在での海外営業など、事業部門で多彩なキャリアを積む。2019年に執行役に就任後、昭和電工株式会社との経営統合において日立化成側の責任者として尽力。2022年より二社が統合した株式会社レゾナック・ホールディングスのCHROとして、事業戦略に連動した人事制度改革、企業文化の醸成、次世代リーダーの育成を推進している。
事業部門からCHROへ、その根底にあった「人」への強い思い
理工学部を卒業され、旧日立化成に入社されてからは事業部門でキャリアを歩まれています。いつ頃からCHROという立場につながる、「人」や「組織」といった領域に関心を持つようになったのでしょうか。
多くの人事の方がおっしゃるように、私も昔から人が好きでした。学生時代は人の心に興味があり、心理学を勉強したいと思ったこともあります。ただ、「理系から文系への転部はできるが、その逆は難しい」という助言がきっかけとなり、大学は理系の道に進むことにしました。
大学卒業後は大学院への進学を周囲から勧められましたが、もっと他のことに挑戦したいと思い、旧日立化成に入社しました。面接では「実験ではなく、グローバルに関わる事業に携わりたい」と伝え、入社後は経営企画部門に配属。海外事業のサポートや、当時としては先駆けであったオープンイノベーションの推進など、アメリカのベンチャーキャピタルと連携して新しい技術を探索し、日本に導入する仕事を担当しました。
新入社員時代から、最先端の技術や文化に触れていたのですね。
はい。シリコンバレーでの経験は、私の価値観に大きな影響を与えました。特に、博士課程の学生から百戦錬磨のベテランまで、年齢や立場といったヒエラルキーに縛られることなく、誰もが対等に議論を交わしていたことが印象に残っています。
一人ひとりの根底には、「この技術領域では自分がプロフェッショナルである」という強い当事者意識と誇りがあり、組織の看板に頼ることなく「個人の名前」で仕事をしていました。そうした強い「個」の集まりがチームとなってイノベーションを創出していたのです。
一方、日本の組織では、「部長」「課長」といった役職が個人の役割意識を強く規定してしまっていると感じました。意思決定や責任の所在を明確にする上で役職は重要ですが、アイデアを出し合い議論を深める場では関係がありません。
「何を言ったか」という本質よりも、「誰が言ったか」という背景が重視されがちな日本の組織文化に対し、私は強い問題意識を抱くようになりました。

シリコンバレーでのご経験が、組織や人に対する課題意識を育んだのですね。
おっしゃる通りです。その後もデュポン社との合弁会社設立、広報・IR、約6年半の米国での営業など、グローバルを中心に主に事業畑を歩みました。そうした経験を経て経営企画に戻り、自社の10年先を考えたとき、あらためて当社のビジネスモデルの核心に思い至ったのです。
当社は機能性化学メーカーです。その本質的価値は、お客さまの多様なニーズに合わせてさまざまな材料や技術を組み合わせ、イノベーションを生み出す「カスタマイズ能力」にあります。この価値は、トップダウンの画一的な戦略では決して生み出せません。最終的な価値創造の担い手は、現場の社員一人ひとりです。
社員一人ひとりが多様な仲間と主体的にチームを組み、自律的に動けるかどうかに企業の未来が懸かっているのです。そのために何よりも重要なのは「人と組織文化」であると、10年ほど前から確信していました。しかし、当時はその考えを提案しても、なかなか周りから理解されませんでした。
2社統合でCHROが挑んだ忖度なき企業文化創造
昭和電工と日立化成という、日本を代表する化学メーカーの統合にあたって、今井さんがCHROに就任された経緯をお聞かせいただけますでしょうか。
両社が統合したきっかけは、私が旧日立化成の立場で、将来のパートナーとして昭和電工が最適だと提案したことです。機能性材料事業を発展させるには、両社が持つ技術を組み合わせることで、大きなシナジーを生みだす必要があると考えました。
当時の私は旧日立化成側の統合リーダーで、昭和電工側のリーダーであった髙橋(現レゾナックCEO)と、1年半以上にわたって「どんな会社を新しく作っていくか」を徹底的に議論しました。
私たちの基本方針は「どちらかの会社に合わせる」のではなく、「完全に新しい会社をゼロから作る」というものでした。過去の慣習やしがらみを捨てて、CXO体制を導入し、執行役員のあり方を含めて、会社の根幹に関わる部分を一切の忖度(そんたく)なく議論を重ねて作り上げていきました。
やがて髙橋が次期社長に就任することが見えてきたタイミングで、強力な経営体制の構築が急務となりました。特にCFO(チーフ・ファイナンシャル・オフィサー)、CSO(チーフ・ストラテジー・オフィサー)、CHROは重要なポストで、当初は3名とも外部から経験者を採用することを考えていました。最終的にCFOとCSOは外部から招き、髙橋から「今井さん、CHROをやってくれないか」と声がかかり、「ぜひやらせてください」と決断しました。
新しい会社作りの延長線上にCHROという大役があったのですね。その改革の柱として「企業文化」から着手されていますが、そこにはどういった意図があったのですか。
企業文化を作ることが、事業戦略そのものだからです。
私たちのビジネスは、社員一人ひとりの力と、チームによる共創がなければ成り立ちません。そして、人のパフォーマンスは環境に大きく左右されます。その環境こそが「企業文化」なのです。社員の力を最大限に引き出す文化がなければ、どれだけ立派な戦略を描いても実行できずに終わってしまいます。これこそ、多くの日本企業が抱えている課題ではないでしょうか。
幸い、CEOの髙橋も全く同じ問題意識を持っていたため、私たちは統合を機に徹底的に企業文化を作り込もうと決意しました。だからこそ、両社の良いところを取るという発想ではなく、私たちが「ありたい姿」は何かを突き詰め、そこから逆算して新しい文化を作り出すことに全力を注ぐことができました。
CEOとCHROは一心同体。経営トップが自ら「広告塔」となること
企業文化の変革を推進する上で、何が最も重要だと考えていますか。
間違いなく、CEOとCHROが「両輪」として機能することです。企業文化の変革は、CEOが本気でコミットし、ビジョンを自らの言葉で語り続けなければ、絶対に実現しません。CHROの役割は、CEOの語るビジョンを具体的な人事戦略や施策に落とし込み、現場の隅々まで浸透させていくこと。どちらが欠けても、変革は失敗します。
多くの企業で変革が進まないのは、CEOがやろうとしているのに人事部門がついてこない、あるいは人事部門だけが意気込んでいてCEOの関心が薄い、というケースがほとんどではないでしょうか。
当社では、髙橋が誰よりも強く企業文化の変革にコミットしています。例えば、社長就任直後の決算説明会の場では、財務の話はCFOに任せて役割を明確にしつつ、自らは人材戦略や組織文化について熱心に語りました。大きな赤字を計上した年の決算発表で、自身の360度フィードバックの結果を包み隠さず開示し、「自分にはこういう課題がある」と語ったこともあります。
トップが本気で変わろうとする姿勢、そしてそれを社外にまでコミットメントする覚悟が、社内外の信頼を得ることにつながったのだと思います。
トップが自ら「広告塔」となり、変革の顔となることが極めて重要なのですね。
その通りです。CEOがビジョンを示し、CHROの私はそれを具体的な「仕掛け」に落とし込んでいく。例えば、社員の行動指針となる「Value(バリュー)」を定め、それを評価制度(MBO)に組み込む。あるいは、マネジャー向けのトレーニングを設計して展開する。
CEOのビジョンとCHROの人事戦略が両輪となって、初めて組織全体を動かす大きな力が生まれます。この二人三脚がなければ、変革は絶対に成功しませんでした。
とにかく現場に行くことで見えてくる従業員の生の声
今井さんは、具体的にどのようにして現場の変革を進めてこられたのでしょうか。

統合当初は、正直どこから手をつけていいか分からない状態でした。髙橋と最初に決めたのは、「とにかく現場に行く」ということです。年間80回以上、二人で全国の拠点を回り、経営が直接現場の社員と対話をするタウンホールミーティングやラウンドテーブルを重ねました。これは今でも続けています。
現場に行くと、社員一人ひとりが何を感じ、何を考えているのかを、生の声として聞くことができます。これを繰り返しながら、次の一手を考える。まさに「走りながら考える」スタイルです。その中で、いくつかの重要なアクションを並行して進めていきました。
一つ目は、象徴となる「クイックウィン」です。変革の狼煙(のろし)を上げる、分かりやすい「見せ物」ですね。例えば、社長就任初年度の年頭挨拶から、髙橋がジーンズで登壇し、カジュアルな服装を全面的に解禁しました。
当初は「服装を変えたくらいで何が変わるのか」と冷ややかな目で見られていたと思います。しかし、こうした象徴的なアクションを続けることで、私たちの本気度を伝えていきました。若手社員が経営陣に直接悩みをぶつける「モヤモヤ会議」なども、その一環です。
二つ目は、徹底した現場との対話です。特に力を入れたのは、対面でのコミュニケーション。人の思いや熱意は、画面越しではなかなか伝わりません。直接対話を重ねることで、髙橋の人間味や事業への熱意が伝わり、社員が徐々に心を開いてくれるようになりました。これを3年、4年と粘り強く続けたことで、現場から「また来てくれたんですね」と歓迎される雰囲気が生まれていきました。
そして三つ目は、マネジャー育成です。変革を推進するうえでは、これが最も重要です。私たちが「心理的安全性の高い文化を作ろう」と叫んでも、現場で実際にその空気を作るのはマネジャーです。彼らが変わらなければ、現場は何も変わりません。変革という言葉だけが先行しているようでは、「結局何も変わらないではないか」と社員がしらけてしまうでしょう。
そのため、変革の初期段階から、マネジャー向けのトレーニングを徹底的に実施しました。ピープルマネジメントで何が重要か、例えば1on1ミーティングの進め方やファシリテーションのスキルなどを、具体的な「武器」として彼らに授けたのです。
「トップからのビジョン発信」と「ボトムから変えるためのマネジャー育成」という二つの仕掛けをセットで、しかも同時に回し続けたことが、私たちの変革の要だと考えています。
変革に着手してから4年が経過し、現場ではどのような変化が起きていますか。
目に見える変化が数多く生まれています。以前は開発部門と製造部門の間に壁がありましたが、今では開発の初期段階から製造が主体的に参加する事例が増えてきました。会社のValueの一つである「枠を超えるオープンマインド」が浸透しつつあると感じています。
また、以前は経営陣にものを言う雰囲気などなかった拠点で、社員が自発的に「モヤモヤ会議」を企画したり、働きやすい職場環境を自分たちで整えようと改善策を提案したりするようになりました。こうした自律的な動きが全国の拠点で加速していることを、毎年現場を訪れるたびに肌で感じられるのが何よりの喜びです。
人事は「方程式のない」クリエイティブな仕事。次世代がポテンシャルを解き放つために
5年後、10年後を見据え、レゾナックをどのような組織にしていきたいと考えていますか。
私が目指すのは、会社を「社員一人ひとりが自己実現や成長を通じて幸せを感じるためのコミュニティ」にすることです。人は誰かとつながり、共に何かを成し遂げることに喜びを感じる生き物。社員一人ひとりが自身の強みを認識し、どう成長していきたいかという意志を持つ「自律した個」であることが重要です。
そうした強い「個」が、社内外の仲間と自由につながり、「共創」を通じて社会のためにより良い価値を生み出していく。プロジェクト型の働き方が当たり前になる組織を作りたいと考えています。ヒエラルキーではなく、イノベーションを起こすための柔軟なチームが随所で生まれる。そんな世界観です。
これは、私が若い頃にシリコンバレーで見て衝撃を受けた光景そのものであり、幼い頃から日本の社会に感じてきた「空気の重さ」のようなものから人々を解放したいという思いにもつながっています。一人ひとりのポテンシャルを、最大限に解き放ちたいのです。
最後に、次世代の人事パーソンに向けて、メッセージをいただけますでしょうか。
人事の仕事は、会社を根底から変える力を持つ、本当に素晴らしい仕事です。会社は「人」で成り立っていて、会社の意思決定は「人」が行います。AIが進化しても、この本質は変わりません。人事とは、その最も重要な「人」に影響を及ぼし、組織の基盤を作る仕事です。
また、人事の仕事の面白さは「決まった方程式がない」ことです。例えば「自律的な人材を育成する」という目標があったとしても、そこに至る道のりは、会社の事業内容や成長フェーズによって異なります。だからこそ人事パーソンには、自社の現状を分析し最適な打ち手を考える「センス」と「クリエイティビティ」が問われます。
人事の仕事は簡単ではありませんが、それゆえに面白く、自らの手で新たな価値を創造していく大きなやりがいがあります。そのダイナミズムを楽しみながら、会社をより良く変えていく仕事に誇りを持って取り組んでほしいですね。

(取材日:7月25日)
この記事を読んだ人におすすめ

各企業の人事リーダーが自身のキャリアを振り返り、人事の仕事への向き合い方や大切にしている姿勢・価値観を語るインタビュー記事です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった1
- 共感できる1
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント