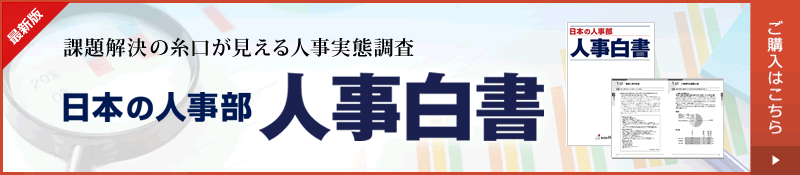テレワーク導入時、67.5%の企業が「社内コミュニケーションやマネジメントへの支障」を懸念していたが、実際に「大きな問題になった」のは1.0%
最も多くの企業で大きな問題になったのは、「ネットワーク環境の不備」(3.9%)
働き方改革の一環として、テレワークやリモートワークを導入している企業は多い。「全社員を対象に導入している」(9.0%)、「一部社員(職種・職位を限定)を対象に導入している」(13.8%)、「一部社員(育児・介護など両立を必要とする社員などに限定)を対象に導入している」(11.7%)の三つを合わせると、34.5%の企業が何らかのかたちで既に導入しているという回答だった。また、「現在は導入していないが今後導入を予定している」(22.3%)を加算すると55.8%で、過半数となる。
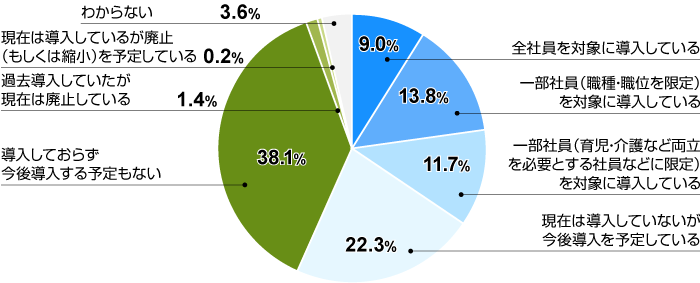
では、テレワーク・リモートワークの導入にあたって、人事担当者はどのような懸念をどの程度、感じていたのだろうか。下記の項目ごとに聞いた。
(1)顧客への対応への支障
(2)社内コミュニケーションやマネジメントへの支障
(3)労働時間管理の業務負担
(4)業務と私生活の区別をつけられず、業務過多になってしまう社員が出ること
(5)制度を導入しても活用されないこと
(6)時間に対してルーズさが許されるものと勘違いする社員が出てしまうこと
(7)テレワーク・在宅勤務の対象ではない部門の社員から不満の声が上がること
(8)ネットワーク環境の不備
「強く懸念していた」と「やや懸念していた」を足した割合が多かったのは、「社内コミュニケーションやマネジメントへの支障」(67.5%)、「時間に対してルーズさが許されるものと勘違いする社員が出てしまうこと」(59.1%)、「労働時間管理の業務負担」(55.7%)、「ネットワーク環境の不備」(52. 7%)、「業務と私生活の区別をつけられず、業務過多になってしまう社員が出ること」(50.2%)だった。
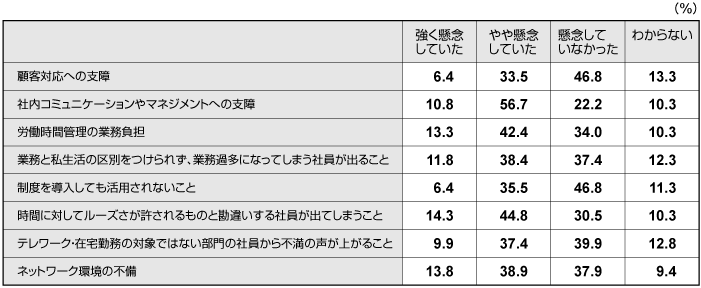
それに対して、実際にテレワーク・リモートワークを導入した企業では、どのような問題が起こったのかを聞いた。結果を見ると、各項目とも「大きな問題になった」と答えた割合は非常に少なく、最も多かった「ネットワーク環境の不備」(3.9%)、続く「時間に対してルーズさが許されるものと勘違いする社員が「ネットワーク環境の不備」(3.9%)、続く「時間に対してルーズさが許されるものと勘違いする社員が出てしまうこと」(2.5%)のほかは、いずれも1~2%程度となった。
「やや問題になった」を合わせた割合を見ると、「ネットワーク環境の不備」(25.6%)、「テレワーク・在宅勤務の対象ではない部門の社員から不満の声が上がること」(25.1%)、「社内コミュニケーションやマネジメントへの支障」(20.2%)が上位だった。
逆に、「問題にならなかった」割合が多かったのは「顧客対応への支障」(81.8%)、「労働時間管理の業務負担」(72.9%)だった。懸念を払拭するために工夫した結果、問題なく導入が進んだという企業は多いようだ。
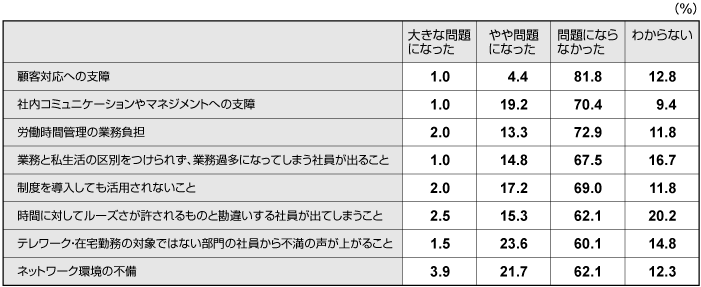
| 実施時期 | 2018年4月2日~4月23日 |
|---|---|
| 調査対象 | 『日本の人事部』正会員 |
| 調査方法 | Webサイト『日本の人事部』にて回答受付 |
| 回答数 | 4,630社、4,907人(のべ) |
| 質問数 | 184問 |
| 質問項目 | 1.戦略人事/2.採用/3.育成/4.制度・評価・賃金/5.ダイバーシティ/6.働き方/7.HRテクノロジー/8.新しい人事課題 |
出典:『日本の人事部 人事白書2018』
この記事を読んだ人におすすめ

全国の人事の実態・課題を明らかにし、解決の糸口を探る『日本の人事部 人事白書』から、調査レポートを公開。貴社の課題解決にご活用ください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント