人事マネジメント「解体新書」 第二回
いま求められる「ダイバーシティ・マネジメント」
ダイバーシティ・マネジメントの「歴史」
◆ダイバーシティ先進国・アメリカでの取り組み
ダイバーシティの「実践」については、アメリカが早い時期から取り組んでいる。それは、アメリカが人種のるつぼと呼ばれるように、さまざまな人種や民族が集まった国だから。そのような事情があって、多様な個人をどう活かせば強い組織ができるのか、国も企業もその研究を盛んに行ったというわけである。少し、その「歴史」をひも解いていこう。
(1)1960・70年代~公民権運動から訴訟問題へ
ダイバーシティ・マネジメントの「出発点」となったのは、1960年代の「公民権運動」に遡る。「公民権法」や「雇用機会均等法」が整備されると、企業は法律の遵守や訴訟回避のために、有色人種や女性の採用、登用を始めた。
1970年代になると、幾つかの大手企業が黒人女性などのマイノリティによって、差別を受けたことを理由に訴えられ、敗訴するケースが出てきた。このときの賠償金は数億ドルに上ったとされており、以降、ダイバーシティ・マネジメントは、企業の重要な「リスクマネジメント」のテーマとして考えられるようになった。
(2)1980・90年代前半~CSR、グローバル化の一環として
その後、ダイバーシティ・マネジメントをCSR(企業の社会的責任)としてとらえる流れが起こった。仮に不祥事などの事件が起きた場合でも、積極的なCSR活動によってダイバーシティを推進しているというイメージが確立している企業では、業績の回復が早くなっていったという。
さらに、冷戦崩壊後のアメリカ企業におけるグローバル展開が、ダイバーシティ・マネジメントに輪をかけた。考えてみてほしい。グローバル市場で画一的な製品しか提供できない企業では、世界の多様なニーズに対応することができないだろう。進出先の国の市場や特性、人々の嗜好や生活スタイルに合わせた商品やサービスを展開していかなければ、もはや受け入れられない時代となってきたのである。
(3)1990年代後半・現在~「違い」を活かすことが競争優位に
そして、1990年代後半からは、多様な人材を積極的に登用することで、事業の成功に結びついていくケースが多数みられるようになってきた。実際、アメリカで女性管理職の比率が飛躍的に伸びたのもこの時期である。
そして現在では、人々の違いに価値を見出すだけでなく、違いを積極的に活かすことが競争優位となる前提で、戦略を進める企業が多数派になってきた。ダイバーシティを推進することが会社の事業運営上の利益につながるという意識が、確実に広まってきたのである。もちろん、この間に払った代償は決して少なくない。しかし、多様性を組織に取り組むことで新たな価値をつくり出していこうという段階へ、既に多くのアメリカ企業が到達している事実を、日本企業はもっと意識していいのではないか。
◆ダイバーシティに対する企業行動のステップ
ところで、ダイバーシティ問題に詳しい谷口真美・早稲田大学大学院商学研究科助教授によると、1960年代以降のアメリカ企業の例にみられるようなダイバーシティにおける企業の「発展段階」を、以下のような4つのステップに分類している。
抵抗(Resistance)~違いを拒否する
ステップ2:
同化(雇用機会均等/Equal Opportunities)~違いを同化させる、違いを無視する、防衛的
ステップ3:
分離(Value Difference/違いに価値を置く)~違いを認める、適応的
ステップ4:
統合(Diversity Management/ダイバーシティ・マネジメント)~違いを活かす、競争優位につなげる、戦略的
一目して理解できるように、谷口氏は非常に明快な分類を行っている。ただ、このステップをみるにつけ、改めて日本企業がダイバーシティ後進国であることを実感せざるを得ない。おそらく、多くの日本企業はまだステップ1~2あたりにいるのではないだろうか。実際問題、女性活用という点からみても、非常に立ち遅れている現実がある。その点で、最近発表された労働政策研究所・研修機構の「仕事と家庭の両立支援にかかわる調査」をみると、日本企業(日本人)の遅れている実態がよく分かると同時に、ダイバーシティ推進に向けたヒントも示されているように感じる。
◆「両立支援」からみたダイバーシティの状況
最初に、「両立支援制度」に取り組む理由を企業に尋ねたところ、「法で定められているから」が85.5%と最も多く、次いで、「企業の社会的責任を果たす」72.8%、「女性従業員の定着率を高める」63.3%、「女性従業員の勤労意欲を高める」59.6%、「採用で優秀な人材を集める」45.0%となっていた。
そして、取り組み理由ごとに得られた効果の評価をみると、「効果あり」(「大いにあった」と「ある程度あった」の合計)とするのは、「女性従業員の勤労意欲を高める」が91.7%と最も高くなっている。以下、「女性従業員の定着率を高める」90.6%、「女性従業員の帰属意識を高める」88.2%、「従業員の仕事に対する満足度を高める」88.0%、「企業の社会的責任を果たす」87.1%などが上位を占めている。このうち、効果が「大いにあった」に限ってみると、「女性従業員の定着率を高める」が33.5%でトップとなっている。企業が従業員の仕事と家庭の両立を支えることは、人事・採用戦略の面でも重要度を増していることがよく分かる結果である。
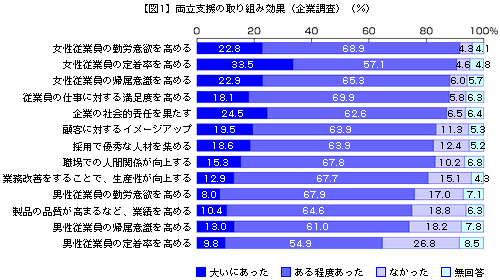
ただ、そういう認識にありながらも、実態はかなり“お寒い状況”である。例えば、両立支援策の一つである「短時間勤務制度」が導入されているにも関わらず、管理職の28.2%が、同制度は「ない」と思っており、「わからない」も9.3%あった。一方、一般社員も、22.9%が「ない」と思っており、「わからない」が20.1%。制度認識の欠如(「ない」と「わからない」の合計)ということでみれば、管理職が37.5%、一般社員が43.0%となっており、何と約4割の社員が自社の制度導入について知らなかったことになる。
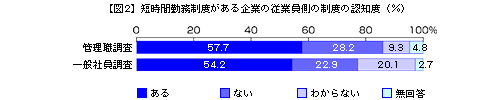
「育児休業制度」でも同じようなことが言える。過去3年間で配偶者が出産した者がいると回答した企業のうち、男性の育児休業取得者数は「0人」が78.0%と大半を占めており、次いで「1~2人」が10.6%と続く程度だ。制度はあれども、ほとんど男性の利用が進んでいない実態がみて取れる。
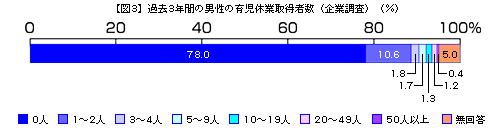
また、男性の部下が育児休業を申し出た場合の管理職の反応についてみると、「解決すべき課題はあるが、と言いながら賛成する」(消極的賛成)が最も多く52.7%、次いで、「積極的に取得に賛成する」(積極的賛成)が21.6%となっている。両者を合わせると7割以上の管理職は取得に賛成しているものの、その多くは“消極派”なのだ。実際、「職場の状況を踏まえ、申し出を慰留する」17.0%、「当人のキャリアを考えて反対する」2.0%、「男性が育児休業を取るなど考えたことがない(したがって、反対)」5.0%という管理職も少なくない。
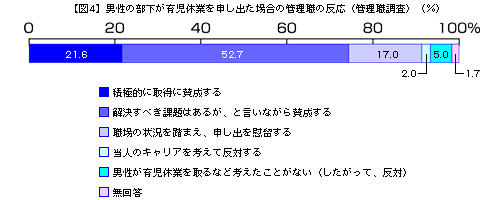
このように、「両立支援」という視点からみても、まだまだ旧来の男性正社員を中心とした画一的な考え方をぬぐえていないことがよく分かる。意識に対して行動が伴っていないということだろうか。ダイバーシティへの認識は感じつつも、その実現への道はけっこう長い…。
この記事を読んだ人におすすめ
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント












