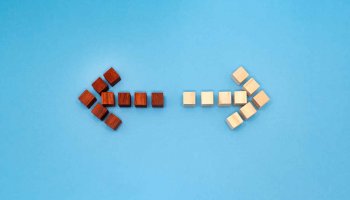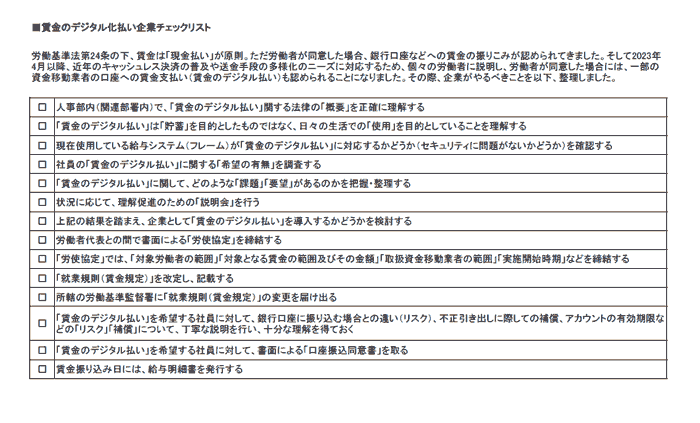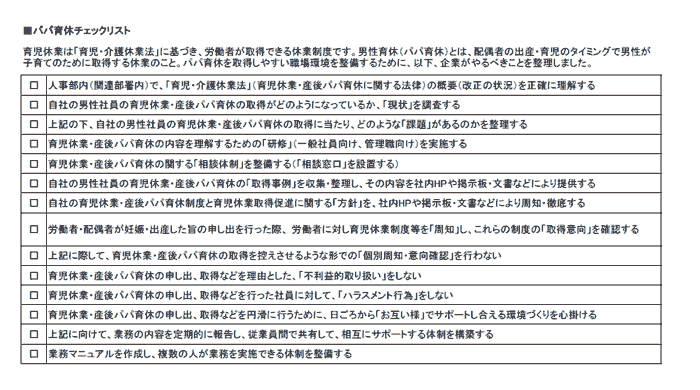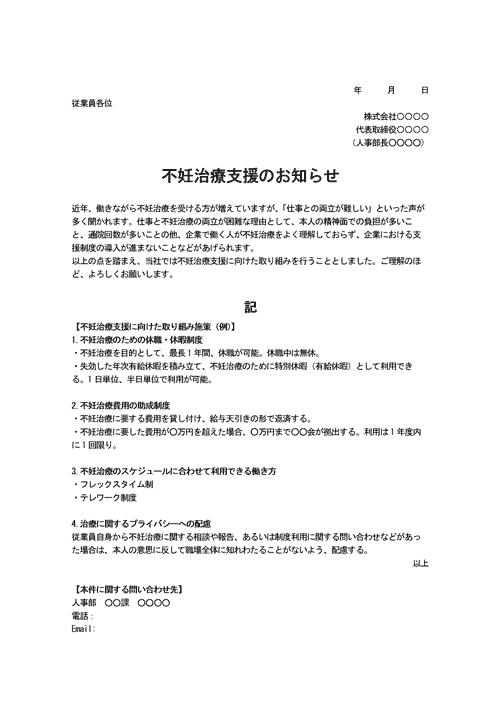バイアス
バイアスとは?
バイアスとは、偏見や先入観を意味する言葉です。無意識に持っているものや、経験に基づいた思い込みなど、さまざまな種類があります。働きやすい職場づくりを行うためには、バイアスについての知識を深め、ネガティブなバイアスを排除することが重要です。
1.バイアスとは

バイアスとは、「偏向」「先入観」「データなどの偏り」を意味する言葉です。心理学と統計の分野で、それぞれ意味合いが異なります。
◎心理学の分野
偏った見方のこと。たとえば、「あの人の意見にはいつもバイアスがかかっている」というように使われる。
◎統計学の分野
母集団の要素が平等に選ばれていないこと。「この統計にはサンプリングバイアスがある」と言った場合、不適切な抽出によって母集団を代表しない性質のデータが紛れ込んでいることを意味する。
2.バイアスの種類
アンコンシャス・バイアス
アンコンシャス・バイアスとは、人が無意識のうちに持っている偏見の総称です。次のようなアンコンシャス・バイアスは、組織の生産性を下げるため、解消しなければなりません。本人が気づいていないゆがんだ認知を是正し、発生しない仕組みを作ることが重要です。
- 「この仕事は女性には難しいだろう」→女性社員がプロジェクトのメンバー選定段階から外される
- 「中堅社員なら、これぐらいの仕事はできてあたりまえだ」→十分な研修がなく、社員に重い負荷を負わせる
確証バイアス
確証バイアスとは、自己の思考や願望にとって都合の良い情報ばかりを集め、逆に考えを否定するような情報を軽視することをいいます。多様な情報があっても、最初の思い込みを支持する情報ばかりが目に付いてしまいます。
たとえば、「一定ランク以上の大学の出身で、体育会系部活動を経験してきた人が活躍する」という先入観を持っていた場合、その通りの学生が入社して活躍すれば、自分が正しいと確信を強めてしまうのです。
ハロー効果
ハロー効果とは、ある一部の現象から受けた印象が対象全体に影響を及ぼし、正当な評価ができなくなる現象のことです。面接や評価面談などで、考課者が無意識のうちに陥りやすいバイアスの一つです。
ハロー効果には「ポジティブ・ハロー効果」と「ネガティブ・ハロー効果」の二つがあります。「ポジティブ・ハロー効果」は、対象を評価する際に、ある特定の項目の評価が高いと感じた場合、別の項目も高くしてしまう現象です。一方「ネガティブ・ハロー効果」は、ある項目が低いと感じた場合に、別の評価も低くしてしまうという現象を指します。
- 【参考】
- 「ハロー効果」とは|『日本の人事部』
アンカリング効果
「アンカリング効果」とは、最初に与えられた数字や条件が基準となり、その後の意思決定に影響を及ぼすことをいいます。
たとえば、買い物で「定価から〇割引」という情報が掲示された場合、人々は「お得」という印象を抱きます。さらに「セールは当日限り」という条件が加われば、「早く買わなければ」という気分にさせられます。アンカリング効果は、マーケティングなどさまざまな面で、人の行動に影響を与えます。
ただし、露骨なアンカリング効果の活用は、企業に不誠実な印象を植え付けてしまう可能性があるため注意が必要です。
後知恵バイアス
「後知恵バイアス」とは、物事が発生した後になって、まるでそのことが予測可能だったかのように考える心理的傾向のことをいいます。職場でなにかトラブルがあった際に、「きっとうまくいかないと思っていた」などと発言することは、後知恵バイアスの一例です。相手に無責任な印象を与える、反論の余地をなくす、といった問題につながります。
正常性バイアス
正常性バイアスとは、異常な事態に直面しても、都合の悪い情報を無視して「大丈夫だろう」と判断してしまう傾向のことをいいます。もともとは災害心理学で用いられてきた用語です。
職場における「うちの職場は不祥事とは無縁」「あの人に限って、パワハラなんてするはずはない」という考え方は、正常性バイアスによるものといえます。バイアスによる過小評価を自覚し、事前に十分な対策をすることが大切です。
3.バイアスがもたらすデメリット
バイアスは程度の違いはあれ、誰もが持っているものです。バイアスを放置していると、職場でさまざまな悪影響が生じる可能性があります。
採用や人事評価においてブレが生じる
採用や人事評価では、バイアスが生じると公平性の妨げとなります。面接官や考課者のバイアスにより、偏った評価が下されると、長期的にみて組織運営に影響が生じる可能性が高くなります。
社員のモチベーションが低下する
バイアスは、従業員が活躍する場を制限する恐れもあります。バイアスによって、プロジェクトから外されたり、正当に評価されなかったりすると、従業員に不満が生じ、モチベーションが低下する可能性があります。
ハラスメントのきっかけとなる
「女性社員は〇〇だ」「外国人だから〇〇だ」という根拠のない発言の裏には、バイアスが潜んでいるかもしれません。セクハラなど、理不尽な差別のきっかけとなる可能性があります。
4.バイアスへの対処方法

バイアスに対処するには、バイアスに関する理解を深め、自身の考えを客観的に振り返る機会を持つことが大切です。
バイアスについての理解を深める
バイアスによる問題は「誰にでも起こりうるもの」という認識を持つことが、バイアスに対処する第一歩となります。バイアスの種類を知り、どのような場合にバイアスが発生しやすいのかを学ぶことが大切です。自身のバイアスに気付くきっかけとなります。
反対の情報を収集する
求めている情報だけではなく、反対意見や逆の情報を収集します。意識することで、確証バイアスや後知恵バイアスに陥るのを防止できます。
第三者の意見を取り入れる
専門家や第三者の意見を取り入れることは、バイアスを取り除くのに役立ちます。自分とは異なる意見を得ることで、自分の思考の偏りに気付けます。ただし、日頃から接する機会の多い人(チームメンバー)や、職場での上下関係がある場合(部下)などからは、適切な意見が得られない可能性もあります。
客観性のある基準を参考にする
客観性の高い情報をもとに判断することは、バイアスを取り除く上で重要です。たとえば、勤務態度を評価する際の項目の一つとして、遅刻や欠席の回数などの数値を設ければ、評価者が違っても、一定の基準に基づいた評価を下すことができます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント