「社内政治」で昇進も離職も決まる?
人事パーソンに必要な「利害調整」スキルとは
法政大学 キャリアデザイン学部 教授
木村 琢磨さん
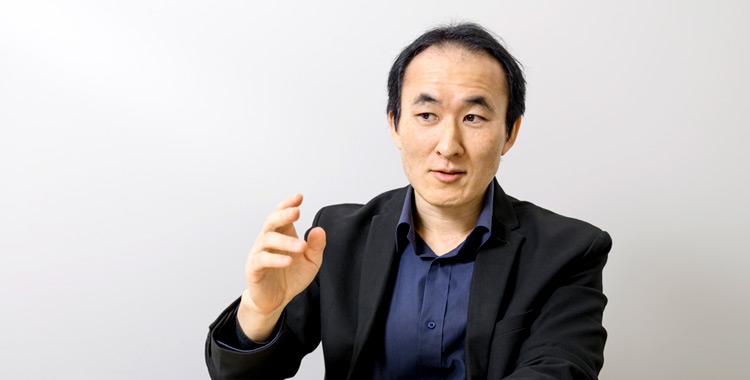
ドラマや映画でおなじみの、派閥争い、重役同士の駆け引き、陰口での評価操作、不正行為――。「社内政治」と聞くと、ネガティブで複雑な人間関係を連想する人も多いでしょう。しかし、それが全てではありません。学術的な意味では、社内政治とは「自己や組織の目的達成のために、正式に承認されていない影響手段を用いる行為」を指します。企業において、この見えにくい影響手段を正しく理解し、適切に向き合うことは、人事部門にとって重要なテーマです。では、人事パーソンは、組織の健全な成長を促すために、社内政治とどう向き合い、どのようなスキルを磨けばいいのでしょうか。日本では数少ない「社内政治」の研究者、法政大学キャリアデザイン学部教授の木村琢磨さんにうかがいました。
- 木村 琢磨さん
- 法政大学キャリアデザイン学部教授、昭和女子大学データサイエンス副専攻特命教授
きむら・たくま/法政大学キャリアデザイン学部教授、昭和女子大学データサイエンス副専攻特命教授。博士(経済学 東京大学)。スタートアップ企業等での勤務を経て現職。経営学分野を中心に国際的学術誌で多数の論文を発表。2015年にInternational Journal of Management Reviewsに掲載された論文(A Review of Political Skill)は2014~2023年の社内政治研究における世界トップ10論文に選出されている(Scivalによる集計)。専門は組織行動論、組織アナリティクス。
根回しとバックステージネゴシエーションの違い
木村さんは「社内政治」をどのように定義していますか。
「社内政治」は研究者によってつくられた言葉ではなく、一般の方々の間で使われはじめた言葉なので、使う人によって定義が異なります。私は「自己または組織の利益の増大または損失の抑止を目的とした意思決定への影響、権力・資源の獲得、利害調整のために、組織から正式に承認されていない影響手段を使用すること」と定義しています。
自己の利益とは、昇進や昇給、評判など処遇やキャリアに関する個人的な便益を意味します。一方、組織の利益とは業績や好業績につながる社会的評判などを指します。利己的な目的のみならず、組織を良い方向に導くためにやらざるを得ない社内政治もあるということです。社内政治は、職務文書や手順書などで公式に規定された行動ではないという点も特徴です。ただし、非公式だからといって組織の規範に反しているとは限りません。
木村さんは日本企業の「社内政治」の研究成果として、「日本の従業員の戦略的ネットワーキング行動の少なさ」を挙げています。
ここでいう「ネットワーキング」は「人脈づくり」です。海外の企業では、社内の誰がキーパーソンなのか、その人と組んだら何ができるようになるかを戦略的に考えたネットワーキングが社内政治行動の一つの特徴です。
一方、日本の大企業では新卒一括採用がベースにあるため、新卒同期入社組の社員が多く存在します。この同期のネットワークが非常に強く、社内で何か困ったときに同期に頼んだり、同期を経由してその先輩や上司に依頼したりするケースが一般的です。
ビジネスパーソンにインタビューをすると「特に親しいわけではないが、同期に頼まれたので自分の仕事ではないけど協力した」という話をよく聞きます。同期同士は協力し合うことが暗黙のルールのようになっているほど、日本では同期が絆(きずな)として重視されています。そのため、戦略的なネットワーキングなしに社内での人脈が形成されます。
海外でも同期入社というくくりはありますが、日本ほど絆は強くありません。海外では本社一括ではなく事業所ごと、部門ごとの採用が多く、それぞれが別の場所で働き、教育研修の場も異なります。そのため、同期入社というだけで広範なつながりがあるわけではないのです。
ただし、日本でも中途で入社した人は戦略的ネットワーキングが必要となるでしょう。社内で誰が力をもっているのか、信頼を得ているのかを考えて関係を構築する必要があります。
社内政治について、日本企業が海外企業と異なる点は他にありますか。
海外にはまったく同じ意味を持つ単語が存在しないこともあり、日本語のまま使われているのが「根回し」です。「NEMAWASHI」としてアメリカのビジネス書にも記載されています。正式な会議で何かを提案するときに、その内容を事前に関係者に伝えておくことですね。
ここで注意すべきは、「根回し」と同じ意味の英単語はないものの、根回し的な行動は海外でも往々にして必要だということです。根回しに似た英語として「バックステージネゴシエーション」があります。これは文字通り「舞台裏の交渉」を意味していて、自分がこれから会議で提案することによって不利益を被ったり、反対したりする可能性のある人にあらかじめ相談し、お互いの利害を確認・調整することです。その結果、そのまま会議に持ち込むこともあれば、交渉内容を踏まえて提案内容を見直すケースもあります。
根回しとバックステージネゴシエーションの違いは、提案内容についてしっかりと相手の意向を聞くかどうかです。企業によって異なりますが、日本の場合は根回しの場で交渉や意見交換をせず、ただ伝えるだけというケースも多いですね。一方、バックステージネゴシエーションは利害調整のための「交渉」が中心です。
この違いはあまり認識されていないため、すれ違いが起きることもあります。例えばアメリカ人が日本で管理職になった場合、部下が相談にやってくると「バックステージネゴシエーションに来たな」と思います。しかし、実際は部下が説明やあいさつ程度の話だけで帰ってしまうので、日本の根回しが奇妙なものに見えるようです。逆に、日本人が海外企業で働いたときに、根回しが必要ないと思い込んで事前の利害調整をしなかった結果、提案が失敗するのみならず、信頼を失うこともあります。
それぞれの違いを把握していないことで、すれ違いが起きるんですね。
日本はハイコンテクスト文化と言われるように、言葉に出さずにお互いの意思を推し量ろうとする傾向があります。「忖度(そんたく)」がその代表です。しかし、ハイコンテクスト文化は、阿吽(あうん)の呼吸に依存することを意味しているのであって、阿吽の呼吸で意思疎通ができるということではありません。よって日本でも、言葉に出さないがゆえに誤解や非効率なやりとりにつながることが少なくありません。
例えば、会議の場で部長が新たな方針を伝えて出て行ったあと、その場に残った部下たちが「部長のあの発言にはどういった意図があったのだろう」と話し合う場面があります。しかし、わからないことがあったら部長に聞けばよいのです。このようなやり取りは無駄であることが多いです。
日本と海外のコミュニケーションの違いが、企業内のコミュニケーションにも表れているのでしょうか。
そうですね。ほかには「建前」という日本語もそのまま海外で使われています。日本人の建前は、否定的な表現や反対を避けて遠まわしに言うことで、ネガティブな雰囲気を避けることです。例えば、ある商品を絶対買わないと決めているのに「検討します」と言うのもそうですね。
一方、アメリカでは建前に近いものとして「リップサービス」があります。リップサービスはその場の雰囲気を盛り上げて仕事を進めやすくしたり、自分への評価を上げたりするためのものです。そこが、建前のせいで結論が不明確または先延ばしになってしまう日本との大きな違いです。
| 項目 | 日本企業 | 海外企業 |
|---|---|---|
| ネットワーキング | 同期との強い絆がベース | キーパーソンと戦略的に関係構築 |
| 根回し | 事前に伝えるだけの場合が多い | 事前に相手の意向を聞き、やりとりして調整する |
| 同期のつながり | 強い | 弱い |
| コミュニケーション文化 | ハイコンテクスト、忖度重視 | ローコンテクスト、明確な意思表明 |
キャリアスポンサーを得ることがキャリアに大きく影響
日本企業において「社内政治」は人事にどのような影響を与えていますか。
社内政治はキャリア全般に大きく影響します。日本ではキャリア研究への関心が非常に高いのですが、キャリアの議論に社内政治の話がほとんど出てきません。一方、海外には社内政治とキャリアを関連づけた研究がたくさんあります。
社内政治によって、意思決定に影響を与えうる権力や、仕事の機会やサポートなどの資源をどれだけ得られたかが、仕事上の成功を大きく左右します。昇進は能力や業績だけでは決まりませんし、そもそも能力や業績は社内の人たちに気づいてもらえないこともあります。そのため、会社では自分を後押ししてくれる「キャリアスポンサー」がいることが重要です。
キャリアスポンサーとは後ろ盾のことです。社内にキャリアスポンサーがいると、引き上げてくれたり、仕事の機会を与えてくれたり、キーパーソンを紹介してくれたりします。自分の上司がキャリアスポンサーになってくれれば幸運です。ただし、キャリアスポンサーには二つの条件があります。会社の資源を動かせるだけの影響力があることと、自分に好感をもってくれていることです。
ビジネスパーソンが特定の会社に長く勤めようと思ったら、大切なのは社内での「強い紐帯(ちゅうたい)」です。これは、頻繁な関わりや強い感情的絆、信頼を特徴としたつながりです。日本では「弱い紐帯を持つのが良い」とよく言われますが、弱い紐帯にもメリットはありますが万能ではありません。キャリアスポンサーとの紐帯は強くなければなりません。権力者との紐帯が弱いと、都合の良いときにだけ利用されるだけの人になってしまうおそれがあります。
キャリアスポンサーは従業員が自分で見つけることもできるのでしょうか。
それを可能にするのが戦略的ネットワーキングです。日本の大企業であれば、同期のつながりや上司、元上司の人脈を利用してキーパーソンとつながるという手があります。ただ、実際にそこまでやれる人は少なく、やったとしてもうまくいくとは限りません。入社時に上司が誰であったかなど、運に左右される部分が大きいことも確かです。
海外でも、誰もがうまく立ち回れるわけではなく、配属でキャリアが決まってしまうことが結構あります。例えば、実績を上げて海外赴任を任された人よりも、ずっと本社にいた人のほうが組織の中枢の人たちと関係が近くなり、キャリア上優遇されるといったケースです。
最近は人事のデータベース化が進み、社内の人材情報が以前より視覚化されています。しかし、実際に誰かに仕事を任せる場面でデータのみで決めるケースは少ないでしょう。自分が目をかけている人にやらせてみようという意思が働くのが自然です。
論文では「人事評価では、成果やスキルをアピールするより、ゴマすりが効果的だった」という記載も目にしました。
日本に限らず欧米でも、自己PRが目立つ部下は上司からあまり良く思われないようです。それよりも、自分をほめてくれる部下のほうがかわいいということですね。人事評価の点数は、部下に対する好感度と相関していました。同じくらいの成果であれば、自分のお気に入りの部下のほうが優れて見えるものです。
また、「海外では仕事の場以外では職場の人と付き合わない」と言われることがありますが、そんなことはありません。上司が自分の気に入っている人だけをお昼休みのランチや週末のパーティーに誘いその場で仕事上の重要な情報を与えることもあります。
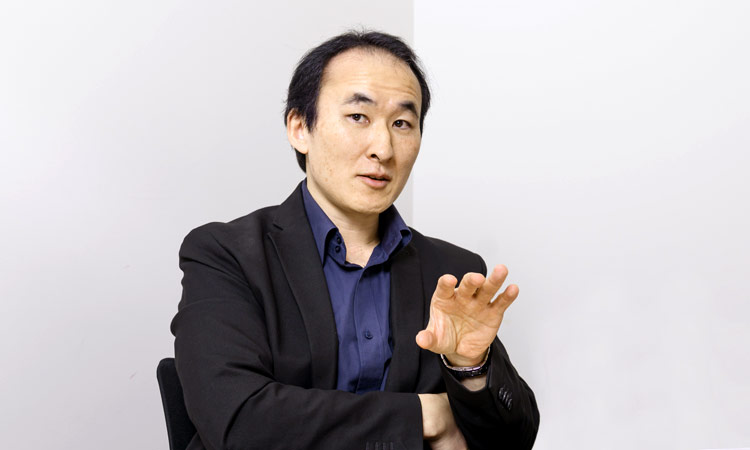
水面下で行われているケースもあるのですね。「離職」に関しても社内政治は影響しているでしょうか。
キャリアスポンサーが得られず、どんなに成果を上げても評価されない、目にとめてもらえない、という人はいます。そういった人は離職して、別の会社でキャリアを積み上げていくという選択をする傾向があります。
ハイパフォーマーが2割、中くらいが6割、ローパフォーマーが2割という「2-6-2の法則」がよく語られます。しかし、その差は能力だけとは限りません。ローパフォーマーにあたる2割の人は社内での政治的なつながりを得られず、活躍の機会がなかっただけかもしれません。ローパフォーマーの2割の人だけで独立して会社をつくったら好業績企業になる可能性もあります。
他者の利害を理解し、他者に影響を及ぼす
社内政治はどの会社にも存在すると思います。企業にとって「社内政治」が正の側面を持つために、人事部門はどうあるべきでしょうか。
社内の部署や個人の利害は異なるので、対立が起きるのは当たり前です。その前提に立ち、争いによって組織を崩壊させないようマネジメントするのが人事部門のやるべきことです。
利害対立を調整する上で重要なことを教えてください。
人事部門は意思決定や資源配分などにおいて「公正」と「正当性」を確保することが重要です。
公正には三つの軸があります。一つ目は「分配的公正」です。これは報酬や資源の分配結果が納得できるものであることです。二つ目は「手続き的公正」です。これは分配に関する意思決定の透明性や一貫性などプロセスに関する公正です。三つ目は「相互作用的公正」です。これはコミュニケーションにおける誠実さのことで、意思決定に関する説明や、対話における尊重を意味します。
もう一つの「正当性」は、行動や意思決定が社内の人々に受け入れられるために必要なことです。正当性には三つの側面があります。一つ目は「実利」で、会社や利害関係者にとって実益があるかどうかです。二つ目は「道徳」で、法律や社会的規範、倫理に反していないことです。三つ目が「認知」で、組織の中での常識として当然のものとされていることです。
このような公正と正当性に着目した上で、人事制度を策定したり、何か衝突が起きたときに提案したりすることが人事部門の役割です。そして、そのために必要なのが「政治スキル」です。
「政治スキル」とは、どのようなものでしょうか。
政治スキルの要素は二つあります。一つは、他者の利害を理解する能力です。個人が何をされたら喜び、何を失いたくないのか、どんな希望をもっているのかを理解することです。もう一つは、その理解をベースに自身や組織の目標達成に役立つよう、他者の行動に影響を及ぼすことです。また、政治に必要な能力としては政治スキルのほかに「政治的知識」と「政治的権力」があります。
政治的知識とは、社内の権力構造や人間関係に関する知識です。政治的権力は意思決定に影響を与える力のことです。政治的権力は役職が高いほど強くなりますが、役職が低くても強大な権力を持つ人もいます。例えば、専門性が高い人、後ろ盾がいる人、過去の功労者などです。単に声が大きくて怖い人が権力を持っていることもあります。
これらの政治的知識や権力はその会社における自分や他者の状況に固有のものであり、組織が変わると通用しなくなるものです。一方、政治スキルはいわゆるポータブルスキルであり、組織が変わっても発揮できるという違いがあります。
社内政治に役立つ知識として、組織の文脈を理解しておくことも大切です。人事として理解しておきたい知識には、「関係知識」「規範知識」「戦略知識」があります。
関係知識は、社内の人間関係や利害に関することです。人事部門は、人材の情報が入ってくる部署ですが、待ちの姿勢のみならず、能動的な情報収集も重要です。また、定量的なデータのみならず、そこに落とし込むのが難しいアナログな知識も必要です。
規範知識とは、この会社ではどのような情報が重視され、好まれるのかという知識です。たとえば人事のベンチマーク情報として、労働組合のデータを好む会社もあれば、業界団体のデータを重視する会社もあります。
戦略知識とは、会社の戦略に関する知識のことです。これは戦略に合わせた動きをするためだけでなく、組織の優先順位をふまえて納得性のある公正、正当な施策を考えたり、説得をしたりするために役立ちます。
【人事に求められること】
- ■公正・正当性
- ・公正:分配的/相互作用的
- ・正当性:実利/道徳/認知
- ■政治スキル
- ・他者の利害を理解する力
- ・他者の行動に影響を及ぼす力
- ■知識・権力
- ・政治的知識:関係/規範/戦略
- ・政治的権力:意思決定に影響を与える力
最後に、人事パーソンへのメッセージをお願いします。
人事パーソンの皆さまに意識してほしいことが三つあります。
一つ目は、エビデンスに基づいた情報を持つことです。例えば、「あの人とあの人はたぶん仲が悪い」「あの人は(口には出さないが)こう考えているのではないか」という憶測は情報ではありません。常にエビデンスが得られるわけではありませんが、直接的なコミュニケーションを増やして相手の意図や考えを理解することに努めることが重要です。
二つ目は、明確な定義がないまま「モヤモヤ」「熱量」のような、使う人によって解釈が異なる表現を乱用しないことです。例えば、新たな評価制度について議論しているときに「この制度、なんだかモヤモヤするんですよね」と誰かが言った場合、その言葉が何を意味しているかわかりますか? わかる人は既にそこに憶測が入っています。
三つ目は、フレームワークを活用することです。抽象化された枠組みを使ってもすぐに答えは出ませんが、現実のさまざまな問題に普遍的に応用でき、解決策を考えるのに役立つからです。人間は一度しか経験していないことで持論を作り出す傾向があるので、フレームワークを持たずに考えると、自分が経験した数少ない具体例を基に判断してしまいがちです。例えば、人事制度改革を行うとしても、改革を何度も経験している人事パーソンは少ないと思います。たった一度の具体的な経験で改革を語りたくなってしまうかもしれません。しかし、問題解決はフレームワークから始め、状況に合わせて具体的な部分を考えていくのが効果的です。具体的なことばかり考えていると、過去に経験したときとの状況の違いが原因で失敗につながります。社内政治の把握にもさまざまなフレームワークを使うことができます。
「社内政治」にはネガティブなイメージがあったのですが、今回さまざまなお話を聞いて、そうでない面があるとわかりました。
そうですね。私たちの多くが、自分のしていることを正義だと思うのと同じように、他の人も自分が正義だと思っています。何かを改革するときは、抵抗したり反対したりする人を悪者にしがちですが、これまでやってきたことを無にされることに不満や不安を感じるのは人間として自然なことです。改革者にとっての正義が本当に正しいとも限りません。それぞれの正義があることを理解した上で、自分が必要だと思う改革を推進するために、利害調整が必要です。
古代ギリシャで生まれた「政治」という言葉のもともとの意味は「多様な市民の利害を調整し、共同体を運営すること」です。人事の皆さまには、社内政治に向き合って自社を良い方向に導いてほしいですね。

(取材:2024年12月11日)

さまざまなジャンルのオピニオンリーダーが続々登場。それぞれの観点から、人事・人材開発に関する最新の知見をお話しいただきます。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







