景気・業績悪化時の人員削減と法的リスク回避策
「希望退職制度」の実施手順と留意ポイント
弁護士(ジョーンズ・デイ法律事務所)
山田亨
1. 現在の状況と希望退職制度の位置付け
(1)経営合理化としての人員削減策
現下の景気の急速な後退と低迷により、多くの企業が倒産の危機に直面し、経営の合理化を迫られており、人員削減を考慮せざるを得ない状況にあります。しか し、日本の裁判所は、使用者側のリストラ策としての従業員の解雇(整理解雇)について、厳しい要件を課してきました。また、経営環境が厳しい状況下におい ても、財務状況の悪化が具体化していないような場合には、経営合理化としての人員削減は、現在の労働法制および裁判所の解雇権濫用法理の下では、難しいと いうのが実務の受け止め方であるといえるでしょう。
そのような中で、希望退職制度は、解雇を回避するための、または解雇に先立って行うべき手続きとしての、従業員との合意に基づく人員削減策として用いられてきました。
(2)裁判所により確立された「解雇権濫用法理」
周知の通り、労働基準法(以下、「労基法」という)20条は、解雇の場合の30日前の予告またはこれに代わる平均賃金の支払いを定めていますが、平成15年改正により判例法理(解雇権濫用法理)を条文化した同法18条の2は、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の解雇を、権利濫用として無効と規定しました(現在は、労働契約法(以下、「労契法」という)16条に規定されている)。
「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」とはいかなる場合を指すのか、明確な基準が存在しないため、実務的には解雇が考慮される多くの場面で解雇無効と裁判所に判断されるリスクを抱えざるを得ず、そのために「日本の労働法制および裁判所は労働者寄りである」という端的な物言いをすることがあります。しかし、裁判所によって確立された解雇権濫用法理とは、国家の政策として従業員の保護としてあるべき姿を司法の判断枠組みに反映するための理論的手段であり、経済発展と国力増進を目的とするもので、従業員の地位の保障を目的とするものではありません。

解雇権濫用法理が手厚い従業員の地位を保障するものとして機能してきたのは、具体的な歴史的背景に基づいた政策的判断によるもの(高度成長期に、「正規従業員=終身雇用・年功的処遇の企業戦士(企業に身を捧げる代わりに終身雇用・年功的処遇の保障を受ける)」という図式の下で競争力をつけようとする企業の戦略が、国家の政策として受容されたもの)だということに注意する必要があります。しかし、市場経済が世界的に浸透し、多くの産業分野における規制の撤廃と国際的競争の激化、産業構造の変化、労働力の国際的流動化、出生率の低下と高齢化が進む現在、終身雇用と年功的処遇という雇用形態では、主要な産業における企業の競争力を維持することが困難になっています。
(3)非正規従業員の増加と判例法理の変容
近年のパート、アルバイト、契約社員、派遣労働者の増加は、雇用調整の困難な正規従業員に代えて雇用調整の容易な雇用形態の労働力を確保しようとする企業側の需要に応えるものといえるでしょう。実際、昨年来の急激な景気の後退に伴う人員削減が、パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者を対象として多くの企業で実施されています。
そして、終身雇用の恩恵による正規従業員への支配力が企業の競争力につながらなくなったのだとすれば、そもそも国家の政策として、従来の解雇権濫用法理の運用をすべての産業分野でそのまま維持する理由はもはやないともいえます。そうだとすれば、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」の内実も変化して然るべきであるということになるでしょう。
(4)希望退職制度の必要性
最近の雇用関係を契約関係として捉え直そうとする労働契約法制の変更や、整理解雇における従来の4要件の柔軟化の兆し(4要素化ないし総合考慮により判断する裁判例-例えば、ナショナル・ウエストミンスター銀行事件-の出現)は、解雇権濫用法理の運用が変容する予兆であると見ることもできます。今後、解雇権濫用法理がどのように変容していくのか予測するのは困難ですが、雇用の流動化の推進が国家の政策として支持されることになれば、正規従業員を含めた雇用調整の自由化も進められることになるでしょう。
ただし、正規従業員に関する雇用調整の自由化は、労契法立法当時の議論では採用が見送られており、解雇規制を維持すべきという立場も有力に主張されている現在、裁判所がいますぐに従来の法的枠組みを放棄したり変更したりすることは望めません。したがって、少なくとも当分の間は、経営の合理化としての人員削減策としてはもちろん、整理解雇の4要件((1)人員整理の必要性、(2)解雇回避努力、(3)解雇対象者選定の合理性、(4)組合・労働者との協議)のうちの解雇回避努力要件充足のための手続きとして、希望退職制度の必要性は存続するでしょう。
2. 希望退職制度の実施手順
ここであらためて希望退職制度を定義しておくと、「人員削減を目的として、一定の募集期間を設けて、企業側で希望者にとって魅力的な退職パッケージを用意し、従業員にアナウンスして従業員の自発的な応募による退職を促す制度」ということができます。人員削減は、上記の通り、整理解雇の要件である解雇回避努力の一環として実施する場合もあれば、整理解雇をする予定がなくても経営効率の向上のために実施する場合もあります。
整理解雇との関連では、解雇回避努力の要件を充足するためには、希望退職制度を実施する義務があるか、という問題があります。裁判例には、希望退職制度を実施しなかった点を指摘して解雇無効を判断したもの(山田紡績事件、あさひ保育園事件)がある一方、希望退職制度の実施は必ずしも必要ないと判断したもの(シンガポール・デベロップメント銀行事件、東京都土木建築健康保険組合事件)もあります。
学説も、原則として希望退職制度実施義務があると主張するものもあれば、解雇回避努力の内容(希望退職制度実施のほか、配転、出向、転籍、残業抑制、非正規従業員の削減、新規雇用抑制等)は具体的事情によるものであり、合理的な努力の内容として希望退職制度実施が含まれないこともありうることを正面から認めるものもあります。実務的には、希望退職制度の実施による具体的なデメリット(従業員の動揺による事業価値の劣化、有用な人材の流出等)が予期できる状況がない限り、希望退職制度を実施するのが適当であると考えられます。
希望退職制度を実施する場合の手順は、次の通りです。
(1)人員削減の対象、目標値、募集時期の検討
(2)退職パッケージの条件の検討
(3)組合・従業員との協議
(4)希望退職制度導入の正式決定(取締役会決議)
(5)従業員への説明
(6)従業からの応募の受付、承認、合意書の作成
以下、各手順について詳しく検討します。
(1)人員削減の対象、目標値、募集時期の検討
希望退職制度による退職は、企業と従業員の任意の合意に基づく労働契約の終了であり、従業員は応募するか否かの決定権を有する一方、制度の対象、目標削減数、募集時期の設定については、企業側の裁量で決定することができます。
制度の対象については、正規従業員全員を対象にすることも可能ですが、例えば、所属部門、勤務地、役職、年齢、賃金レベル、勤続年数等を基準にして、制度の適用される対象を絞ったり、適用される条件に差異を設けたりすることができます。ただし、差異化に合理性がないと、不満を持つ従業員からの応募がなされなかったり、従業員が疑心暗鬼になったりするなど、ネガティブな影響が出るおそれがあるため、あらかじめ慎重な検討が必要です。
また、強行法規、公序や労働協約に違反する差別的取扱いは認められません。例えば、性別による適用の差別化は、退職勧奨について性別による区別をすることを禁ずる男女雇用機会均等法に具現化されている両性の平等の趣旨に照らして違法無効と判断されるおそれが強いといえますし、国籍、門地による区別も同様です。
目標削減数については、設定しないことも可能ですが、どの程度の人員でどのような事業運営を想定しているのかという青写真は、効率的経営や事業再生の一環として行う削減の決定に不可欠ですから、制度に明示的に組み込まないとしても、企業体としての基本方針に合致したものであることを確認する必要があります。
募集時期については、適用対象となる従業員が応募するかどうかが不明な状態は、適用対象となる従業員自身はもちろん、適用対象とならない従業員の職務遂行にも影響を与えるため、目標削減数にもよりますが、1週間から2週間程度の短期間とするのが望ましいといえます。
(2)退職パッケージの条件の検討
退職パッケージは通常、次のような項目で構成されます。なお、さらに、ストックオプション等が付与されている場合にはそれらの買上げがなされることもあります。
(2)割増退職金(退職加算金)の支払い(severance pay)
(3)未消化有給休暇の買上げ
(4)退職日前の有給の就業不要(再就職専念)期間の付与
(5)希望がある場合の再就職の支援
法律上、退職パッケージの条件についての規制は存在しません。しかし、退職パッケージは、対象者の自発的な応募を促す魅力的なものである必要があるため、自己都合退職や整理解雇の場合よりは従業員に有利な条件を設定することになります。
例えば、(1)について、会社都合退職の支給率を適用せず、自己都合退職の支給率を適用することもできますが、その場合は(2)の割増退職金や(4)の有給の就業不要期間の設定によって、全体として従業員の受ける利益を調整することになります。経営状態、財務状況による制約があるのはもちろんですが、魅力の薄い退職パッケージの提示は、対象者以外の従業員や取引先にも企業に対するネガティブな印象を与えかねないため、注意が必要です。
実務的には、(2)の割増退職金をどの程度に設定するかが問題になります。一般的には、月例給与の12ヵ月ないし24ヵ月分が目安といえますが、使用者である企業の属性、対象者の属性を考慮して設定することが必要です。具体的には、(ア)業種・職種・勤務地(雇用の流動性の低い業種・職種・勤務地であれば高めの設定とする)、(イ)リストラ後の企業の規模(リストラ後も相当程度の規模で事業を継続する場合は高めの設定とする)、(ウ)対象者の年齢(中高年であれば高めの設定とする)、(エ)勤続年数(長ければ高めの設定とする)等を総合的に考慮することになります。
(4)の有給の就業不要期間を設ける場合は、数週間から数ヵ月の幅で設定されるのが通常です。就業不要期間中、出社して社内の設備(電話等)を使用することを認めるケースもありますが、不慮の事故による責任が発生する可能性や営業秘密の保護の観点からすると、必要がある場合を除いて出社させないことにするのが望ましいといえます。
(5)は、再就職支援サービスを提供する外部機関を利用するのが一般的です。
(3)組合・従業員との協議
後述の通り、雇用対策法(以下、「雇対法」という)上の再就職援助計画の作成には組合(従業員代表者)との協議が要求されていますが(同法24条2項)、希望退職制度一般についても、円滑な実施のため、実施に先立ってその内容を組合等と協議し、理解を得ておくのが望ましいといえます。
なお、労働協約に規定がある場合は当然それに従わなければなりません。
(4)希望退職制度導入の正式決定(取締役会決議)
リストラ策の一環としての希望退職制度の導入は、「重要な業務執行」(会社法362条4項)に該当するため、取締役会設置会社においては、取締役会決議が必要になります。
(5)従業員への説明
従業員に応募を促すためには、希望退職制度の具体的内容について伝達する必要があります。一般的には、従業員に対して希望退職制度の説明会を実施します。従業員の利害に関することですので、希望退職制度導入の必要性をはじめ、募集対象者(業務に必要不可欠な者や普通解雇・懲戒解雇対象者については承認しないことについても説明する)、募集期間、退職パッケージの条件の詳細を誤解が生じないように伝えることが肝要です。業務に必要不可欠な者として応募があっても承認しないことが決まっている従業員に対しては、個別に通知します。
従業員への説明については、希望退職制度に応募しなかった従業員が、その原因は企業による再建策の内容や実現可能性に関する説明不足にあるとして提訴した、東邦生命保険事件(東京地判平成17年11月2日)があります。この事件で裁判所は、倒産の危機に瀕した企業が大規模なリストラのために希望退職制度を実施する場合に、「その制度の具体的内容及びこれを選択した場合の利害得失に関する情報を、従業員が自らの自由意思においてこれに応募するか否かの判断ができる程度に、提示すべきことは当然である」としつつ、「しかしながら、さらに進んで、当該企業が雇用する従業員に対し、希望退職制度実施に当たり、同制度採用当時における業務状況の詳細や再建策実施後の将来の見通しについて具体的根拠を示して説明すべき法的義務は、特段の事情がない限り、これを肯定することはできない」と判示し、その理由として「(財務状況や再建計画の概要等に関する情報)の開示の内容・程度、時期等については、将来の経営状態への見通し、開示による影響等を十分に考慮し、企業再建・存続を実効あらしめるため、高度の経営上の判断に基づいて決定されるべき性質のものであるからである」と述べました。
しかし、この裁判例においても、企業側が財務状況や再建計画の概要について情報を提供しなかったわけではないこと(経営状況が極めて厳しいことや、スポンサーとの業務提携の概要を冊子にして配布していた)に注意する必要があります。また、労契法4条1項に「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と規定されたことにより、「理解を深める」方法として、従来よりもいっそう充実した説明が要求されることとなったとの解釈もできることから、上記裁判例の射程については、保守的に理解しておくのが妥当でしょう。
具体的には、財務状況や再建策の概要について、再建策の実現を図るのに支障がない範囲を見極めて、その範囲で情報提供に努めるとともに、ビジネスに付帯するリスクがないと誤解しかねない断定的な物言いを慎むことが必要になります。
(6)従業員からの応募の受付、承認、合意書の作成
リストラ策の一環としての希望退職制度の導入は、「重要な業務執行」(会社法362条4項)に該当するため、取締役会設置会社においては、取締役会決議が必要になります。
以上の手続きに関し、法的には、次のような問題があります。
(1)いつの時点で企業と応募者の間に合意退職に関する法的義務が生じるのか。
(2)企業側で募集を変更・撤回できるか。
(3)従業員から応募を撤回できるか。
(4)企業側は応募に対する承認を自由に拒絶できるか(承認権の行使に何らかの制約があるか)。
(1)については、事案(具体的な応募手続)によって異なりますが、応募後企業の承認を経て合意書を作成することになっており、その旨が応募者に知らされている場合は、合意書作成をもって法的拘束力が生じる、と解されます(ピー・アンド・ジー明石工場事件)。
しかし、この裁判例においても、企業側が財務状況や再建計画の概要について情報を提供しなかったわけではないこと(経営状況が極めて厳しいことや、スポンサーとの業務提携の概要を冊子にして配布していた)に注意する必要があります。また、労契法4条1項に「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」と規定されたことにより、「理解を深める」方法として、従来よりもいっそう充実した説明が要求されることとなったとの解釈もできることから、上記裁判例の射程については、保守的に理解しておくのが妥当でしょう。
(3)については、上記ピー・アンド・ジー明石工場事件において、「『合意書』を作成する前に、本件退職申出を撤回しているから、…退職の合意(労働契約解約の合意)は成立していないと一応認めることができる」としていることから、労働契約解約の合意が成立するまでは応募を撤回することが可能と考えられます。ただし、応募後、承認手続が終了して、応募者の退職を前提とした措置が企業によってなされた場合には、応募の撤回が制限される可能性があります。他方、目標数を確保したい企業としては、応募後の承認、合意書作成手続を速やかに進めることが肝要です。
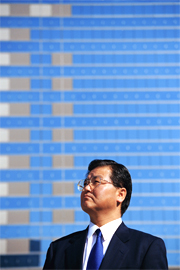
(4)については、選択定年制(60歳の定年前に定年扱いによる退職を選択した場合に割増退職金を支給する制度)についてではありますが、神奈川信用農協早期退職事件において、原審が「上告人は、従業員がした本件選択定年制による退職の申出に対して承認をするかどうかの裁量権を有するが、不承認とすることが従業員の退職の自由に対する制限となることなどからすれば、上記裁量権の行使は、本件選択定年制の趣旨目的に沿った合理的なものでなければならず、上告人が不合理な裁量権の行使により不承認とした場合には、申出のとおり本件選択定年制による退職の効果が生ずるとするのが相当」と判断したのに対し、最高裁判所がこれを覆して「上告人がその承認をするかどうかに関し、上告人の就業規則及びこれを受けて定められた本件要項において特段の制限は設けられていないことが明らかである。…退職の申出に対し承認がされなかったとしても、その申出をした従業員は、上記の特別の利益(引用者注:割増退職金を意味する)を付与されることこそないものの、本件選択定年制によらない退職を申し出るなどすることは何ら妨げられていないのであり、その退職の自由を制限されるものではない。」と判示したのが参考になります。
この論理によれば、希望退職制度の仕組み上、承認に一定の条件が付されている場合はともかく、そうでない場合には、承認がされるまでは応募者に割増退職金等の利益の付与が保証されているわけではなく、承認されなかったことによって応募者が法的保護に値する不利益を蒙ったということもできないから、企業による承認権の行使は制約を受けない、ということになります。もっとも、公序に反する不法な目的(例えば、性別、国籍、門地に基づく差別等)で承認権を行使する場合は、違法と評価される余地はあるでしょう。
これに関連して、あらかじめ承認しないことを通知していた従業員から応募があった場合の対応が問題になることがあります。上記の通り、理論的には「不可欠だから」という理由で承認拒絶することが可能ですが、事前の通知にもかかわらず応募してくる従業員を無理やり引き止めることが得策かどうかについては慎重な考慮が必要で、実務的には承認するという対応もありうるでしょう。
3. その他の留意点・ポイント
(1)利害関係人との調整
人員削減が必要な企業は、多くの場合、銀行債務等によって、新規の債務負担を伴う経営判断に制約を受けています。したがって、応募者に付与する利益の内容については、債権者との契約上必要な調整をすることが必要になります。
また、再建策の実施に当たって、スポンサーの支援を受ける場合は、スポンサーによる退職パッケージの条件の承認が不可欠です。
(2)上場会社における適時開示義務
上場会社の場合は、有価証券を上場させている金融商品取引所の上場規程を遵守する必要がありますが、上場規程は、「人員削減等の合理化」の決定を適時開示の対象としています(東証・有価証券上場規程402条1号ab、大証・上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則2条1号w)。したがって、上場会社にあっては、希望退職制度実施の取締役会決議後、速やかにその内容を開示する必要があります。
(3)雇用対策法上の再就職援助計画
雇対法24条によれば、経済的事情により、1つの事業所において1ヵ月に30人以上の離職者を生じさせる事業規模の縮小等を行おうとするときは、最初の離職者が生じる1月前までに再就職援助計画を作成し、従業員の過半数で組織する労働組合(組合がないときは労働者の過半数代表者)の意見を聴取し、公共職業安定所長の認定を受けることが事業主に義務付けられています。30人未満の場合でも、任意で再就職援助計画を作成することが可能です。
計画の認定を受けた事業主には、公共職業安定所から求人情報の提供等の援助がなされるほか、対象従業員に求職活動等のために休暇を付与し、通常の賃金以上を支払った場合には、雇用・能力開発機構から労働移動支援助成金が支給されます。
(4)数次にわたる希望退職制度相互の関係、退職勧奨との関係
希望退職制度を実施しても、目標とする人員削減が達成されないことが多いのが実情です。したがって、実務的には、次のようなことを実施することがあります。
(1)数次にわたって希望退職制度を実施する。
(2)個別に従業員に接触して応募を促す。
(3)希望退職制度の募集期間外に退職勧奨を行う。
(1)や(3)については、二次以降の希望退職制度や個別の退職勧奨において、退職パッケージの条件をより魅力的なものに変更することも可能です。しかし、「粘ればもっと好条件の提示がなされるのではないか」との期待感から逆効果となる可能性もありますし、早期の希望退職募集に応じた従業員からクレームを受けることも覚悟しなければなりません。したがって、条件の変更には慎重な考慮が求められます。
(2)や(3)については、従業員の退職合意の任意性を損わないように留意する必要があります。強迫、詐欺と解されるような行為(退職に応じるよう執拗に説得するなど)は慎まなければなりません。また、(2)については、個別の接触において、対象従業員全体に対する説明と相違する説明がなされたり、他の従業員に開示されない情報が開示されたりすることのないよう、留意する必要があります。


やまだ・とおる●1990年東京大学法学部卒。1992年司法研修所修了(44期),弁護士登録(第一東京弁護士会)。1997年ハーバード・ロースクールLL.M.修了(フルブライト奨学生)。1998年ニューヨーク州弁護士登録。現在,外国法共同事業・ジョーンズ・デイ法律事務所パートナー。著書に「有限責任事業組合(LLP)の法律と登記」(日本法令・共著)「World Online Business Law,Oceana Publications,Inc」(共著)等がある。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







