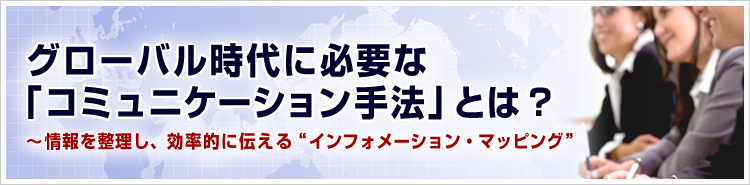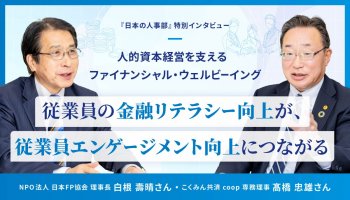グローバル環境での企業活動が拡大する昨今、多くの日本企業では「英語」を中心としたコミュニケーションに関する問題が表面化しています。特に、英語を母国語としないノンネイティブ同士が仕事を遂行していく際に、情報としての「言葉」や「文書」をどのように伝えあうのかは、実務における大きな課題となっています。今後ますますグローバル展開が進んでいく中、人と人とはいかにコミュニケーションを取り合い、情報をやりとりしていけばいいのでしょうか。この問題に詳しいゲストをお招きし、グローバル時代に必要なコミュニケーションのあり方について、語りあっていただきました。

- 秋山進さん
- プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社代表取締役
情報構造化研究所株式会社代表取締役
(あきやま・すすむ)京都大学卒業後、リクルートに入社。商品開発、戦略策定などに従事したのち、インディペンデント・コントラクターとして各種トップ事業のCEO補佐を行う。2度の外資系企業役員を経験。その後、コンプライアンスとリスク管理に重点を移し、産業再生機構下にあった株式会社カネボウ化粧品のチーフ・コンプライアンス・オフィサー代行を務める。2008年より現職。

- 小川達也さん
- 情報構造化研究所株式会社 所長
(おがわ・たつや)複数の外資系企業にて国際間プロジェクトを多数経験し、さまざまな業種の事業立ち上げやプロジェクトマネジメントを行う。海外企業とのビジネス交渉および協業、海外事業展開を主体とし、実務オペレーション支援活動およびコンサルティング業務活動に従事する。現在、情報構造化手法の導入支援コンサルティングおよび教育を通じて、異文化コミュニケーション環境におけるビジネス実務の効率化やグローバル化支援等の研究開発とコンサルティング支援を行っている。

- 中原孝子さん
- 株式会社インストラクショナルデザイン代表取締役、ASTDグローバルネットワークジャパン代表
(なかはら・こうこ)岩手大学卒業後、米コーネル大学大学院にて、教育の経済効果、国際コミュニケーション学などを学ぶ。外資系製造販売会社、金融機関、IT企業にて人材戦略部門のマネジャーを歴任後、2002年5月に株式会社インストラクショナルデザインを設立。インストラクショナルデザインによる効果的研修設計やOJTを含む研修設計の支援、パフォーマンスコンサルティング、人材開発機能の設計・支援、タレントマネジメントの運営支援などを提供している。現在、ASTDインターナショナルジャパン、米ASTDをはじめ、国際カンファレンスでのスピーカーを多数務めるなど、グローバルに活躍中。人材関連専門誌への寄稿記事も多数。2011年にASTDグローバルベーシックシリーズ『HPIの基本』(ジョー・ウィルモア)を翻訳。
グローバルマネジャーに求められるものとは
秋山:近年、グローバル展開のスピードが一段と速くなり、グローバルマネジャーの育成が大きな課題となっていますが、企業の現状をどのように感じていらっしゃいますか。
中原:「グローバル人材」や「グローバルマネジメント」に関する定義が不明瞭なまま、「いったい何をしたらいいのだろう」と迷っている企業が多いように思います。グローバル展開する上での最終的なビジネスゴールが何なのか定まっていれば、必ず英語が話せなくてはならない仕事なのか、英語が話せなくても経営判断やマネジメント能力があれば達成できる仕事なのかなどの要件も見えてくるはず。しかし、実際には明確になっていなくて、共有もできていません。言葉の問題にしてしまっている傾向がありますね。
秋山:海外に進出した際には、現地の仕事を適切に遂行できることが何より重要であり、語学力はそのためのコミュニケーションの手段ということになります。その優先順位が逆になっている企業は多いようですね。
中原:グローバルマネジャーを選抜する際に、「とりあえず英語ができる人」と考えてしまうんですね。マネジャー側でも、TOEICで700点取るとか、800点取るとか、それ自体が目的になっている感じがします。
秋山:日本では能力的に素晴らしいマネジャーでも、海外に行くとうまくいかないということもあるのでしょうか。

中原:ありますね。マネジメントに対する海外との共通のフレームが日本に無いからです。日本人が持っているマネジャー像と、海外の子会社などがイメージしているマネジャー像とにギャップがあります。そうした中で、日本から来た人が自己流のマネジメントを行うと、現地での期待値とのギャップが生じてしまう。逆に、現地で優秀な方を採用しているケースを見ると、マネジャー候補にはMBAなどでしっかりと勉強している人が多いんですね。MBAではある一定のマネジャー像というフレームがありますから、日本人マネジャーはそれと違っていて、「いない方が仕事スムーズにいく」と言われてしまうこともあります。
小川:海外に行くと、いわゆる日本流の自分を守るものや武器がありません。マネジメント力とともに、人としてどうかという「人間力」が問われます。そういう意味では、コミュニケーションをとる際に、もう一歩踏み込んで話ができるか、伝えるべきことをきちんと伝えられるかが重要です。そうした観点からすると、日本人には下手な人もいれば、うまい人もいますね。
秋山:海外に行くと、マネジャーとしての権限を行使する際には、本人の能力とコミュニケーションスキルとをうまく合わせて、どうにか理解してもらい実行してもらわなければなりません。まさに、「生の自分」で勝負しなくてはならない。一方、日本では長年やってきているので、あうんの呼吸で仕事が進みます。その辺りに、温度差があるように思います。
海外では通用しない日本のコミュニケーション
秋山:日本は、コミュニケーションの仕方も独特です。何よりハイコンテキスト社会で、皆がお互いに分かり合えているので全部を言わないし、全部を書きません。例えば、議事録。本来、議事録は後で見てもそこで話し合われたことが再現されていて、第三者が見ても分かるように書くことが大事なはずです。しかし、日本ではあえてそこまで踏み込みません。なぜなら、分かり合える人にはそれで十分であり、自分のやるべきことも分かるからです。しかし、このようなやり方では、第三者に見せる時に全く通用しないでしょう。
中原:会議とは本来、何か物事を決めるはずの場なのに、決めない会議になっているケースがとても多いことが日本では昔から問題になっています。先ほどの話も決めるためではなく、皆が集まりましたという証拠を作る会議になっていますね。

秋山:皆が集まることで、「もうこれをやるしかないよね」などと、大勢がその方向に流れている「空気」を作るのが会議の大きな目的になっているからです。何となく話をして大勢がその方向に向かっているという空気ができれば、次の会議で正式に「やる」と決められるのです。そうした空気を作る会議を行わないで、いきなり話し合っても、「俺はやらない」「手伝わない」という人が出てきます。
小川:まずは空気を作ることに専念し、決めることは先送りにしているんですね。
秋山:あえて極端な言い方をすると、「決まりました」ではなく、「こういうことが話し合われました」と書くのが日本的な会議の議事録なんです。しかし、海外の子会社の従業員がその議事録を読んだら、果たしてどう思うでしょうか。
小川:集まった実績と証拠を残したけれど、決めたという結論がない議事録になる訳ですね。これでは海外の人たちは戸惑うばかりです。
中原:海外の人とコミュニケーションをとる場合、ロジックで考えていかないと絶対に伝わりません。「私の前提条件はここだけれど、あなたの前提条件はどこ?」というところから始めなければいけないわけですが、日本の場合は前提条件を既に考慮した上で、コミュニケーションが始まるということですね。
曖昧な表現の多い日本語を、英語に翻訳する難しさ
中原:日本の会社にはそれぞれ、コミュニケーションのルールがあります。そのため、例えばグローバルマネジャーが海外拠点の人材とコミュニケーションをとる場合などには、自分たちのルールが世界共通ではないことに、気付かなければならないと思います。
秋山:そうですね。例えば、日本の大企業でプレゼンテーションする場合、「状況的に考えると、○○であると思われます」という言い方をします。しかし、本当はその人がそれなりに客観的に考えた上で、主観的にそう思っているのですから、そのように言えば良いのですが。しかし、もし、「私はそう思います」などと言ったら日本では生意気だと怒られてしまいます。「お前のアイデアを聞いているのではない。世の中ではどう思っているのか、それを知りたいのだ」と。日本企業には、そういう独特のコミュニケーションがあります。

中原:日本の大企業のプレゼンテーション資料を翻訳する仕事に関わったことがあるのですが、結局、何を言いたいのか、日本語でもよく分からないスライドがたくさんありました。英語に訳す場合、構造をシンプルにしなければいけないのですが、実際に英語にしてみても何かが違っていて、結局、日本語でも英語でもよく分からないということが如実になったことを覚えています。やはり、日本語は表現の仕方や言葉の構造として曖昧な部分があり、英語とはかなり違いますね。
小川:それは、会話でも同じです。日本語から英語にするにしても、途中に相当優秀な翻訳者がいて、その意味を汲み取って表現してくれないと、大変なことになるケースがあります。
秋山:確かに語学力の問題もあると思いますが、情報伝達という点で考えた場合、何を伝えるのかをできるだけシンプルに誰にでも分かるような形まで凝縮して、きちんとまとめられたら、何とか伝わるのではないでしょうか。
小川:言葉やテクニックの問題ではなくて、本当に伝えたいことが頭の中で整理できているかどうかが、大事だと思います。その際に重要なのは、相手にはどういうバックグラウンドがあるのかをよく理解できていること。日本ではない、違う国の違う組織の人に対して、どうやって伝えていくのかを整理しなければなりません。このように体系立てて伝えられることは、重要なスキルです。
中原:日本語で作った資料を英語に変えてプレゼンテーションしなければいけない時には、できるだけシンプルな言葉に置き換えるようにしていますが、後で元の日本語を見ると、「この言い方はとても曖昧で分かりにくく、伝わっていなかったかもしれない」と感じることがよくあります。そういう意味でも、日本人が英語でプレゼンなどを行う場合、よりシンプルに伝えることが重要です。そのためには、自分の頭の中の整理、情報の整理が欠かせません。そういう基本ができていなければ、英語、日本語にかかわらず、相手に伝わらないという状況が多々出てくるでしょう。

HRのトレンドと共に、HRソリューション企業が展開するさまざまサービスをご紹介。自社に最適なソリューションを見つけてください。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!


 サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 調査
調査 人事辞典
人事辞典 イベント
イベント