勧告・指導、改善状況の実態は?労働基準監督署による企業監督事例(上)
事例その1-A社(小売業)
1年単位の変形労働時間制の運用に問題があった事例
1 監督署の勧告・指導状況
A社は、労使協定を締結して1年単位の変形労働時間制を採用していましたが、各労働者の1年間の所定労働日を特定することができずに、1カ月ごとに期間を区切り、1カ月ごとの総労働日数および総労働時間数を協定し、各1カ月の初日の30日前までに各労働者の勤務シフトを作成し労働者代表の同意を得る協定となっていましたが、各期間の初日の30日前までに勤務シフトを作成することができずに、期間の始まる数日前に作成し労動者代表の同意を得ることなく労働者に示していました。
また、振替休日と称して頻繁に休日に労働を行わせ、実際には、振替休日をほとんど取らせることなく、休日に出勤した賃金も支払うことなく、労働者の中には、数10日の振り替えられなかった休日出勤分の賃金が支払われていませんでした。
このことから、A社に対して以下の違反を指摘しました。
(1)休日出勤に対する割増賃金を支払っていないこと(労基法37条)
(2)労基法36条に基づく協定の範囲を超えて、労働者に時間外労働を行わせていたこと(労基法32条)
(3)1カ月ごとに期間を区切って労働日数、労働時間数を定めている1年単位の変形労働時間制の労使協定において、各月の30日前までに労働日ごとの労働時間数を決定し労働者代表の同意を得る等の手続きをしておらず、適法に1年単位の変形労働時間制を行っていないことから、1年単位の変形労働時間制により行うことができるかどうか検討した上で、改善すること(指導事項)
(4)1年単位の変形労働時間制を採用した場合には、通常の繁閑等を理由に休日振替を行うことはできないことから、1年単位の変形労働時間制以外の労働時間制度(1カ月単位の変形労働時間制等)にする等も含めて検討すること(指導事項)
2 1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制は、業務の繁閑のある事業場において、繁忙期に長い労働時間を設定し、閑散期に短い労働時間を設定することにより効率的に労働時間を配分して、年間の総労働時間の短縮を目的にしたもので、対象期間を平均して1週間当たり40時間以内(対象期間が1年間の場合、1年間の所定労働時間を2,085時間以内)となるように労働日および労働時間を特定する制度です。
対象となる期間が1年間と非常に長いことから、労基法により様々な規制を設け、この要件を満たした労使協定を締結しなければ採用できません。
今回は、上記1の(3)、(4)に絞って1年単位の変形労働時間制の説明をいたします。
1.対象期間の労働日、労働時間の特定
1年単位の変形労働時間を採用するためには、労働者ごとに対象期間のすべての労働日およびその労働日ごとの労働時間を労使協定の締結時に特定しなければなりません。
つまり、対象期間を経過して結果として1週を平均して40時間以内(例えば、対象期間が1年間の場合、対象期間の1年間が経過したときに、労働時間が2,085時間以内)となっていればいいのではなく、労使協定を締結するときに、事前に、対象期間のすべての労働日および労働日ごとの労働時間を特定しておかなければならず、協定した場合は原則として変更することができません。
解釈例規によると、以下の通りとされています。
労使協定において特定された日又は週の労働時間を対象期間の途中で変更することは出来ない。仮に、労使協定において「労使双方が合意すれば、協定期間中であっても変形制の一部を変更することがある。」旨明記されていたとしても、これに基づき対象期間の途中で変更することはできない。
(昭63.3.14基発第150号・婦発第47号、平6.3.31基発第181号)
1年単位の変形労働時間制を採用している事業場を調査すると、労使協定で特定した労働日、労働時間通り労働させていない事業場が多くみられ、場合によっては、結果として対象期間を平均して1週40時間以内となっていたとしても、割増賃金の支払いが必要になってきます。
2.対象期間の労働日、労働時間の特定の例外
労使協定を締結するときに、事前に対象期間のすべての労働日および労働日ごとの労働時間を特定しておくことが原則ですが、1年先の労働日、労働時間を特定することができない場合には、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分し、(1)最初の期間の労働日および労働日ごとの 労働時間、(2)最初の期間を除く各期間の労働日数および総労働時間数を労使協定の中で定めればよいことになっています
この場合でも、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間をその期間の始まる少なくとも30日前に労使協定の労働者代表の同意を得て書面により定めなければなりません。これを図示すると次のようになります。
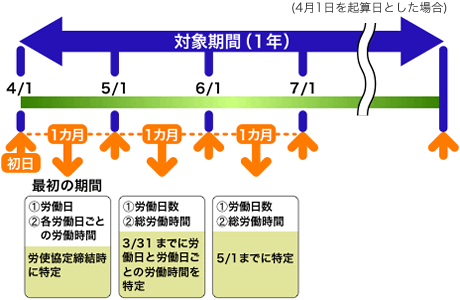
A社の場合、1年単位の変形労働時間制の労使協定を締結するときに、対象期間(1年間)を1カ月ごとに区分し、(1) 最初の期間の労働日および労働日ごとの労働時間、(2)最初の期間を除く各期間の労働日数および総労働時間数、を労使協定で定めていましたが、最初の期間を除く1カ月の労働日、労働時間をその期間の始まる数日前に勤務シフトを作成して各労動者に示しており、30日に労働者代表の同意を得ていなかったものです。
各期間の30日前までに、労働者代表の同意を得られなかった場合には、区分された期間の労働日数および総労働時間しか決定されておらず、労働日および労働日ごとの労働時間が特定しないことから、労使協定で定めた労働日数、総労働時間数の範囲内で原則的な労働時間を定めた労基法32条の規定により労働させることになります。(平6.5.31基発330号、平11.3.31基発168号)
つまり、A社の場合も、各期間の勤務シフトについて労働者の代表の同意をとっていないため、労基法32条が適用され、週40時間、1日8時間を超えて労働させた時間は時間外労働となり、割増賃金の支払いが必要になってきます。
3.1年単位の変形労働時間制の休日振替
A社においては、作成した勤務シフトの所定休日に労働させることが多く、中には、1カ月の所定休日すべてに労働している労働者がいました。
1年単位の変形労働時間制を採用した場合の休日振替については、解釈例規によると、以下の通りとされています。
1年単位の変形労働時間制は、使用者が業務の都合によって任意に労働時間を変更することがないことを前提とした制度であるので、通常の業務の繁閑等を理由として休日振替が通常行われるような場合は、1年単位の変形労働時間制を採用できない。
なお、1年単位の変形労働時間制を採用した場合において、労働日の特定時には予期しない事情が生じ、やむを得ず休日の振替を行わなければならなくなることも考えられるが、そのような休日の振替までも認めない趣旨ではなく、その場合の休日の振替は、以下によるものであること。
(1)就業規則において休日の振替を必要とする場合に休日を振り替えることができる旨の規定を設け、これによって休日を振り替える前にあらかじめ振り替えるべき日を特定して振り替えるものであること。この場合、就業規則等において、できる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいこと。
(2)対象期間(特定期間を除く。)においては連続労働日数が6日以内となること。
(3)特定期間においては1週間に1日の休日が確保できる範囲内であること。また、例えば、同一週内で休日をあらかじめ8時間を超えて労働を行わせることとして特定していた日と振り替えた場合については、当初の休日は労働日として特定されていなかったものであり、労働基準法第32条の4第1項に照らし、当該日に8時間を超える労働を行わせることとなった場合には、その超える時間については時間外労働となるものである。
(平6.5.31基発第330号、平9.3.28基発210号平11.3.31基発168号)
A社の場合、頻繁に休日振替が行われていたことから、1年単位の変形労働時間制を採用できるかどうかを含めて指導を行いました。
3 振り替えられなかった休日出勤分の賃金
A社の場合、振替休日制度と称していても、ほとんど振替日の指定が行われず、実際に休日も取得しておらず、ほとんどの労働者が何日も振り替えられなかった休日出勤が溜まっており、その分の賃金が支払われていませんでした。
賃金の支払いについては、毎月一定期日に全額を支払わなければならないこととなっており、月給制の場合、その月の所定労働時間を超えた労働に対する賃金もその月の賃金で支払わなければならないことになります。
つまり、その月の賃金計算期間の所定労働時間を超えて働いた休日については、その月に休日を取らないと所定労働時間を超えて働いたことになるため、代休分としてためておくのではなく、その月の休日出勤分として賃金を支払わなければならないことになります。
4 その他の勧告・指導事項
(1)管理監督者に対して、深夜労働の割増賃金を支払っていないこと(労基法37条)
(2)年次有給休暇がほとんど取得されていないため、年次有給休暇取得簿等を整備し、取得促進に努めること(指導事項)
(3)地方在住の医師を産業医として選任しているが、本社に対し産業医の職務を行える医師を選任すること(指導事項)
5 A社の改善状況
監督署の指導を受けたA社は、労働時間管理の見直しを行い、次の通り改善しました。
(1)1年単位の変形労働時間制の労使協定を次回から締結することをやめ、1カ月単位の変形労働時間制を採用しました。
(2)溜まっていた休日出勤分の賃金の支払いを行い、労働者に対して振替休日制の説明を行った上で、振替日を特定し、必ず休ませるようにしました。
事例その2-B社(食料品製造業)
雇入れ時の健康診断を実施することによって労働者の異常所見を事前に把握し、作業転換等の措置を講ずることによって労働者の事業場内での死亡を防ぐことができた可能性のあったケース
1 災害発生状況
B社は、生鮮食料品を一部加工してレストラン等に朝早く卸す仕事を行っていることから、深夜勤務や、冷蔵庫内での作業等の有害業務を行っていました。
高校1年の夏休みからB社で短時間勤務のアルバイトとして働いていた労働者Xが高校卒業前後の2月下旬からフルタイムのアルバイトとして働くようになり、その年の4月に正社員として入社しましたが、18歳となっていたことから、フルタイムで働くようになった2月下旬から深夜業を含む勤務を行うようになり、正社員となってからは、午後9時から翌日の6時までの勤務となりました。
労働者Xは、正社員となって4カ月目の7月初旬に食料品の入った冷蔵庫で深夜勤務を行っていたところ突然倒れて死亡しました。
死因は、虚血性心不全で、死体検案書によると、高度の肥満(181cm、126kg)、心臓肥大、肝肥大、扁桃腺肥大、やや高度の脂肪肝、冠状動脈硬化症、等となっていました。
2 監督署の指導状況
労働者Xの災害については、死体検案書の死因が病死、自然死となっており、時間外労働もほとんど行われていない等、業務との因果関係は薄く、労働災害とは認められませんでした。
B社は、年1回毎年秋に健康診断を行っていたましたが、深夜業従事者に対する年2回の健康診断および雇入れ時の健康診断は行われていなかったため、B社にアルバイトとして働き始めたときから死亡するまでの間、労働者Xに健康診断を受診させていなかったため、次の事項について勧告しました。
(1)常時使用する労働者を雇い入れたときに定期健康診断を行っていなかったこと(安衛法66条、安衛則43条)(2)常時深夜業に従事する労働者に対して6月以内ごとに1回定期健康診断を実施していないこと(安衛法66条、安衛則45条)(3)健康診断の項目に異常所見があると診断された労働者の定期健康診断の結果に基づき当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師の意見を聞いていなかったこと(安衛法66条の4)
(1)常時使用する労働者を雇い入れたときに定期健康診断を行っていなかったこと(安衛法66条、安衛則43条)
(2)常時深夜業に従事する労働者に対して6月以内ごとに1回定期健康診断を実施していないこと(安衛法66条、安衛則45条)
(3)健康診断の項目に異常所見があると診断された労働者の定期健康診断の結果に基づき当該労働者の健康を保持するための必要な措置について、医師の意見を聞いていなかったこと(安衛法66条の4)
3 定期健康診断
安衛法に基づいて行われる健康診断は、労働者自身が自らの健康状況を確認するだけのものではなく、事業者が健康診断を行うことによって、(1)その労働者が仕事を行っている職場環境のチェック、(2)労働者が現在行っている仕事を健康に行っていくことができるかどうかのチェック等を行うためのものです。
雇入れ時に健康診断を行うのは、仕事に就かせる前に労働者に健康診断を行うことによってその労働者の健康状況に異常がないかどうかをチェックし、これから就かせようとする仕事に問題なく対応できるかどうかの判断を行うためのものです。
B社では、雇入れ時の健康診断を行っていなかったため、秋の健康診断を行うまで、4月に入社した労働者の健康状況を把握することなく各職場に配置しており、B社は、労働者Xの健康状況を把握しないままに、冷蔵庫内での深夜労働という体に負担のかかる業務に従事させ、労働者Xが社員となってから4カ月後に死亡するという事態に陥ったものです。
健康診断を行った結果、検査項目に所見があった場合は医師による意見聴取を行い、その意見により、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講じなければならないことになっています。
また、深夜業を含む業務や著しく寒冷な場所における業務等、安衛則13条2号に掲げる業務に常時従事する労働者に対しては、6月以内ごとに1回定期健康診断を行わなければならないことになっており、労働者Xが従事する業務についてはこの基準に該当するため、B社としては、秋に行う健康診断のほか、6カ月後の春にも健康診断を行わなければならないことになります。
今回の事案について、労働者Xが雇入れ時の健康診断あるいは深夜業を含む業務に従事する労働者に対して行う6月以内ごとの健康診断を行っていれば、その結果に基づき、医師による意見聴取を行い、就業場所の変更、作業の転換、就業禁止等の措置を講ずることによって死に至ることを防ぐことができたかもしれません。
監督署が事業場に臨検し健康診断の受診率を聞くと、ほとんどの労働者が受診していますと胸をはって答える担当者がおりますが、健康診断は、会社として実施していればいいのではなく、それぞれ一人ひとりの労働者に受診させなければならないことになります。
99%の労働者が健康診断を行っていたとしても受診しなかった労働者の中に労働者Xのような異常所見のある労働者が入っていたら、今回の事例と同じ様なことが起こる可能性があるからです。
4 B社が行った改善状況
監督署の指導を受け、常時使用する労働者を雇い入れたときおよび深夜業を含む業務に従事する労働者に対して6月以内ごとに1回健康診断を実施し、健康診断の結果に基づき産業医の意見を聴き、必要に応じて作業転換、就業時間の変更等を行うよう体制を整えました。

【執筆者略歴】
●ビジネスガイド編集部
労働基準監督署による企業監督事例を紹介し、監督署が実際に行った勧告・指導の内容、その後の改善状況を見ていきます。他社の事例を参考にしていただき、自社の労務管理体制の構築・改善につなげていただくきっかけとなればと思います。今回は、主に「変形労働時間制」「健康診断」に関する事例を見ていきます。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント







