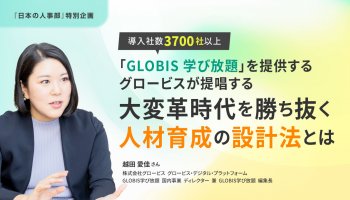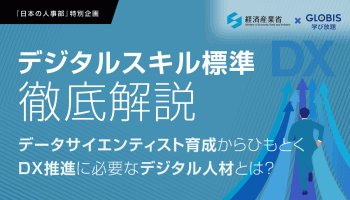eラーニング
eラーニングとは?
eラーニング(e-learning)とは、電子技術や情報技術を活用した学習方法です。従来の集合研修には、運営にコストや労力がかかるほか、学習者側の時間調整などの面でさまざまな課題がありました。eラーニングは時間と場所を選ばずに利用できるため、集合研修が持つ課題を解決できるとして注目を集めています。社員の主体的な学習をサポートするeラーニングは、今後の企業成長においても大きな意味を持ちます。
「eラーニング」に関する人事用語を絞り込む
1. eラーニングとは

eラーニングはelectronic learningの略称であり、電子技術や情報技術を活用した学習方法のことをいいます。パソコンやスマートフォン、タブレットなどのデジタル機器を使用し、インターネット上で提供される教材(コンテンツ)を自主的に学習する形式です。
eラーニングを導入することにより、学習者はデジタル機器を使用して自分の好きな時間・場所で主体的に学習できるようになります。新人研修や各階層の研修をはじめ、ナレッジの共有や社内制度の理解促進、資格取得など、活用の方法は多種多様です。
eラーニングの発展
eラーニングは、もともと1970年代に「CAI(Computer Assisted Instruction、コンピューター支援教育)」という名称で登場しました。その後、1990年代になるとパソコンの普及とCD-ROMの登場により「CBT(Computer Based Training)」が浸透し始めます。CD-ROMに録画された教材を自分のパソコンで視聴するCBTのスタイルは、昨今のeラーニングにおける学習スタイルの先駆けといえます。2000年代には、教材を修正できないCBTのデメリットをカバーする「WBT(Web Based Training)が登場し、eラーニングという言葉も広がりました。
昨今のeラーニングの傾向を見ると、DVDやパソコンソフトを視聴する形式から、インターネット上でログインして視聴するクラウド型が主流になりつつあります。クラウド型の特徴は、自社の課題に合わせてより柔軟な学習スタイルを構築しやすいことです。例えば、チャットで気軽に質問したり、ライブ学習機能によって臨場感のある雰囲気で講習を受けられたりと、集合研修に近い状況の再現が可能です。また、メールと連携したスケジュール管理が可能なサービスも提供されています。学びやすさに加え、学習意欲の向上や効率的な学習を実現するためのさまざまな工夫がなされています。
eラーニングの目的
従来、社員研修は体系的な知識・スキルの習得やOJTでは学べない内容を学習する方法として、人事施策において重要な位置付けとされてきました。しかし、対面形式で行われる集合研修では多くの手間やコスト、時間がかかるため、手軽に実施できるものではありませんでした。
eラーニングは、誰もが好きな場所で受講でき、通信環境さえ整備すれば、準備の手間や時間もかかりません。研修についてこれまで企業が抱えていた課題を解決しながら、社員に学習の機会を与えられます。個々の能力開発はもちろん、モチベーションアップや組織力向上を目的とした導入も可能です。
次々と新たなサービス・商品が生み出される現代のビジネスでは、変化に対応するためのスピード感が重要視されます。社員の早期戦力化に役立つ学習法としても、eラーニングの導入が進んでいます。
企業(管理者)・学習者別、eラーニングの使い方
eラーニングの使い方は多種多様であるため、効率的に活用するには、あらかじめ使い方を想定しておく必要があります。また、eラーニングによる学習効果を最大限に高めるためには、学習者側の視点に立って活用方法を検討することが重要です。
| eラーニングの使い方 | |
| 企業側 |
|
| 学習者側 |
|
eラーニングは、個人ごとの視聴がメインとなるため、基本的にはインプット型の学習が向いています。一方で、活用方法によってはアウトプット学習や交流もでき、目的に応じて柔軟な使い分けも可能です。企業にとっても、学習計画の作成や受講者情報の管理を効率化できるなど、社員を育成する上でさまざまなメリットがあります。
昨今は、経営戦略の実現に向けて人材マネジメントを行う「戦略人事」の考え方を取り入れ、経営目標を意識した人材育成を行う企業が増えています。目標を意識した人材育成において、学習に関する情報や計画を一元的に管理できるeラーニングは有効です。
2. eラーニングのメリット

企業側のメリット
研修担当者の負担が軽減される
eラーニングは、インターネット環境さえ整備されていれば、従業員が個人で学習を進めることができます。そのため、受講者のスケジュール調整や研修場所の確保、講師との打ち合わせ、特別な機器の準備といった負担が発生しません。研修担当者はコア業務に専念できるようになり、結果的に人事部門の生産性向上につながります。対面での集合研修で必要となる会場費や移動費、宿泊費などのコストを節約できる点もメリットです。
受講者の進捗管理が容易
eラーニングシステムでは、受講者の学習状況を一元的に管理できるため、「誰がどこまで学習しているのか」が一目瞭然です。進捗が遅れている従業員には、個別にアプローチするなどの対応が可能です。進捗状況と理解度を照らし合わせれば、従業員の課題の傾向もつかめます。また、人気のない教材を把握してコンテンツのブラッシュアップに生かすなど、効果的な運用ができるメリットもあります。
最新の情報を届けられる
eラーニングでは教材の修正が簡単なため、最新の情報を反映しやすいこともメリットです。クラウド型のeラーニングでは、保険料率や法令といった毎年のように改正されるものを自動的にアップデートしてくれるサービスも提供されています。
学習内容の質を一定に保てる
集合研修では、講師の能力や教え方との相性が受講者の習熟度に影響します。そのため、講師によって質にばらつきが生じたり、「わかりにくい」という感想が多くなったりすることもあり得ます。eラーニングは教え方によるばらつきがないため、一定の質を保てます。組織内の知識レベルを標準化する上でも効果的です。
受講者側のメリット
場所を選ばずに学習できる
通信環境とパソコン・スマホ・タブレットなどの端末さえあれば、会場に行かなくても自宅やワークスペースで学習できます。移動中や隙間時間を利用した学習もできるため、自分のライフスタイルに合わせた柔軟な受講が可能です。集合研修と比べて移動の手間がないため、ストレスの軽減や業務効率化においてもメリットがあります。
自分のペースで学習できる
集合研修と違い、eラーニングはあらかじめ用意されたテキストや動画を視聴するので、基本的に受講する時間が限定されません。業務に合わせて自分でスケジュールを組める上に、受講期間内であれば「途中まで学習して、続きは明日」というように、学習ペースの調整もできます。また、聞き逃した部分や理解できなかった部分は繰り返して視聴できるので、理解を深める上でも効果的といえます。
映像や図解、イラスト、音声を活用できる
eラーニングでは、映像や図解、イラストなどの視覚を通して理解を促進する教材が多くあります。さらに音声による解説も加わり、文字のみの教材と比べて理解度を深めやすい点が特徴です。キャラクターを登場させたり、ストーリー仕立てにしたりするなど、飽きずに学習を続けられるように工夫しやすい点もメリットの一つです。
フィードバックを受けられる
フィードバックによって、疑問点の解消や改善点の把握がすぐにできるため、短期間で習熟度を高めることが可能です。対面研修では「ほかの受講者もいるから」と質問できなかったケースも想定できますが、eラーニングでのフィードバックはクローズドな場で個別に対応してもらえるため、誰でも不安なく利用できます。
3. eラーニングのデメリット

企業側のデメリット
配信・管理するためのシステムが必要
eラーニングを導入するには、配信・管理するためのシステムや受講するためのデバイス(パソコンやタブレットなど)が必要です。eラーニングの受講環境は基本的に企業側で整える必要があるため、従業員が端末を持っていない場合、一定の初期費用が発生することは避けられません。eラーニングシステムを管理するためのスキルや知識を身に付けてもらうために、担当者への教育が必要になる場合もあります。
教材制作に専門性や技術が必要な場合がある
教材を自社で制作する場合、「構成はどうするのか」「動画制作はどうするのか」といったことを自分たちで考えて編集しなければならないため、負担が大きくなります。また、制作した教材に不備や変更が生じた場合も、自分たちで修正しなければなりません。教材作成を担当する社員の育成にも、手間やコストがかかります。
フォロー不足による受講者の学習意欲や理解度の低下
eラーニングでは、対面研修のように、受講者の様子を確認しながらリアルタイムでフォローすることが難しいため、学習意欲が低下してしまうことがあります。また、集合研修のように講師が目の前にいないこと、聞き逃しても視聴し直せることなどにより、集中力が緩んでしまい、理解が進まないケースも考えられます。学習意欲や理解度を高めるには、十分なフォローが必要です。
学習者側のデメリット
リアルタイムの交流ができずモチベーションを保ちづらい
eラーニングでは周囲に講師や受講者がいないため、対面研修のような緊張感が生まれず、モチベーションを保てなくなるケースがあります。リアルな会話がなく一方的に話を聞いているだけでは、学習に飽きてしまうことも懸念されます。また、リアルタイムで交流できないことから「学習して終わり」となってしまい、インプットした内容を実践に十分に生かせない可能性もあります。
体験を伴う研修ができない
eラーニングは、パソコンやタブレット、スマートフォンを用いた一方通行型の学習になりがちで、実技を伴う体験型の研修が難しい側面があります。ほかの受講者とリアルタイムでつながれないため、グループワークの実施も難しいといえます。ただし、近年はVR(仮想現実)を活用したeラーニングが増えているなど、体験学習を可能にしているサービスも提供されています。
通信環境の整備が必要
eラーニングでは、安定して受講できる通信環境の整備が不可欠です。そのため、社員側も通信環境を整備する負担が生じます。例えば、自宅での学習を想定している場合、自宅のWi-Fi環境を整えることが必要です。フォローの例として、携帯型Wi-Fi端末の貸し出しや、マニュアルの用意が挙げられます。
4. eラーニングの導入に必要な「LMS」
eラーニングを導入するためには、教材以外にも「LMS(学習管理システム)」を準備する必要があります。LMSはLearning Management Systemの略であり、eラーニングの配信や情報を一元的に管理できる学習管理システムを指します。eラーニングでの学習を進めるに当たっては、インターネットを通じて教材(コンテンツ)を配信する学習管理システム(LMS)が必要です。
LMSの主な役割は、受講者の学習状況と教材の管理です。テストの実施やフィードバック、結果データの集計・蓄積など、システムによってさまざまな機能が備わっています。LMSで管理する情報を活用すれば、自社の課題改善や育成の効率化も可能です。
5. eラーニングを社内に浸透させる方法

eラーニングを導入しても活用されず、放置されてしまうケースがあります。eラーニングを活用してもらうには、社員の実際の声を収集するなどして受講が進まない理由を明らかにし、改善していくアプローチが必要です。
- 長時間で飽きてしまう
- 教材の内容が自社の業務や労働環境に合っていない
- 学習環境が整っていない
- 学習時間が労働時間としてカウントされない
- eラーニングを受ける意味がわからない
- 学んで終わりになっている
- 一人だとモチベーションを維持できない など
浸透させる施策例
隙間時間に学習できるデバイスを用意する
社員が効率的に学習を進められるよう、移動中や待機時間など、ちょっとした隙間時間に学習できるデバイスが必要です。企業側で端末を用意するか、従業員が持つ私用の端末を使うことも考えられます(※)。可能であればPCやタブレット、スマホなどのいずれでも学習できるようにすれば、さらに柔軟に学習できます。
※私用の端末を使う場合は、セキュリティーに注意が必要です。
学んだことを共有・実践できる場をつくる
「学習したら終わり」ではなく、学んだ内容を共有・実践できる機会をつくることで、eラーニングの効果が組織内に展開されます。テストやレポートの提出などは、その一環です。各自が学んだことの発表会や、学習内容と関連付けたグループワークを開催する方法もあります。
「誰に何を受けさせるのか」「なぜ受けてもらうのか」を明確にする
eラーニングを受ける理由がわからないと、従業員にとっては学習の手間が増えるだけになってしまいます。受講対象者と学習内容、実施の目的を明確に周知することで、これらを基に従業員とコミュニケーションを取ることも可能です。企業での学びに何を望むのかを確認し、改善につなげることもできます。
「評価と連動させるかどうか」を決めて、明確に周知します。評価と連動させることで学習に対するモチベーションを高められる効果が期待できますが、一方でプレッシャーになる可能性もあるため、連動させるかどうかは企業次第です。明確にしないことは、従業員からの不信につながります。
受講者同士のコミュニケーションが取れる環境を用意する
一人ではモチベーションを維持できない人のために、受講者同士でコミュニケーションを取れる場を用意するのも一つの方法です。社員同士が交流しながらモチベーションを維持できるようになれば、社内の良好な人間関係の構築にもつながります。
アンケートを取り改善に生かす
eラーニングを浸透させるためには、まず社員目線での課題を把握する必要があります。受講者にアンケートを取り、eラーニング運用の改善に生かすことも社内への浸透に効果的です。アンケートの質問方法として、先述の「社員が実施しない理由」を想定しながら、eラーニングが続かない理由を選択方式で聞いていくことが考えられます。
企業の成功事例
eラーニングを社内に浸透させる上では、特にナレッジマネジメントが重要です。個人が学習した内容が共有・展開されることで、これまで組織になかった新たな知識が生み出されるきっかけになることもあります。
例えば、ライオン株式会社では、新たな学びの仕組みとして「ライオン・キャリアビレッジ」を実施し、その一環としてeラーニングを導入しました。
【ライオン株式会社の事例】eラーニングは、個人で学習を進める流れが一般的であるため、企業側のフォローがないとインプット作業で終わってしまいがちです。ナレッジマネジメントを念頭に置くことで、より実践的な力が身に付くといえます。
6. 自社に適したeラーニングシステムを選ぶポイント
eラーニングにはさまざまな機能や教材があるため、社員の成長につなげるには、自社に適したeラーニングシステムの導入が重要です。自社に最適なeラーニングシステムを選ぶために押さえるべきポイントは、下記のとおりです。
- 導入目的を明確にし、必要な機能を洗い出す
- 現状の課題に加え、中長期的な目標も踏まえて必要な機能を検討する
- 使用イメージを明確にする(デバイスやターゲットなど)
- 自社の社員にとって使いやすいかどうかに注目する
- コストや機能、保証期間などを項目ごとに比較する
- 自社で制作することも検討する
eラーニングシステムの導入には一定の費用がかかる上、情報を蓄積していくため、一度導入したら簡単には変更できません。導入するeラーニングシステムは、ポイントを踏まえて慎重に検討することが大事です。
コンプライアンス、CSR関連のeラーニングサービス
コンプライアンスに対するメディアの目は厳しくなる一方であり、従業員に対する教育が必要です。eラーニングは教育手法の中でも効果的といわれます。

コンプライアンス、CSR関連eラーニングサービスの現状と傾向|日本の人事部
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント