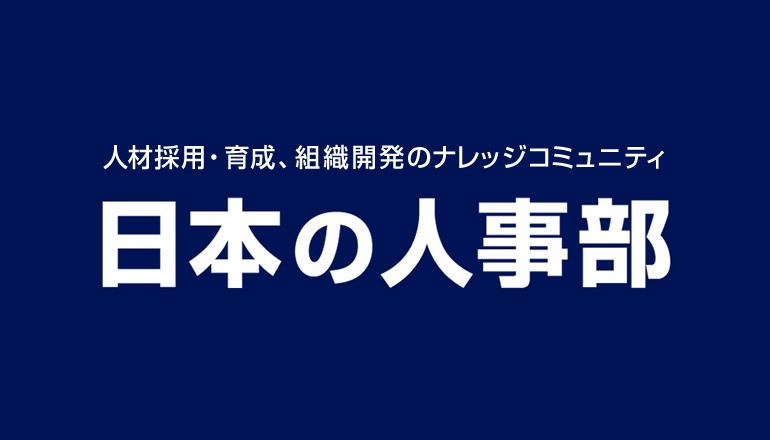「退職届」「退職願」の法的整理と撤回等をめぐるトラブル予防策
弁護士(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)
岩出誠氏
(この記事は、『ビジネスガイド 2009年6月号』に掲載されたものです。)
1 昨今の世界同時不況による影響
最近、転職のために労働者が在職中の会社に退職届を提出した後、転職希望先の業績悪化等の理由により、「退職届を撤回したい」と申し出てくることがあります。
退職届には、後でご説明するように、撤回が認められない場合と一定の条件の下で撤回が認められる場合があります。しかし、人事労務の現場において、退職届に関する正確な知識がないために、人事諸規程・書式等の制度上も対応ができていない場合があり、退職届の撤回をめぐり混乱が生じたり労使紛争に発展したりするケースも少なくありません。
特に、昨今の世界同時不況下においては、希望退職制度の実施の中で、あるいは、その後に実施されることの多い退職勧奨を受けた後に労働者から提出された退職届が、強要・脅迫・錯誤等を理由として、取り消されたり、無効とされたりする場合も少なくありません。
そこで、本稿では、以上のような退職届をめぐる問題の法的論点を整理したうえで(法的論点については、拙編著『論点・争点 現代実務労働法』改訂増補版〔民事法研究会〕665頁以下、714頁以下参照)、その論点を踏まえて企業が留意すべきポイントと関係書式の一例を紹介することにします。
2 労働契約の合意解約の申込みとしての退職届
(1)退職届の法的性質、「退職届」と「退職願」の異同

まず、一般の退職届は、一方的な労働契約の解約ではなく、会社に対する労働契約の合意解約に関する申込みの意思表示であると考えられ、会社の承認(承諾)がなされるまでの間は撤回が可能であると考えられています(昭和自動車事件・福岡高判昭53.8.9労判318号61頁、白頭学院事件・大阪地判平成9.8.29労判725号40頁)。そうすると、どのような場合に退職届に対する会社の承認があったとされることになるのかが問題となります。
この点について、大隈鉄工所事件(最三小判最判昭62.9.18労判504号6頁)は、次のような判断により、人事部長による退職願の受理を承認の意思表示と認め、すでに、労働契約の合意解約が成立しているとして、労働者による撤回を認めませんでした。
つまり、「私企業における労働者からの雇用契約の合意解約申込に対する使用者の承諾の意思表示は、就業規則等に特段の定めがない限り、辞令書の交付等一定の方式によらなければならないというものではな」く、会社の職務権限規程によれば「人事部長の固有職務権限として、課次長待遇以上の者を除く従業員の退職願に対する承認は、社長、副社長、専務、関係取締役との事前協議を経ることなく、人事部長が単独でこれを決定し得ることを認めた規定」があり、人事部長には「退職願に対する退職承認の決定権があれば人事部長が退職願を受理したことをもって雇用契約の解約申込に対する会社の即時承諾の意思表示がされたものというべく、これによって雇用契約の合意解約が成立したものと解するのがむしろ当然である」としたのです。
なお、企業社会では、「退職届」と「退職願」という2つの形式があります。一見すると、退職届が一方的な解約告知であり、退職願が解約の申込みであると、単純に区分できるようにも見えます。しかし、法的にはそう単純ではなく、確かに退職願は解約告知と解される可能性は低いでしょうが、退職願の中でもあるものについては、そして、少なくとも退職届については、実態的に判断がなされ、「解約告知」か「合意解約の申込み」かを判断されることになることにご留意ください。
(2)「退職届の受理権限の有無」が決め手
結局、退職届を受け取った者が、退職の受理(退職の承認)の権限を持つかどうか、そしてそれを正式に(いわゆる「預り」ではなく)受け取ったかどうかが決め手となるわけです。
例えば、上記大隈鉄工所事件最高裁判決後においても、常務取締役観光部長には単独で退職承認を行う権限はなかったとして、常務による退職願の受理の翌日になされた退職願の撤回が有効と認められた裁判例も出ています(岡山電気事件・岡山地判平3.11.19労判613号70頁)。
(3)「退職届提出後の時間の経過等」の意味

なお、退職届の撤回が認められるかどうかの要素として、退職願提出後の時間の経過等が大きな意味を持つでしょう。なぜなら、相当期間経過後に退職届が撤回されたりすれば、会社としても後任者の手配などを済ませた後であるといったケースもあり、玉突き的な影響を関係各所に及ぼし、経営上重大な支障が出るおそれがあるからです。
裁判例でも、本人の都合で退職の発令を延期した後の撤回のように、合意解約の撤回が使用者に不測の損害を与えるなど信義に反する事情があるときは、一方的な撤回は認められないとした例があり、注目されます(佐土原町土地改良区事件・宮崎地判昭61.2.24労判492号109頁、土田道夫「労働契約法」〔有斐閣〕562頁参照)。
(4)「合意書面の存在」の必要性
なお、最近のフリービット事件(東京地判平19.2.28 労判948号90頁)では、労働者が、他職員への引継ぎや就職活動を行っている行動状況から、労働者と会社との間で退職する旨の合意が成立しているとみることもできるが、正式な退職に関する書面等が交わされておらず、労働者が当該退職合意の存在を否定している以上、労働者と会社との間における合意退職の存在の主張には理由がないとされており、労働契約の合意解約としての退職の効果が争われないためには、一定の書面が必要と考えるべきです。
同様に、書面の存否が決め手になったのが、ピー・アンド・ジー明石工場事件(大阪高判平16.3.30 労判872号24頁)です。ここでは、特別優遇措置による退職者募集に応じて退職申出書を提出した者につき、「特別優遇措置による退職者希望受付について」と題する書面における募集受付方法欄に記載された「合意書」が作成されるまでは退職の受付は完了していないとされ、退職者募集に応じて退職申出書を提出したが「合意書」を作成する前に退職申出を撤回しているとして合意解約の成立が否定され、成立を肯定した原決定が取り消されています。希望退職に応じた労働者による退職願の撤回を認めた事例であり、合意書の成立を重視している点で実務上留意すべきです。
同様の判断は、労働契約法4条2項における「労働者及び使用者は、労働契約の内容について、できる限り書面により確認するものとする。」との労働契約の内容の書面化義務の観点から、今後ますます多くなるものと予想されます。
3 労働契約の一方的な解約告知としての退職届(辞職)

2で述べた通り、一般の「退職届」は、労働契約の合意解約の申込みと解されていますが、労働契約の一方的な解約告知と解される場合もあります。
また、「退職願」においても、例外的に、それが会社の都合などまったく関係なく、退職願に記載された退職日付に「なりふり構わず退職する」という労働者側の強引な態度がみてとれる場合等も、労働者による一方的な解約とされます。
このような労働契約の一方的な解約告知と解されるケースでは、就業規則に特別な定めのない限り、通常は民法627条1項等に従い、2週間前などの必要な所定の予告期間をおけば労働契約は終了することになります。そして、解約告知により、確定的に、告知された時点での労働契約は終了する関係が成立し、この退職届(退職願)の撤回は認められません。
4 退職時の状況によって異なる退職届の効力
(1)提出時の状況により退職が無効となることも
次に、退職届の性質が、合意解約であれ解約告知であれ、撤回が認められない場合であっても、退職時の状況によっては、その意思表示たる合意解約や解約告知に「錯誤」(民法95条)や「強迫・詐欺」(同法96条)等の瑕疵があるとして、無効や取消事由に当たるとされることがあります。特に昨今、リストラや懲戒解雇事由がある場合の退職勧奨等の場面において問題となることが少なくありません。
(2)強要や錯誤等を理由に無効とされた例
裁判例では、例えば、バス会社の営業所長が入社後間もない未成年の女子従業員に対し、同女の男子従業員との情交が懲戒解雇事由に当たるとして強迫により退職届を提出させた行為が取り消し得べきものとされ、精神的自由と人格権を侵害したとして慰謝料が認められたケース(石見交通事件・松江地益田支判昭44.11.18労民20巻6号1527頁)、使用者が、客観的に相当な理由がないもかかわらず、従業員への懲戒解雇や刑事告訴の可能性を告知して従業員から退職届を提出させることは、従業員を畏怖させるに足りる強迫行為として取り消し得るとされたケース(ニシムラ事件・大阪地判昭61.10.17労判486号83頁)等があります(その他、近時、強迫を理由に退職の意思表示の取消しを認めた例として白頭学院事件・大阪地判平9.8.29労判725号40頁、認めなかった例として東洋情報システム事件・大阪地判平10.3.25労判748号154頁等)。
また、最近のジョナサン他1社事件(大阪地判平18.10.26 労判932号39頁)では、裁判所は次のように判断しています。
【判決要旨】
使用者が、幹部職員が集まるミーティングにおいて、従業員を全員解雇する旨告げた際、特段の異論が出なかったことをもって退職合意があったと認めることはできず、その後の退職金に関する紛糾をみても、上記ミーティングの時点で、退職についての十分な条件が提示されたような事情はまったく窺えず、原告らが退職に合意するような状況にあったとは言い難いとされ、旧店舗の閉店が偽装であるというためには、閉鎖の時点で、すでに新店舗の開店を計画していたことが必要十分とされ、使用者は、銀行からの多額の入金が予想されたことから、旧店舗を一気にリニューアルし、かつ、人件費の削減を実施するために、新店舗の開店計画を秘したまま、全従業員を解雇したうえ、旧店舗を閉店したものと認められ、本件解雇は、新店舗の開店計画を秘したまま、旧店舗の閉店を理由に、原告らを含む全従業員を解雇したものであって、それ自体で、解雇権を濫用したもので無効であり、仮に、当時、旧店舗の経営状態から、一定程度の人員を削減するための整理解雇の必要性が存したとしても、上記の事情が認められる限り、整理解雇を認めることはできないとされ、仮に、退職合意があったとしても、本件退職合意の意思表示は、詐欺を理由とする取消しにより無効、もしくは、要素の錯誤により無効とされたうえ、本件解雇の方法は、長年就労してきた従業員に対し、虚偽の事実を告げて、一方的に解雇するという方法であり、解雇権の濫用の程度は悪質といわなければならず、後日、被告2社による新店舗の開店を知った原告らの驚きと憤懣は容易に想像でき、大きな精神的苦痛を被ったとして、慰謝料(30~50万円)の支払いを命じる。
新店舗開設計画を秘匿して解雇、退職合意をなした行為が解雇・合意無効にとどまらず、解雇が不法行為として慰謝料まで認容された珍しい事例で、企業のリストラ時の誠実な説明責任が問われたものとも解されます。同様の判断は、労働契約法4条1項の「使用者は、労働者に提示する労働条件及び労働契約の内容について、労働者の理解を深めるようにするものとする。」との労働契約の内容の理解の促進義務の観点から、今後ますます多くなるものと予想されます。
(3)心理留保を理由に無効とされた例
さらに、労働者が退職届を提出したのは、反省の意を強調する意味であり、実際には退職する意思を有しておらず、上司も同人に退職の意思がないことを知っており、退職の意思表示が心裡留保(民法93条)により無効とされたケース(昭和女子大事件・東京地決平4.2.26労判610号72頁)があります。
(4)退職届が有効とされた例
参考までに、退職届の有効性が争われ、有効と判断された近時の裁判例を紹介しておきます。
まず、積水化学工業事件(大阪地判平16.3.12労判873号91頁)は、会社を退職した元従業員が、退職の意思表示は上司らによる退職強要によるものであり、実質的には解雇であり、当該解雇は合理的な理由がないから無効である、あるいは退職の意思表示には瑕疵があり、無効または取り消しうべきものであると主張して、会社に対し労働契約上の権利を有する地位にあることの確認および未払い賃金の支払いを求めたものですが、元従業員は、会社に対して退職の意思を明らかにしたうえで、自らの意思で退職願を作成してこれを提出し、また、自ら退職する意思で退職メモを作成してこれを会社に提出し、その後、元従業員である原告の意思に沿った形で退職の手続きが進められたのであることから、退職の意思表示を解雇と同視することはできず、退職の意思表示に瑕疵もないとして労働契約上の地位確認請求を棄却しています。

次に、日本旅行事件(東京地判平19.12.14 労経速1990-23・労判954号92頁)では、役職定年後、移籍に応じない場合には退職せざるを得ないと誤信して退職届を提出した原告の錯誤無効の主張につき、会社の役職定年制においては、管理職が55歳に達したとしても、会社の提示する移籍先への移籍に応ずるか、プロフェッショナル職としてとどまるかを選択することができるところ、会社がことさらに原告を役職定年に達して移籍に応じない場合には退職せざるを得ないものと誤信させたということはできないし、原告が誤信したことは、自らが退職するという効果意思と表示行為との間に不一致があったというものではなく、退職届を提出する必要がある場合か否かについての錯誤であるから、動機の錯誤にとどまるというべきで、これが要素の錯誤にあたるためには、そのことが表示されたことを要するところ、退職の動機が役職定年により移籍を拒否するからである旨黙示に表示したものとみる余地もあるが、就業規則には、定年が60歳に達した月の末日である旨が明記されていること等からすると、原告が錯誤により退職の意思表示をしたことについては重大な過失があったものと言わざるを得ず、原告が退職の意思表示につき無効を主張することはできない、とされています。
実際上、かかる慣行がある企業は少なくなく、実務的には留意すべき事例でしょう。
5 退職届の撤回に関する実務上の留意点
人事労務管理の実務では、退職届受理後の撤回について、当事者間の合意があれば実際に行われているものと思われます。特に、2(3)で述べたように、退職願を提出して時間的経過もそれほどなく人事異動上の支障も少ない場合で、当該労働者が優秀な人材であり会社が慰留していた場合などには撤回を認めることも許されるでしょう。しかし、その場合には、退職勧奨による退職届提出等のケースにおいても、届出直後の撤回を認めざるを得なくなる事実上のリスクが高くなることを覚悟すべきです。
また、これとは異なり、時間的な経過により撤回を認めることが人事異動上の支障をもたらす危険のある場合には、認めるべきではないでしょう。
6 退職届の撤回をめぐる紛争の予防策

裁判例からもわかる通り、退職届の取扱いに関する社内ルール、管理職の職務権限などを明確にしておくことがどうしても必要となります。また、単なる「預り」ではなく、正式な受理・承認であることの記録を残すためにも、日付入りの受理・決裁印や退職者への受取り通知、その受領印を取っておくことなど、基本的には、合意解約の意思表示が文書などの記録によって証拠固めできるような体制を整えておくことが必要です。
なお、「退職届の提出は会社の強要によるものだ」などと後々言われないためには、相手のパーソナリティーに応じ、退職願の受取りの際に立会人をつけたり、慰留の際には当該労働者の固辞の様子をテープ等に残しておいたりする必要も出てきます。
例えば、退職慰留や勧奨の際の退職金の額の説明が間違っていたりすると、「退職の前提事項への錯誤があった」などという撤回の根拠を労働者に与えることにもなりかねません。
7 紛争回避のための書式例
最後に、退職届撤回をめぐる紛争回避のための退職届の書式例を挙げて、留意点を再確認しておきます。
書式例

いわで・まこと● 弁護士。ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー。元厚生労働省労働政策審議会労働条件分科会公益代表委員。千葉大学大学院専門法務研究科(法科大学院)客員教授,青山学院大学客員教授,同大学院ビジネス法務専攻講師,首都大学東京法科大学院講師。
この記事を読んだ人におすすめ

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント