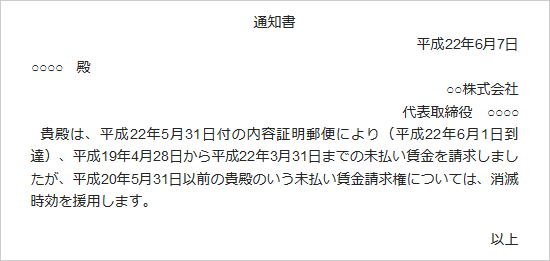未払い残業代に関する「時効」の知識と実務的留意点
弁護士 向井 蘭・岸田 鑑彦/狩野・岡・向井法律事務所
1 未払い残業代債権の時効の重要性
労働者の権利意識の高まり、労働基準法改正による1ヵ月60時間を超える残業時間に対する割増賃金率の引上げ等、今日、「未払い残業代請求」が1つのトピックとなっています。
そういった中で、過去の未払い残業代請求と労基法115条の2年間の消滅時効との関係が問題となってきます。すなわち、未払い残業代請求権も、賃金の一部未払い分の請求権であり、賃金請求権ですから、原則は2年間の消滅時効にかかります。
しかし、未払い残業代については、会社との雇用契約関係があるうちは、なかなか請求しにくいといった事情もあり、おのずと、退職後ないしは退職間際になって請求されるケースがあり、従業員側にとっては、過去の数年にわたる残業代を請求する場合には、この「2年間の消滅時効」が1つの壁となっています。
一方、消滅時効については時効の中断という制度があり、時効の中断が認められた場合は、消滅時効の進行が止まる場合もあります。
ただ、「いかなる場合に時効の中断が認められるか」についての法的基準は必ずしも明確ではなく、会社が従業員との交渉などにおいてうっかり時効の中断にあたる行為を行ってしまう場合も散見されます。
以下では、実際の裁判例をもとに、未払い残業代と消滅時効の関係について見ていきたいと思います。
2 消滅時効の期間 ─2年間とは限らない─

上記の通り、未払い残業代請求権も、賃金の一部未払い分の請求権であり、賃金請求権ですから、原則は2年間の消滅時効にかかります。しかし、これまでの裁判例の中には、他の法律構成を取ることにより、2年間以上の未払い残業代の請求が認められたものもあります。
このケースは、残業代を支払わずに従業員に長時間労働させたことなどを理由にして、すでに時効で消滅した期間の残業代と慰謝料を請求した事案です(杉本商事事件・広島高裁平成19年9月4日、労判判例952号33頁)。
(元)従業員側が時効で消滅した期間の残業代をも請求することは稀です。ほとんどの訴訟事件では、最初から請求期間を過去2年間に限定して、2年間の未払い残業代の請求しか行いません。
不法行為の場合、時効は、被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時から3年間(時効)、不法行為の時から20年(除斥期間)となります(民法724条)。
また、時効の起算点は、損害および加害者を知った時から3年ということですから、損害つまり自分に未払い残業代があり、会社に対して請求ができると認識した時ということになり、時効の起算点を、より現在に近付ける解釈も成り立つところです。
この点、この裁判例は、管理者が、部下職員の勤務時間を把握し、時間外勤務について法所定の割増賃金請求手続を行わせるべき義務に違反したとして、不法行為に基づく損害賠償請求を認めました。つまり、2年間の時効期間でいえば消滅するはずの1年分の未払い残業代についても支払えと命じたのです。
この事案における判断は、会社が、長年、「自己啓発や個人都合である」という解釈に基づき一部残業代を支払わないという状態が常態化していたこと、原告が34年間同じ会社に勤務している間、会社が労働時間を把握することを怠っていたことなど、特殊な事情があり、他のすべての事案に当てはまるものではありません。しかし、会社が労働時間の把握を怠ったり、法律上認められがたい理由(難癖)を付けて残業代の支払いを行わなかったりする場合は、裁判所は、いわば会社に対するペナルティーとして3年間の未払い残業代の支払いを命じる可能性は今後もあります。
会社が長年にわたり、意図的に従業員の労働時間把握を怠った場合などは不法行為構成により消滅時効の期間が3年に延びることもありうる。
3 時効の「中断について」
まず、時効の中断について、確認します。
時効の中断も、停止とともに、時効の完成を阻止する制度ですが、中断となる事実が生じると、その時までに進行してきた時効の進行が中断し、中断事由がなくなれば、再びその時点から時効が進行を開始します。中断によって、時効期間が一度途切れますので、その後の時効の進行はゼロからスタートすることになります。
民法上、時効の中断事由は、147条に規定されています。
1号 請求
2号 差押え、仮差押えまたは仮処分
3号 承認
これらの事由が生じれば、その中断事由が生じた当事者およびその承継人の間で、中断の効力を有することとなります(民法148条)。
未払い残業代の支払いという観点から見ると、147条1号の請求、同3号の承認の有無が争われることが多く、問題となるところですから、本稿では「請求」と「承認」について見ていき、請求に付随して問題となる、時効中断の予備的措置である「催告」についても触れたいと思います。
(1) 「請求」について
民法147条1号の「請求」とは、権利者が、時効によって利益を得る者に対して、その権利内容を主張する裁判上および裁判外の行為を総称したものです。
代表的なものとしては、裁判上の請求(民法149条)、催告(民法153条)が挙げられますので、各々検討します。
1 裁判上の請求(民法149条)
裁判上の請求とは、訴えを提起することです。「未払い残業代を支払え」という給付訴訟を起こすことにより消滅時効が中断します。中断時期は訴状が被告に届いたときではなく、訴状を裁判所に提出したときに中断の効力が生じます。
2 催告(民法153条)

催告とは、債務者に対して履行を請求する債権者の意思の通知を指します。
民法153条は「催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、……をしなければ、時効の中断の効力を生じない」と定めます。催告は、それ自体としては時効の完成を6ヵ月猶予するだけで、独立の中断事由ではありません。つまり従業員が会社に対して、「残業代を支払ってほしい」と書面や口頭で求めただけでは、時効は中断しません。これらは民法153条の催告であって、「中断」させるには6ヵ月以内に裁判上の請求等をする必要があります。
残業代の請求は、当然のことながら(元)従業員側が行います。(元)従業員側は、タイムカードなどの資料を有しないことが多く、金額や根拠を示さず単に概括的に「未払い残業代を請求する」とのみ記載して内容証明郵便で送る場合があります。
このような請求内容が民法153条の「催告」に当たるのでしょうか?「催告」に当たらない場合は、6ヵ月以内に訴訟を起こしても、訴訟を起こすまでに消滅時効は進むことになり未払い残業代の金額が大分減ってしまいます。
実務的には、次のような場合が考えられます。
――金額や根拠を示さない未払い残業代の請求について Aは、C社を退職後、B労働組合に加入し、在職中の残業代を、B労働組合を通じて請求したが、Aはタイムカードなどを有していなかった。そのため、AはC社に対し「賃金台帳、タイムカード、勤務表に基づいて、平成○年○月以降の時間外および深夜の割増賃金を支払うこと」と文書に記載して請求したが、請求金額やその内訳は明記しなかった。その後、会社が団体交渉において未払い残業代の存在を否定したため、Aは未払い残業代を請求する訴訟を提起した。訴訟において、C社は、労働組合を通じた従業員Aの上記請求は「民法153条の『催告』には当たらない」と主張した。
同様の事案では、裁判所は以下の通り判断しています(日本セキュリティシステム事件・長野地裁佐久支部平成11年7月14日判決、労働判例770号98頁)。
金額や根拠を示さない未払い残業代の(裁判外の)請求も時効中断事由の「催告」に当たる。
(2) 「承認」について
時効中断事由たる「承認」とは、時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利の存在することを知っている旨を表示することです。未払い残業代の一部支払いなどがこれに当たります。
実務上問題となるのが、<事例2>のような交渉段階における会社側の回答です。会社側が意図しなくとも、会社側の対応が消滅時効中断事由にいう「承認」に当たる場合があります。
DがE社を退職後、Fユニオンに加入した。E社とFユニオンは、在職中の業務推進手当がいわゆる残業代として支払ったものであるかどうか団体交渉において争った。E社は「Aが時間外労働を行ったことは認めるが、業務推進手当は残業代として支払ったものであるから、未払い残業代はない」と主張し、Fユニオンとの交渉は並行線をたどった。Dは未払い残業代を請求する訴訟を提起したところ、E社はすでに一部の未払い残業代は消滅時効にかかったと主張し、会社の団体交渉での受け答えが消滅時効中断事由の承認に当たるかが問題となった。
オンテック・サカイ創建事件(名古屋地裁平成17年8月5日判決、労働判例902号72頁)によれば、団体交渉出席者の団体交渉での対応について、「原告本人によっても、被告らが法定時間外労働時間に対する未払い債務が存在することを団体交渉の場等において承認していたと認めることはできず、他に被告らによる債務承認の事実を認めるに足りる証拠はない」として、会社が時間外労働の存在を認めるだけで、未払い残業代の存在を否定した場合、会社の回答は時効中断事由たる「承認」には当たらないと判断しました。
従業員側と会社が交渉した場合、会社が時間外労働の存在を認めても未払い残業代の存在を認めなければ、時効中断事由たる「承認」には当たらない。
(事例2と同じ事案で)E社が「業務推進手当を残業代として支払ったことについて譲るつもりはないが、話合いで解決するために○万円の解決金を提示したい」と述べたが、結局話合いは不調に終わり、Dは未払い残業代を請求する訴訟を起こした。E社はすでに一部の未払い残業代は消滅時効にかかったと主張したところ、E社が団体交渉で解決金を提示したことが消滅時効中断事由の承認に当たるかが問題となった。
この事例のような裁判例は見当たりませんが、実務上はよくあると思われます。
交通事故の調停の席で、加害者が、持参した残額20万円くらいの預金通帳を提示して、「預金がこれくらいありますからこれでどうですか」と述べたことをもって、賠償額の具体的な提示は、時効の利益の放棄の意思表示となると判示したものがあります(大阪地裁判決昭和53年6月12日、判例時報906号77頁)。
一方で、交渉の席で当事者が解決のために譲歩することはよくあることであり、これらの譲歩すべてが時効の中断や時効の利益の放棄に当たるのであれば、誰も譲歩しなくなるのではないかとの反対意見もあるでしょう。
しかし、私見ですが、消滅時効中断事由の「承認」とは、時効の利益を受ける当事者が、時効によって権利を失う者に対して、その権利の存在することを知っている旨を表示することですので、解決金として○万円を提示したとはいえ、一定の未払い賃金の存在を前提として解決金を提示しているため、元従業員側が主張する未払い残業代全体について、消滅時効中断の「承認」をしたと言えるのではないかと考えます。

したがって、団体交渉において、会社が、元従業員が労働基準法上の管理監督者に当たるといい、未払い残業代の存在そのものを否定したとしても、団体交渉過程で未払い残業代の存在を前提として解決金を提示した場合は、その時点で時効中断事由たる「承認」があったと言えます。もっとも、もともと管理監督者であっても支払義務のある深夜労働についての割増賃金のみを支払うという場合は、深夜労働以外の未払い残業代については時効中断事由たる「承認」には当たらないと言えますが、「解決金として○万円を提示したい」と述べた場合は、時効中断事由たる「承認」にあたると言えます。
従業員側と会社が交渉した場合、会社が未払い残業代について解決金を提示したり、未払い残業代について減額交渉を行ったりした場合は、時効中断事由たる「承認」に当たる。
4 時効の援用について
時効は、当事者による援用がなければ、裁判所はこれによって裁判をすることができません(民法145条)。未払い残業代について2年間の消滅時効期間が経過しても、会社が「消滅時効を援用する」と述べなければ、未払い残業代は時効によって消滅しないのです。
従業員側は、まれに2年間を超える未払い残業代を訴訟外で請求する場合があります。このような場合は、会社は早期に時効を援用する旨主張しなければなりません。書式例としては下記「通知書」の通りです。
5 時効利益の放棄および信義則による時効援用の制限について
「承認」は時効完成の前にだけできるもので、時効完成の後は「時効の利益の放棄」が問題となります。一見すると、会社が時効利益の放棄などすることはないように思われますが、実務上はそうではありません。未払い残業代の請求の場面でも問題となります。
元従業員GがH社を退職後、入社から退職までの未払い残業代を支払えとの内容証明郵便を送付してきた。Gは約3年前にH社に入社したため、すでに入社から1年分の未払い残業代は消滅時効にかかっていた。しかし、H社社長は、時効制度のことを知らずにGに対し、内容証明郵便で「すべてを支払う金はないが、分割払いなら応じることができる」旨回答した。Gは弁護士に依頼して未払い残業代を請求する訴訟を起こした。その訴訟の中でH社代理人は、「従業員Gの未払い残業代債権はすでに一部2年を経過しているため、消滅時効を援用する」と主張した。ところが、Gの代理人は「時効完成後に債務を承認したのであるから、Gはもはや時効を援用しないとの期待を抱くため、信義則上、その債務について時効を援用することは許されない」と主張した。H社社長は、すでに2年経過しているのに時効を援用できなくなるのはおかしいと考えている。H社社長は未払い残業代債権について消滅時効を援用できるか?

時効の利益の放棄は、放棄される権利の存在を知っていなければなりません。しかし、時効が完成していれば、債務者は時効援用により債務を免れますので、通常は損をしたくないために時効の利益を放棄しません。最高裁(請求異議事件・昭和41年4月20日判決、民集20巻4号702頁)は、時効完成後の債務承認について、「時効が完成したのちに債務の承認をする場合には、その時効完成の事実を知っているのはむしろ異例で、知らないのが通常であるといえるから、(中略)消滅時効完成後に当該債務の承認をした事実から右承認は時効が完成したことを知ってされたものであると推定することは許されない」と判断しつつ、時効完成後に債務を承認する行為があった場合は、相手方も債務者はもはや時効を援用しないとの期待を抱くから、信義則上、その債務について時効を援用することは許されないと判断しました。
設例の事例では、H社社長が「すべてを支払う金はないが、分割払いなら応じることができる」旨回答したため、Gは「もうH社は消滅時効を援用しない」のだと信用することになり、その期待を保護するために、H社の消滅時効を認めない、すなわち入社から退職までのすべての期間の残業代について未払い残業代を支払わなければならないという結論になります。
通常、代理人たる弁護士や労働組合を通じて未払い残業代を請求する場合は、多くはあらかじめ2年分に限定して請求を行いますが、従業員本人が未払い残業代を請求する場合などは、特に制限を設けず請求する場合があります。このような場合に、うっかり消滅時効を援用せず、未払い残業代の減額交渉などを始めると後々消滅時効が援用できなくなりますので、注意が必要です。
未払い残業代の支払いを求める文書が届いた場合は、まず2年前のものが含まれているかどうかをチェックし、2年以上前のものが含まれていた場合は消滅時効を援用する。
6 権利濫用について
元従業員IがK社を退職後、労働組合Jに加入し、在職中の未払い残業代を請求した。ただし、Iはタイムカードを有していなかったため、併せて、元従業員は労働組合Jを通じて、タイムカードを提出するよう求めた。しかし、K社は団体交渉に応じたものの、「Iは自発的に作業をしていただけで、残業を当社は命じていない。したがってタイムカードを提出する必要はない」と主張し、まったく未払い残業代の存在は認めずタイムカードも提出しなかった。団体交渉では話しがまとまらず、労働組合Jは労働委員会にあっせんの申立てをした。しかし、K社はあっせんには出席したものの、タイムカードは提出せず同じ主張を繰り返した。Iは、訴訟を起こそうと決意したが、タイムカードがないため、労働時間の計算に時間がかかり提訴が遅れ、催告から6ヵ月が経過してしまった。そのため、K社は、「催告から6ヵ月が経過しているため、提訴から2年以前の未払い残業代については消滅時効を援用する」と主張した。K社の主張は認められるか?

形式的には上記の事例では消滅時効の援用が認められそうですが、K社はタイムカードを提出せず、そのため提訴が遅れたことからすれば、消滅時効の援用により未払い残業代が一部時効により消滅することは元従業員Iに酷であるように思えます。
少々事案は異なりますが、会社がタイムカードや賃金台帳を開示しなかったため、提訴が遅れたという事案で、裁判所が、会社側の不誠実な対応を理由に、会社の消滅時効援用は権利濫用に当たり許されないと判示したものがあります(日本セキュリティシステム事件・長野地裁佐久支部平成11年7月14日判決、労働判例770号98頁)。
このような事案は稀であると思われますが、会社が資料提供などで不誠実な態度を見せた場合は、いわばペナルティーとして、裁判所が消滅時効援用を認めないという可能性があります。
会社は資料提出などについて誠実に対応しない場合は、消滅時効の援用が認められない場合がある。

むかい・らん● 平成9年東北大学法学部卒業。平成13年司法試験合格。平成15年弁護士登録(第一東京弁護士会)。使用者側で労働事件を主に扱う事務所に所属(狩野・岡・向井法律事務所)。最近の執筆記事に、「労働組合対応時に陥りやすい誤り&正しい団体交渉ルールの定め方」(『ビジネスガイド』2008年9月号)、「『裁判員休暇制度』正しい考え方と導入時の留意点」(同2009年1月号)、「非正規雇用社員の『組合化』進行と団体交渉への企業対応」(同2009年4月号)、「ローパフォーマンス社員」対応の法律実務(同2010年8月号)。
◆ ホームページ: http://www.labor-management.net/
きしだ・あきひこ● 狩野・岡・向井法律事務所・弁護士。昭和57年鳥取県生まれ。平成17年慶應義塾大学法学部法律学科卒業。平成20年明治大学法科大学院卒業。平成20年新司法試験合格。平成21年弁護士登録(第一東京弁護士会所属)。経営法曹会議会員。

人事の専門メディアやシンクタンクが発表した調査・研究の中から、いま人事として知っておきたい情報をピックアップしました。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント