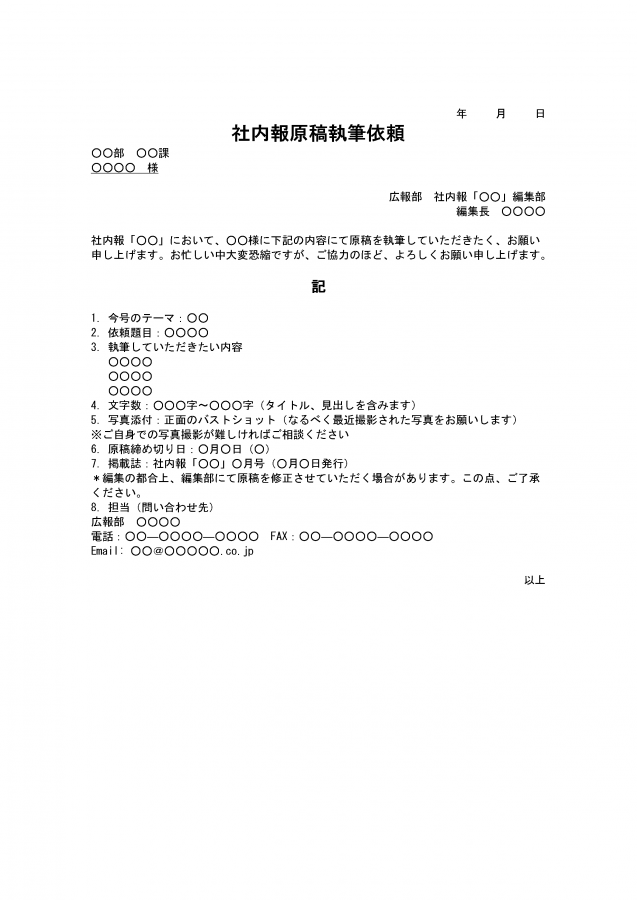組織開発・組織活性化
組織開発・組織活性化とは?
近年、人事関連分野の中で、組織開発・組織活性化というテーマが注目を集めています。組織開発とは、戦略や制度といった組織のハードな側面だけでなく、人や関係性といったソフトな側面に働きかけ、組織を変革するアプローチのこと。一方の組織活性化とは、組織本来の目的を構成員が共有し、主体的・自発的に協働しながら、達成しようとしている状態のことをいいます。
1.組織開発・組織活性化とは
組織開発の目的
組織開発(Organization Development)は多くの場合、ODという略称で呼ばれます。ODにはいろいろな定義がありますが、日本の組織開発研究の第一人者である南山大学人文学部の中村和彦教授は、「部署や部門間、組織全体の効果性と健全性を高めることを目的に、プロセスに気づき、働きかけていくアプローチ」としています。
日本企業は1970~80年代くらいまで、チームで働くことを得意としていました。ただし、当時は終身雇用の時代で、職場の仲間とは一生の付き合いであるという認識がありました。そのため、組織開発という概念は特に必要がありませんでした。
組織開発と似た言葉として、「人材開発」があります。人材開発は、企業や組織に所属する人材の能力・スキルを強化し、引き出すことを目的としています。それに対して組織開発は、人と組織の関係性が多様化していく中で、組織が環境に適合しながら変革し、効果的に機能するようにすることが目的です。日本では組織の力より個人の力を高めていくことを目的に、人材開発が長い間行われてきました。日本企業では研修が非常に多く、さまざまな研修を使って個人に働きかけるアプローチがメインだったため、人材開発とうまくマッチしたのです。
近年、組織開発が注目を集めるようになったのは、不確実性が増す中で企業がさまざまな問題に対処していくには、従来のような硬直的で閉鎖的な組織から弾力的で開放的な組織へ変革していかなければならない、との認識があったことが大きな理由の一つです。また、従業員の中に個人主義的な傾向が強まってきたこと、非正規社員や外国人、高齢者など雇用の多様化が進む中で、組織に対する帰属意識を醸成し、チームワークを重視する意識を高める必要性が出てきたことも、理由といえます。多くの企業が、肥大化した組織に活力を与えることで組織の体質を改善し、将来の環境変化に対応するための基盤を強化しています。
最近では、組織開発のコンサルや支援サービスを行う専門業者も数多く出て来ています。組織開発を大学院で学ぶビジネスパーソンが増えるなど、組織開発は一種のブームとなっているようです。

組織開発のプロセス
組織開発をどのように進めていくのかは、中村和彦教授の論文「組織開発の特徴とその必要性」の中で、「OD Map」というモデルを用いて説明されています。OD Mapでは、組織開発を以下の八つのフェーズに分けて進めていきますが、さまざまなデータに基づきながら、OD実践者と組織・部署の当事者が計画と実践を行い、協働的に取り組みを進めていくことが重要です。
【OD Map】
- エントリーと契約
組織開発を進めていくに当たり、まずOD実践者は組織・部署の当事者のニーズを的確に把握し、目的を確認します。そして、進め方やお互いの役割について合意を行います。 - データ収集
OD実践者はインタビュー、アセスメント、観察などによって、組織内のプロセスに関するデータ(問題)を収集します。 - データ分析
収集したデータを、診断モデルなどに基づいて整理・分析します。 - フィードバック
得られたデータ結果を、組織・部署の当事者にフィードバックします。ここでは組織・部署の当事者との対話を通じて、組織内のプロセスにおける気づきを促進します。 - アクション計画
フィードバックによってフォーカスされ、共有された組織内のプロセスを変革するためのアクションを計画します。 - アクション実施
計画されたアクションを適切に実行します。 - 評価
アクションを実施した後、合意された変革目的がどれくらい達成できたかを、さまざまな事例を通して評価します。 - 終結
評価によって、変革目的が達成されたと判断された場合、終結します。そして、また新たな組織開発に向けて、アクションを起こします。
組織活性化の狙い
企業として経営ビジョンを実現するためには、総合的な組織力の向上が不可欠です。その一つの方法として、組織活性化が注目されています。活性化している組織は、従業員一人ひとりが独立しているのではなく、組織として最大の力が引き出されています。「働く個人がモチベーション高く仕事に取り組んでいる」「個人プレーではなく、組織としてシナジー(相乗効果)が起きている」状態であることが必要です。
今日、組織活性化が求められるようになった背景には、経営環境を取り巻く大きな変化があります。その変化のスピードに対応するため、一人ひとりがバラバラで業務に当たるのではなく、情報を共有し、知恵を結集して、チームとして対応する必要性が高まっているのです。さらに、政府が力を入れている働き方改革の影響もあり、働く時間や働き方の異なる人たちの足並みを揃える必要性が出てきました。そこで、職場を活性化するためのさまざまな制度や施策、手法が取り入れられるようになりました。
職場を活性化する方法は数多くありますが、どれを取り入れれば正解、というものはありません。事業の特性や働く環境、仕事内容やそこで働く人たちによって異なります。だからこそ、それぞれの状況に適した制度・施策、手法を導入し、うまく行かない点は修正を施して、創意工夫しながら自社独自の取り組みに変えていくことが重要です。

2.組織形態の種類
組織形態(モデル)の種類とその特徴
組織の形態(モデル)には、さまざまな種類があります。以前は、大きく「機能別組織」と「事業部制組織」、あるいは「ピラミッド型組織」と「フラット型組織」といった一般的によく知られる組織が対比され、その機能・効用について比較・検討されてきました。しかし近年は、会社経営の根幹となる事業のあり方やビジネスモデルが大きく変化(統廃合)する中で、組織形態も事業を効率的に推進するために、より適した形へと進化しています。さらに、雇用形態の多様化に伴い、組織構成員の身分・立場が異なるようになってきたことも影響しています。以下、主要な組織形態の種類と特徴を挙げていきます。
| 機能別組織 | 生産・販売・開発など、経営機能ごとに部門を持つ組織。 |
| 事業部制組織 | 製品・市場・顧客などの区分により、自己完結的な部門を持つ組織。業績責任などを明確にしやすく、多くの大企業で採用されている組織。高度成長時代に、経営の多角化に伴って生じました。 |
| マトリクス組織 | 機能別組織と事業部制組織とをマトリクスにして、双方の弱点を補う組織。二重となる命令系統をどう調整するかが、問題点となっています。 |
| ピラミッド型組織 | ピラミッド型の階層構造となっている組織。指揮命令系統は一つで、指示は上から下へと降ります。そのため、組織メンバーは上意下達で、階層の上位の者からの指示命令に従って業務を行うことになります。 |
| フラット型組織 | 管理の最適化と組織メンバーの多能化を図るため、階層の中間層をできるだけ少なくした組織。一つのタスクや職務遂行グループが主たる権限を持ったリーダーの下で機能するため、意思決定が迅速になります。 |
| ネットワーク組織 | 公式に指示を出す階層組織を最低限とし、組織内部の相互連結構造を強化した組織。「蜘蛛の巣組織」とも呼ばれます。 |
| ドーナツ型組織 | ごく少数の経営決定機関のみを組織の中心に据え、同心円上に複数の事業ユニットや現業チームを配置した組織。 |
| モジュラー・コーポレーション組織 | 主力を知識集約度の高い業務に特化し、部品製造、物流、情報処理、経理などをモジュラー(購入可能な標準化されたユニット)として、専門企業にアウトソーシングする組織。 |
| バーチャル型組織 | 事業活動の速度を上げるために、相互にコアとなる事業を活用し合う組織(企業連合)。 |
| ポリ・エージェント組織 | エージェント(単位)が自律的に活動しながらも、他との協調を図る組織。エージェントが複数(ポリ)集合し、相互に影響し合い、学習・進化します。 |
| アド・ホクラシー組織 | 多くのスムーズに機能する創造的チームにより、エキスパートの能力を融合させた組織。臨機応変型組織とも呼ばれます。 |
| ハイパー・テキスト型組織 | 事業開発のためのプロジェクト、通常の事業部、知識創造のための仕組みの三つが独立し、相互に有効機能している組織。 |
3.組織開発・組織活性化の手法・アプローチ・制度
組織開発の観点から
組織開発は、1950年代の後半にグループ・ダイナミクス(集団力学)や行動開学の理論を入門とし、実際の経営に応用する中で生まれた考え方で、欧米企業を中心に発達してきました。日本ではやや遅れて、1970年代に入ってから組織開発を目指す企業が増えてきました。しかし、その多くは組織全体を対象としたものではなく、部分的な職場開発の域を出ていないのが実情でした。また、製造業の現場において広がった「QCサークルによる小集団活動」が組織開発の例として取り上げられることもありました。組織開発は、以下のような手法・アプローチ・制度を通じて実践されます。

| アクション・ラーニング | 数人のチームを結成し、実際に職場で起きている問題の解決策を検討し、実践する学習システム(アクション+ラーニング)です。個人とグループの分析力や実行力が向上すると同時に、職場の問題も解決するため、非常に効率の良い手法と言えます。 |
| ファミリー・トレーニング | 特定の階層を対象とした集合研修方式ではなく、一つの職場や部門単位で進める訓練方法。同一のテーマの研修を職場全員に実施することで、研修内容を実際に活用しやすくし、組織全体のレベル向上を図る方法です。 |
| 交流分析(TA:Transactional Analysis) | TAは、1950年代後半、精神科医エリック・バーンによって提唱された心理学パーソナリティ理論と技法として発展しました。自己洞察と他者の関わり合いの分析を通じて、対象者に気づきを与え、行動変容を促します。これにより、職場のコミュニケーションが活性化されることが期待されます。 |
| ナレッジ・マネジメント | 個人の知識・ノウハウ(暗黙知)を組織内で共有し、活用(形式知)する手法です。組織の問題解決能力や生産性が高まることが期待されています。また近年は、社内SNSなどのイントラネットを活用したものが導入されるようになっています。 |
| モチベーション向上施策 | 目標管理制度などの施策を導入し、従業員のモチベーションを高め、生き生きとした組織を構築します。 |
組織活性化の観点から
組織活性化を実現するには、どのような組織観、人間観をベースとして手法・アプローチ・制度を開発し、運営していくのかを明確に認識することが大切です。なぜなら、組織、人間に関する一定の「価値観」に基づいて整合的に開発されたものは、高いシナジー効果を期待でき、組織の活性化に大きく貢献するからです。ここでは成果の期待できる組織活性化の手法・アプローチ・制度を、コミュニケーション関連、チャレンジ関連、自己啓発関連に分けて紹介します。
| コミュニケーション関連 | スピークアップ制度:会社の方針や経営者に対する意見、疑問、不満などは、通常の対話の中では話しにくいものです。そうした問題を救い上げるチャネルとして、匿名性が保証された投書形式によるスピークアップ制度があります。 |
| 提案制度:職場を活性化させるには、従業員一人ひとりが仕事の効率化・改善について 真剣に考えることが必要です。そのために仕事の改善、コストダウン、消費者サービスの向上などの提案を出させ、優れたものを表彰する制度です。 |
|
| モラール・サーベイ:企業の組織・職場管理に対して、従業員がどういう点にどの程度満足し、またどんな問題意識を持っているのかを、科学的に調査分析する手法です。一般的に、「従業員意識調査」「従業員満足度調査」などと呼ばれています。 | |
| チャレンジ関連 | 自己啓発制度:従業員一人ひとりに、現在の仕事についての評価・満足度、今後の進路についての希望、担当したい仕事などを申告させ、それを配置転換、教育研修などに活かしていく制度です。 |
| 社内公募制度:新商品開発や新規事業の担当、新しい営業所の所長などに当たる者を広く社内から募集し、応募者の中から能力、意欲、計画性などから評価し、担当者を決定し、任命する制度です。 | |
| ジョブリクエスト制度:一定の勤続年数を経験し、自分の能力や会社全体の仕事を知っている従業員に限定して、仕事のリクエストを出してもらい、配置転換を行う制度です。 | |
| 自己啓発関連 | 自己啓発支援制度:従業員が自己啓発活動に取り組むことにより、能力開発が図られ、仕事に対する適応力が向上し、モチベーションが向上します。自己啓発支援制度は、「資格取得援助」「通信教育援助」「セミナー参加」など、金銭面、時間面などからバックアップする制度です。 |
| リフレッシュ休暇制度:リフレッシュ休暇は、勤続年数が比較的長くなった従業員に対して、一定日数の特別有給休暇を与え、心身のリフレッシュや自己啓発を図ってもらうことを目的とした制度です。 |
4.組織開発・組織活性化の理論
組織開発・組織活性化のカギを握る理論・考え方
ここでは、組織開発・組織活性化においてカギを握る重要な理論や考え方を紹介します。
- 【診断型組織開発・対話型組織開発】
- 「診断型組織開発」とは、1960年代から伝統的に継承されてきた組織開発の考え方(理論)。客観的に組織に関係するデータを把握し、その整理・分析に基づいた対話が組織変革にとって重要であるというものです。それに対して、近年注目されているのが「対話型組織開発」。対話型組織開発では、組織構成員による対話や交渉の「プロセス」が、組織の現実を構成していると捉えます。そのような観点から、今日における組織改革は、組織内の人々の「語り方」が変わることによって成し遂げられるとする、新たな組織開発に対するアプローチです。 対話型組織開発は、サイモンフレーザー大学ビジネススクール教授のジャルヴァース・ブッシュ(専門はリーダーシップ・組織開発)と、組織開発コンサルタントとして40年以上活躍しているロバート・マーシャクが、2009年に提唱した新しい組織開発の考え方です。以来、組織開発における「対話」の重要性とあり方が再認識され、各界から大きな支持と注目を集めており、マネジメントや組織活性化のあり方にも、大きな影響を与えています。
- 【X理論・Y理論】
- X理論は、人間は本来なまけたがる生き物で、責任を取りたがらず、放っておくと仕事をしなくなる、という考え方。一方のY理論は、人間は本来進んで働きたがる生き物で、自己実現のために自ら行動し、進んで問題解決をする、という考え方です。会社経営ではX理論に行きがちですが、これでは人や関係性が疲弊します。組織開発では、Y理論をベースに組織の人間的側面のマネジメントに取り組むことがとても重要です。
- 【マネジリアル・グリッド】
- マネジリアル・グリッドとは、1964年に米国の経営コンサルタントであるブレイクとムートンによって提唱された行動理論です。どのようなリーダーになっていくことが望ましいかを明確にして、その軸を評価に取り入れることは、リーダーの養成を通した組織開発において非常に重要です。伝統的な組織開発の「マネジリアル・グリッド」でも、管理者であるマネジャーに目指す方向を示し、評価の枠組みとなる軸が存在しています。マネジリアル・グリッドではリーダーシップの行動スタイルを「人間に対する関心」「業績に対する関心」の2軸に注目し、それぞれの軸を9段階に分け、81の格子(グリッド)に分け、典型的な五つのリーダーシップ(放任型、人情型、権力型、理想型、妥協型)に分類しています。
- 【AI(アプリシエティブ・インクワイアリー】
- AI(アプリシエティブ・インクワイアリー)は、アメリカで開発された組織開発のアプローチの一つ。「Appreciative Inquiry」の略で、Appreciative は「真価が分かる」「価値を認める」、Inquiryは「探究」「質問」などの意味。ポジティブな問いや探求によって、個人と組織における強みや真価、成功要因を発見し、認め、それらの価値の可能性を最大限に活かした、最も成果が上がる有効な仕組みを生み出すためのプロセスを指します。
- 【Tグループ】
- ドイツの心理学者クルト・レヴィンが発見した手法を発展させた、トレーニンググループの略称。参加者相互の自由なコミュニケーションにより、人間的成長を目指すグループアプローチ(集中的集団体験)を指します。人間関係の体験学習の中でも、特に密度の濃い体験のできるトレーニングが期待できます。
- 【チェンジ・エージェント】
- 組織開発を推進する人(OD実践者)を、チェンジ・エージェントと呼びます。グループや組織、社会の中で起こっているプロセスに気づき、働きかけることを通して、民主的な風土や関係性が形成されるよう、自らが所属するグループや組織、社会を変革していく担い手であるという思いが、チェンジ・エージェントという言葉には込められています。
- 【ユース・オブ・セルフ】
- OD実践者であるチェンジ・エージェントが持つ大切な考え方に「ユース・オブ・セルフ」があります。通常の組織変革の方法の場合、変革のためのツールやガイドラインは、リエンジニアリングや評価制度などのノウハウ。しかし、組織開発では変革のツールは、ユース・オブ・セルフです。大切なのは、変革に向けて自分自身が気づきや価値観を用いていくことである、ということです。
- 【コミュニケーション・チャネル】
- 組織活性化のカギを握るのは、コミュニケーション。そのため、どの企業においても上意下達、下意上達の双方向を持つコミュニケーション・チャネルの構築に、大きな力を注いでいます。組織活性化の観点から見た場合、「会社と管理者」「管理者と従業員」「従業員と会社」の三つのラインに分けて、コミュニケーション・チャネルを捉えることができます。まず、会社と管理者のラインは、会社を代表して従業員に接する管理者が、経営トップと同じ視点に立ち、従業員と意思の疎通を図ることが前提条件です。そして、上司である管理者と部下である従業員のラインを通して、日常的な業務、人事上の問題を解決していくことになります。しかし、時として管理者と従業員のラインで解決が困難な状況に直面することがあります。そうした際に、従業員と会社のラインが機能し、組織の活性化に貢献することになります。
5.組織開発・組織活性化の見通し・課題
現状を見る限り、日本企業では組織開発や組織活性化への取り組みは、まだ十分とは言えません。どのような課題が存在し、今後はそれにどう対処していけばいいのか、いくつかポイントを絞って考えてみたいと思います。
コミュニケーション不全への対応
組織開発・組織活性化に向けた取り組みについて、その歴史を振り返ってみると、まずバブル経済崩壊後の対応を挙げることができるでしょう。この頃は、会社を立て直すために組織の「ハードな側面」の改革が多く実施されましたが、結果的に組織は良いものになりませんでした。そこで、人や関係性に関わる「ソフトな側面」、具体的な例で言うと、コミュニケーション不全への対策として、コーチング研修やファシリテーター研修が大企業を中心に導入されました。しかし、コミュニケーション・チャネルが主にリーダー層に対する研修だけでは、大きな変化はもたらされません。もっと組織全体を俯瞰し、組織全体をマネージする観点が必要であり、そこで改めて注目されたのが組織開発、そして組織活性化のアプローチです。
問題は、組織開発を専門とする部署が、日本企業にはあまり存在しないこと。また人事部の中に、組織開発の専門家が少ないのも実情です。今後は人材開発部だけでなく、「組織・人材開発部」または「人材・組織開発部」などという形で、組織開発の機能を広げていくことが求められます。
生産性向上に向けて
組織としていかに生産性を向上していくのかが大きな経営課題となっている中、生産性向上設備投資促進税制が特別措置法として施行され、生産性向上設備などを取得した場合の特別償却または税額控除が行われました。中小企業向けには、ITを導入して生産性向上に取り組んだ場合に補助金を支給する助成も行われています。また、厚生労働省も業務効率化を図り労働生産性を向上させた事業所に対して、労働関係助成金の割増を行っています。さらに国土交通省では、建設現場の生産性を向上する革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト公募を開始しました。
このように政府が行う生産性向上の支援策には、ハード面を中心としたアプローチが多くなっていますが、大切なのは、組織としていかにシステム思考を持ってこの課題に継続して取り組んでいくか、ということです。それには組織開発の視点から、「現状分析」→「現状の見える化・フィードバック」→「取り組むべき課題の共有」→「具体的な施策の検討」→「実践・モニタリング」→「検証」というPDCAサイクルを回していくことが、実効性を高める上でとても重要です。
組織形態の再構築
昨今は事業展開がダイナミックに進んでいく中で、組織形態を再構築していく必要性が生じています。事業再編成が起きたときの対策には、設備投資の削減、その他の経費削減、人件費の抑制、経営姿勢の見直しなどがありますが、このような後ろ向きの対策では、持続的な成長を期待することが難しいでしょう。重要なのは組織とその構成員を元気にし、新しい時代に対抗できる組織へいかに変革していくか、ということです。例えばこれまでの縦の関係から、横の関係のコミュニケーションを重視した自主的な組織への転換を目指していく。そのためには、組織開発のアプローチ・手法の中から自社に有効と思われるものを比較検討し、うまく取り入れていくことがポイントとなります。
学習する組織(組織文化)
アメリカの経営学者ピーター・M・センゲは、学習する組織を「変化の激しい競争下で、さまざまな衝撃に耐え、復元するしなやかさ(レジリエンス)を持つとともに、環境変化に適応し、学習し、自らをデザインして進化し続ける組織である」と述べています。つまり、組織も人と同様、学習して成長する、ということです。長年の成功体験(失敗体験も含みます)の間に、徐々に組織メンバー共通の意識として構築されてきた信念、思想、価値観、理念などは、組織のDNAとして着実に受け継がれていきます。そして、これがうまく機能している間は、組織がよくまとまり、外部との競争にも団結して当たることができます。
しかし、組織も成熟期、停滞期に入ると、組織文化は根を下ろしすぎてマンネリ化し、新しい理念や考え方に対して、防御姿勢を取り始めます。このような事態に陥ると、新しい時代の変化に付いていけなくなり、業績は下降線をたどって、働く人々のモチベーションは低下します。こうした負の連鎖を避けるためには、経営トップの意識的な組織文化に対する揺り動かし(スローガンとなるもの)が必要不可欠。その経営トップが思い切った意思決定できるよう、人事部が現状の問題点と課題をきちんと整理しておくことが大切です。
人材をうまく活用した組織作り
いま企業には、組織開発を進めることによって組織体質そのものを変革し、新しい時代に対応できる組織を作っていくことが求められています。そのためには組織や制度を工夫するのと同時に、人材をうまく活用した組織づくりを改めて考えていく必要があります。組織の中の歯車としての存在ではなく、自ら全体の経営に気を配り、全体の中の一員として行動し、全体に対して義務と責任を負う、というイメージです。タテの関係よりもヨコの関係を重視し、上からの指示命令を待つのではなく、メンバーが自ら積極的に行動する。また、上に立つ者は指示命令をするよりも、アドバイザーとしての役割を担う。このような組織が、これからはより求められるのではないでしょうか。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント