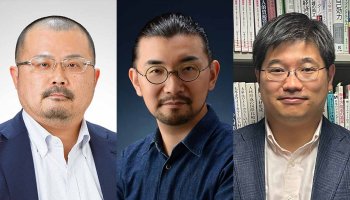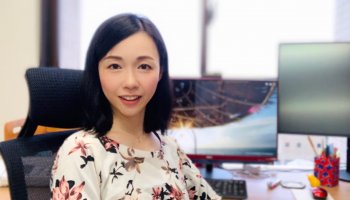人事管理のリサーチ・プラクティス・ギャップ【第2回】
「よい人事管理」を研究者はどう見てきたか
南山大学 経営学部 准教授
余合 淳氏

同じ人事管理という領域に対峙しているにもかかわらず、研究者と実務家の関心になぜギャップが生じるのか――。そんな問題意識から、『日本の人事部』と神戸大学 江夏幾多郎氏、同志社大学 田中秀樹氏、南山大学 余合淳氏が人事実務家を対象とした共同調査を実施。その結果から、日々の経験・関心・学びはどのように人事実務家の知見を育て、仕事に役立っているのか、実務家は研究にどう接すればいいのかを明らかにしていきます。
研究者なりの人事管理への向き合い方
今回は人事管理という現象を研究者がどのように捉え、何が分かっているかについて紹介します。海外、とりわけ米国と日本における研究成果を事例にして、研究者がどのように実務を理解・説明しようとしてきたかについて、簡単にまとめてみたいと思います。2024年に刊行した書籍(※1)の序章から第1章に相当する内容をまとめなおしたものなので、詳細はそちらを参照してください。
経営学を学んだことのある方であれば、なじみのあるキーワードかもしれませんが、これまでの人事管理研究として挙げられるのは、科学的管理法、労務管理論、人間関係論、人的資源管理論、戦略的人的資源管理論といったアメリカでの研究の流れです。また日本では、これらの科学的管理の受け止め方、「能力主義管理」の生成や普及、「成果主義」「ジョブ型」の挑戦や混迷などに関する研究です。近年では関心がより多様化していますが、こうしたテーマはこれまで多くの研究者が取り組んできたものです。
例えば20世紀終盤から近年にかけて、戦略的人的資源管理(Strategic Human Resource Management: SHRM)論という考え方が普及しています。実務的には「戦略人事」とか「人事戦略」と呼ばれますが、この研究では「個別あるいは複数の人事施策の束(bundle)が、外部環境(産業構造、労働市場など)と内部環境(経営戦略、組織構造など)に対して適合的であれば、それが従業員の労働生産性や企業の収益性などを高めるメカニズムを持つ」と考えます。戦略にあった人事制度が必要である、というだけではなく、人事施策同士、例えば賃金制度と評価制度や、昇進制度と異動の仕組みがそれぞれ適合的であることが重要であるとされています。つまり、「良い人事管理とは、人事制度に関連する内外の環境に適合するようなまとまったものである」という主張です。
現実は研究の知見通りになっているか?
こうした主張は、1980年代以降アメリカで特に多くの研究がなされ、日本でもその後知られるものとなりましたが、必ずしも「古くて日本では使えない研究」ではありません。日本でも、同じような指摘がされています。
例えば「ジョブ型雇用」の生みの親である濱口桂一郎氏によれば、ジョブ型雇用とは従業員の能力や年齢などの属人的要因ではなく、特定の職務の市場における価値、あるいは社内における価値に基づいた雇用条件が決まるものとされています(※2)。
そして、「ジョブ型雇用」の実現に際しては、個別具体の人事施策、労使協議の体制、労働者の活用や解雇に関して企業に課せられた規制、就業機会の平等性や質を重視する労使双方の意識、といったさまざまな要素の相互補完が重要であると主張しています。つまり、さまざまな外部環境、内部環境に適合した人事管理(その具体例としてのジョブ型雇用)が重要なわけですから、SHRM論の主張とも重なるところがあります。
「ジョブ型」とよく対比される「メンバーシップ型」の概念的な特徴を踏まえたとき、SHRM論の主張を借りるとすれば、どちらが優れているかは本来環境に依存するので、即断できないはずです。しかし、国家や社会レベルでの雇用システムや各企業の雇用慣行との複雑な補完性、例えば、ジョブ型と異動・昇進・退職との組み合わせ方、法律や人々の意識との適合といったものが十分に議論されないまま、実際には給与や等級などを既に「ジョブ型」に移行している企業も多くあるように思われます。つまり、研究上の知見は必ずしも人事の実践に届いていないことになります。
日本において、能力主義管理(1960年代)、成果主義(1990年代)、そして近年のジョブ型といった人事管理のトピックは、それぞれの時代において、実務的にも学術的にも関心を集めてきたキーワードですから、研究者と実務家が必ずしも「異なる現象に関心がある」わけではなさそうです。それにもかかわらず、どうして「研究と実務のギャップ」が起きるのでしょうか。
研究と実務のすれ違い
実はDeNisiらの研究(※3)によって、その理由の一部は既に指摘されています。研究者が提供する知見が、必ずしも実務家のニーズに応えきれていないこと、研究者が提供する知見を実務家が十分に摂取できていないことの背景には、一方が他方に十分に向き合えないという事情がありそうです。
例えば、研究者は大学などの研究機関で職を得て、そのコミュニティの中で評価されなければいけません。このため、科学的厳密性を大事にして「良い論文」を書かねばなりません。「良い論文」とは、厳密な分析、論理的で一貫性、一般性を重視した知見です。つまり、研究者同士の評価軸には通常、「実務にどれぐらい役立つか(有用性)」が考慮されません。研究者もまた組織人であり、コミュニティの一員ですから、大学や研究者に評価されなければ生業にはなりません。結果として、実務家には伝わりにくく、難解であったり、具体性が足りなかったりする研究が生まれやすいわけです。
一方で実務家もまた、同じようなテーマに関心をもっているにもかかわらず、十分に科学的な知見を取り入れられない事情があります。上述のように、実務家が欲するのは「有用性」のある知識であり、他社と差別化をしたい企業が、既に普及している一般的な施策を導入するのには躊躇があるでしょう。また、時流に敏感なため「科学的厳密性」よりも「ベンチマークとする企業が利用しているかどうか」の方が重要になってしまうこともあります。企業が直面している課題というのは、通常複雑に絡まり合っていて、金銭的、時間的に制約がある場合も多いため、その中で「自社に使えるかどうか分からない研究者の知見」を取り入れることにはリスクも多いはずです。
こうした事情を踏まえると、両者の溝は簡単には埋まらないかもしれませんが、それでも何かしらの打開策がほしいところです。人事管理の研究と実務をつなぐ実態を十分に理解するためには、実際の研究者や実務家の関心を捉えたデータを検証する必要があります。研究者も実務家も関心をもってきたものもあれば、一方しか関心を寄せてこなかったものもあると予想されます。研究者と実務家がそれぞれどのように人事管理に向き合えばよいのかについて、より具体的に示していく必要があります。
次回(第3回)は、実際に私たちが調査したデータの分析結果を紹介したいと思います。
【脚注】
※1
江夏幾多郎・田中秀樹・余合淳 (2024).『人事管理のリサーチ・プラクティス・ギャップ―日本における関心の分化と架橋』有斐閣.
※2
濱口桂一郎(2021).『ジョブ型雇用社会とは何か―正社員体制の矛盾と転機』岩波書店.
※3
DeNisi, A. S., Wilson, M. S., & Biteman, J. (2014). Research and practice in HRM: A historical perspective. Human resource management review, 24(3), 219-231.

- 余合 淳氏
- 南山大学 経営学部 准教授
よごう・あつし/神戸大学大学院 経営学研究科 博士後期課程、岡山大学大学院 社会文化科学研究科 准教授、名古屋市立大学大学院 経済学研究科 准教授を経て、現職。現在の研究関心は、働き方の人事施策の効果と従業員知覚への影響、専門職女性のキャリアと就業継続など。主な論文に「歯科衛生士の就業継続」(『キャリアデザイン研究』・共著)、「働き方の人事管理と従業員の受け止め方」(安藤史江編著『変わろうとする組織 変わりゆく働く女性たち』晃洋書房)。
この記事を読んだ人におすすめ

HR領域のオピニオンリーダーによる金言・名言。人事部に立ちはだかる悩みや課題を克服し、前進していくためのヒントを投げかけます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント