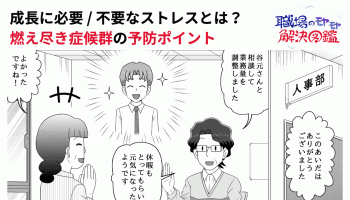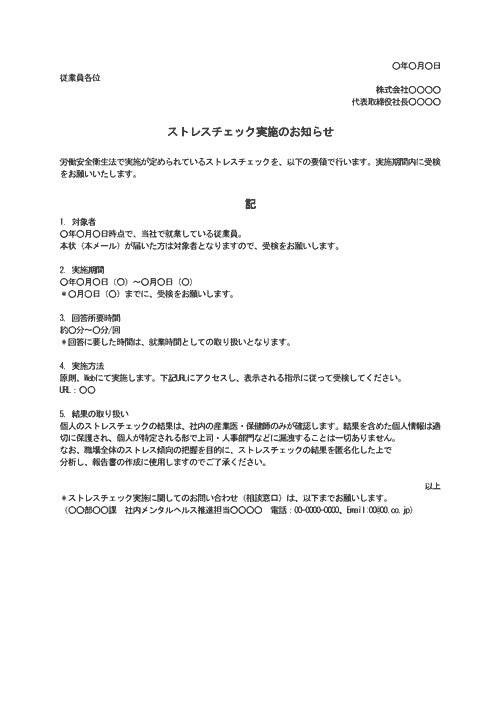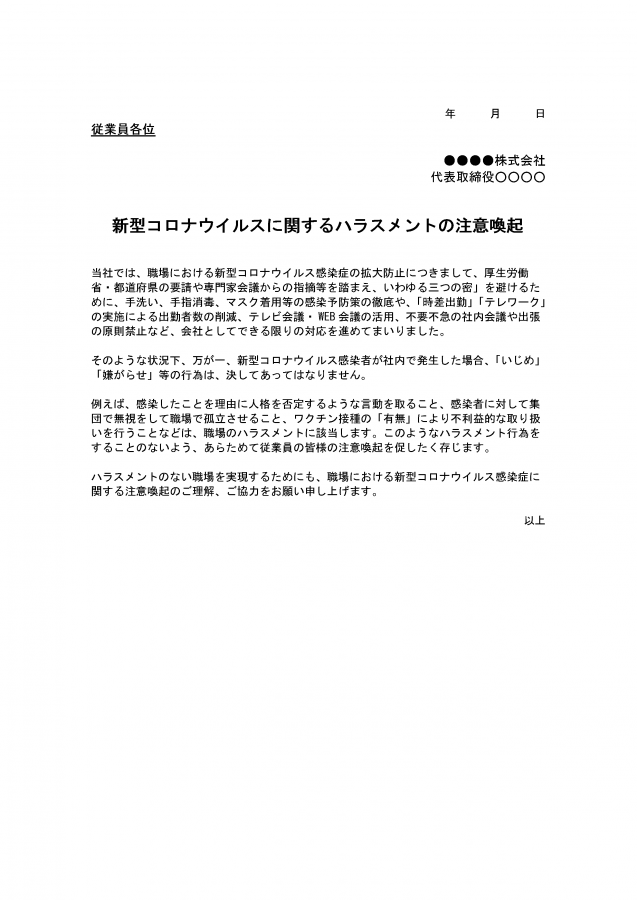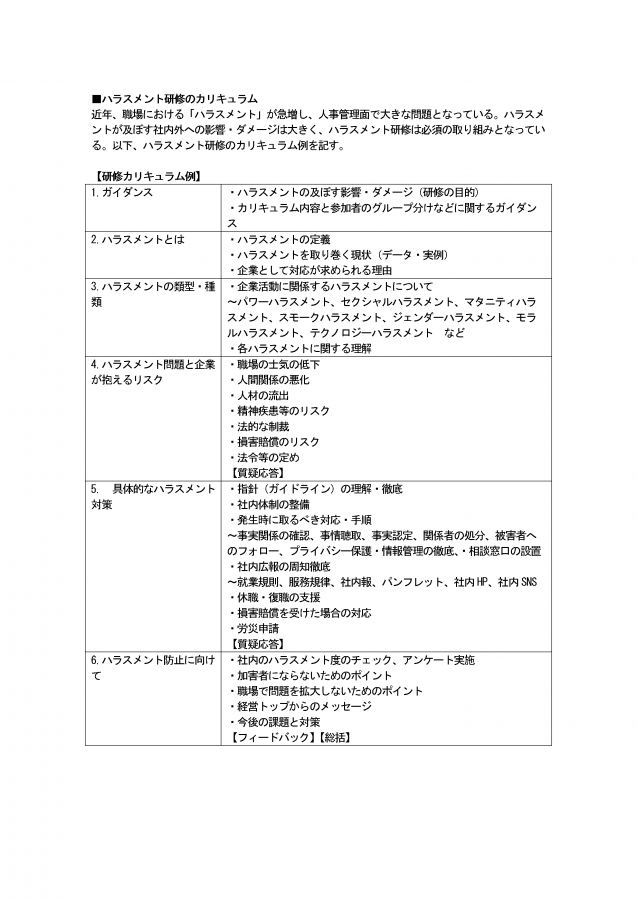リベンジ退職
リベンジ退職とは?
「リベンジ退職」とは、職場への不満や在職中に受けた不当な扱いへの報復として、企業に損害を与える形で退職する行為。「リベンジ(復讐)」という言葉の通り、職場へのネガティブな感情が引き金となります。重要なプロジェクトの最中に突然退職を告げる、引き継ぎを全く行わない、企業の機密情報やノウハウを持ち出す、SNSで内部事情を暴露する、といった行動が挙げられます。企業イメージの低下や組織崩壊にまで発展するリスクをはらんでいるため、未然に防ぐための対策が必要です。
なぜ「復讐」を招くのか
リベンジ退職の発生要因と企業の予防策
リベンジ退職が注目される背景には、労働市場の流動化やSNSの普及があります。転職が一般的となり、個人が情報を発信しやすくなったことで、従業員の不満が企業への直接的な攻撃として顕在化しやすくなりました。
リベンジ退職の典型的な行動として、後任者が困ることを意図した不十分な引き継ぎや、主要な取引先に迷惑をかけるような業務への直接的な妨害、口コミサイトやSNSへの根拠のない誹謗中傷の書き込みなどが挙げられます。これらの行動が、残された従業員の士気低下や採用活動の停滞など、長期間にわたり影響を与えることもあります。
こうした行動の引き金となるのは、上司からのパワーハラスメント、同僚と比べて不当に低い評価や給与、過度な長時間労働の強要といった、従業員が在職中に感じる「怒り」や「不公平感」。自身の尊厳を傷つけられたと感じ、会社との信頼関係が崩壊したとき、「自分を不当に扱った会社に一矢報いたい」という強い復讐心が芽生えるのです。
近年話題となった「静かな退職(Quiet Quitting)」が、契約の範囲内でしか働かないという“消極的な抵抗”であるのに対し、リベンジ退職は企業に損害を与えることを目的とした“積極的な攻撃”です。
リベンジ退職を未然に防ぐには、従業員との健全な関係構築が不可欠です。人事部門が主導すべき対策の第一歩は、心理的安全性の高い職場環境を整備すること。定期的な1on1ミーティングやエンゲージメントサーベイを活用して、従業員が抱える不満や悩みを察知する仕組みづくりが求められます。ハラスメント相談窓口を形骸化させず、実効性のあるものにすることも有効です。
評価や処遇の公平性・透明性の担保も欠かせません。評価基準を明確にし、フィードバックを丁寧に行うことで、従業員の納得感を高めることができます。「頑張っても報われない」という不公平感をなくすことが、リベンジの芽を摘むことにつながるのです。退職の意向が示された際は、その理由を丁寧にヒアリングする「エグジットインタビュー(退職者面談)」を実施し、組織課題の改善につなげる姿勢を示します。
リベンジ退職は、特定の個人の問題として片付けられるものではありません。組織内に存在するゆがみや不満が噴出した危険信号です。従業員一人ひとりを尊重し、誠実に向き合うことこそが、最大のリスクマネジメントと言えるでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント