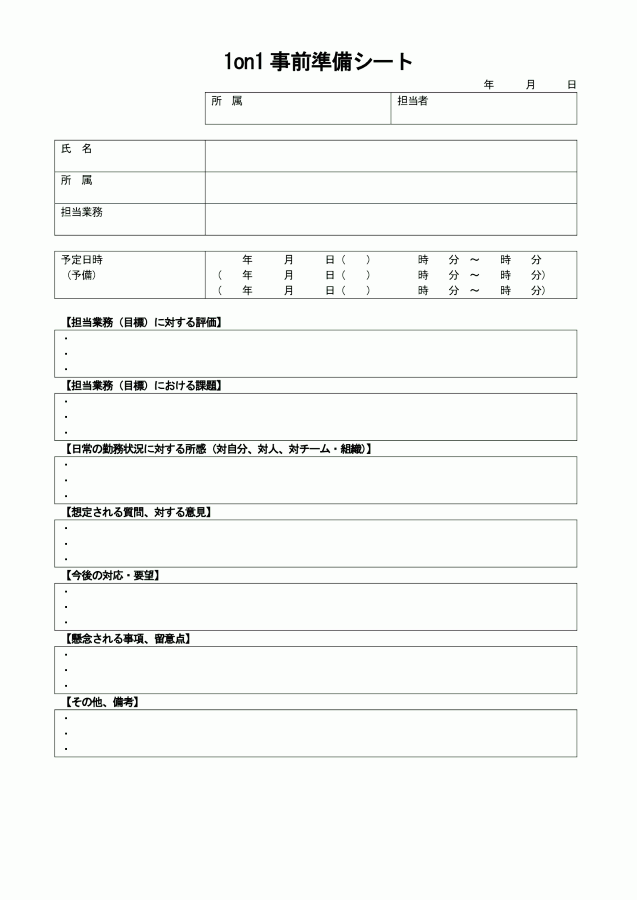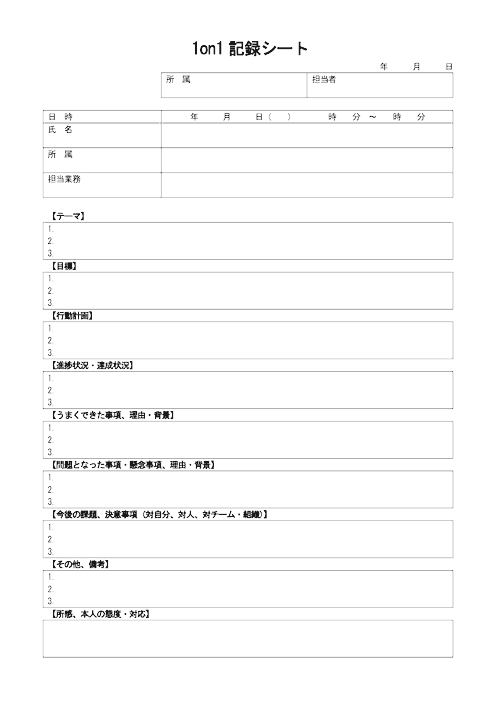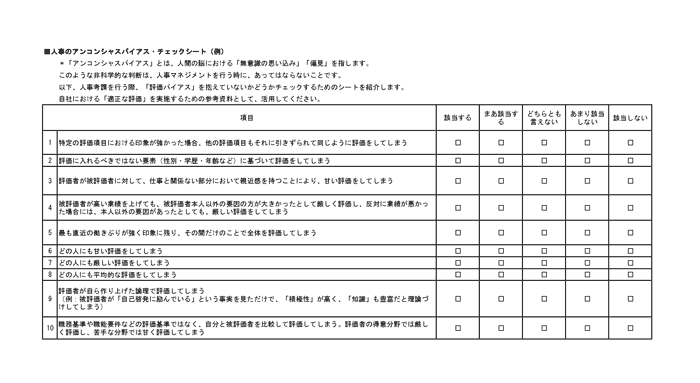SDS法
SDS法とは?
「SDS法」とは、「Summary(要点)」→「Details(詳細)」→「Summary(要点)」の順に話を展開していくフレームワークのこと。文章やプレゼンテーションなどにおいて、聞き手・読み手の理解を促したいときに有効な表現手法です。類似のフレームワークにPREP法やDESC法などがありますが、自己紹介やスピーチなどでSDS法は最も汎用性が高く、日常生活からビジネスシーンまで幅広い用途で使うことができます。
何気なく聞いているニュースも
実はSDS法からなっている
「昨日、サッカーでチームAがチームBに3対2で勝ち、初めて優勝を果たしました。昨日の試合では、2点差のついた後半15分、ペナルティキックから1点を返して同点。残り2分で勝ち越し、勝利をものにしました。チームAは創立5周年を優勝で飾りました」
このニュース原稿をよく見てみると、SDS法で構成されていることがわかります。「昨日、サッカーでチームAがチームBに3対2で勝ち、初めて優勝を果たしました」と要点から始まり、どのような試合だったかという描写が続きます。最後には締めとして「チームAは創立5周年を優勝で飾りました」と要点が繰り返されています。このように、ニュース番組ではSDS法が頻繁に使われているのです。
ビジネスシーンにおいても、聞き手から「で、結論は?」などと言われたことがある人には、SDS法の活用がおすすめです。説得力を高めるフレームワークとして「PREP法(Point:要点、Reason:理由、Example:例、Point:要点)」や「DESC法(Describe:描写、Express:表現、Suggest:提案、Consequence:結果)」がありますが、SDS法は最もシンプルであるため、活用しやすいのです。
本を読み始めるときに、目次をざっと眺めて全体像を理解するように、SDS法でも最初に要点を伝えることで聞き手が全体像をイメージしやすくなります。最も大切な詳細の部分を伝えた後に、再度要点を繰り返すことで、聞き手は頭の中で情報を整理することができ「記憶」に残りやすくなるというわけです。会社のプレゼンでいきなり挑戦するのが不安だという人は、まず報告書や日記など、書き言葉から挑戦してみるとよいでしょう。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント