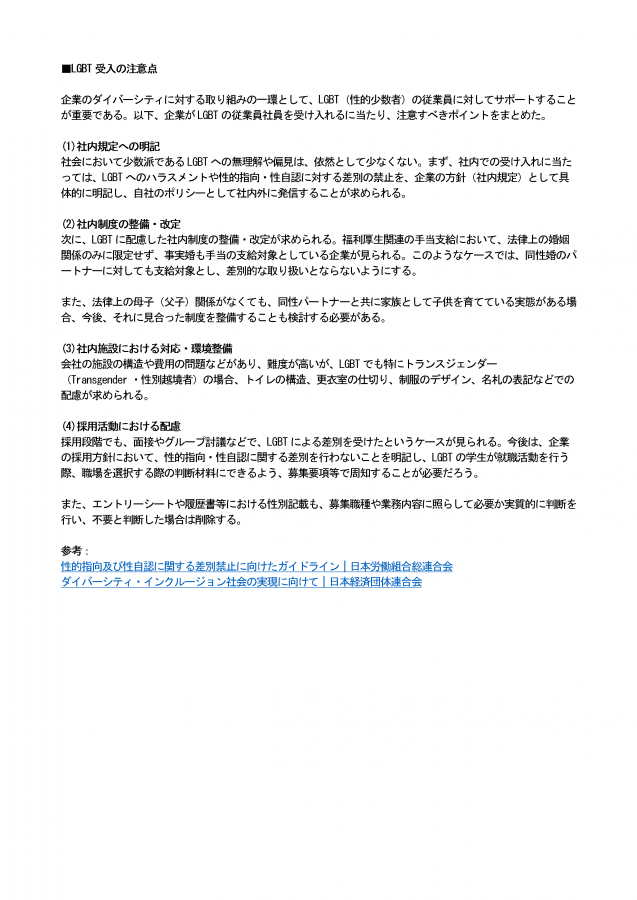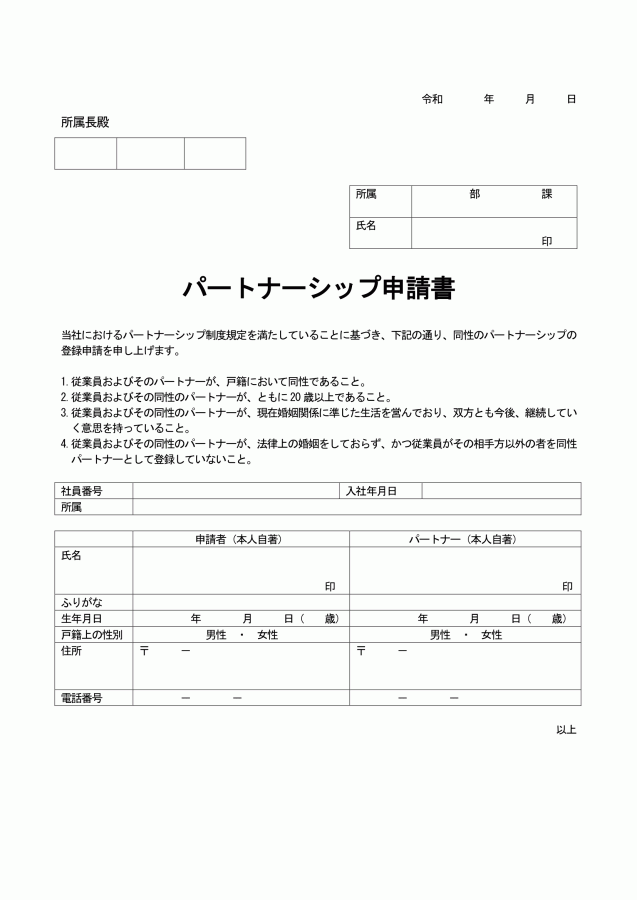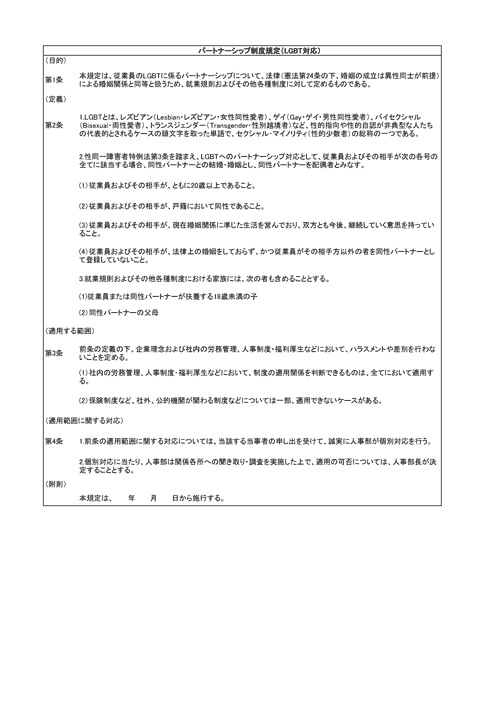アライ(ally)
アライ(ally)とは?
「アライ」とは、英語で「同盟、支援」を意味する「ally」が語源で、LGBT(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー)の当事者ではない人が、LGBTに代表される性的マイノリティを理解し支援するという考え方、あるいはそうした立場を明確にしている人々を指す言葉です。世界中の人々が訪れることになる2020年の東京オリンピックを控え、「ダイバーシティ&インクルージョン社会の実現が急務」との機運が高まり、多くの企業がアライの活動に取り組み始めています。
アライの調査と取り組み

電通ダイバーシティ・ラボが2019年1月に発表した調査結果で、2018年現在、LGBTに該当する人は日本において8.9%であるとされています。例えるなら、血液型がAB型、あるいは左利きである割合とほぼ同じとなりますので、あらゆるコミュニティに存在しているといえるでしょう。
しかし、性的マイノリティかどうかは外見からは判別がつきにくいこと、当事者の大半は自己防衛のためにやむを得ず多数派を装っていることが原因で、多くの人が「自分の周囲に性的マイノリティはいない」と誤認しがちです。実際には、すぐ身近にいる職場の同僚が、いわれなき差別に苦しんでいるかもしれません。
近年では、多くの企業が、LGBTを理解し支援する活動「アライ」への取り組みを始めています。ここで、野村證券株式会社およびギャップジャパン株式会社の取り組み事例を見てみましょう。
野村證券のアライへの取り組み
野村證券は、リーマン・ブラザーズの欧州とアジアのビジネスを継承したのをきっかけに、2009年から「ダイバーシティ(組織に多様な価値観・人材が存在する状態)&インクルージョン(多様性を受容し、強みを生かしている状態)」の取り組みを始めており、その一環としてアライの活動も始まりました。当事者ではなく、アライが中心となる活動であるために、アライの「A」を加えて「LGBTA」と表記。LGBTに関するイベントへの参加・協賛、社員には当事者への理解を促すパンフレットや虹色の卓上コーン、バナー、ステッカーなどを作成・配布しています。当事者の社員から「社内で相談できる相手が見つかってよかった」との声も寄せられています。
ギャップジャパンのアライへの取り組み
ギャップの米国本社は、1969年の創業以来、ダイバーシティ&インクルージョンの取り組みを行っています。ギャップジャパンにおいても、2018年には全従業員向けのアライトレーニングを開発し、研修を行っています。研修後にLGBT支援者となる「アライ宣言」をした従業員には、アライであることを対外的に表示できるピンバッジやスタンド、ステッカーなどのグッズを配布しています。
アライが注目される理由
アライが注目されているのは、2020年に東京オリンピックが開催されるからです。北米に端を発するアライの活動は、芸能人やスポーツ選手など多くの著名人の共感を得て、世界中に広がっています。しかし日本においては、性的マイノリティへの取り組みが、欧米と比べて大きく立ち遅れているのが現状です。
近年はメディアに登場する当事者が増え、認知度は高まりつつあります。しかし就労の現場では、いまだに理解が進んでいません。当事者が働きづらさを感じたり、セクハラを受けたりするケースは少なくないといわれます。そもそも当事者は、就職活動の段階から、履歴書の性別欄の記述、あるいはリクルートスーツの着用により傷つけられているといわれています。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務




 イベント
イベント