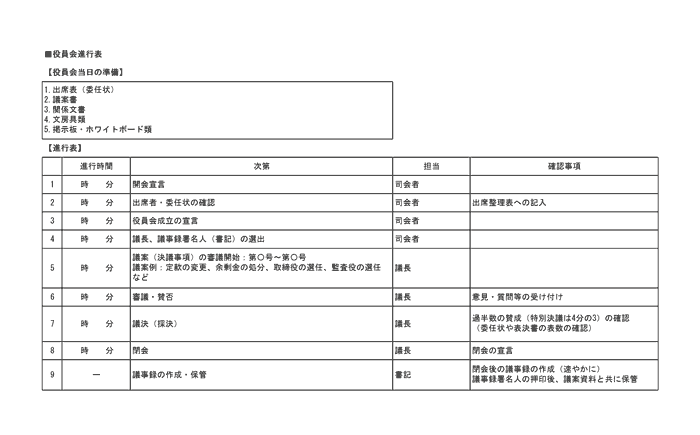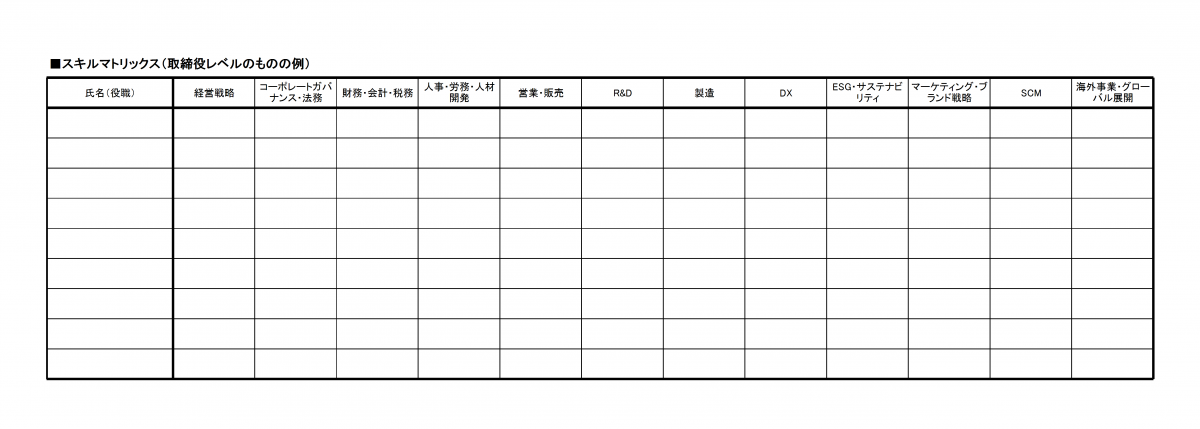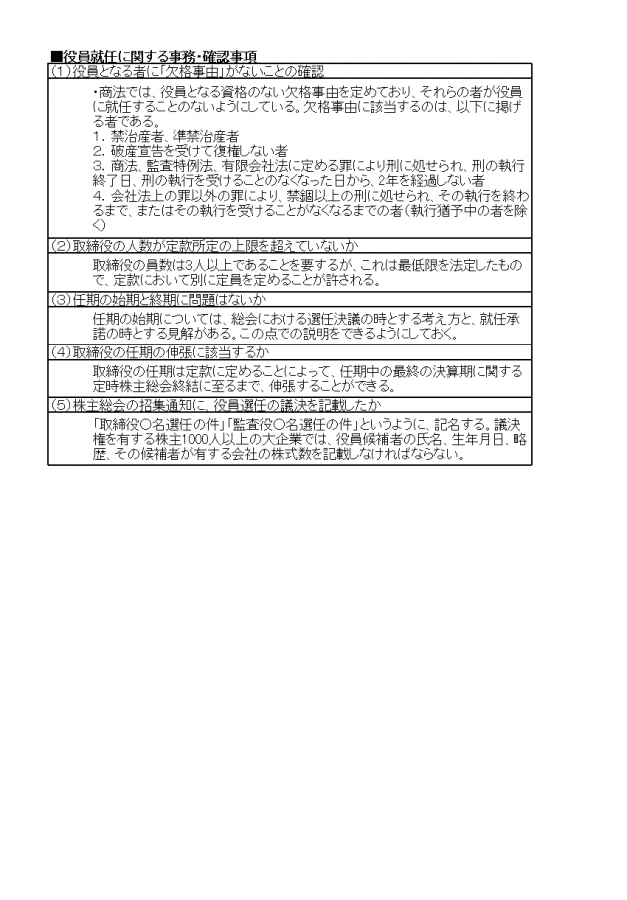イノベーション
イノベーションとは?
イノベーション(innovation)とは、「新機軸」や「革新」を意味し、新たな仕組みや習慣を取り入れて、革新的な価値を創造することを指します。企業のみならず社会全体に多大な影響を与えますが、イノベーションを起こすためには乗り越えなければいけない課題が多く存在します。

イノベーションの定義や概念について
イノベーションの「革新」の中身について、さまざまな研究者・団体が定義をしています。オーストリアの経済学者ヨーゼフ・シュンペーターは、1912年に出版した著書『経済発展の理論』の中で、「新結合」という言葉を用いてイノベーションを解説しています。
この理論は、日本では1950年代に「技術革新」として普及したのち、モノや仕組み、サービス、組織、新しいビジネスモデルの改革を含めた幅広い概念として使われるようになりました。
経済産業省は、2019年にイノベーションについての定義を下記のように発表しています。
- 社会・顧客の課題解決につながる革新的な手法(技術・アイデア)で新たな価値(製品・サービス)を創造し
- 社会・顧客への普及・浸透を通じて
- ビジネス上の対価(キャッシュ)を獲得する一連の活動を「イノベーション」と呼ぶ
イノベーションは技術革新のみならず、市場に新しい価値を生み出すことです。それには自前主義からの脱却をはじめとした、企業改革が必要になります。
- 【参照・引用】
- 日本企業における価値創造マネジメントに関する行動指針│経済産業省
1)シュンペーターの五つのイノベーション
イノベーションの要素について、有識者がさまざまな考え方を示しています。ヨーゼフ・シュンペーターは、著書『経済発展の理論』で、5種類のイノベーションについて解説しています。
-
新しい財貨(プロダクト・イノベーション)
従来とは異なる、革新的な新商品(新製品・新サービス)を開発すること。 -
新しい生産方法(プロセス・イノベーション)
新たな生産方法や、流通方法を導入すること。 -
新しい販路(マーケット・イノベーション)
新たな市場に参入し、新規の顧客、ニーズを開拓すること。 -
新しい供給源(サプライチェーン・イノベーション)
商品をつくる原材料や、供給ルートを新規開拓すること。 -
新しい組織(オーガニゼーション・イノベーション)
組織を変革することで、業界に大きな影響を与えること。
2)ドラッカーのイノベーションのための7つの種
マネジメントの祖と呼ばれるピーター・F・ドラッカーは、イノベーションを創出するための「7つの種」を解説しています。上から成功しやすい順に並べられています。
- 予期せぬもの
- ギャップ
- ニーズ
- 産業構造の変化
- 人口構造の変化
- 意識の変化
- 発明発見
予測のしにくい要素が挙げられていますが、中でも「ギャップ」「ニーズ」は成功しやすいと同時に予測や分析が比較的容易なものです。イノベーションを目指すならまずは市場の需要を調査することも方法の一つです。

- 【参照・引用】
- イノベーションのための7つの種│ドラッカー学会
3)クリステンセンのイノベーションのジレンマ
イノベーション研究の第一人者、ハーバード・ビジネス・スクール教授のクレイトン・クリステンセンは、著書『イノベーションのジレンマ』の中で、二つのタイプのイノベーションについて解説しています。
1.持続的イノベーション
持続的イノベーションとは、既存の製品やサービスの改善を積み重ね、性能を向上させる手法です。同書には、「持続的技術革新は、主要市場のメインの顧客が今まで評価してきた性能指標にしたがって、既存製品の性能を向上させるもの」としています。
2.破壊的イノベーション
破壊的イノベーションは、持続的イノベーションとは全く異なる発想から生まれるものです。新しい製品やサービスが市場に生み出された結果、既存の事業を破壊させる場合もあることから、破壊的イノベーションと呼ばれています。クリステンセンは、著書の中で「破壊的技術は、従来とはまったく異なる価値基準を市場にもたらす」と述べています。
イノベーションのジレンマとは、大企業が、既存商品の改善(持続的イノベーション)に捕らわれてしまい、破壊的イノベーションを起こせないことをいいます。
既存商品が市場のニーズよりも過剰になると(オーバーシューティング)、新たな破壊的イノベーターに太刀打ちできず、競争力を失ってしまいます。このことは、組織内の同質性が高い日本企業の大きな課題といえるでしょう。
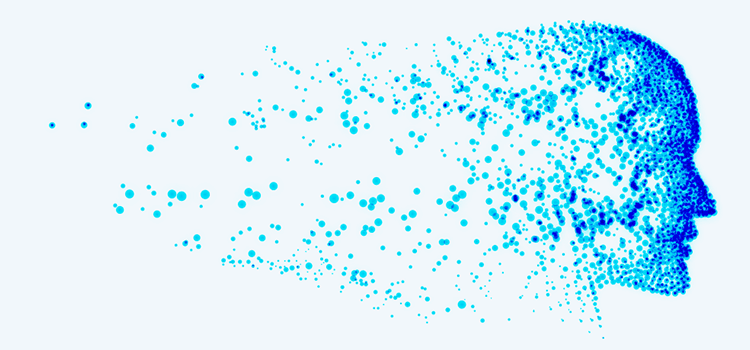
破壊的イノベーションの事例
クリステンセンは同著の中で、メインフレームとミニコンを例に挙げています。例えば、IBMはメインフレーム市場で圧倒的なシェアを誇っていましたが、シンプルなミニコン(ミニコンピューター)の出現によって、市場を奪われました。しかし、その後「デスクトップ・パソコン」の出現によって、ミニコンは地位を失ったのです。
インクジェットプリンターの技術も、破壊的イノベーションといえるでしょう。インクジェットプリンターが出現した当時、レーザープリンターが市場を占めており、性能においても差があることから、比較対象にもなりませんでした。
しかし、その後インクジェットプリンターの性能が向上すると、デスクトップ・パソコン用の卓上プリンターとして、確固たる地位を築いたのです。
クリステンセンは、技術革新だけにフォーカスしているわけではありません。同著では、ホンダの北米市場開拓についても触れています。
ホンダが北米に進出した当時、米国では長距離用の大型バイクが主流でした。ホンダは「スーパーカブ」の市場開拓に難航しましたが、「レクリエーション用のオフロード・バイク」という未開拓の市場を見つけることで、小型バイク市場における地位を確立しました。
4)チェスブロウのオープン・イノベーション
オープン・イノベーションとは、2003年にアメリカの経営学者、ヘンリー・チェスブロウによって提唱された概念。チェスブロウは、著書『オープンイノベーション』の中で、イノベーションには二つのタイプがあると解説しています。
[1]クローズド・イノベーション
クローズド・イノベーションは「組織や製品開発において、すべて自社の資源で内省化する考え方」と定義されています。しかし、技術や人材を全て自社で調達して新製品を市場に出すまでには、一定の期間が必要になります。
近年、ITなどの技術が急速に進化・発展することによって、新製品が世の中に出るスピードが速くなり、製品ライフサイクルは短くなりました。同氏は企業が競合他社に勝ち、事業を継続するには、クローズド・イノベーションだけでは限界があるとしています。
[2]オープン・イノベーション
オープン・イノベーションは「組織の改革を促進するために、意図的に外部のアイデアや資源を取り入れることで、新たな価値を創造すること」と定義されています。具体的には、研究機関や企業と協働することで、外部のアイデアや知識、技術などを自社の製品やサービス開発に活用することなどがあります。
チェスブロウは、自社のリソースだけで完結するよりも、外部のリソースをうまく活用しながらスピードをもって市場に新製品を投入できるオープン・イノベーションこそ重要だとしています。
オープン・イノベーションの事例
チェスブロウは、オープン・イノベーションの事例として、Xerox PARC(Palo Alto Research Center)について記しています。
PARCは、Xerox PARC(米国ゼロックスの研究組織)として、1970年に創設された研究所です。創立当時から既存の製品にこだわることなく、異なる技術を組み合わせてさまざまな新しい技術を開発し、その技術は後に多くの製品に活用されています。
例えば「グラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)」や、Ethernetなどのネットワーク・プロトコル、フォント制御プログラムであるPostscriptなども、PARCの研究員によって開発された技術です。チェスブロウ曰く、「PARCで社内的な政治が働いていたら、これらの技術は生み出されなかった」とのこと。
後にPARCを離れた研究者によって、Apple社やMicrosoft社で技術が生かされ、新たな製品が開発されました。同氏は、PARCの研究者がXeroxにとどまっていれば、これらの革新的な製品は生まれなかっただろうと推測しています。
この事例から、オープン・イノベーションは、人的リソース、技術的交流によって生み出されるものであるともいえるでしょう。

上場企業に義務付けられた人的資本の情報開示について、開示までのステップや、有価証券報告書に記載すべき内容を、具体例を交えて解説します。
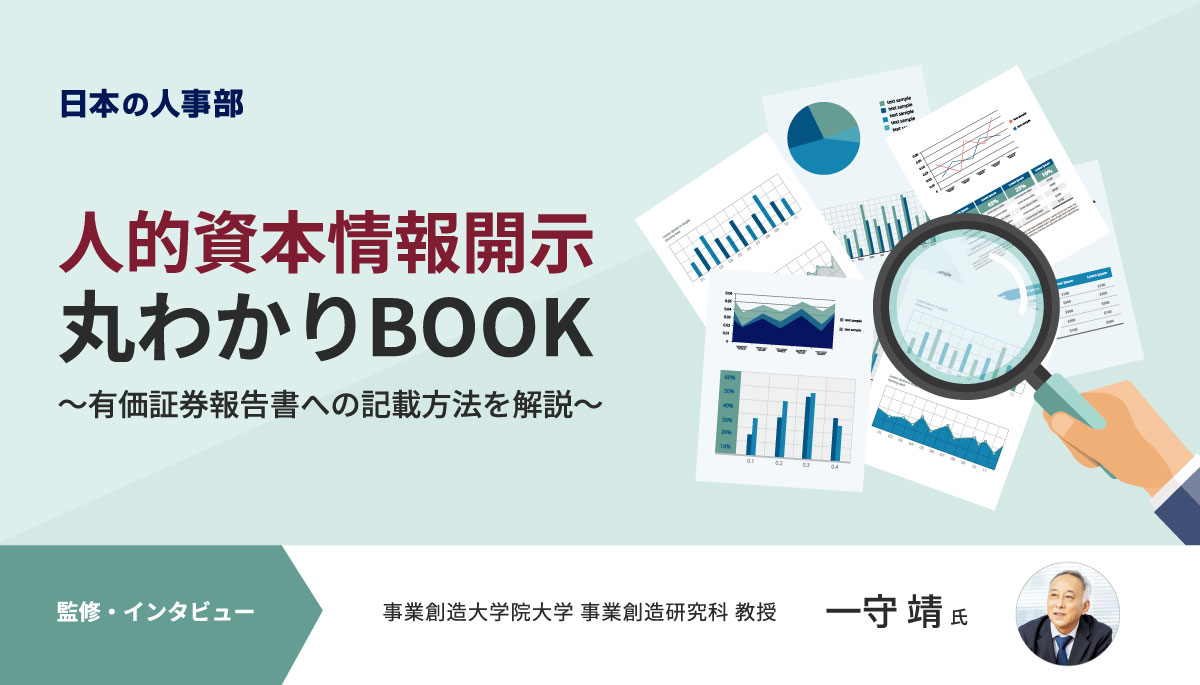
人的資本情報開示~有価証券報告書への記載方法を解説~│無料ダウンロード - 『日本の人事部』
「イノベーション」について深く知る記事一覧

イノベーション
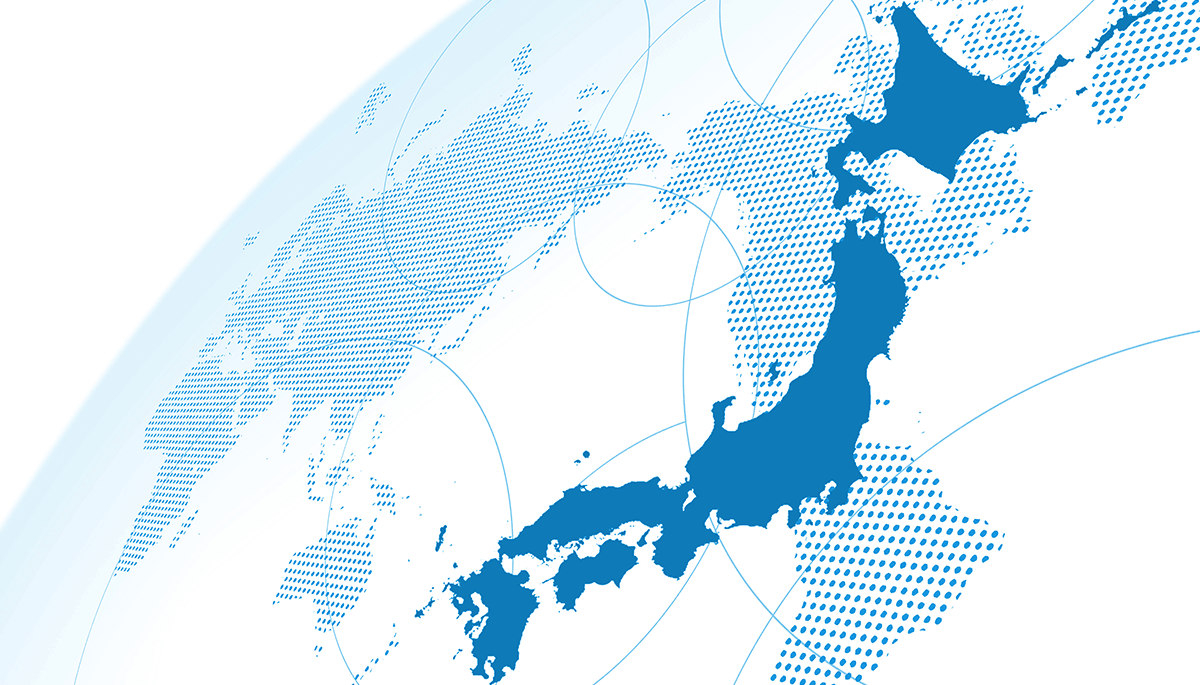
イノベーションを生み出すためには何が必要か
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント