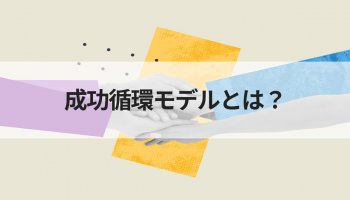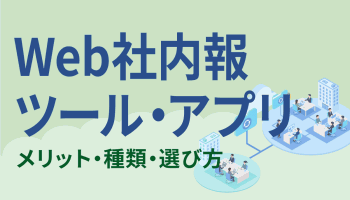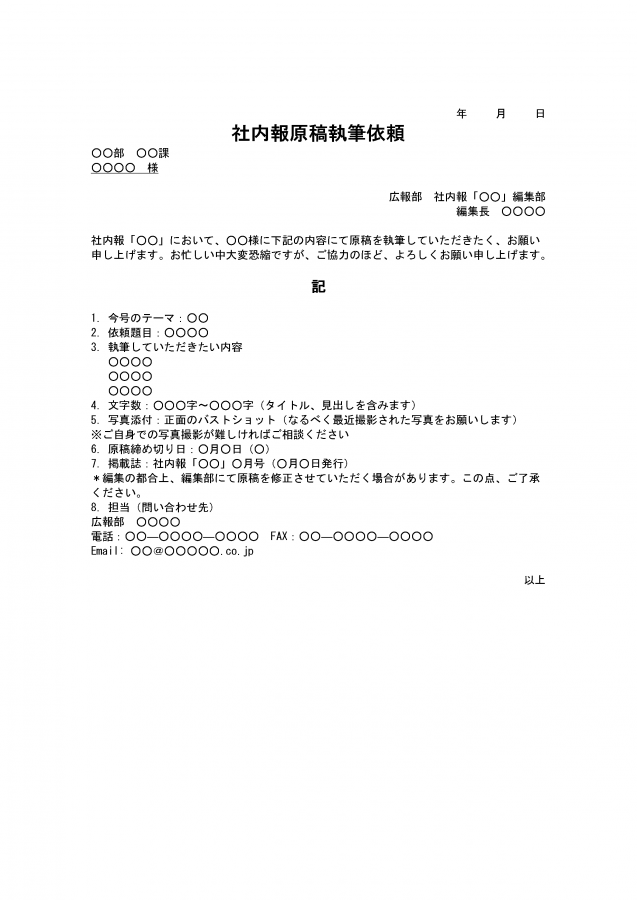オープンスペーステクノロジー
オープンスペーステクノロジーとは?
「オープンスペーステクノロジー」(OST)は、関係者が一堂に会して話し合うホールシステム・アプローチの代表的な手法です。大まかなテーマに沿って、参加者自らが解決したい問題や議論したい課題を提示、進行の段取りも自主的に決めるなど、個人の主体性を重視することで参加者のコミットメントを最大限に引き出すのが特徴です。OSTは、参加人数の多少にかかわらず、生産的かつ創造的なミーティングやカンファレンスを実施し、集合的意思形成に向けた取り組みを促します。
はじまりは“コーヒーブレーク”
本音を共有し合える話し合いの場作りを
会議中の議論は低調で退屈だったのに、打ち切ってブレークを入れた途端、がぜん本音トークで盛り上がった──。誰にでもそんな経験があるでしょう。何を、どう決めるか、検討課題や進行手順まであらかじめ細かく設定され、結論が読めるような予定調和の会議よりも、むしろリラックスした雰囲気の中で誰かがふと提起した話題のほうがメンバーの関心を集め、本音の話し合いを導きやすいものです。
OSTの提唱者であるハリソン・オーウェン氏も、1985年に行われたある会議で、参加者全員が最も充実していたと振り返った瞬間がコーヒーブレークだったという事実に着目。そこに見られる高い相互作用や創造性、リラクゼーションをシステムとして再現し、公式な話し合いの場に取り入れることはできないかと考えました。同氏はかつて西アフリカのある村に滞在した経験から、ヒントを得たといいます。その村の部族では何かを決めるとき、人々が必ず車座になって話し合っていました。OSTを実施する際も、参加者の座席配置は円形が基本。“車座”になることによって、場の中心を認識し、互いに顔を見合わせ、発言の順番や順位を無くし、立場や上下関係から参加者全員を解放することができるからです。
OSTの基本原理では、「参加者がすべてを自由意思で選択する」ことを何よりも重視します。したがってOSTによるミーティングやカンファレンスの参加者は、始まるまでアジェンダを知りません。アジェンダはそれを持っている参加者自身が提案するのです。議論したいテーマとセッション(少人数に分かれての会議)の時間帯、場所を紙に書いて張り出し、他の参加者はそれを見て、参加したいセッションを選びます。進行手順などに制約はなく、テーマに対して自由にお互いの“本音”を交換します。参加したセッションが面白くないと感じれば、ほかのテーマの会議に移ることも自由です。
OSTの手法はもはや先端的、実験的なものではありません。企業や部門のビジョンを策定したり、職場の構造的な問題を解決したりといった長期的かつ根本的なテーマの合意形成に有効とされています。P&GやIBM、イケアといった多くのグローバル企業で導入されているほか、世界各国の行政、教育、NPOなどで活用され、高い成果を上げています。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント