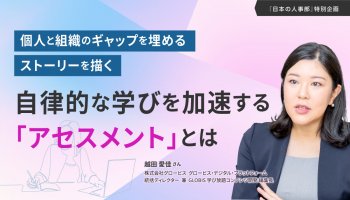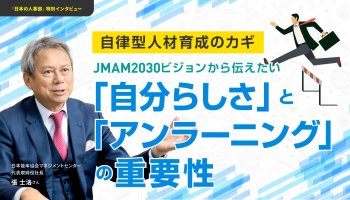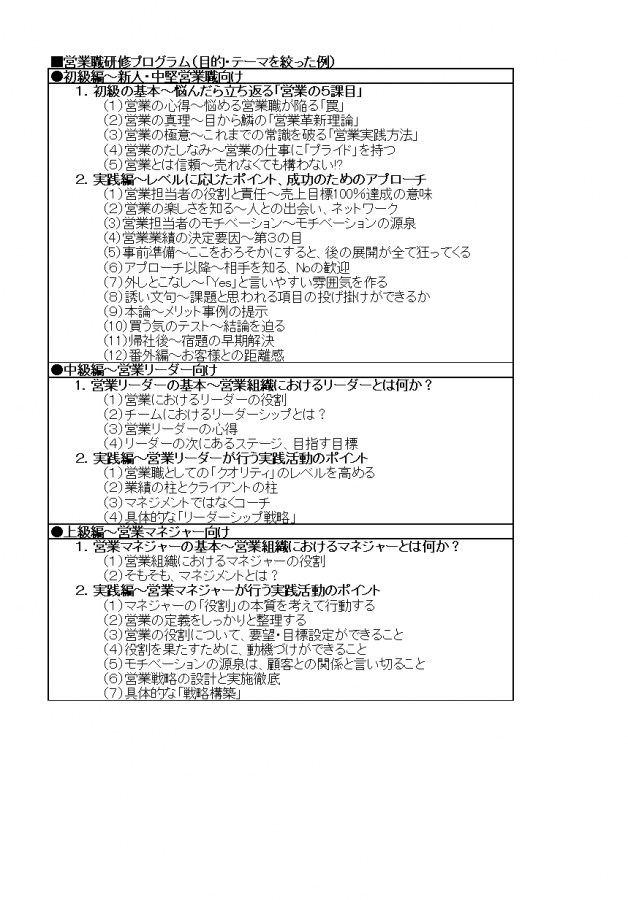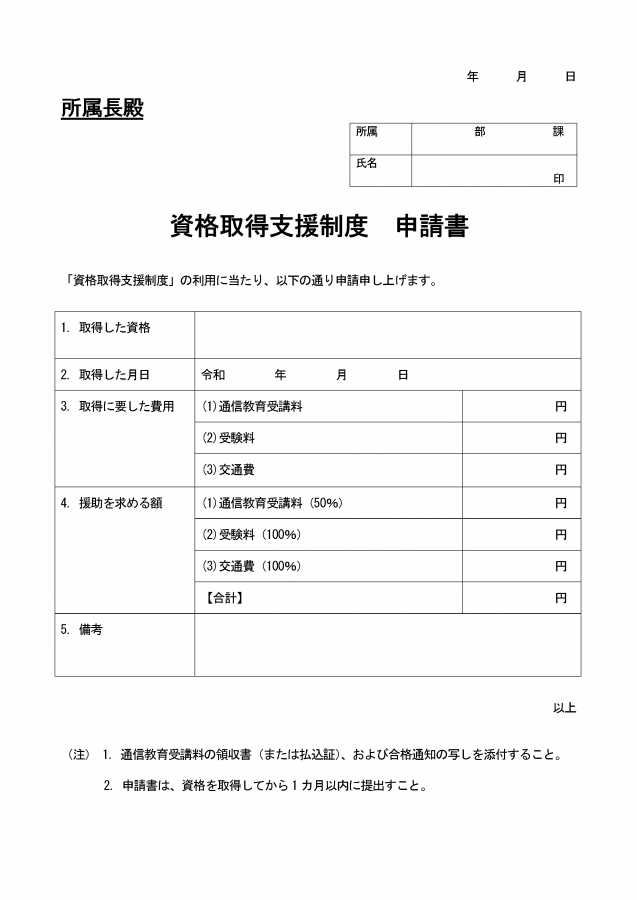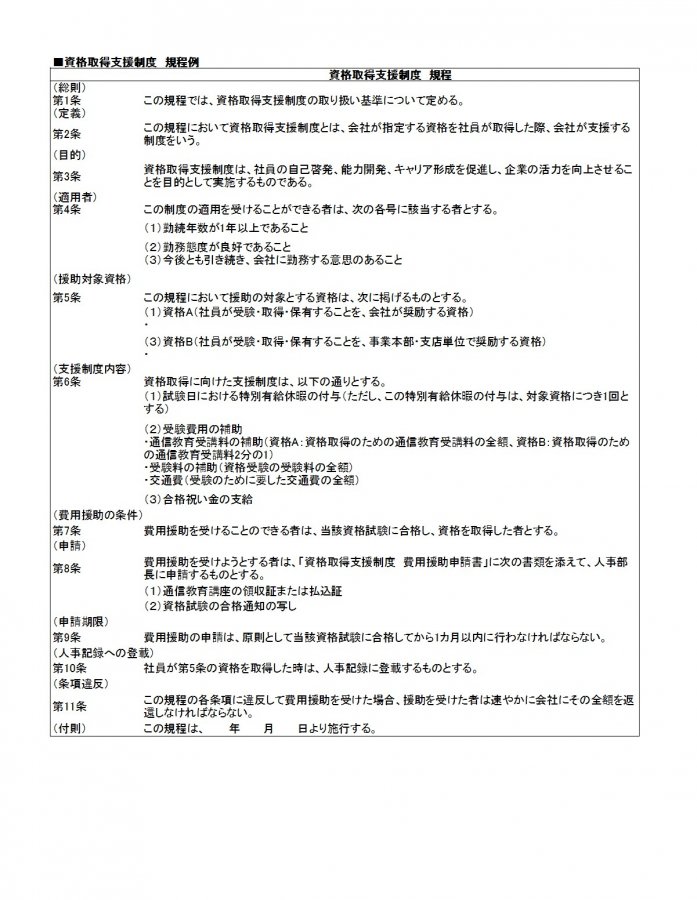アンラーニング
アンラーニングとは?
「アンラーニング」(unlearning)とは、いったん学んだ知識や既存の価値観を批判的思考によって意識的に棄て去り、新たに学び直すこと。日本語では「学習棄却」「学びほぐし」などと訳されます。個人や組織が激しい環境変化に適応して、継続的な成長を遂げるためには、いわゆる学習(ラーニング)と学習棄却(アンラーニング)という、2種類の一見相反する学びのプロセスのサイクルをたえず回していくことが不可欠とされます。
一人前になった後の学びが足りない
熟達化の足かせを解く“学びほぐし”
近年、人材育成の現場では、企業における学び、あるいは教育のあり方として、いわゆる「熟達化」のアプローチが浸透してきました。企業の拠って立つ理念や価値観、組織が培ってきた知識やスキルを研修などによって習得するだけでなく、実務への参加を通じて仕事に熟達する――現場での実践的な学びこそが個人を成長させ、組織の競争力を高めるという考え方が主流になってきたのです。平たくいえば、それは未熟な新入社員や経験の乏しい若手を、組織の一員として“一人前”にしていくプロセスにほかなりません。
では、“一人前になった後の学び”についてはどうでしょうか。日本では「学習=未熟な者が足りない知識を補うこと」というイメージが強いせいか、企業の人事担当者の関心も、学びというと「若手の学び」「部下の学び」に傾きがち。仕事に熟達し、組織のメンバーとして一人前に成長した中堅や部下を持つ立場になった上司がその先、何をどう学んでいくかという問題は、残念ながら、まだ切実にとらえられていないのが現状です。一人前以降の学び、すなわち「大人の学び」を企業としてどう支援していくかについても、次世代リーダー育成や後継者育成などの実践事例はあるものの、その対象はごく限られた範囲にならざるを得ないでしょう。
しかし大人になっても、一人前になっても、学ぶ必要がなくなるわけではありません。学びとは本来、自ら変わり続ける営みであり、まして現代のビジネス環境のように急激な変化や想定外の事態が続く状況下では、長い経験によって熟達したスキルがある日突然、時代遅れになることはめずらしくありません。熟達化という概念そのものが環境適応への足かせとなり、致命的な判断ミスを招く恐れもあります。過去の成功体験にこだわって、熟達することの優位性を強く意識し過ぎた結果、自分が追求してきた価値観や考え方、行動パターンがすでに通用しなくなっていることに気づくのが遅れてしまうのです。
「アンラーニング」の発想に注目が集まる要因が、ここにあります。特定の分野や方向に固執し、ひたすら熟達化を進めるのではなく、むしろ熟達を求めるあまり硬直化してしまった自らの思考様式や行動様式をいかに解きほぐすか。「学びほぐし」の視点が、現在のビジネスに必要な大人の学び、一人前以降の学びへつながっていくと考えられています。
ずっとあたりまえだった知識や価値観をアンラーンするためには、自分自身の置かれている状況やこれまでに行ってきたことを批判的に振り返る「リフレクション」(内省)のプロセスが欠かせません。自分は仕事を「正しく行っているか」を振り返るのではなく、仕事において「正しいことを行っているのか」を、いったん職場や日常業務から離れて、冷静に問い直す機会が求められています。
- 参考になった1
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
- 1
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント