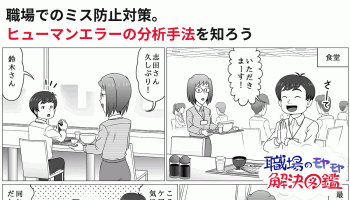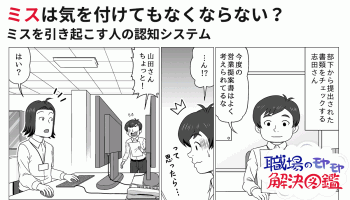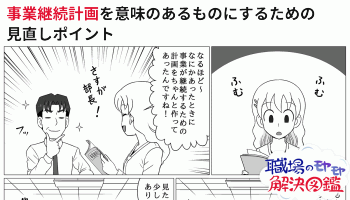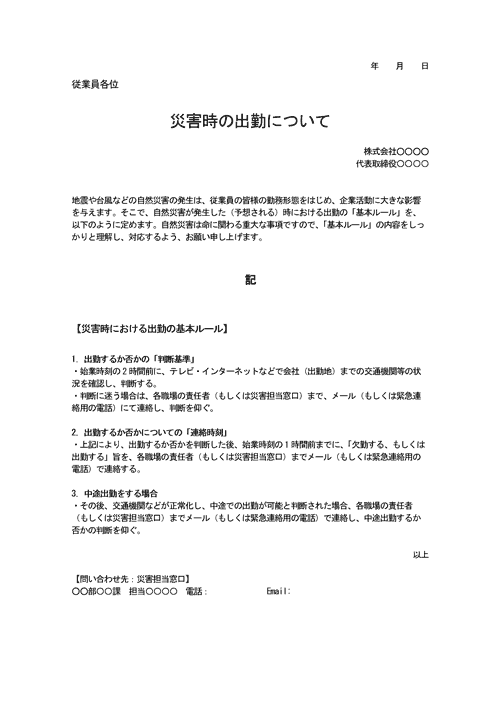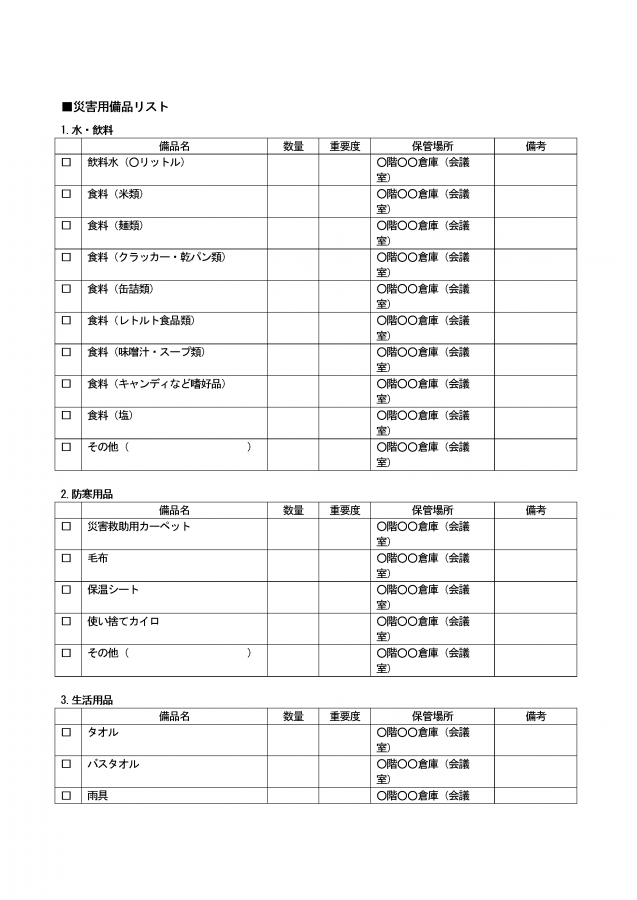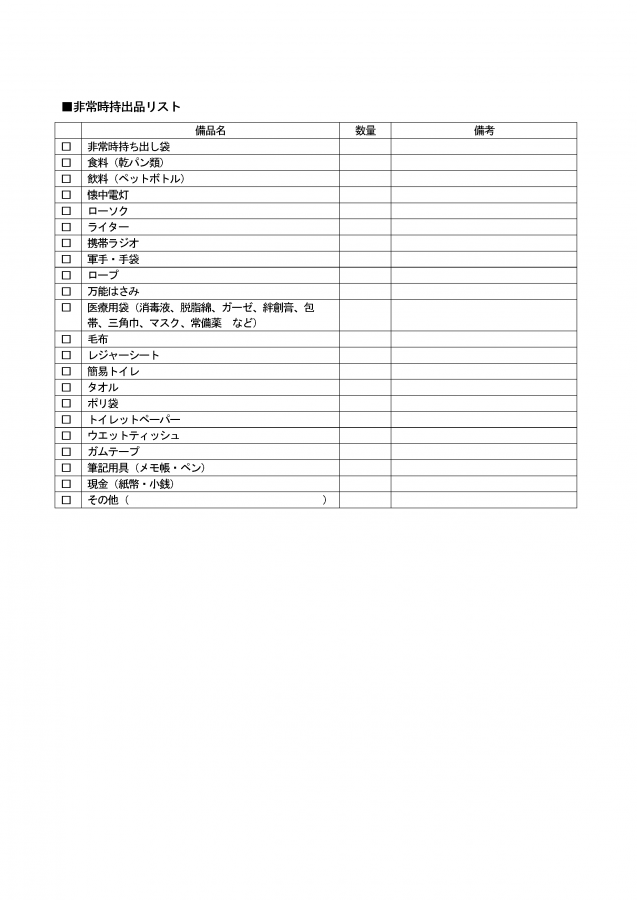ハインリッヒの法則
ハインリッヒの法則とは?
「1件の重大な事故・災害の背後には、29件の軽微な事故・災害があり、その背景には300件の異常がある」という労働災害に対する経験則の一つ。アメリカの損害保険会社の技術・調査部に勤務していたハーバート・ウィリアム・ハインリッヒが、1929年に出版した論文の中で発表したことから「ハインリッヒの法則」と呼ばれています。
労働災害の98%は予防できる
ささいな“ヒヤリハット”が重大事故の予兆
従業員の生命の安全を脅かし、企業の存続までも揺るがしかねない産業事故や不祥事は決して偶発的なものではない、そこには必ず何らかの“予兆”が潜んでいるという教訓を統計学的に示しているのがこの「ハインリッヒの法則」です。
ハインリッヒ氏は、同一人物が起こした同一種類の労働災害を5,000件以上調べ上げ、その発生確率を分析しました。その結果、明らかになったのは、1:29:300という数値――「重傷」以上の災害が1件発生したら、その背後では29件の「軽傷」を伴う災害が起きており、さらに事故には至らなかったものの、一歩間違えば大惨事にもなるような、「ヒヤリ」「ハッと」する事例が300件あるという法則性でした。ハインリッヒの法則は、別名「ヒヤリハット」の法則とも呼ばれます。
さらに同氏は、重大な事故・災害が発生する労働環境には数千件もの「不安全行動」と「不安全状態」が存在することを明らかにし、こうした“リスクの芽”を見逃さずに取り除けば災害もなくなることから「労働災害全体の98%は予防できる」と指摘しました。ハインリッヒの法則をはじめとする同氏の教訓を受けて、製造現場では環境の改善が進められ、労災の大幅な減少に成功。ハインリッヒ氏は「災害防止のグランドファーザー」、同氏の著作は「災害防止のバイブル」と呼ばれるようになりました。
その後、より多くの事例に基づく類似の調査研究が行われ、ハインリッヒの法則に続く法則が数多く発表されました。1969年にバードが発表した「バードの法則」では、アメリカの21業種297社、1,753,489件のデータから「重大事故:軽傷事故:物損事故:ニアミス=1:10:30:600」という比率が示されています。また70年代にイギリスの保険会社のデータ約2万件から導き出された結果は、「重大事故:軽中傷事故:応急処置を施した事故:物損事故:ニアミス=1:3:50:80:400」の比が成り立つというものでした。
いずれにせよ、事故の発生確率に関する数字そのものは時代や業種によって異なるので、本質的に重要ではありません。ハインリッヒの法則に学ぶべき教訓とは、重大な労働災害には予兆となるささいな失敗や異変が必ずあるということ、そしてそれを見逃さない取り組みを普段から地道に進める以外に、事故防止の有効な手立てはないということです。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント