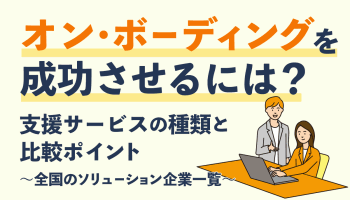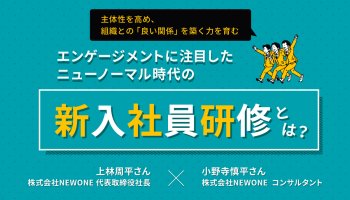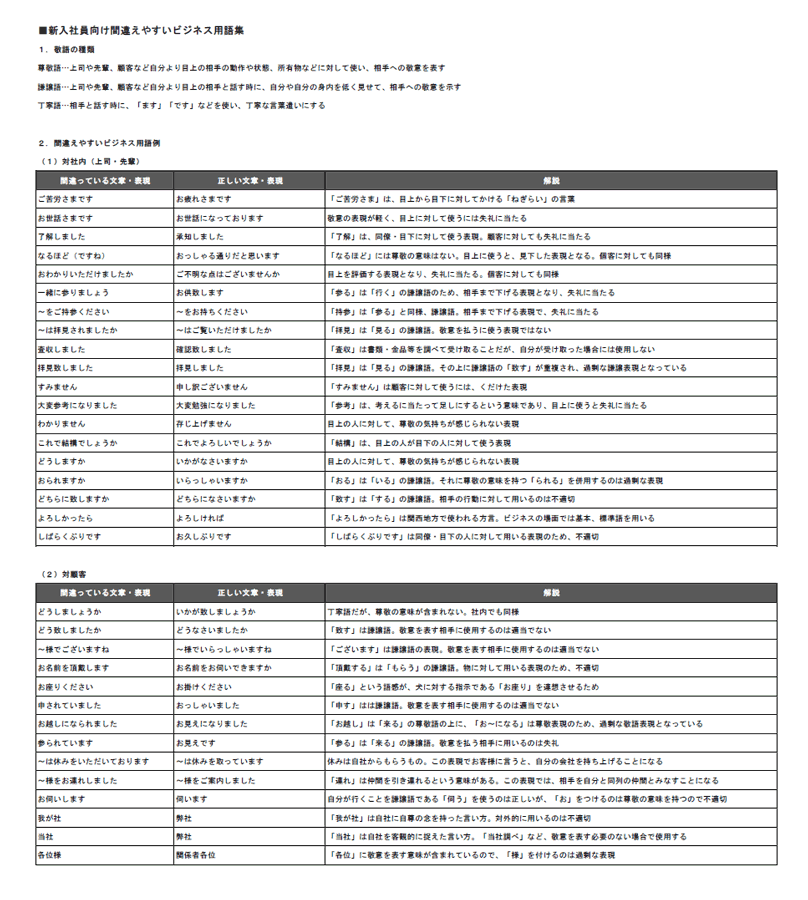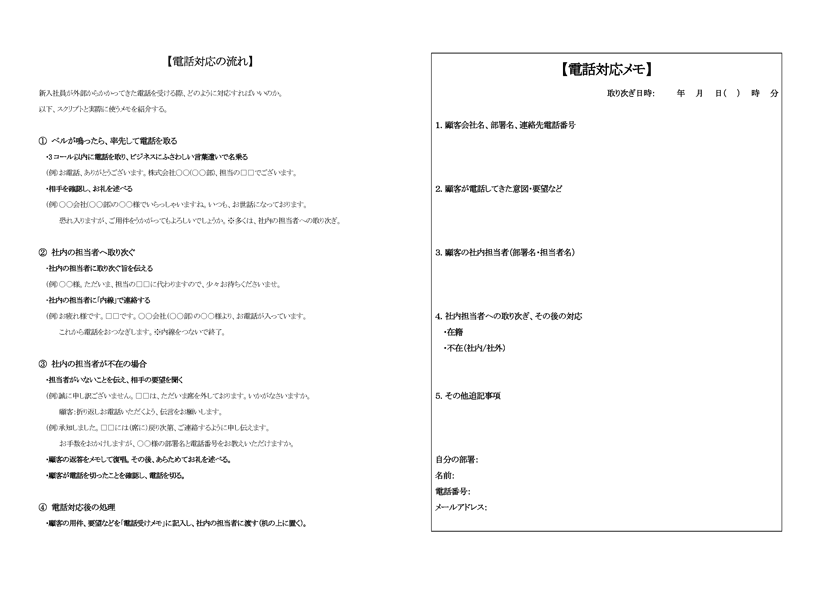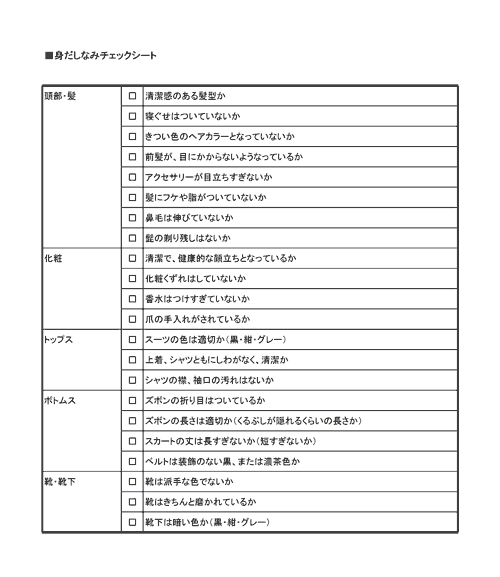プロアクティブ行動
プロアクティブ行動とは?
「プロアクティブ行動」とは組織行動学における用語で、組織からの期待に応えるために、自ら行動を起こして学んだり、組織になじもうとしたりする行動のことです。新入社員の行動を例にすると、研修などの受け身の学びだけでなく、職場にいち早く溶け込むために自ら勉強会を企画するなど、主体的・自律的な適応行動を挙げることができます。ただ待つのではなく、自ら考え変化のために行動できることは、VUCAの時代に求められる姿勢といえるでしょう。
プロアクティブ行動は
若手のうちから鍛えるが吉
企業が新卒採用を行う理由として「新入社員は色がついていないから、自社の色に染めやすい」という声がよく聞かれます。確かに他社の経験がない分、自社の文化に染まりやすい側面はあるかもしれません。しかし、「染まる」にもさまざまなタイプがあります。
新参者が組織に適応していくプロセスのことを「組織社会化」といいます。新入社員研修やOJT、社内行事などを通じて、その組織らしさを身に着け、社会化していくのです。その一連のプロセスに対して、終始受け身で構えるのではなく、自分から積極的に動き、先輩にフィードバックを求めたり、勉強会を企画したりしながら自らを能動的に社会化させていくことをプロアクティブ行動といいます。
どちらも同じ組織に“染まる”という過程ですが、なぜプロアクティブ行動ができる人のほうが好ましいとされるのでしょうか。その背景には産業構造の変化により、若手に限らず、主体的・自律的に考えられる人材が求められるようになっていることがあります。上司の指示に従っていただけの若手が中堅や管理職になったとき、急に自発的に行動できるようにはならないのです。小さなプロアクティブ行動であっても、コツコツと成功体験を積み重ねていくことが大切です。
では、人事が従業員にそのような態度を身に着けてもらうには、どうしたらいいのでしょうか。プロアクティブ行動の結果、仮に失敗したとしても責めないこと、そして、行動したこと自体が評価されるような風土を醸成することが必要です。
ただ実際のところ、プロアクティビティには個人差があり、学生時代から自然とできてしまう人もいれば、そうでない人もいます。受け身になりがちな人を無理にストレッチさせるのではなく、自ら進んでいける人とペアを組み、実務をサポートするなどチームとして機能させる。そうすることで、受け身だった人を取りこぼすことなく成功体験を重ねてもらうことができます。
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,500以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。
会員登録をすると、
最新の記事をまとめたメルマガを毎週お届けします!
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント