【対談】北極冒険家 荻田泰永さん(5)

「日常を飛び出し、自分の想像を超える体験をする」世界有数の北極冒険家・荻田泰永さんへの取材の全貌を全6回にわたって紹介します。第4回では挑戦、一歩踏み出すことに対する考え方について伺いましたが、第5回では「冒険研究所書店」の始まりから読書とそこから得られるマインドセットについて探索します!
【略歴】
荻田 泰永(おぎた やすなが)さん
1977年神奈川県生まれ。北極冒険家。2000年に冒険家・大場満郎氏が主宰した「北磁極を目指す冒険ウォーク」に参加。以来、カナダ北極圏やグリーンランド、北極海を中心に主に単独徒歩による冒険行に挑戦。2019年までの20年間に18回の北極行を行った日本唯一の「北極冒険家」。2016年、カナダとグリーンランドの最北の村をつなぐ1000kmの単独徒歩行(世界初踏破)。2018年、南極点無補給単独徒歩到達に成功(日本人初)。同年「2017植村直己冒険賞」を受賞。2019年には、若者たち12人との北極行「北極圏を目指す冒険ウォーク2019」を実現。2012年からは小学生の夏休み冒険旅「100milesAdventure」を毎年行っている。2021年神奈川県大和市に「冒険研究所書店」開業。主な著書に『北極男 増補版』(山と渓谷社)、『考える脚』(KADOKAWA)(第9回「梅棹忠夫・山と探検文学賞」受賞)、井上奈奈との共著絵本『PIHOTEK 北極を風と歩く』(講談社)(第28回「日本絵本賞」大賞受賞)などがある。
※全6回シリーズです。
第1回 究極の越境学習~若者12名が北極圏で得た学びとは~
第2回 関わり方の本質~厳しいことを伝え、同時に主体性をもたせるコミュニケーションとは~
第3回 計画とは「こうであるはずだ」の集合体~当初の計画を手放す勇気~
第4回 待つことと応答すること~意味はあとからついてくる~
第5回 机上の理論と路上の実践~冒険と読書の関係~ ←今回はここです。
第6回 対談を終えて(グローバル人材戦略研究所の視点)

【第5回 机上の理論と路上の実践~冒険と読書の関係~】
小平:ここまで、北極冒険家 荻田泰永さんの人材育成論について伺わせていただきありがとうございました。若者たち12人との北極行は『君はなぜ北極を歩かないのか』(産業編集センター)として書籍化されていますが、なぜこのタイトルにしたのでしょうか。
荻田さん:『君はなぜ北極を歩かないのか』というタイトルは逆説的に「私はこういう理由で北極を歩きました」ということを伝えているわけです。それをダイレクトにタイトルにすると独りよがりになってしまい、当然読み手からすれば他人事です。私自身も本というツールを通して日常を飛び出してきました。ぜひ読者の方々にも同じようにこの本を通じて世界を飛び出してみてほしい、もしくはその一つのきっかけになればいいなと思います。今回出会った12人の彼らはほんの一部で、それ以外にも出会ってないたくさんの「彼ら」がいます。だからこそその「彼ら」に「私は北極を歩いていますが、あなたたちはどうですか」と問いかけたい。この本を届けたい。そのような思いからこのタイトルにしました。
小平:ありがとうございます。本日は荻田さんが経営されている「冒険研究所書店」にお邪魔をして対談させていただいています。荻田さんが冒険で使用したソリなど装備も展示されているほか、室内に小屋があるなど、温かみのある素敵な空間です。
荻田さん:「冒険研究所書店」はこれから冒険を目指す人たちが集える場となっています。私自身の事務所も兼ねているので、ここに来れば、実際に話をしてアドバイスも提供しています。
小平:世界的な極地冒険家に直接相談できるなんて、とても贅沢な話です。冒険関連の書籍はもちろん、各ジャンルの書籍もあるので敷居が低く、足を運びやすいのがいいですね。こちらには5000冊以上あるということで本好きの私からすると夢のような空間です。そもそも冒険家である荻田さんご自身が「越境体験」を通じてどんどん世界を広げていらっしゃいます。単独の冒険からはじまり、若者向けの冒険チャンスの提供、書籍の執筆、そしてこちらの書店も営まれているわけですが、どうして冒険家の荻田さんが書店、なのでしょうか。
荻田さん:冒険家と書店に遠さを感じるかもしれませんが、私の中では「冒険と読書」というのは極めて近い存在だと思っています。
「探検とは、知的情熱の身体的表現である」
これは先ほども話にでた、イギリスのスコット隊とノルウェーのアムンセン隊による南極点到達レースを後方支援したイギリスの極地探検家アプスレイ・チェリー=ガラードによる極地探検記の古典にして名著『世界最悪の旅』にある有名な一節です。知的情熱を養うものの最たるものが読書でしょう。読書を通して知的情熱が養われ、好奇心が醸成され、やがて衝動となって身体を動かし、身体的表現によって行われる活動が「探検」であり、それはそのまま「人間」の営みであると思っているのです。
小平:読書による知的なものと、冒険による身体的なものはつながっているのですね。
「理論なき実践は盲目であり、実践なき理論は空虚である」という言葉がありますが、私自身は「机上の理論(Book smart)」と「路上の実践(Street smart)」と表現しています。人材育成においては「机上の理論」に偏りすぎており、それはそれで大事なのですが、単に知識を得ることが目的化してしまっていないか、実践が疎かになっていないか、という問題意識です。グローバルという視野で見ると特にコロナ禍以降は地政学リスクや円安、そしてリモートコミュニケーションの普及・一般化により実際に現地に足を運ばずにスクリーン越しで満足していないか、行動してみるという実体験が圧倒的に足りていないのではないか、と。大切なのは「机上の理論」と「路上の実践」ーーー荻田さんの場合は「氷上の実践」かもしれませんが(笑)ーーーを行き来することだと思っており、次世代リーダー育成ではこの点を重視しています。
ところでこの場、冒険研究所書店では冒険家を招いたり、先日も若者12名との北極行に撮影担当として同行した写真家の柏倉陽介さんとのセミナーも開催していますね。本に出会い、荻田さんとも話せ、さらにセミナーでは興味あるテーマをクローズドな場で聞ける・質問できるという場の存在は貴重だと思います。
荻田さん:ありがとうございます。「日常を飛び出し、自分の想像を超える体験をする」冒険とは場所ではなく、態度・スタンスの話です。今後も様々な活動を通じて実践していきたいと思っています。
【第5回のポイント】
・読書で養われた知的好奇心が行動につながり、探検は「知的情熱の身体的表現」である。
・本は日常から世界に飛び出すきっかけとなるツール。
・「机上の理論(Book smart)」と「路上の実践(Street smart)」両方の行き来が成長には不可欠。
このコラムを書いたプロフェッショナル

小平達也
株式会社グローバル人材戦略研究所
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。

小平達也
株式会社グローバル人材戦略研究所
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。
| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、グローバル、リーダーシップ、マネジメント |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
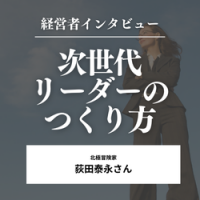
- レポート・調査データ
- 経営者・経営幹部研修
- リーダーシップ
- 管理職研修
次世代リーダーのつくり方~ 北極冒険家 荻田泰永さん~

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 経営戦略・経営管理
- キャリア開発
- グローバル
- マネジメント
- コミュニケーション
AI・ChatGPT時代に対応! 次世代リーダーに求められる課題形成力と6つの能力が身につくサイクルアプローチ
開催日:2023/06/23(金) 12:00 ~ 2028/12/31(日) 18:00

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
異業種交流型で他社事例共有【駐在員が知っておくべき部下育成とリスク対応】
開催日:2026/03/12(木) 10:00 ~ 16:00
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









