【対談】北極冒険家 荻田泰永さん(3)

「日常を飛び出し、自分の想像を超える体験をする」世界有数の北極冒険家・荻田泰永さんへの取材の全貌を全6回にわたって紹介します。第2回では荻田さんのご経験からマネジメントにおける相手との関わり方について伺いましたが、第3回では主に視野の広げ方、無意識バイアスからの解放について探っていきます!
【略歴】
荻田 泰永(おぎた やすなが)さん
1977年神奈川県生まれ。北極冒険家。2000年に冒険家・大場満郎氏が主宰した「北磁極を目指す冒険ウォーク」に参加。以来、カナダ北極圏やグリーンランド、北極海を中心に主に単独徒歩による冒険行に挑戦。2019年までの20年間に18回の北極行を行った日本唯一の「北極冒険家」。2016年、カナダとグリーンランドの最北の村をつなぐ1000kmの単独徒歩行(世界初踏破)。2018年、南極点無補給単独徒歩到達に成功(日本人初)。同年「2017植村直己冒険賞」を受賞。2019年には、若者たち12人との北極行「北極圏を目指す冒険ウォーク2019」を実現。2012年からは小学生の夏休み冒険旅「100milesAdventure」を毎年行っている。2021年神奈川県大和市に「冒険研究所書店」開業。主な著書に『北極男 増補版』(山と渓谷社)、『考える脚』(KADOKAWA)(第9回「梅棹忠夫・山と探検文学賞」受賞)、井上奈奈との共著絵本『PIHOTEK 北極を風と歩く』(講談社)(第28回「日本絵本賞」大賞受賞)などがある。
※全6回シリーズです。
第1回 究極の越境学習~若者12名が北極圏で得た学びとは~
第2回 関わり方の本質~厳しいことを伝え、同時に主体性をもたせるコミュニケーションとは~
第3回 計画とは「こうであるはずだ」の集合体~当初の計画を手放す勇気~ ←今回はここです。
第4回 待つことと応答すること~意味はあとからついてくる~
第5回 机上の理論と路上の実践~冒険と読書の関係~
第6回 対談を終えて(グローバル人材戦略研究所の視点)

【第3回 計画とは「こうであるはずだ」の集合体~当初の計画を手放す勇気~】
「自然」という視座、そこから見える「社会」
小平:荻田さんのご著書では視座や視野という単語をよく目にしますが、私自身も次世代リーダー育成に際しこの考え方を大事にしています。私の理解では視座というのは見る立場、視野とは見る範囲、視点・論点とは自分で問いを設定することであり、特に現在のように変化が激しい時代には大切な能力です。
荻田さんはご著書の中で、特に自然のダイナミズムの視座からものを見たときの人間の愚かさや傲慢さについて語られていましたね。ご自身の考える自然という視座は私たちにどんな示唆を与えてくれているのでしょうか。
荻田さん:そもそも自然の中に入れば人間の都合というのは関係ないものです。先ほどもお話しましたが、「自然」それ自体は、思い通りにもならなければ裏切りもしません。「自然」はただ単にそこにあるもので、計画・管理し人が動かす「社会」とは正反対のものです。私たちが社会の中で物事を考えているうちは、目的、目標、都合、予定を意識しながら生活し、それがあたかも絶対的な善であると考えてしまいます。しかしそれは社会の中の理屈でしかなく、自然の中に入ればそれらは全く通用しません。
私が20歳過ぎの頃、北極圏でイヌイットと生活したことがありました。幼い頃から約束は守りましょうと叩き込まれた私にとって衝撃だったのは、当たり前のようにイヌイットたちが約束を守らないことでした。それはなぜだろうと訳を考えてみたとき、彼らは人間同士の約束、いわゆる社会の都合ではなく自然の都合で生きているのだと気が付きました。例えばイヌイットのお爺さんと「明日の朝、狩りに行こう」と話していても、その約束を守ってくれることはほとんどなく、約束の時間に行ってもまだ寝ていたりと狩りに行ける状況ではないのです。なぜならお爺さんはその日の天気など、まさにその時、その瞬間の状況を踏まえて私との約束ではなく自然の様子で判断しているからです。社会の都合でものを言えば、「昨日約束したから狩りに行きましょう」が正解です。でも自然の中では自然を無視し、社会の理屈を優先して狩りに行けば死んでしまうのです。どちらが正しい、間違っているかではなく、おかれている環境・状況、視座の中で価値・判断基準が異なってくるのです。
小平:「自然の中では、自然の都合を無視した社会の理屈を優先して狩りに行けば、死んでしまう」ーーー重たい言葉ですが確かにその通りですね。北極圏に限らず、ビジネスシーンにおいてもその時の外部環境を十分踏まえた上で判断していくべきですね。外部環境にはその時代の常識なども含まれると思います。私は文化に言及するときに「文化とは特定の集団が共通してもつ、感じ方、考え方、行動の仕方のパターンである」と紹介していますが、面白いことにこの「特定の集団が共通してもつ、感じ方、考え方、行動の仕方のパターン」とは文化以外にも別の日本語の定義でもあるということです。その日本語とは「常識」です。「文化とは(常識とは)特定の集団が共通してもつ、感じ方、考え方、行動の仕方のパターン」であり、事実は一つでも、立場の異なる相手がどのような視座で見ているかで、認識・解釈は大きく異なる可能性があるわけです。
計画とは「こうであるはずだ」の集合体~そして手放す勇気~
小平:荻田さんは最も危険なこととは人間自身の思い込みであるとおっしゃっています。人間側の都合など自然相手には無意味であるということだと思いますが。私の専門分野である経営学・組織論ではそのような思い込みは「無意識バイアス(無意識の偏見)」といわれ「〜であるはずだ」というような常識やステレオタイプ(単純化された固定的な概念やイメージ)のことを指します。代表的なものとしては経験バイアス(過去の経験にもとづいて判断)や現状維持バイアス(新しい行動をさけ、現状を維持しようとする)、社会的手抜き(集団になると個人は手を抜く)などがありますが、荻田さんが冒険の中で特に注意しているバイアスは何かありますか?
荻田さん:冒険をする上では、まず計画を立てなくてはなりません。計画とは現地に行った時にこうだろう、こんなことが起こるだろう、こういう場所があるだろうという、「こうであるはずだ」の集合体です。ということは計画というのもバイアスの一つなのかもしれません。その「こうであるはずだ」という計画を立て、それを外れないようにしますが、自然というものは計画できず、自然の都合を優先しながら進んでいくべきなのです。その未知をどこまで読み取れるのかに難しさがあり、それゆえ面白さがあります。全部事前にわかってしまうと面白くないけれども、計画はある程度必要である。その塩梅が冒険の醍醐味です。
例えば私はある時、北極において難しいルートに挑戦しようとしていました。事前に衛星写真や過去の探検隊の記録を調べ、地図上で何度もシュミレーションしました。すると歩いた48日間では意外なことは起こらず、もちろん大変なことはあれど全て事前の想定の範囲内でした。その時、事前に私は読み切ってしまったのだと、北極に対する未知性が乏しくなってしまったのだと気が付きました。それが南極に行く大きなきっかけにもなりました(注:2018年、荻田さんは日本人初の南極点無補給単独徒歩到達に成功)。海の氷の上を歩く北極圏とくらべると平坦な陸地が続く南極での冒険の難易度はさほど難しくないと言われていますが、私自身行ったことがなく、新しい体験をしたいと思い南極に行くことにしたのです。つまり「こうであるはずだ」の集合体である計画は自分の能力の確認作業には非常に役立ちます。しかしそれだけでは想像を超えてこない、そして自分自身の未知性をも超えてこないのです。自分自身の成長を求めるならば、いったん計画を手放してみることです。
小平:計画自体がバイアスなのかもしれない、とは考えたこともありませんでした。今の話で、以前別の機会で荻田さんが「どんな人間が遭難するのか」という質問に対し「周りの状況を観察しないで手元の地図しか見ていない人は遭難する」とお答えになっていたことを思い出しました。地図や計画は有用なものの、地図しか見ていない、当初立てた計画に固執してしまうとまずいということですね。そして、「成長を求めるならば、いったん計画を手放してみること」とは自分自身を当初想定した枠組み、計画から解放させるということですね。リベラルアーツとは文字通り「解放するための技術」であると言われますが、何から解放するか。それは自分自身のものの見方、認知フレーム・バイアスからの解放です。
荻田さん:私も視野を広げるとは、言い換えると自分を手放すこと、自分から離れることだと思っています。自分が自分である限り視座は固定されてしまいます。もちろん、それがアイデンティティともなるのですが。冒険だけでなく、日常の中で視野を広げるためには本を読むこともおすすめです。読書は1000年以上前の人の視座すらわかる重要なツールです。しかしその方法論以前のメンタリティとして重要なのは、自分の視座を脇に置いて、どれだけ本の視座に立つことができるかにかかっています。
最近読んだ本の中でそれを完璧に実践しようとしたのが、歴史学者・保苅実さんの『ラディカル・オーラル・ヒストリー』(岩波現代文庫)です。本書はアボリジニの語りから彼らの歴史観を検証するというものでアボリジニたちは「(アメリカ大統領であった)ケネディが来た」など事実に基づかないことを「本当にあったこと」として語り、それを西洋のアカデミズムは学問として可能な形で解釈しようとしました。それに対して保苅実さんは事実に基づかないことであってもこちらが解釈をするのではなく彼らの言ったことを「彼らの中では本当にあったこと」として捉え、その上で彼らの語りをどう聞くかという研究をされました。保苅さんは「『尊重』という名の包摂は、結局のところ巧妙な排除なんじゃないでしょうか。」と西洋の歴史学者の姿勢に疑問を呈していました。西洋の学者たちは対象の語りを尊重しようとします。しかしその後、主体を西洋の学問、自らの枠組みの中に移動させて、その視座から解釈、取り込んでしまう。それは尊重ではなく排除だというのです。保苅さんは自分の理論は脇に置いておいて、自分を手放し、絶対的にこのアボリジニのお爺さんを主体にしよう、というところから逃げないのです。そうすることでしか見えない世界がある。まさにそれは私が自然に対してすることと同じなんです。管理できないからこそ、主体は自然でしかあり得ない。自然の視座に立ち、自分を手放すしかないのです。
【第3回のポイント】
・自然の中では人間社会の都合は通用しない。置かれている環境・状況の中により価値基準、判断基準、視座は異なる。
・計画は「こうであるはずだ」の集合体。自分の能力の確認作業には役立つものの、成長を求めるならば、いったん計画を手放してみる。
・視野を広げる為に読書は有効。ただし、自分の視座を脇に置いて、どれだけ本の視座に立つことができるかがカギ。
このコラムを書いたプロフェッショナル

小平達也
株式会社グローバル人材戦略研究所
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。

小平達也
株式会社グローバル人材戦略研究所
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。
| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、グローバル、リーダーシップ、マネジメント |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
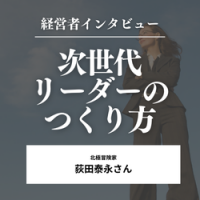
- レポート・調査データ
- 経営者・経営幹部研修
- リーダーシップ
- 管理職研修
次世代リーダーのつくり方~ 北極冒険家 荻田泰永さん~

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 経営戦略・経営管理
- キャリア開発
- グローバル
- マネジメント
- コミュニケーション
AI・ChatGPT時代に対応! 次世代リーダーに求められる課題形成力と6つの能力が身につくサイクルアプローチ
開催日:2023/06/23(金) 12:00 ~ 2028/12/31(日) 18:00

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
異業種交流型で他社事例共有【駐在員が知っておくべき部下育成とリスク対応】
開催日:2026/03/12(木) 10:00 ~ 16:00
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









