【対談】北極冒険家 荻田泰永さん(2)

「日常を飛び出し、自分の想像を超える体験をする」世界有数の北極冒険家・荻田泰永さんへの取材の全貌を全6回にわたって紹介します。第1回では若者12名が北極圏で得た学びを深堀していくことを通して越境学習について理解を深めました。第2回では、荻田さんのご経験からマネジメントにおける相手との関わり方について伺います!
【略歴】
荻田 泰永(おぎた やすなが)さん
1977年神奈川県生まれ。北極冒険家。2000年に冒険家・大場満郎氏が主宰した「北磁極を目指す冒険ウォーク」に参加。以来、カナダ北極圏やグリーンランド、北極海を中心に主に単独徒歩による冒険行に挑戦。2019年までの20年間に18回の北極行を行った日本唯一の「北極冒険家」。2016年、カナダとグリーンランドの最北の村をつなぐ1000kmの単独徒歩行(世界初踏破)。2018年、南極点無補給単独徒歩到達に成功(日本人初)。同年「2017植村直己冒険賞」を受賞。2019年には、若者たち12人との北極行「北極圏を目指す冒険ウォーク2019」を実現。2012年からは小学生の夏休み冒険旅「100milesAdventure」を毎年行っている。2021年神奈川県大和市に「冒険研究所書店」開業。主な著書に『北極男 増補版』(山と渓谷社)、『考える脚』(KADOKAWA)(第9回「梅棹忠夫・山と探検文学賞」受賞)、井上奈奈との共著絵本『PIHOTEK 北極を風と歩く』(講談社)(第28回「日本絵本賞」大賞受賞)などがある。
※全6回シリーズです。
第1回 究極の越境学習~若者12名が北極圏で得た学びとは~
第2回 関わり方の本質~厳しいことを伝え、同時に主体性をもたせるコミュニケーションとは~ ←今回はここです。
第3回 計画とは「こうであるはずだ」の集合体~当初の計画を手放す勇気~
第4回 待つことと応答すること~意味はあとからついてくる~
第5回 机上の理論と路上の実践~冒険と読書の関係~
第6回 対談を終えて(グローバル人材戦略研究所の視点)

【第2回 関わり方の本質~厳しいことを伝え、同時に主体性をもたせるコミュニケーションとは~】
危険な場所でどこまで管理するか?~発酵型上司と腐敗型上司~
小平:氷の下に陸がある南極大陸とは違って北極圏ですよね。若者12名との北極行では海が凍結した海氷上も歩き、当然のことながら下は海ですよね。私などは荻田さんの文章を読むだけでもゾクゾクしてしまい、恐怖を感じます。そこでお伺いしたいのですが、危険も多く存在する環境下ではどのようにメンバーの管理をしていけばいいのでしょうか。
荻田さん:北極での若者たちにしろ日本での小学生たちにしろ「彼らを管理する」ということであればそれは楽です。安全第一とするならば、これはだめ、あれはだめとルールで縛りつければいいのですからこちらは安心です。しかしそうすれば、彼らは家畜のように自分の思うようには動けず、非常に窮屈に感じてしまいます。要は楽しくないのです。彼らに対してどこまで枠を拡張してあげられるのか、枠を意識させないようにしつつ、いかに自由にさせるか、というこちら側の度量が試されます。西遊記の中に、孫悟空は縦横無尽に飛び回っているつもりが実際はお釈迦さまの手の上で飛びまわされているだけ、という話がありますが、例えるならば彼らは孫悟空、そして私自身はお釈迦さまのようなものです。手のひらの大きさ、つまり枠を決めることができるのは、私のこれまでの経験、知識、技術、考え方などの実績に裏打ちされたものです。その枠を出そうになった時、危なくなった時には元に戻してあげながら、自由に飛び回らせてあげるわけです。どこまで彼らを自由に飛び回らせてあげられるか、というのは私自身の力量と表裏の関係であり、彼らの感情、行動、成長の結果に対し、結局は私自身が試されているのです。
小平:今のお話は職場において、いかに部下に能力を発揮してもらうかという組織論としても捉えられると思います。マネジメントのスタイルは大きく分けて、上司が答えを持っていて部下に指示をする「Teach型」と、上司は部下の考えや意見・行動を引き出す支援をするという「Coach型」があります。特に後者の「Coach型」においては、単なるコミュニケーションテクニックというよりは、両者の関係性や場の雰囲気、上司の経験に裏打ちされた余裕ある態度などがその前提となります。部下が自分自身の強みをいかし、自ら提案、意見表明、能力発揮ができるかについてはまさに上司自身の力量が問われているわけです。よく「部下が腐ってしまう」などという上司がいますが、よくよく考えてみると腐る、すなわち腐敗と発酵は微生物による変化という同一の現象を「食べられれば発酵、食べられず有害であれば腐敗」と人間が勝手に言っているわけです。今の荻田さんのお話を伺って、部下に化学反応をあたえ、能力を開花させる=発酵型上司と、逆に上司に力量が無く、部下を腐らせてしまう=腐敗型上司がいるのではないかと思いました。
荻田さん:その通りです。相手を腐らせているのは自分自身である可能性がある、ということを上の立場の人間は肝に銘じておくべきです。その意味で私自身と若者の関係において相手をみるということは自分自身の鏡をみているということなのです。
北極に行く前に合宿を北海道で行いましたが、事前のトレーニングの中で最低限守っておくべきこと・ガイドラインを伝える、いわばパソコンのOSをインストールしておくことを徹底すればリスク管理はできます。北極行においても「100milesAdventure」においても、目的地、出発地、日程案などはありますがこれといった細かいルールはありません。それを決めないことで初めて面白いこと、予想を超えてくることが起きるのです。その一方で、「俺(荻田)の枠はここだよ」「俺は今、○○と感じているぞ」と自分の感情をふくめ、しっかりと意思表明しておくというコミュニケーションが非常に重要です。
小平:通常、感情を出すことはよくないと思われがちですが、アサーティブコミュニケーションというものがあります。これは、攻撃的にならずに、自分自身の意思を表明するコミュニケーション手法で年齢や性別、国籍など多様な背景をもつメンバーとの意思疎通で有効なテクニックです。荻田さんの場合は自分の感情を相手にぶつけるのではなく、「自分自身はこのように感じている」という「メッセージ」であり、まさにアサーティブコミュニケーションですね。
リスク管理と主体性の両立のポイント~観察し、変化のタイミングを見逃さない~
小平:ここまで、危険な場所でどこまで管理するかということについて荻田さんのお考えをお聞かせ頂きました。その上で伺いたいのですが、リスク管理に加えて彼ら、彼女らの主体性を引き出すためにはどのような点に留意されたのでしょうか。
荻田さん:それはなによりも変化のタイミングを見逃さないよう、しっかりと観察することです。
例えば12人との北極行での出来事です。出発から2週間たち、若者たちが、前日ホワイトアウトで視界が悪い中、私がどのようにチームを先導したかについて質問してしてきたことがありました。その時まで彼らは単に私についてきているだけで、チームをリードすることに興味を示していなかったのです。その彼らが質問をしてきたーーー2週間経ってようやく自分たちのやっていること、自分たちの隊が進むためにはどのようにリードしたらいいか、ということに興味を持った瞬間だったわけです。自分たちのしていることに興味をもつ、というのは主体性を持ち始めたということです。この質問してきたという兆候、タイミングを見逃さず、さっそく翌日から彼らにチームのリードを任せてみました。このように彼らの言動をしっかりと観察し、変化を見逃さないようにしなくてはなりません。
小平:観察や適切なタイミングでの介入・コミュニケーションが大切になるのですね。私自身を含め、人は往々にして自分の想定している範囲内で相手を管理しようと思いがちですが、実際には他人を変えることはできません。上司にできることは相手との関わり方、すなわち関係性を管理・マネジメントすることだと思います。
荻田さん:はい。そのためには「信頼」がキーワードになってきます。往々にして人々は自分が安心したいがために管理をしたがります。相手が自らの意思で自由に動き回ることがなければ危険はない、自分は安心だと思うわけです。しかしながら管理をすればするほど、逆に相手のこちらに対する信頼を失なってしまいます。こちらも彼らを信頼して、少し遠目から観察することが大切です。「こちらが安心したい」というのは独りよがりであり、裏切られる未来を恐れて相手を信じていないということです。信頼することは怖いと思われるかもしれませんが、こと「自然」それ自体は、思い通りにもならなければ裏切りもしません。「自然」は文字通りあるがままですし、自然を計画することはできません。ただ単にそこにあるもので、計画・管理し人が動かす「社会」とは正反対のものです。私にとって北極行をともにした若者たちも「100milesAdventure」に参加した小学生たちも自然物であり、どうにもできない対象なのです。対自然においては、しかるべきタイミングーーーこの場合は自分たちのチームのリードに興味をもち、主体性をもつことーーーがくることを信じて待つことが大切なのです。この「信じて待つ」という姿勢はとても大事なものです。
【第2回のポイント】
・自然をはじめ、自分が計画できない他者には「信じて待つ」というのが基本姿勢。
・質問をしてくる、ということは興味をもっていることであり主体性を持ち始めた兆候。
・常に観察し、変化の兆候、タイミングを見逃さない。
このコラムを書いたプロフェッショナル

小平達也
株式会社グローバル人材戦略研究所
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。

小平達也
株式会社グローバル人材戦略研究所
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。
人材育成・組織開発の専門家として対話型プログラムを多数開発。組織における関わり合い無形資産として捉えエンゲージメントと組織活力の向上を行っている。政府有識者・大学講師ほか経団連グローバル人材育成スカラーシップ設立時から一貫して支援している。
| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、グローバル、リーダーシップ、マネジメント |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 港区 |
このプロフェッショナルの関連情報
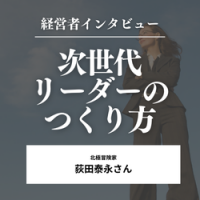
- レポート・調査データ
- 経営者・経営幹部研修
- リーダーシップ
- 管理職研修
次世代リーダーのつくり方~ 北極冒険家 荻田泰永さん~

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
- 経営戦略・経営管理
- キャリア開発
- グローバル
- マネジメント
- コミュニケーション
AI・ChatGPT時代に対応! 次世代リーダーに求められる課題形成力と6つの能力が身につくサイクルアプローチ
開催日:2023/06/23(金) 12:00 ~ 2028/12/31(日) 18:00

- 無料
- WEBセミナー(オンライン)
異業種交流型で他社事例共有【駐在員が知っておくべき部下育成とリスク対応】
開催日:2026/03/12(木) 10:00 ~ 16:00
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









