多様性が成果を最大化する〜互いの成長を促進する相互支援

大手技術系企業様でスタートした1年間のプロジェクト「次世代リーダー育成研修」が
スタートして3ヶ月が経とうとしています。
多忙な業務の中、育成対象者のみなさんの多くは
前向きに学び、実践課題に取り組んでおられて
とても頼もしく感じている今日この頃。
今回のメルマガでは、その実践課題を通して
よりリーダーとして成長していただくための
仕掛け「相互支援」の重要性について
改めて気づいたことについてお伝えしたいと思います。
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
■互いの成長を促進する「相互支援」
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
今回ご紹介するA社(IT企業・約5,000名規模)では、
全6回のオンライン研修に加えて、それぞれの研修間で
継続的な現場実践を行う内容となっています。
通常業務と並行して常に現場実践があるので
育成対象者の中には負担が大きいと感じる方も
最初は出てきますが、
複数の案件や課題を抱えながらチームを率いて
その都度判断を下していく、という管理職としての
キャパシティ増強のためには欠かせない取り組みとなっています。
とはいえ、1人で現場課題をしていると
ちょっとした迷いや不安に陥ることも少なくありませんので、
実践スピードを落とさない仕組みとして
当社が設定しているのが「グループ内の相互支援」
という仕組みです。
A社のプロジェクトにおいても、
個々人の現場実践結果をグループ内で報告しあい、
互いにアドバイスしたり、がんばりを認め合うなど
積極的に関わることを推奨しています。
今回、育成対象者がそれぞれ提出した課題を
添削しながら改めて気づいたことが、
良い形で相互支援ができているグループは、
全体的にアウトプットの質が高まっているというのが
一目瞭然である、ということでした。
相互コメントする際のコツもオンライン研修で
お伝えしているのですが、その意図を自分なりに
受け止め、実践しているメンバーが1人でもいると、
グループ全体がそれに引っ張られて
お互いの成果・成長を引き出し合っているという
印象を受けたのです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
■多様性が成果を最大化する
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
一方で、約50名の育成対象者の中で
全体のお手本となるようなアウトプットを出した
Bさんというメンバーがいたのですが、
Bさんが属するグループのその他のメンバーが
出したアウトプットは、本来の力を発揮できていない
ということが見て取れました。
よく見ると、相互支援のコメントの質が
その他のグループに比べてうまくいっていない
ということに気づいたのです。
たとえ、1人が素晴らしい能力を持っていたり
群を抜いて成果を上げていたとしても、
グループ全体としてアウトプットの質は、
相互支援できているグループと比べると
結果として低く見えてしまうのだと、
改めて相互支援の重要性を強く実感した次第です。
これは、リーダーが仕事をする上で
とても大切な考え方につながっていくと
私は考えています。
こんな言葉を思い浮かべた方もいらっしゃるかもしれません。
-------------------------------------------------------------------
早く行きたいなら、一人で行きなさい。
遠くへ行きたいのなら、皆で一緒に行きなさい。
-------------------------------------------------------------------
たった1人の成果よりも、
チーム全体の多様性を活かし合った結果の
質や量は、想定を超えたものになるのではないでしょうか。
Bさんのグループでは、Bさん以外のメンバーが
実際に自分がどのあたりで理解につまずいているのか、
どうすれば上手くいくのか、ということに
気付くタイミングを失っている状態で、それはつまり
本来の強みや能力を発揮する機会を逃してしまうという
非常にもったいないことになりかねません。
さらに、Bさんにとっても、自分1人では辿り着けなかった
成果を手にするチャンスも失ってしまうということに
他ならないと思いました。
私は即、Bさんのグループでキーパーソンとなりそうな
メンバーを数名ピックアップして、互いにコメントする際、
表面的なコメントにならないための、多様な視点を入れる
コツについて改めて丁寧にお伝えしました。
ここからは、いかに自律的に実践するかどうかです。
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
■受け取る力と自律性
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
組織やチームで多様性を引き出し合うためには、
さまざまな考え方に触れることが大切だと考えます。
A社のプロジェクトにおいて、アウトプットの質が
高かったグループでは、相互コメントの欄が
真っ黒になるほどびっしりと感想やアドバイスが
書かれていました。
メンバーごとのコメント欄の冒頭には必ず
「ここがすごく良いと思った」など、
相手の取り組みを承認するメッセージが
寄せられています。
さらに、
「私の経験ではこんなことがありました」
「先輩がこんな対応をして上手くいっていましたよ」
など、経験談や事例を使ったアイディア提供や、
「私も同じところで悩んでいます。ぜひ連携して取り組みませんか」
といった提案をしている様子も伺えました。
こういった関わり方のコツやポイントは、
私から事前にお伝えしていた内容でもあったので、
それを正面からしっかりと受け取って、
実際に行動に移してくれたことに私はとても感動しました。
アウトプットの質を高め、成果につなげていくためには、
何より「自律性」が重要であることは言うまでもありません。
学んだことを自分事として受け入れて
行動として実践しようという捉え方も含めて
私は「自律性」だと考えています。
学びを受け取り、全力でやってみよう、
というあり方が、必ず成果につながっていくと
私は確信しています。
┏━━━━━━━━━━━━━━━┓
■「多様性・自律性」をもたらすために
┗━━━━━━━━━━━━━━━┛
人材育成の現場では、自律性がなかなか引き出せない、
という課題にぶつかることも少なくないかもしれません。
知識やモノを与えられることに慣れてしまうと、
「教えてもらっていないので、できません」
「言われていないから、やりません」
など、自律性とはかけ離れてしまった状態で
仕事に向き合っていることに気づかないメンバーの
対応に悩んでいる経営者や管理職、人材育成担当者の方も
いらっしゃるかと思います。
相手を変えることはできませんが、
自分自身の関わり方を変えていくことは可能である以上、
相手の気づきを促し、マインドを醸成するような
関わりを続けていく必要が、特に育成に関わる
リーダー層や人事担当者にはあるのではないかと思います。
だからこそ、相手の心の変化をもたらすような施策を考え、
「多様性・自律性」をもたらすための刺激を与えるような、
視野を広げる取り組みについて考えていただく機会を
リーダー層や人事担当者の方には、
ぜひ設けていただきたいと心から願っています。
本人が気づきを得て、そこから自律的な行動として
いかに繋げられるかというストーリーを描くことが、
組織・チームとして飛躍的に成長を遂げるきっかけの
1つになると私は思っています。
このコラムを書いたプロフェッショナル

細木聡子
株式会社リノパートナーズ代表取締役/しなやか経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士
元NTT女性管理職10年、約500名のSE部門における人事育成担当3年の豊富な現場経験を持つ。これまで延べ8,000人以上の技術系企業の女性管理職育成に携わる。技術系企業のジェンダーギャップ解消を突破口としたダイバーシティ経営推進を支援。

細木聡子
株式会社リノパートナーズ代表取締役/しなやか経営コンサルタント/(公財)21世紀職業財団客員講師/中小企業診断士
元NTT女性管理職10年、約500名のSE部門における人事育成担当3年の豊富な現場経験を持つ。これまで延べ8,000人以上の技術系企業の女性管理職育成に携わる。技術系企業のジェンダーギャップ解消を突破口としたダイバーシティ経営推進を支援。
元NTT女性管理職10年、約500名のSE部門における人事育成担当3年の豊富な現場経験を持つ。これまで延べ8,000人以上の技術系企業の女性管理職育成に携わる。技術系企業のジェンダーギャップ解消を突破口としたダイバーシティ経営推進を支援。
| 得意分野 | 経営戦略・経営管理、モチベーション・組織活性化、キャリア開発、リーダーシップ、マネジメント |
|---|---|
| 対応エリア | 全国 |
| 所在地 | 千代田区 |
このプロフェッショナルの関連情報
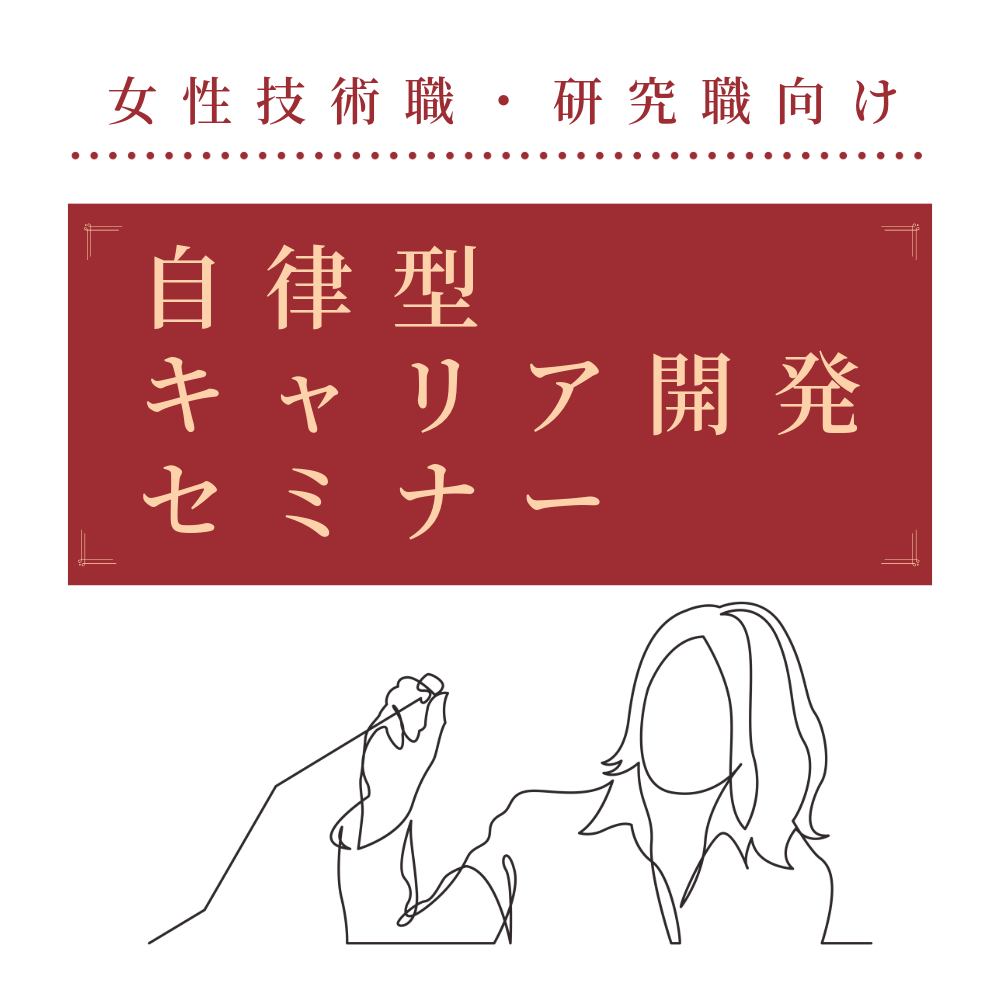
他、雇用管理・給与計算 自律型キャリア開発セミナー
●6時間で意識変革×行動設計×経験共有 ●NTT出身の元技術系女性部長の実体験に基づく、行動を促すキャリア研修
- 参考になった0
- 共感できる0
- 実践したい0
- 考えさせられる0
- 理解しやすい0
無料会員登録
記事のオススメには『日本の人事部』への会員登録が必要です。


 テーマで探す
テーマで探す サービス
サービス セミナー
セミナー 資料
資料 Q&A
Q&A 記事
記事 ニュース
ニュース 学び・実務
学び・実務





 イベント
イベント









